洗濯機が脱水できない時にどうするべきか分からずに困った経験はありませんか?
いざというときに脱水だけできない状況に陥ると、洗濯物がびしょびしょのままで途方に暮れてしまいますよね。
脱水トラブルの原因は様々で、洗濯物が回転しない状態になったり、すすぎに戻る現象が起きたりすることがあります。また、以前と比べて脱水力が弱くなったと感じる場合や、排水口の詰まりが影響している場合もあるんです。
こうした状況では、強制排水の方法を知っておくことが役立ちますし、洗濯物をそのまま干すべきかどうかの判断も迷うところですよね。
この記事では、洗濯機の脱水ができない原因を症状別に詳しく解説し、それぞれに対応した具体的な対処法をご紹介します。また、予防策や最新の洗濯機情報についても触れていますので、今すぐ解決したい方から将来的な対策を考えたい方まで、幅広くお役立ていただける内容となっています。
洗濯機が脱水できない時どうする?主な症状

洗濯機の脱水トラブルには、いくつかの典型的なパターンがあります。
まずは症状を正確に把握することで、適切な対処法を選択できるようになりますよ。ここでは、最も頻繁に発生する5つの主要な原因について詳しく見ていきましょう。
洗濯物の片寄り
洗濯機の脱水トラブルで最も多い原因は、洗濯物の片寄りです。脱水運転では洗濯槽を高速回転させて遠心力を利用するため、衣類が一箇所に固まってしまうと回転バランスが崩れてしまいます。
洗濯機には安全装置が内蔵されており、異常な振動を検知すると自動的に運転を停止する仕組みになっています。特に、厚手のタオルやバスタオル、毛布などの重い洗濯物を一緒に洗うときに起こりやすいトラブルです。
洗濯物が片寄る主な理由として、洗濯容量に対して衣類の量が多すぎることが挙げられます。また、洗濯ネットに詰め込みすぎてボール状になっている場合も、脱水時に偏りやすくなる原因の一つです。
対処法としては、まず洗濯機の蓋を開けて洗濯物の状態を確認しましょう。衣類が一箇所に偏っている場合は、手で均等に配置し直してから再度脱水を開始してください。洗濯物の量が多い場合は、複数回に分けて脱水することをおすすめします。
予防策として、洗濯容量の7~8割程度に留めることが大切です。また、重い衣類と軽い衣類を混在させる際は、バランスを考慮して配置することで片寄りを防げます。
排水口や排水ホースの詰まり

排水関連のトラブルも脱水できない原因として頻繁に見られます。洗濯時に出る糸くずや髪の毛、衣類の繊維などが徐々に蓄積され、排水経路を塞いでしまうケースです。
排水口の詰まりは、洗濯機下の排水トラップ部分で起こることが多いのです。排水トラップは下水臭や害虫の侵入を防ぐ設備ですが、複雑な構造のため汚れが溜まりやすい場所でもあります。
排水ホースの詰まりを確認する方法として、洗濯機から排水ホースを取り外し、ホース内に水を流してみることが有効です。水の流れが悪い場合や逆流する場合は、ホース内に汚れが蓄積している可能性があります。
掃除の手順として、まず洗濯機の電源を切りコンセントを抜きます。次に、排水口の蓋を外し、排水トラップの各部品を順番に取り外してください。部品は中性洗剤と歯ブラシを使って丁寧に洗浄し、汚れを完全に除去します。
排水ホースの内部清掃には、市販のパイプクリーナーが効果的です。ただし、使用前に洗濯機のメーカー推奨品を確認し、適切な手順で作業することが大切ですね。
定期的なメンテナンスとして、排水口は月1回程度、排水ホースは半年に1回の清掃を心がけましょう。これにより、突然の脱水トラブルを予防できます。
洗濯機が傾いていて回転しない

洗濯機本体の傾きやガタつきも、脱水機能に大きな影響を与える要因です。設置時は水平だった洗濯機も、長期間の使用により振動で徐々に傾いてしまうことがあります。
特にドラム式洗濯機は重量があるため、床材の変形や調整脚の沈み込みが起こりやすく注意が必要です。傾きがあると脱水時の振動が増大し、安全装置が作動して運転が停止してしまいます。
水平状態の確認には、洗濯機に内蔵されている水準器を使用します。水準器の気泡が中央の円内に収まっていれば適正な状態です。気泡が円から外れている場合は、調整脚を使って水平に修正する必要があります。
調整脚の操作方法は、洗濯機の前面にある脚部を回転させて高さを変更します。右回りで高く、左回りで低くなるのが一般的です。調整後は、洗濯機の天面対角コーナーを交互に押して、ガタつきがないことを確認してください。
ただし、調整脚の操作には力が必要で、作業中に指を挟む危険もあります。不安な場合は、販売店や設置業者に依頼することをおすすめします。
設置環境の見直しも重要なポイントです。柔らかい床材の上に設置している場合は、専用の防振マットを使用することで沈み込みを防げます。
フタのロックセンサーが原因

現代の洗濯機には安全機能として、フタのロックセンサーが搭載されています。このセンサーが正常に作動しないと、脱水運転が開始されない仕組みになっているのです。
フタが完全に閉まっていない場合や、ロック部分に汚れが付着している場合にトラブルが発生します。また、長年の使用により、ロック機構の爪部分が破損したり摩耗したりすることもあります。
まず確認すべきことは、フタがしっかりと閉まっているかです。見た目には閉まっているように見えても、ロック機構まで到達していない場合があります。フタを一度開けて、確実に「カチッ」という音がするまで押し込んでください。
ロック部分の清掃も効果的な対処法です。フタのロック部分や洗濯機本体の受け部分に、洗剤カスや糸くずが付着していることがあります。濡らした布で丁寧に拭き取り、動作を確認してみましょう。
センサー部分の故障が疑われる場合は、メーカーサポートへの相談が必要です。特に、フタを閉めてもロックされない状態や、ロック表示が点灯しない場合は、部品交換が必要な可能性があります。
私も家電量販店で働いていて、フタのロックセンサーに関するお問い合わせをよく受けますが、多くの場合は清掃で解決できることが多いんです。
糸くずフィルターの詰まり
糸くずフィルターの詰まりは、特にドラム式洗濯機で起こりやすいトラブルです。このフィルターは洗濯時に出る繊維や髪の毛をキャッチする役割を担っており、詰まると排水性能が低下してしまいます。
ドラム式洗濯機の糸くずフィルターは、通常本体下部の前面パネル内に設置されています。フィルターが詰まると、洗濯水の排水がスムーズに行われず、脱水時に水が残ってしまう原因となります。
フィルターの清掃時期の目安は、洗濯機の使用頻度にもよりますが、週1回程度が理想的です。毎日洗濯をする家庭では、より頻繁な清掃が必要になります。
清掃方法として、まず洗濯機が空の状態であることを確認してください。洗濯途中でフィルターを外すと、汚水が溢れ出す危険があります。フィルターを反時計回りに回して取り外し、流水で汚れを洗い流します。
頑固な汚れが付着している場合は、中性洗剤と歯ブラシを使用して清掃しましょう。フィルター本体だけでなく、設置部分の奥も忘れずに清掃することが大切です。
縦型洗濯機でも糸くずフィルターは設置されていますが、位置や形状が異なります。洗濯槽内の上部や側面に設置されていることが多く、定期的な確認と清掃が必要です。
洗濯機が脱水できない時にどうする?その他のケース

主要な症状以外にも、洗濯機の脱水に関する様々なトラブルが存在します。
ここでは、より具体的な状況や応急処置の方法について解説していきます。日常的に遭遇しやすい問題から、緊急時の対応まで幅広くカバーしていますので、参考にしてくださいね。
脱水だけができない
洗濯や、すすぎは正常に動作するのに、脱水工程だけがうまくいかないケースがあります。この現象は排水系統のトラブルや、洗濯機の制御部分に問題がある可能性が考えられます。
脱水専用モードで動作させてみることで、問題の切り分けができます。洗濯機の操作パネルから「脱水のみ」を選択し、単独で脱水運転を試してください。この方法で正常に動作する場合は、洗濯工程から脱水への移行部分に不具合がある可能性があります。
洗濯槽内に水が残っている状態も、脱水ができない原因の一つです。洗濯機は安全機構として、槽内に水が残っていると脱水運転を開始しない設計になっています。先ほどもお伝えしたように、排水経路の詰まりが主な原因として考えられます。
衣類の素材も影響する要因です。防水性のある衣類や、水を大量に吸収するクッション類は、脱水時に偏りやすく、安全装置が作動することがあります。このような衣類は、洗濯機の取扱説明書で禁止されている場合が多いのです。
エラーコードの確認も重要なポイントです。多くの洗濯機では、脱水に関するトラブルが発生すると、操作パネルに英数字のコードが表示されます。このコードを取扱説明書で確認することで、具体的な原因を特定できます。
解決しない場合は、洗濯機をリセットしてみましょう。電源プラグを抜いて5秒以上待ってから再度接続することで、制御系統がリセットされ、正常動作に復帰することがあります。
すすぎに戻ってしまう
脱水工程中に自動的にすすぎに戻ってしまう現象は、洗濯機の自己診断機能による補正動作です。衣類の偏りを検知した洗濯機が、水を入れ直して衣類の位置を調整しようとする機能なんです。
パナソニックの洗濯機では、この現象に対して「U13」というエラーコードが表示されることがあります。連続して3回補正運転を行っても改善されない場合は、自動的に運転が停止する仕組みになっています。
補正運転が繰り返される主な原因は、洗濯物の量や配置に問題があることです。特に、大きなバスタオルと小さなハンカチを一緒に洗うような場合に起こりやすくなります。
対処法として、洗濯物を一度取り出して再配置することが効果的です。重い衣類と軽い衣類をバランスよく配置し、洗濯槽全体に均等に広がるように調整してください。
洗濯物の素材を統一することも有効な予防策です。綿製品は綿製品同士、化学繊維は化学繊維同士でまとめることで、脱水時の挙動が安定します。
また、洗濯容量を適正範囲内に収めることも大切です。容量ギリギリまで詰め込むと、衣類が移動しにくくなり、偏りが発生しやすくなってしまいます。
脱水が弱くなった

以前と比べて脱水効果が弱くなったと感じる場合は、複数の要因が考えられます。洗濯機の経年劣化や、メンテナンス不足が主な原因として挙げられます。
脱水時間の設定を確認してみることから始めましょう。誤って脱水時間が短く設定されている場合や、ソフト脱水モードになっている可能性があります。通常の脱水時間に戻すことで改善することがあります。
洗濯槽のバランサー機能に問題がある場合も、脱水力の低下につながります。洗濯槽を手で回してみて、異常な音がしたり、動きが重く感じたりする場合は、内部機構のトラブルが疑われます。
排水ポンプの性能低下も考えられる要因です。長期間の使用により、ポンプ内部に汚れが蓄積し、排水能力が落ちることがあります。この場合は、専門業者による清掃や部品交換が必要になります。
洗濯機の設置環境を見直すことも重要です。床の沈み込みや傾きにより、脱水時の回転効率が低下している可能性があります。水準器で水平状態を確認し、必要に応じて調整してください。
使用年数が8年を超えている場合は、買い替えを検討する時期かもしれません。洗濯機の一般的な耐用年数は10年程度とされていますが、脱水機能の低下は全体的な性能劣化のサインでもあります。
強制排水のやり方
洗濯機内に水が溜まったまま動かなくなった場合の強制排水方法をご紹介します。停電時や緊急時に役立つ知識として覚えておくと安心です。
基本的な強制排水の手順として、まず洗濯機の電源が入っていることを確認します。排水ホースが排水口に正しく接続されているかもチェックしてください。
蛇口を閉めて給水を停止した後、操作パネルから「脱水のみ」コースを選択します。洗濯物が入っている場合は、可能な限り取り出してから実行することをおすすめします。
メーカー別の強制排水方法として、パナソニックでは「脱水」コースを選択してスタートボタンを押します。日立の場合は「脱水」または「槽洗浄」コースで対応可能です。東芝は「脱水のみ」運転で、シャープは「脱水」コースまたは「槽クリーン」で排水できます。
電源が入らない場合のリセット方法も知っておきましょう。コンセントを5秒以上抜いてから再接続することで、制御系統がリセットされ、動作が復旧することがあります。
完全に動かない場合の応急処置として、洗濯槽下部の排水弁を手動で開ける方法があります。ただし、機種によって方法が異なり、素人作業では危険な場合もあるため、メーカーサポートへの相談をおすすめします。
バケツで手動排水する方法もありますが、時間がかかり体力も必要です。サイフォン原理を利用して、排水ホースを排水口より低い位置に持っていくことで、自然排水させることも可能です。
洗濯機本体のガタつきを調整する方法
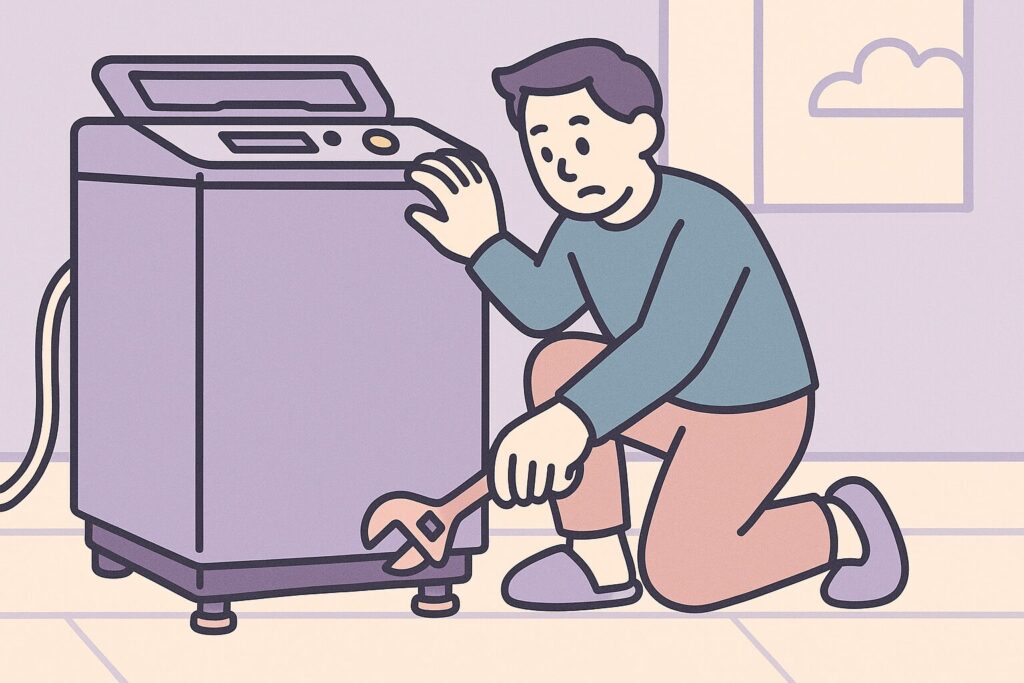
洗濯機のガタつきは脱水性能に直接影響するため、適切な調整が必要です。購入時は水平だった洗濯機も、使用とともに徐々に傾いてしまうことがよくあります。
まず、ガタつきの確認方法をお伝えします。洗濯機の天面対角コーナーを交互に押して、揺れや傾きがないか確認してください。少しでもガタつきを感じる場合は、調整が必要です。
水準器による水平確認も欠かせません。洗濯機に内蔵されている水準器の気泡が、中央の円内に収まっているかチェックします。気泡が円から外れている場合は、その方向が低くなっていることを示しています。
調整脚の操作方法として、一般的には前面の調整脚を回転させて高さを変更します。右回りで高く、左回りで低くなる仕組みです。微調整を繰り返しながら、水準器の気泡が中央に来るまで調整してください。
特にドラム式洗濯機は重量があるため、床材の変形や沈み込みが起こりやすい特徴があります。設置後も定期的に水平状態を確認し、必要に応じて再調整することが大切です。
調整作業時の注意点として、洗濯機を少し浮上させる必要があるため、指を挟まないよう十分注意してください。力が必要な作業でもあるため、不安な場合は設置業者に依頼することをおすすめします。
防振マットの使用も効果的な対策です。洗濯機の下に専用マットを敷くことで、振動を軽減し、床材への影響を最小限に抑えられます。
びしょびしょのまま干すのはアリ?

脱水がうまくいかず、洗濯物がびしょびしょの状態で困った経験がある方も多いのではないでしょうか。この状態で干すことについて、メリットとデメリットを詳しく解説します。
基本的には、十分な脱水を行わずに干すことはおすすめできません。水分が多く残った状態では、乾燥時間が通常の数倍かかってしまい、その間に雑菌が繁殖しやすくなってしまいます。
生乾き臭の発生リスクも高くなります。水分が多い環境は細菌にとって繁殖しやすい条件となり、不快なニオイの原因となってしまうのです。一度付いてしまった生乾き臭は、洗い直しても除去が困難になることがあります。
衣類への影響として、重い水分により型崩れが起こる可能性があります。特にニット製品や柔らかい素材の衣類は、水分の重みで伸びてしまい、元の形に戻らなくなることがあります。
ただし、緊急時やデリケートな衣類の場合の対処法もあります。まず、タオルで軽く水分を取り除くことから始めましょう。可能な限り手で絞って、余分な水分を除去することが大切です。
風通しの良い場所で干すことも重要なポイントです。屋外であれば直射日光を避けた風通しの良い日陰、室内であれば除湿機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間を短縮できます。
最近の洗濯機には「手絞り風脱水」や「やわらか脱水」といった機能も搭載されています。デリケート衣類でも適度な脱水が可能なので、これらの機能を活用することをおすすめします。
総括:洗濯機が脱水だけできない時はどうする?
それでは最後に、この記事の内容をまとめます。



