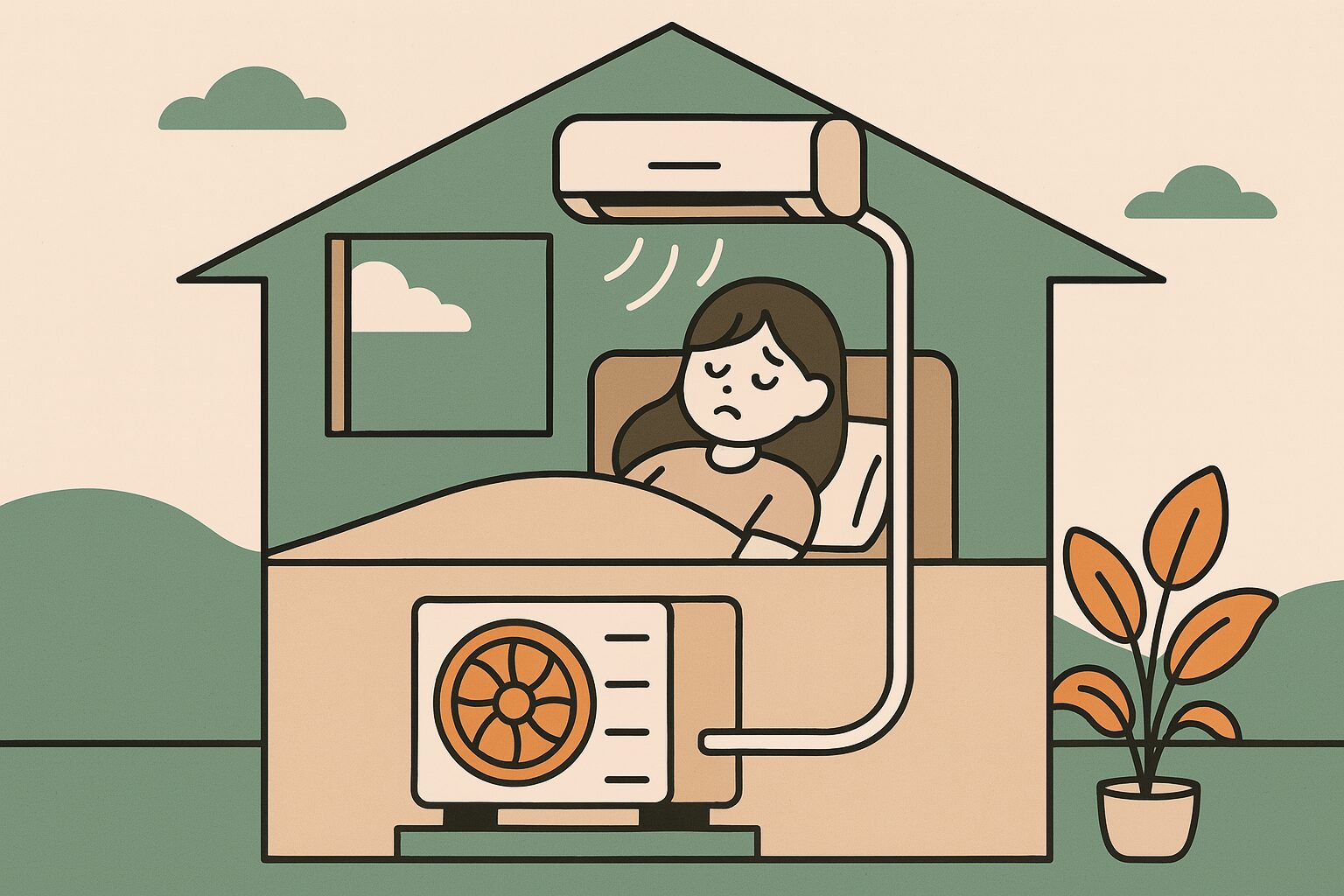2階の部屋を快適にするためエアコンの設置を検討しているけれど、室外機をどこに置くかで悩んでいませんか?
ベランダが狭かったり、そもそもベランダがなかったりすると、1階に室外機を設置するという選択肢が浮かんできますよね。
確かに1階への室外機設置は物理的に可能な方法ですが、実は知っておくべき重要なデメリットがいくつも存在します。配管が長くなることで電気代が上がってしまったり、エアコンの効きが悪くなったりする可能性があるんです。
私も家電量販店で働く中で、お客様から「設置してから後悔した」というお話を伺うことがあります。工事費用が思った以上にかかってしまったり、想定していなかった問題が発生したりするケースは決して珍しくありません。
この記事では、2階のエアコンと1階の室外機という組み合わせで生じる具体的なデメリットから、それらを解決するための実践的な対策まで、包括的にお伝えしていきます。
2階にエアコン1階に室外機のデメリット|対策ガイド

まずは2階のエアコンと1階の室外機という組み合わせで生じる主要なデメリットについて詳しく見ていきましょう。
配管延長による影響から設置費用の増加まで、事前に知っておくべき重要なポイントを順番に解説していきます。
2階のエアコンの室外機はどこに置く?
まず基本的な考え方をお伝えすると、室外機は室内機と同じ階か、できるだけ近い位置に設置するのが理想的です。具体的には、室内機との距離が4メートル以内に収まるのがベストですね。
2階のエアコンの室外機設置場所として、一般的には以下の6つのパターンが考えられます。
最も標準的なのは、2階のベランダに地面置きで設置する方法です。水平確保がしやすく、メンテナンスも楽になります。ただし、ベランダが狭い場合や、洗濯物干しスペースを確保したい場合には不向きかもしれません。
ベランダ天井からの天吊り設置も選択肢の一つです。床面積を有効活用できる反面、南向きのベランダでは室外機に直射日光が当たりやすく、電力効率が低下する可能性があります。
外壁への壁面取り付けは、ベランダがない部屋でも設置可能です。しかし、高所作業となるため設置費用が高額になりがちで、足場が必要な場合は十数万円の追加費用がかかることもあります。
屋根置きは室内機との距離を最短にできるメリットがありますが、直射日光や雨風の影響を直接受けるため、室外機の劣化が早まるリスクがあります。
2台の室外機を上下に重ねる二段置きは、設置スペースの節約には効果的です。ただし、下段の室外機は上方向への通気が制限され、冷却効率が低下してしまいます。
最後に、1階地面への立ち下ろし設置があります。こちらは今回のテーマである「2階にエアコン、1階に室外機」の設置方法ですね。ベランダや屋根がなくても設置できる反面、配管が長くなることで様々なデメリットが生じます。
どの設置方法を選ぶかは、住宅の構造や環境、予算によって決まります。次の章では、それぞれの方法の騒音面について詳しく見ていきましょう。
室外機を2階に設置するとうるさい?

室外機の騒音問題は、特に2階設置の場合により深刻になることがあります。なぜなら、2階は隣家の窓や寝室に近い位置にあることが多く、音が響きやすい環境だからです。
室外機の騒音レベルは、一般的に40~50デシベル程度とされています。これは図書館内の静寂レベルから、エアコンの室内機の運転音程度に相当します。数値だけ見ると大したことないように思えますが、実際の生活では振動や共鳴によって体感的な騒音が増大することがあるんです。
2階設置で特に問題となるのは、床への振動伝達です。室外機の振動が床を通じて建物全体に伝わり、1階の部屋でも「ブーン」という低周波音が聞こえることがあります。特に木造住宅では、この現象が顕著に現れやすいと言えるでしょう。
壁面設置の場合は、外壁への振動伝達により、室内に音が響くケースがあります。防振ゴムである程度抑えることはできますが、完全に解消するのは難しいのが現実です。
天吊り設置では、ベランダの天井材質によって音の反響具合が変わります。コンクリート製であれば比較的音は抑えられますが、薄い鉄板などの場合は音が増幅されることもあります。
一方で、1階地面への設置は騒音面では有利です。地面に直接設置することで振動が分散され、建物への伝達が最小限に抑えられます。また、隣家の生活空間からも離れやすく、近隣トラブルのリスクを軽減できます。
ただし、どの設置方法でも定期的なメンテナンスは欠かせません。室外機内部の汚れやファンの不具合は騒音の原因となるため、年に1回程度の清掃や点検をおすすめします。
騒音対策として最も効果的なのは、設置時の基礎工事をしっかり行うことです。水平設置の徹底と適切な防振対策により、多くの騒音問題は解決できます。
配管延長による効き問題

2階のエアコンと1階の室外機を配管でつなぐ場合、配管の長さが標準の4メートルを大幅に超えることになります。一般的に2階から1階への配管は6~8メートル程度必要で、この延長が冷暖房の効きに影響を与えるのは避けられません。
配管が長くなることで最も問題となるのは、冷媒ガスの循環効率低下です。冷媒は室内機と室外機の間を循環することで熱交換を行いますが、配管が長いとその過程で熱の損失が発生します。特に夏場の冷房時は、配管内を通る冷気が外気温の影響でぬるくなり、室内を冷やす力が弱まってしまいます。
暖房時も同様で、ヒートロスにより効率が下がります。冬場に「エアコンをつけても暖かくならない」と感じる原因の一つが、まさにこの配管延長による熱損失なんです。
配管延長による具体的な影響として、エアコンの起動から設定温度に達するまでの時間が長くなることが挙げられます。通常であれば10~15分で快適な温度になるところが、20~30分かかることも珍しくありません。
また、冷媒ガスの量も重要な要素です。メーカーが設定している標準の冷媒量は、4メートル程度の配管を前提としています。6メートル以上の延長を行う場合は、追加でガスチャージ(冷媒補充)が必要になることが多いです。
ガスチャージを行わずに長い配管で運転を続けると、室外機に過度な負担がかかります。コンプレッサーが必要以上に働くことになり、電気代の増加や早期故障のリスクが高まってしまいます。
ただし、メーカーが定める有効配管長の範囲内であれば、適切な施工とガス管理により問題は最小限に抑えられます。例えば、チャージレス10メートル、最大15メートルまで対応の機種であれば、10メートル以内なら追加のガス補充なしでも正常に動作します。
横引き配管の場合は、さらに注意が必要です。配管が水平に長く伸びると、ドレンホースの排水不良により水漏れのリスクが増大します。適切な勾配を確保しないと、最悪の場合はエアコン内部の電子基板が漏電で故障することもあります。
これらの問題を軽減するためには、配管ルートの最適化と断熱材の充実が欠かせません。配管カバーの設置も、外観保護だけでなく断熱効果向上の観点から重要と言えるでしょう。
室外機が遠い
年間6,000〜12,000円の負担増
年間18,000〜30,000円の負担増
運転時間延長で更なる電気代増
室内機と室外機の距離が離れることで生じる問題は、単に配管が長くなるだけにとどまりません。距離が遠いことによる様々な影響について詳しく見ていきましょう。
まず電力効率の観点から考えると、距離が離れるほどエネルギーロスが増大します。冷媒を循環させるために室外機のコンプレッサーがより多くの電力を消費し、結果として電気代が上昇します。4メートルの距離と8メートルの距離では、年間で数千円から1万円程度の電気代差が生じることもあります。
メンテナンス面でも課題があります。室外機が1階にあると、2階の室内機に不具合が生じた際の原因特定が困難になりがちです。故障時の修理作業も、技術者が室内機と室外機を往復しながら点検する必要があり、作業時間が長くなる傾向にあります。
配管の劣化も距離に比例して進行しやすくなります。長い配管は紫外線や風雨、温度変化の影響を受ける面積が広く、結果として配管の寿命が短くなる可能性があります。特に配管カバーを設置していない露出配管の場合は、5~8年程度で交換が必要になることもあります。
冷媒ガスの管理も複雑になります。距離が離れていると微細なガス漏れの発見が遅れがちで、知らないうちに冷媒不足となり、エアコンの性能低下や室外機の故障につながることがあります。
工事費用の面でも影響があります。配管延長により材料費が増加するのはもちろん、高所作業や特殊な配管ルートが必要な場合は人件費も上昇します。標準工事費に加えて2~3万円の追加費用がかかるのが一般的です。
ただし、距離が遠いことによるメリットもあります。室外機を1階に設置することで、ベランダのスペースを有効活用できます。また、室外機の音や振動が居住空間から離れるため、騒音問題の軽減にもつながります。
将来的なリフォームや増設を考えた場合も、1階に室外機があることで作業がしやすくなることがあります。例えば、追加でエアコンを設置する際に二段置き架台を利用しやすくなります。
距離の問題を最小限に抑えるためには、配管ルートの最適化が重要です。可能な限り直線的で短いルートを選び、不要な曲がりや高低差を避けることで、性能低下を抑制できます。
室外機のダメな置き方
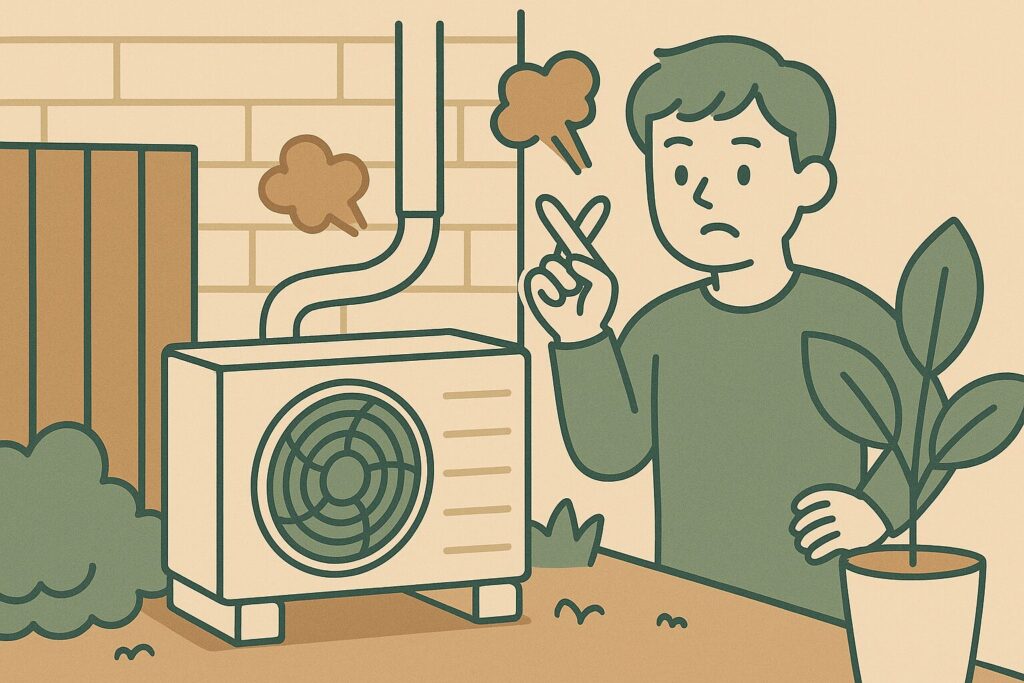
室外機の設置場所や方法を誤ると、エアコンの性能低下や故障の原因となります。特に2階から1階への設置では、通常の設置方法とは異なる注意点があるため、避けるべき置き方について詳しく解説します。
最も避けるべきなのは、直射日光が長時間当たる場所への設置です。室外機は熱交換器を内蔵しており、本体温度が上昇すると冷却効率が著しく低下します。特に南向きや西向きの場所では、夏場に室外機内部が50度以上になることもあり、エアコンが正常に動作しなくなる可能性があります。
通気スペースの不足も深刻な問題です。室外機の周囲には、左右・背面に25センチ以上、前方に25センチ以上のスペースが必要です。壁際にぴったりと設置したり、物置や植栽で囲まれた場所に置いたりすると、熱がこもってしまい冷却能力が大幅に低下します。
水平設置ができていない場合も問題となります。室外機が傾いて設置されていると、内部の冷媒が適切に循環せず、振動や騒音の原因にもなります。特に屋根置きや二段置きの場合は、専用の架台を使用して確実に水平を保つ必要があります。
雨水の浸入リスクが高い場所への設置も避けるべきです。室外機は防水設計されていますが、横殴りの雨や台風時の大量の雨水が内部に侵入すると、電子部品の故障や漏電事故につながる恐れがあります。
配管の取り回しが不適切な場合も多くの問題を引き起こします。配管に無理な曲げや圧迫がかかると、冷媒の流れが阻害されます。また、ドレンホースに適切な勾配がついていないと、排水不良により水漏れが発生することがあります。
隣家境界線からの距離が不十分な設置も、近隣トラブルの原因となります。室外機の運転音や排出される温風が隣家に迷惑をかけることがないよう、適切な距離を保つ必要があります。
地面が不安定な場所への設置も危険です。軟弱地盤や傾斜地では、室外機の重量により地盤沈下や転倒のリスクがあります。必要に応じてコンクリート基礎を設置し、安定した土台を確保することが大切です。
配管の露出状態で長期間放置することも避けるべきです。むき出しの配管は紫外線による劣化が進みやすく、美観上も好ましくありません。配管カバーの設置により、劣化防止と外観改善の両方を図ることができます。
これらの問題を避けるためには、設置前の現地調査が欠かせません。専門業者に依頼し、建物の構造や周辺環境を総合的に判断してもらうことで、最適な設置方法を選択できます。
電気代は上がる?
2階のエアコンと1階の室外機という組み合わせは、残念ながら電気代の上昇を避けることができません。その理由と具体的な影響について詳しく説明していきます。
配管延長による電力消費増加が最も大きな要因です。室内機と室外機の距離が離れることで、冷媒を循環させるために室外機のコンプレッサーがより多くの電力を必要とします。6~8メートルの配管延長により、通常より10~20%程度の電力消費増加が見込まれます。
具体的な金額でお伝えすると、6畳用エアコンの場合、標準設置と比較して月額500~1,000円程度の電気代上昇が考えられます。14畳用の大型エアコンであれば、月額1,500~2,500円程度の差が生じることもあります。年間で計算すると、かなりの金額差になることがお分かりいただけるでしょう。
冷媒ガスの不足も電気代上昇の原因となります。配管延長に対して適切なガスチャージが行われていない場合、室外機は設定温度に達するまでにより長時間運転することになります。特に冷房時は、ガス不足により冷却能力が30~50%も低下することがあり、その分長時間運転による電力消費が増加します。
熱損失による効率低下も見逃せません。長い配管を通る間に冷媒の温度が外気温の影響を受け、本来の性能を発揮できなくなります。夏場の炎天下では配管内の冷媒温度が上昇し、冬場は放熱により温度が低下してしまいます。
室外機の設置環境による影響もあります。1階地面設置の場合、直射日光を避けやすい反面、地面からの照り返しや周囲の構造物による風通しの悪化により、室外機の冷却効率が低下することがあります。
ただし、電気代上昇を最小限に抑える方法もあります。まず重要なのは、適切なガスチャージです。配管延長に応じた冷媒量の調整により、エアコン本来の性能を維持できます。
配管の断熱強化も効果的です。厚手の断熱材や配管カバーの使用により、熱損失を最小限に抑えることができます。特に横引き配管の部分は、断熱材の重要性が高くなります。
室外機の設置位置選択も電気代に大きく影響します。風通しが良く、直射日光を避けられる場所を選ぶことで、室外機の負担を軽減し、電力消費を抑制できます。
定期メンテナンスの実施も欠かせません。室外機の清掃やフィルターの交換により、常に最適な状態を維持することで、無駄な電力消費を避けることができます。
エアコンの使用方法を見直すことも重要です。設定温度を1度調整するだけで、10%程度の電力消費削減が可能です。また、タイマー機能を活用し、無駄な運転時間を削減することも効果的と言えるでしょう。
2階にエアコン1階に室外機のデメリット|解決法
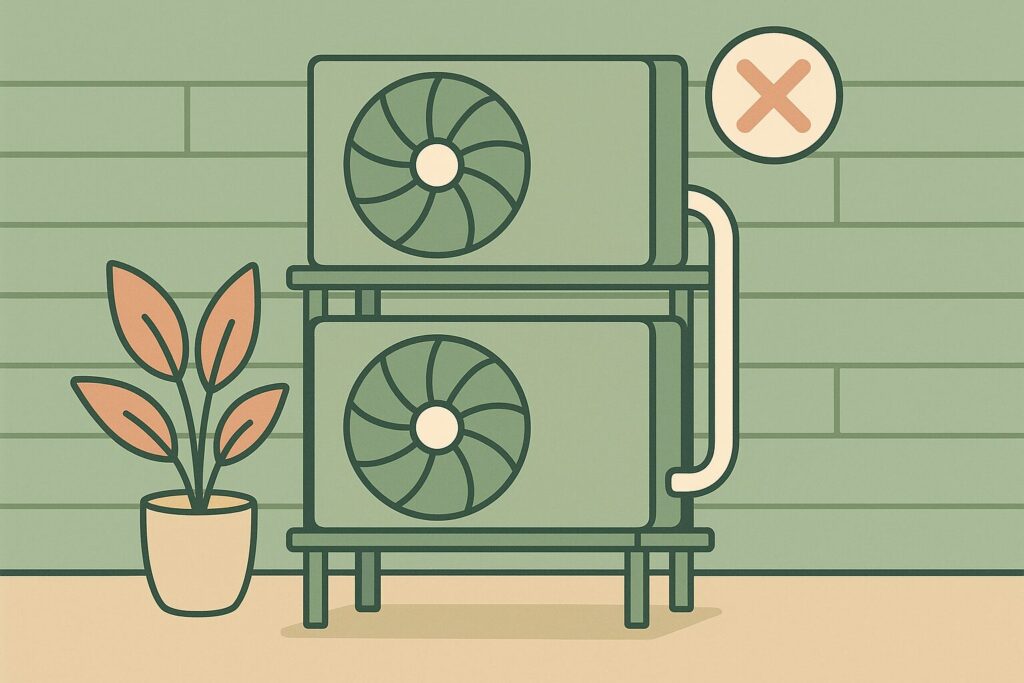
ここからは、前章で取り上げたデメリットを軽減したり解決したりするための具体的な方法をご紹介します。
二段置きやマルチエアコンなど、様々な選択肢の中から最適な解決策を見つけていきましょう。
室外機の二段置き
室外機の設置スペースが限られている場合の有効な解決策として、二段置きという方法があります。これは2台の室外機を上下に重ねて設置する方法で、1台分のスペースで2台分の室外機を配置できる優れた手法です。
二段置きの最大のメリットは、設置面積の大幅な節約です。通常であれば2平方メートル程度必要な設置スペースを、約1平方メートルに圧縮できます。狭小住宅や都市部のマンションなど、スペースに制約がある環境では非常に有効な解決策と言えるでしょう。
設置方法としては、専用の二段置き架台を使用します。下段の室外機に専用の架台を取り付け、その上に上段の室外機を固定する構造です。架台は十分な強度を持ち、上段室外機の重量と振動に耐えられる設計となっています。
工事費用については、既設の室外機2台を二段化する場合、基本脱着費用が8,000~12,000円×2台、二段置き架台が15,000~20,000円、配管延長が必要な場合は別途費用がかかり、合計で30,000~40,000円程度が相場となります。
ただし、二段置きにはいくつかのデメリットもあります。最も大きな問題は、下段室外機の通気不足です。上段の室外機により上方向への排熱が妨げられ、冷却効率が10~20%程度低下することがあります。
振動や騒音の増加も懸念材料です。2台の室外機が同時に運転すると、振動が重なり合い、単体設置時より大きな音が発生することがあります。特に深夜や早朝の運転時は、近隣への配慮が必要になります。
メンテナンス性の悪化も見逃せません。下段の室外機は上段に遮られ、清掃や点検作業が困難になります。フィルターの交換や内部清掃の際は、上段室外機を一時的に移動させる必要が生じることもあります。
安全性の観点では、上段室外機の落下リスクがあります。地震や強風時の揺れにより、固定が緩む可能性があるため、定期的な点検と締め直しが必要です。
これらの問題を軽減するためには、適切な架台選択が重要です。通気性を考慮した設計の架台を選び、下段室外機の排熱経路を確保することで、効率低下を最小限に抑えられます。
振動対策としては、防振ゴムの設置が効果的です。架台の接地部分や室外機の固定部分に防振材を使用することで、振動の伝達を抑制できます。
定期点検の頻度を上げることも大切です。月1回程度の外観点検と、年2回程度の専門業者による詳細点検により、問題の早期発見と対処が可能になります。
二段置きは確かに有効な解決策ですが、設置環境や使用条件によってはデメリットが大きくなることもあります。導入前には専門業者と十分に相談し、メリットとデメリットを総合的に判断することをおすすめします。
室外機を壁掛けする

ベランダや地面に設置スペースがない場合の解決策として、壁掛け設置という方法があります。これは建物の外壁に専用の架台を取り付け、室外機を空中に固定する設置方法で、スペース効率の観点から注目されています。
壁掛け設置の最大のメリットは、地面スペースを全く使用しないことです。ベランダがない部屋や、庭のスペースを有効活用したい場合には理想的な解決法と言えるでしょう。また、地面からの照り返しや湿気の影響を受けにくく、室外機の動作環境としては良好な条件を提供できます。
設置可能な条件として、まず外壁の構造強度が重要です。室外機の重量は30~50キログラム程度あり、運転時の振動も加わるため、十分な耐荷重性能を持つ壁面である必要があります。木造住宅の場合は構造材への確実な固定が、鉄筋コンクリート造の場合は適切なアンカーボルトの使用が必要です。
工事費用は設置高度により大きく変動します。1階部分の壁面であれば脚立作業で済むため、34,000~45,000円程度が相場です。しかし、2階以上の高所になると足場設置が必要となり、工事費用は60,000~120,000円程度まで跳ね上がることがあります。
設置高度による制約もあります。一般的な工事業者では、安全性の観点から地面から3メートル程度までの高さに制限している場合が多いです。それ以上の高さでは、特殊な高所作業車や本格的な足場設置が必要となり、費用対効果が悪化します。
隣家との距離も重要な考慮事項です。壁掛け設置を行う際は、長尺脚立を75度の角度で設置する必要があり、隣家との距離が狭すぎると作業が不可能になります。都市部の住宅密集地では、この制約により壁掛け設置を断念せざるを得ないケースもあります。
振動伝達の問題も見逃せません。室外機の振動が外壁を通じて建物内部に伝わり、「ブーン」という低周波音が室内に響くことがあります。特に寝室に近い壁面への設置では、睡眠の妨げとなる可能性があります。
この問題の対策として、防振ゴムの使用が効果的です。室外機と架台の間、架台と壁面の間に防振材を挟むことで、振動の伝達を大幅に軽減できます。
排水処理も重要な検討事項です。壁掛け設置の場合、ドレンホースを室外機の下から地面まで延長する必要があります。ホースの取り回しルートや排水先の確保について、事前に十分な検討が必要です。
メンテナンス性については、地上設置と比較して作業が困難になります。清掃や点検の際は脚立や高所作業車が必要となり、メンテナンス費用が高くなる傾向があります。
美観上の配慮も必要です。外壁の色や材質に合わせた架台の選択により、建物の外観への影響を最小限に抑えることができます。白やグレー系の色調を選ぶことで、多くの住宅外壁に調和させることが可能です。
壁掛け設置は確かに有効な解決策ですが、建物構造や周辺環境によっては実現困難な場合もあります。検討段階で専門業者による現地調査を受け、技術的な実現可能性と費用対効果を慎重に判断することが大切です。
室外機1つにエアコン2つのマルチエアコン

複数の部屋にエアコンを設置したい場合の革新的な解決策として、マルチエアコンという選択肢があります。これは1台の室外機に最大5台までの室内機を接続できるシステムで、室外機の設置スペース問題を根本的に解決できる方法です。
マルチエアコンの最大の魅力は、圧倒的な省スペース性です。通常であれば複数台の室外機が必要なところを1台に集約できるため、ベランダや庭のスペースを大幅に節約できます。見た目もすっきりとし、建物の外観を損ねることがありません。
各部屋の個別温度制御が可能なことも大きなメリットです。リビングは22度、寝室は25度といったように、部屋ごとに異なる温度設定ができます。家族それぞれの好みに合わせた快適環境を実現できるのは魅力的ですね。
室内機の種類を自由に組み合わせできる点も注目に値します。リビングには一般的な壁掛けタイプ、和室には目立たない天井埋込型、書斎にはコンパクトな床置き型など、部屋の用途や内装に合わせて最適な室内機を選択できます。
起動の早さも特徴の一つです。他の室内機が稼働中であれば、新たに電源を入れた室内機から即座に温風や冷風が出てきます。冬場の暖房立ち上がり時間の短縮は、日常生活の快適性向上に直結します。
年間の電力消費量については、ダイキンのPAC-403AV(室内機2台セット)の場合、1,351kWhとなっており、月平均の運転コストは約3,377円程度です。個別エアコンを複数台設置する場合と比較すると、使用状況によっては電気代の節約効果も期待できます。
しかし、マルチエアコンにはいくつかの注意すべきデメリットもあります。最も大きなリスクは、室外機故障時の影響範囲です。室外機が1台しかないため、故障すると接続されている全ての室内機が使用不可能になります。真夏や真冬の故障は生活に深刻な影響を与える可能性があります。
電気代については、使用状況により個別エアコンより高くなる場合があります。1部屋だけを使用する場合でも室外機は全体を管理して動作するため、余分な電力消費が発生することがあります。
同時運転時の性能低下も懸念材料です。複数の室内機を同時に動かすと、1台の室外機では負荷が大きくなり、個々の室内機の冷暖房パワーが低下することがあります。特に真夏日に全室でフル稼働させると、期待した冷房効果が得られないケースもあります。
設置工事の複雑さも課題の一つです。複数の室内機への配管を1台の室外機から分岐させるため、配管ルートが複雑になり、工事期間が長くなる傾向があります。また、専門的な技術が必要なため、対応できる業者が限られることもあります。
初期費用の高さも見逃せません。マルチエアコンシステム自体の価格が個別エアコンより高く、さらに専用の電源工事(200V屋外電源)が必要になるため、総工事費用が高額になりがちです。
メーカーや機種の選択肢が限定的なことも制約要因です。マルチエアコンを製造しているメーカーは限られており、家電量販店でも取り扱いが少ないのが現状です。私が働いている店舗でも、ダイキンのみの取り扱いとなっています。
これらのデメリットを軽減するためには、いくつかの対策が有効です。まず、使用方法を工夫することで負荷を分散できます。全室同時使用を避け、必要な部屋から順番に使用することで、室外機への負担を軽減できます。
ピーク時間帯の使用を避けることも効果的です。電力需要の高い時間帯を避けて運転することで、電力効率の改善と電気代の節約を両立できます。
定期的な専門メンテナンスの実施も重要です。複雑なシステムだからこそ、年2回程度の専門業者による点検を受けることで、トラブルの早期発見と予防が可能になります。
万が一の故障に備えて、予備の冷暖房器具を準備しておくことも賢明です。扇風機やヒーターなど、簡易的でも代替手段があれば、室外機故障時の影響を最小限に抑えられます。
マルチエアコンは確かに魅力的なシステムですが、ライフスタイルや住宅環境によって向き不向きがあります。導入を検討される際は、メリットとデメリットを十分に理解した上で、専門業者と相談しながら最適な選択をしていただければと思います。
アパート2階部屋の場合
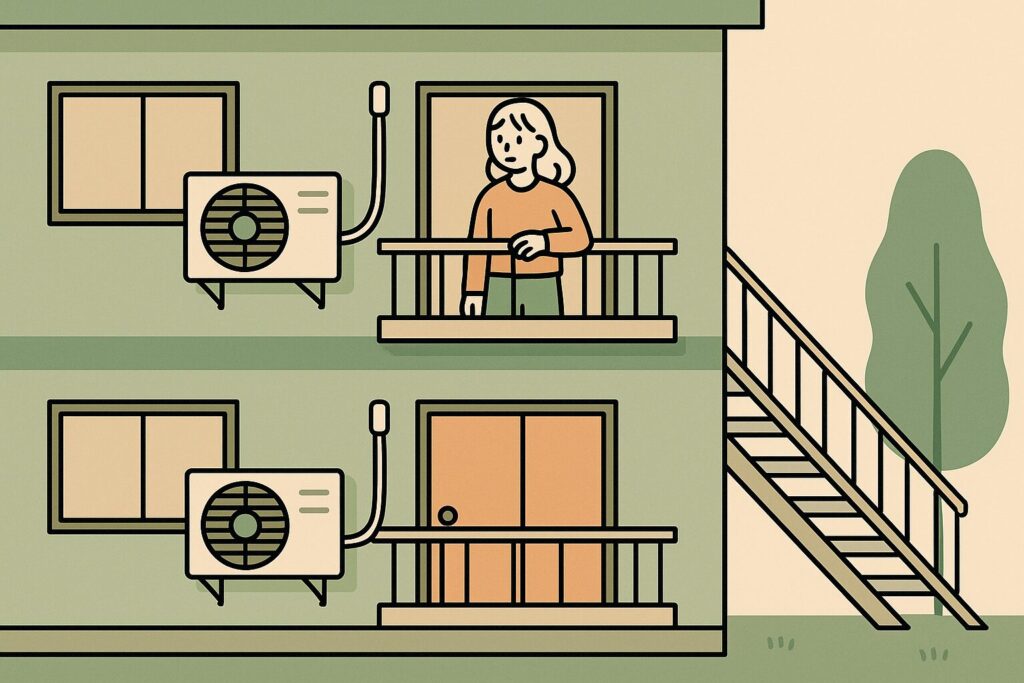
アパートやマンションの2階部屋では、戸建て住宅とは異なる特殊な制約があります。賃貸物件特有の制限や近隣住民への配慮など、注意すべき点が多岐にわたるため、詳しく解説していきます。
まず最も重要なのは、管理会社や大家さんからの許可取得です。エアコン設置工事は建物に穴を開けたり、外壁に架台を取り付けたりする場合があるため、事前の許可が必須となります。無許可での工事は契約違反となり、トラブルの原因になりかねません。
共用部分への室外機設置は原則として禁止されています。廊下や階段部分は共用スペースのため、室外機を設置することはできません。専用使用権のあるベランダ部分のみが設置可能エリアとなります。
隣室との距離制限も重要な考慮事項です。室外機の運転音や排出される温風が隣の部屋に影響しないよう、適切な距離を保つ必要があります。特に窓際への設置では、隣室の窓から1メートル以上離すのが望ましいとされています。
ベランダの使用制限についても確認が必要です。多くの賃貸物件では、ベランダの一部を避難経路として確保することが義務付けられており、室外機設置により避難の妨げとならないよう配慮しなければなりません。
設置スペースの寸法確認も欠かせません。室外機設置には最低でも奥行490~550ミリメートル、横幅900~1,000ミリメートル、高さ700~750ミリメートルのスペースが必要です。ベランダが狭い場合は、コンパクトタイプの室外機を選択する必要があります。
壁面取り付けの許可確認も重要です。ベランダに設置スペースがない場合、外壁への壁掛け設置を検討することがありますが、これには建物の構造上の許可と、美観上の配慮が必要になります。
埋没配管の有無も確認すべき点です。新築のアパートでは、建築時にエアコン用の隠蔽配管が設置されている場合があります。これを利用できれば、外観を損ねることなくエアコンを設置できます。
騒音対策は近隣関係に直結する問題です。深夜や早朝の運転音が隣室に迷惑をかけないよう、防振ゴムの使用や運転時間の配慮が必要です。特に木造アパートでは振動が伝わりやすいため、より慎重な対策が求められます。
退去時の原状復帰義務も考慮しなければなりません。エアコン設置により開けた穴の補修や、取り付けた架台の撤去など、入居時の状態に戻す義務があります。これらの費用も含めて設置を検討する必要があります。
1階への室外機設置を検討する場合は、より複雑な許可手続きが必要になります。1階の専有部分や共用部分への設置は、他の住民や管理組合の同意が必要になることが多く、実現が困難な場合が少なくありません。
これらの制約を踏まえた上で、アパート2階での最適な解決策を考えてみましょう。最も現実的なのは、ベランダ内での工夫です。天吊り設置や壁面設置により、限られたスペースを有効活用することができます。
どうしてもベランダに設置できない場合は、窓用エアコンという選択肢もあります。工事が不要で、退去時の原状復帰も簡単なため、賃貸物件では有力な選択肢となります。
アパートでのエアコン設置は制約が多く複雑ですが、事前の十分な調査と関係者との協議により、多くの問題は解決できます。不明な点があれば、管理会社や専門業者に相談し、トラブルのない設置を心がけることが大切です。
総括:2階にエアコン設置で1階に室外機のデメリット
それでは最後に、この記事の内容をまとめます。