日立エアコンの凍結洗浄機能について調べていると、メリットばかりが強調されがちですが、実際にはいくつかのデメリットも存在します。電気代の上昇や運転音の問題、そして意外にもカビ発生のリスクなど、購入前に知っておきたい注意点があるのも事実です。
私も家電量販店で働く中で、お客様から凍結洗浄に関する様々なご質問やご相談をいただきます。特に多いのが「本当に効果があるの?」「音はうるさくないの?」といった不安の声です。また、実際に使用されているお客様からは「思っていたより電気代がかかる」「カビ臭くなった」といった体験談もお聞きしています。
凍結洗浄は確かに画期的な技術ですが、その仕組みや限界を正しく理解せずに使用すると、期待した効果が得られないだけでなく、かえってトラブルの原因となることもあります。
この記事では、日立エアコンの凍結洗浄機能における具体的なデメリットと、それらを最小限に抑えるための対策方法について詳しくお伝えします。購入を検討されている方はもちろん、すでにお使いの方にも役立つ情報をご紹介していきます。
日立エアコンの凍結洗浄機能のデメリット|考えられる原因

凍結洗浄機能は魅力的な技術ですが、使用する上で知っておきたいデメリットがいくつか存在します。
ここでは電気代の上昇やカビ発生、運転音の問題など、実際に報告されている課題とその原因について詳しく見ていきましょう。
凍結洗浄の効果と基本的な仕組み
日立エアコンの凍結洗浄は、熱交換器を凍らせて霜を付け、その霜を一気に溶かして汚れを洗い流す画期的な機能です。この独自技術により、エアコン内部を清潔な状態に保ち、ホコリによる性能低下を防ぐことができます。
動作プロセスは約20~120分間かけて行われます。まずファンを逆回転させてホコリを熱交換器や排水トレーへ集め、次に急速冷却で熱交換器に大量の霜をつけます。そして一気に解凍して汚れを洗い流し、最後に乾燥させて完了となります。
2025年現在のXシリーズでは、さらに進化した「凍結洗浄除菌ヒートプラス」を搭載しています。高温加熱で油汚れを軟化させてから凍結洗浄を行うため、従来では落としにくかった料理由来の油汚れまで効果的に除去できるのです。
ただし、汚れやカビをすべて洗い流せるわけではありません。熱交換器の表面汚れには効果的ですが、ファンやドレンパンといった奥の部分には限界があります。そのため、定期的な専門クリーニングとの併用が推奨されています。
電気代の上昇と運転コスト
凍結洗浄機能を利用すると、通常運転よりも電力消費が増加するというデメリットがあります。実際のデータを見ると、洗浄運転時の消費電力は通常運転の約1.5倍程度になるケースが報告されています。
具体的な電気代への影響は、使用頻度によって変わります。一般的に凍結洗浄を頻繁に行う場合、年間で約1,000~3,000円程度の追加コストがかかるとされています。しかし、これは使用環境や設定によって大きく異なります。
興味深いことに、情報源によって電気代への見解が分かれています。一部では年間400~500円程度と比較的低い追加コストとする見解もあり、むしろ熱交換器が清潔に保たれることで無駄な消費電力を抑える節電効果が期待できるという意見もあります。
実際の消費電力の一例として、外気温度35℃、室内温度28℃の条件下で、業務用モデルでは最大消費電力量1.3kWh/回という数値が公表されています。家庭用モデルではこれより少なくなりますが、それでも通常運転と比べると電力消費の増加は避けられません。
凍結洗浄後のカビ発生リスク

凍結洗浄を行った後にカビが発生するという報告が複数寄せられています。これは一見矛盾しているように感じられますが、実際にはいくつかの理由が考えられます。
最も大きな原因は、凍結洗浄後の乾燥不足です。凍結・解凍プロセスでエアコン内部の湿度が一時的に高まり、その後の乾燥が不十分だとカビの繁殖条件が整ってしまいます。特に夏場の高湿度環境では、この傾向が顕著に現れるようです。
実際のユーザーからは「凍結洗浄を行ったらカビ臭くなった」「6月から使い始めて臭いはなかったのに、凍結洗浄後にカビ臭い臭いがしてきた」という声が報告されています。また、設置から3年以内のエアコンでも、凍結洗浄機能を使用していたにもかかわらず内部にカビが発生したケースも確認されています。
対策としては、凍結洗浄後に必ず送風運転や暖房運転で内部をしっかり乾燥させることが効果的です。また、冷房運転後には毎回内部乾燥を行うことで、カビの発生リスクを大幅に軽減できます。
運転音がうるさい?
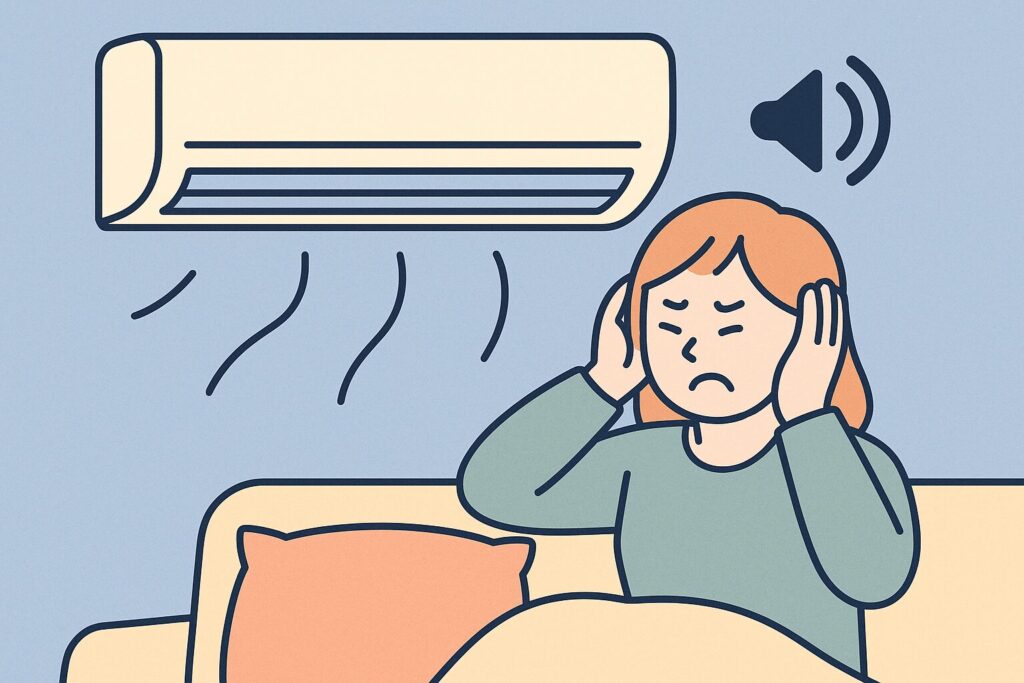
凍結洗浄の動作中は、通常運転時よりも大きな音が発生することがあります。特に夜間に自動で凍結洗浄が作動すると、音が気になって眠りを妨げられるという声が寄せられています。
具体的には、凍結・解凍する際の温度変化で「ピキピキ」「パキパキ」という音や、冷媒が流れる際の「シャー」という音が発生します。これらの音は故障ではありませんが、静音性を重視する家庭では配慮が必要でしょう。
音の問題は設置環境や個人の感受性によって大きく左右されます。昼間であれば気にならない程度の音でも、夜間の静かな環境では気になることが多いようです。実際に「凍結洗浄の運転音が夜中だと気になる」という口コミも複数確認されています。
対策としては、タイマー設定を活用して夜間の運転を避けることができます。また、凍結洗浄の開始時刻を設定できる機種では、在宅時や昼間の時間帯に動作するよう調整することで、音の問題を軽減できます。
壊れやすい?
凍結洗浄機能は繰り返しの凍結・解凍プロセスを行うため、エアコン内部の部品に負荷をかけやすいという懸念があります。特に電子基盤や金属パーツへの影響が長期使用で指摘されています。
洗浄時に発生する結露水も、部品劣化のリスク要因となります。適切に処理されない結露水が内部に残ると、電子部品の腐食や動作不良を引き起こす可能性があります。また、凍結洗浄を中途半端に中止すると、乾燥工程まで進まない結露水がエアコン内部に残り、かえって部品劣化やカビ発生を早める恐れもあります。
ただし、これらのリスクは適切な使用方法を守ることで大幅に軽減できます。凍結洗浄を途中で停止せず最後まで完了させること、定期的なメンテナンスを怠らないことが大切です。
実際の故障率や耐久性に関する具体的なデータは限られていますが、適切な使用と定期的なメンテナンスを行えば、通常のエアコンと同程度の耐久性は期待できると考えられます。むしろ熱交換器が清潔に保たれることで、本体の負荷軽減につながる面もあります。
日立エアコンの凍結洗浄機能のデメリット|真相と対策

デメリットの原因が分かったところで、次はそれらの真相と具体的な対策方法をご紹介します。
適切な使い方や日常のメンテナンスにより、多くの問題の軽減につながるはずです。
頻度はどのくらい?
凍結洗浄の実行頻度は、エアコンの累積運転時間によって自動的に決まります。基本的には冷房や暖房の運転時間が42時間経過後、運転を停止すると自動で洗浄が開始されます。これは約週1回程度のペースに相当します。
上位機種では、搭載されているカメラセンサーが汚れの蓄積状況を判断し、汚れが溜まりにくい環境だと検知した場合には84時間まで延長される仕組みになっています。この機能により、無駄な洗浄を避けて電力消費を抑制できます。
ただし、使用環境によってはこの標準的な頻度では不十分な場合があります。キッチン近くに設置されたエアコンや、ペットがいる家庭、喫煙環境などでは、より頻繁な洗浄が必要になることもあります。
手動での凍結洗浄も可能で、リモコンの「凍結洗浄」ボタンを押すだけで即座に開始できます。汚れやニオイが気になる時期や、長期間使用しなかった後などは、手動で洗浄を行うことをおすすめします。カビが発生しやすい梅雨時期や、油汚れが蓄積しやすい冬場の鍋料理シーズンなどは、特に注意が必要でしょう。
つけっぱなしでも大丈夫?

凍結洗浄はエアコンの運転停止後に動作する機能のため、つけっぱなし運転では実行されません。そのため、24時間連続運転を行っている場合は、定期的に運転を停止して凍結洗浄を実行させる必要があります。
つけっぱなし運転を続けると、熱交換器にホコリや汚れが蓄積し続けることになります。これにより冷暖房効率が徐々に低下し、結果的に電気代の増加や性能低下につながる可能性があります。
対策としては、週に1回程度は運転を停止し、凍結洗浄を実行させることが推奨されます。また、つけっぱなし運転中でも、定期的なフィルター掃除や室内の換気を行うことで、汚れの蓄積を抑制できます。
特に夏場の連続冷房運転では、エアコン内部の湿度が高い状態が続きやすくなります。そのため、可能な限り短時間でも運転を停止し、内部乾燥や凍結洗浄を実行させることが、長期的な性能維持には欠かせません。省エネ効果を求めてつけっぱなしにする場合でも、エアコンの健康状態を保つための配慮が必要です。
実際の口コミと評判
-
凍結洗浄は万能ではないため、2-3年に一度はプロクリーニングが必要
-
凍結洗浄後は必ず送風運転で内部を乾燥させる
-
タイマー設定で夜間の運転音を避ける
-
フィルター掃除は自動機能があっても月1回は確認
-
梅雨時期や高湿度環境では特に注意が必要
私が家電量販店で働いている中で、お客様から直接伺った凍結洗浄に関する生の声をご紹介します。良い評価と気になる点の両方をバランスよくお聞きしています。
まず満足度の高い声として、「3年使っているが熱交換器の汚れが他社に比べて明らかに少ない」「凍結洗浄後にニオイが改善された」「フィルター掃除の頻度が減った」といった意見があります。また、「音が静かで夜でも気にならない」「23年故障なしで使えてコスパが良い」「冷暖房のパワーが抜群」など、基本性能への高い評価も多く寄せられています。
一方で気になる点として、「凍結洗浄の運転音が夜中だと気になる」「凍結洗浄後もカビ臭いことがある」「凍結洗浄が終わるまで時間がかかる」といった声もあります。特に「ファン部分のカビは取れていない」という指摘は、凍結洗浄の限界を表している重要な意見だと思います。
また、「水漏れが発生することがある」「設定が複雑で分かりにくい」「本体価格が他社より2-4万円高い」という実用面での課題も挙げられています。これらの口コミから、凍結洗浄は確実に効果がある一方で、万能ではないことが分かります。
正しいやり方で凍結洗浄効果を最大化
凍結洗浄の効果を最大限に引き出すためには、適切な動作条件を理解することが大切です。室内温度が16℃以上、外気温が5℃以上という基本条件を満たさないと、凍結洗浄は正常に動作しません。
特に重要なのは、凍結洗浄後の乾燥プロセスです。洗浄が完了した後は、必ず送風運転や暖房運転で内部をしっかり乾燥させてください。これにより、カビの発生リスクを大幅に軽減できます。夏場に凍結洗浄を行った後は、短時間でも構わないので暖房運転を行うことをおすすめします。
タイマー設定を活用することで、運転音が気にならない時間帯に凍結洗浄を実行できます。在宅時や昼間の時間帯に設定することで、夜間の音の問題を避けられます。
また、凍結洗浄中は窓や戸を開放しないよう注意してください。湿気が室内に流入すると、露が付いて家財を濡らす原因になることがあります。室外機の凍結洗浄は工場出荷時には設定されていないため、必要に応じて手動で設定を行う必要があります。
デメリットを補う日常メンテナンス
送風運転
汚れ確認
掃除
凍結洗浄の限界を補うためには、日常的なメンテナンスが欠かせません。最も基本的なのはフィルター掃除で、自動お掃除機能が付いていても月1回は汚れ具合を確認することをおすすめします。
フィルターの目詰まりを取り除くだけで、約5~10%の省エネ効果が得られます。また、フィルターが清潔だと本体への負荷も軽減され、凍結洗浄の回数や消費電力も抑えることができます。
冷房運転後の内部乾燥は、カビ対策として非常に効果的です。凍結洗浄は週1回程度しか実行されないため、残りの6日間はエアコン内部がカビの温床となりがちです。そのため、冷房使用後には毎回短時間でも送風運転を行うことが重要です。
室外機周りの掃除も忘れてはいけません。吸い込み口や吹き出し口周りのゴミを取り除き、本体に付いているホコリも手で取れる範囲で除去しましょう。これにより風量低下や消費電力増加を防げます。
専門業者によるクリーニングは、2~3年に一度の頻度で実施することをおすすめします。凍結洗浄では届かないファンやドレンパンの汚れを根本から除去でき、エアコンの性能を長期間維持できます。
総括:日立エアコンの凍結洗浄機能のデメリット
それでは最後に、この記事の内容をまとめます。




