2階の窓や吹き抜けのガラス、外側の汚れが気になっているのに手が届かなくて困っていませんか?
高い場所にある窓ガラスの外側は、雨風や排気ガスで思った以上に汚れているものです。でも脚立に乗って身を乗り出すのは危険だし、プロに頼むのも費用が気になりますよね。
実は、窓ガラスの外側を安全に掃除する裏ワザがいくつもあるんです。
家にあるフローリングワイパーや新聞紙を使った手軽な方法から、伸縮ポールやスクイージーといった専用道具を活用するテクニック、さらには窓用バキュームクリーナーや窓掃除ロボットなど最新家電を使った方法まで、届かない窓ガラスの掃除には様々なアプローチがあります。
ただし磁石式クリーナーはペアガラスに注意が必要ですし、高圧洗浄機は熱割れのリスクがあるなど、知っておくべきポイントも。
この記事では、家電量販店で実際にお客様からよく相談される窓掃除の悩みをもとに、安全性と効果の両面から見た最適な掃除方法をご紹介します。
あなたの家の窓に合った、安全で効果的な掃除方法がきっと見つかるはずですよ!
窓ガラスの外側が届かない掃除の裏ワザ
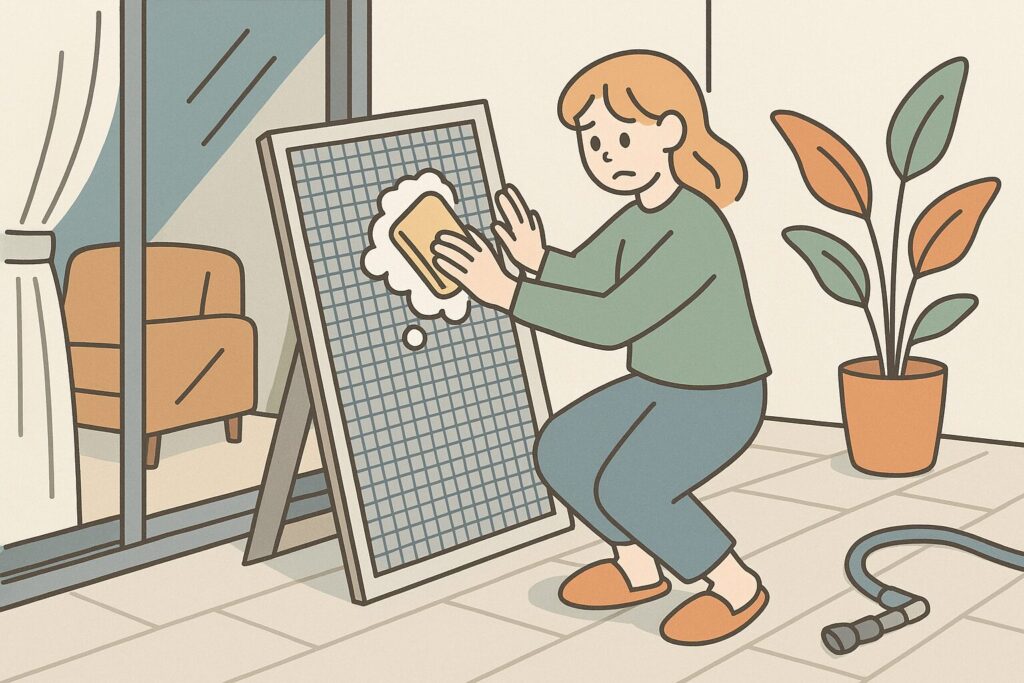
手が届かない場所の窓掃除、本当に困りますよね。特に2階や吹き抜けの窓は、汚れているのが見えても「どうしようもない」と諦めがちじゃないでしょうか。
ここではまず、お掃除の基本的な知識と、家にあるものや手軽な道具を使った「裏ワザ」的な方法を見ていきましょう。安全に作業するための大事なポイントも解説しますね。
掃除の基本: 曇りの日と網戸から
窓掃除って、実はお天気がすごく重要なの、ご存知でしたか?
「晴れた日にピカピカにしたい!」と思うかもしれませんが、実はそれ、逆効果になっちゃうことがあるんです。
晴れた日差しが強い日だと、窓ガラスにスプレーした水や洗剤があっという間に乾いてしまいます。そうすると、拭き取る前に乾いてしまって、水滴の跡や洗剤の成分が白くムラになって残ってしまうんです。せっかく頑張ったのに、かえって汚れて見えちゃうなんて悲しいですよね。
だから、窓掃除は「曇りの日」がベストタイミングなんです。湿気があって水分が乾きにくいので、慌てずにしっかり拭き上げることができますよ。私も休みの日に窓掃除をしようと思って、あえて曇りの日を選んでやっています。
それともう一つ、大事なのが「掃除の順番」です。
窓ガラスを先にピカピカにしても、その後にすぐ外側にある「網戸」を掃除すると…想像つきますよね?網戸にびっしり付いたホコリや砂埃が、せっかくキレイにしたガラスにまた付着してしまうんです。これは本当に「あるある」で、二度手間になってしまいます。
お掃除の鉄則は、「網戸 → 窓ガラス(外側 → 内側)」の順番です。まずは網戸の汚れをしっかり取り除いてから、窓ガラスの掃除に取り掛かってくださいね。
網戸掃除も家電におまかせ
網戸掃除って、ブラシでゴシゴシするのも大変ですよね。家電で何とかならないか、お店でもよくご相談いただくんです。
正直なところ、「網戸専用ノズル」として標準で付属しているモデルは、最近は少し珍しくなっているかもしれません。ですが、その代わりに多機能なブラシが付属しているモデルが増えていて、これが網戸掃除にとても便利なんです。
例えば、日立の「パワかる」シリーズや、スティックタイプの「かるパックスティック」に付属している「ほうきブラシ」や「2WAYすき間ブラシ」は、お客様からも「ブラシの毛先が細かくて、網戸のホコリをかき出すのにちょうど良い」と好評なんですよ。
もう一つの方法として、ケルヒャーなどのスチームクリーナーも網戸掃除に活躍します。
高温のスチームで汚れを浮かせながら掃除できるので、水洗いしにくい場所にもおすすめです。家電を上手に使うと、面倒な網戸掃除も少し楽になりますよ。
この2つの基本、「曇りの日」と「網戸から」を押さえるだけで、窓掃除の効率と仕上がりがグッと良くなると思います。
フローリングワイパー活用の注意点
さて、ここからは具体的な「裏ワザ」です。
まず一番手軽に試せるのが、ご家庭に必ずある「フローリングワイパー」を使う方法ですね。
やり方はとても簡単です。
- まず、フローリングワイパーにウェットシートを取り付けます。
- 柄(え)をできるだけ長く伸ばして、窓の外側を拭いていきます。
- 次に、シートを乾いたマイクロファイバークロスやタオルに付け替えます。(ここがポイント!)
- 同じように乾拭きして、水分と汚れを取り除きます。
これなら、ベランダのない2階の窓でも、室内から少し手を伸ばせば届く範囲が広がりますよね。お客様からも「とりあえずこれで拭いてみた」というお話、時々聞くんですよ。
ただし、この方法には非常に重要な注意点があります。
それは、「ワイパーの落下防止」です。
落下事故に厳重注意!
万が一、2階の窓からフローリングワイパーを落としてしまったら…想像するだけで怖いですよね。下に人がいたり、車や隣家の所有物があったりしたら、大変な事故につながります。
この裏ワザを試す時は、必ずワイパーの柄に紐やロープを結びつけ、その紐のもう片方を室内の重い家具(机の脚や柱など、絶対に動かないもの)に固く固定してください。
「ちょっとだけだから大丈夫」という油断が一番危険です。安全対策は「やりすぎかな?」と思うくらいがちょうど良いんですよ。
そして、この方法には「限界」もあります。
ウェットシートで拭いて、乾いた布で拭き上げるだけでは、どうしても水ダレの跡や拭きスジが残りやすいんです。ガラスを完璧にクリアに仕上げるのは、正直かなり難しいと思います。
あくまで「応急処置」や「軽いホコリ汚れを取るため」の裏ワザ、と考えるのが良いかもしれませんね。この「拭き跡が残る問題」は、後でご紹介する家電がスッキリ解決してくれますよ。
新聞紙やストッキングでの掃除方法
「もっとコストをかけずに、家にあるもので何とかしたい!」という方には、昔ながらの知恵もおすすめです。
それは「新聞紙」と「ストッキング」の活用です。
「え、新聞紙?」って思うかもしれませんが、これが意外と優秀なんです。
新聞紙を使ったお掃除
新聞紙の繊維は、汚れを吸着しやすい構造になっています。さらに、新聞紙のインクに含まれる油分が、ガラス表面にツヤを出し、汚れをつきにくくするコーティングのような役割も果たしてくれるんです。昔の人の知恵ってすごいですよね。
掃除の方法は簡単です。
- 新聞紙を数枚、片手に収まる大きさに丸めます。
- 水で軽く湿らせた新聞紙で、窓ガラス全体の汚れを拭き取ります。「の」の字を描くように拭くとムラになりにくいですよ。
- 仕上げに、乾いた新聞紙で円を描くようにクルクルと乾拭きし、磨き上げます。
これで、洗剤を使わなくてもかなりピカピカになります。
ただし、これも手が届く範囲の窓に限られてしまうのが難点ですね。
ストッキングを使ったお掃除
使い古して伝線してしまったストッキングも、捨ててはいけません!
ストッキングは、静電気の力でホコリを吸着するのが得意なんです。
こちらも使い方は簡単で、ストッキングの中に靴下などを詰めて「団子状」にします。これで網戸や窓ガラスを軽く拭くだけで、面白いようにホコリを絡め取ってくれますよ。
ハンガーとの合わせワザ
このストッキング、針金ハンガーに被せると、即席の「隙間お掃除棒」に変身します。ハンガーを少し変形させれば、サッシの細い隙間や、エアコンの上など、手の届きにくい場所のホコリ取りにも大活躍します。
これもエコで便利な裏ワザですよね。
新聞紙もストッキングも、主に軽いホコリ汚れに対する方法です。泥はねや排気ガスのような頑固な汚れには、やはり洗剤や専用の道具が必要になってくると思います。
手の届く範囲の「仕上げ磨き」や「網戸掃除」に活用するのが良さそうですね。
2階に届く?伸縮ポールとスクイージー

「DIYでも、もう少し本格的に掃除したい!」という場合、専用の掃除道具が選択肢になります。その代表格が、柄の長い「伸縮ポール付きワイパー」ですね。先端にスポンジや布(ウォッシャー)と、ゴム製の水切り(スクイージー)が一体になっているタイプが主流です。
これなら2階の窓にも届きそうですよね。実際に、ビルの清掃業者さんが使っているのも、このでっかいスクイージーです。
ただし、家庭で使うにはいくつか知っておくべき「限界」があります。
ポールの「長さ」と「重さ」
まず、2階の窓にしっかり届かせるには、少なくとも3mから5mの長さのポールが必要になります。お店の掃除用品コーナーにも並んでいますが、5mクラスのポールって、想像以上に長くて…そして、重いんです。
アルミ製のものでも、5mクラスだと1.3kg前後になることもあります。
「たった1.3kg?」と思うかもしれませんが、それを目一杯伸ばして、先端で窓を拭く作業を想像してみてください。かなりの腕力とバランス感覚が必要で、特に女性が一人で操作するのは結構大変だと思います。
「スクイージー」の難しさ
もう一つの難関が、「スクイージーでの水切り」です。プロの清掃員さんは、あれを「スーッ」と一気に引き下ろして、水滴ひとつ残さず仕上げますよね。あれ、実はものすごい技術なんです。
素人がやると、均等な力で引き下ろすのが難しくて、どうしてもゴムとガラスの間に隙間ができてしまいます。そうすると、拭き跡(スジ)がくっきり残ってしまうんです。
お客様からも「高いポール買ったけど、結局スジだらけになっちゃって…」というお話をよく聞きます。特に5mも先の先端部分に均等な力をかけ続けるのは、至難の業だと思います。
参考:伸縮ポール・ワイパーの例
あくまで一例ですが、市場にはこのような商品があります。購入の際は「最大何メートルまで伸びるか」と「重さ」をしっかり確認してくださいね。
| メーカー(参考) | 商品名(参考) | 伸縮範囲(目安) | 特徴(目安) |
|---|---|---|---|
| アズマ工業 | TK伸縮自在ガラス網戸ワイパー | 約63~120cm | ガラスと網戸両用。比較的短いタイプ。 |
| 山崎産業(コンドル) | 2989.jp+ グラスワイパーN-38EX 5m | 約2.5m~5.49m | 2階建て対応のロングタイプ。アルミ柄。 |
| モアマン (Moerman) | エクステンションポール 5m | ~5m | プロ仕様。高耐久だが高価。 |
※上記はあくまで一例です。価格や仕様は変動する可能性があるため、購入時にご確認ください。
伸縮ポールは確かに届きますが、「重くて扱いにくい」「キレイに仕上げるには技術が必要」というハードルがあることを覚えておいてくださいね。
磁石式クリーナーはペアガラスに注意
室内から外側を掃除できる「裏ワザ」として、もう一つ有名なのが「磁石式(両面)ガラスクリーナー」です。
2つのクリーナー(スポンジ)を、窓ガラスを挟んで磁石で「パチン!」とくっつけて、室内のクリーナーを動かすと、外側のクリーナーも一緒に動いて拭いてくれる…という道具です。
これ、理論上は「夢のような道具」ですよね!
室内から安全に外側が拭けるんですから。私も最初の頃は「これすごい!」って思った記憶があります。
ですが…。
実はこの道具、お客様から「買って失敗した」というお声が一番多い商品かもしれないんです。
この道具には、購入前に必ず確認しないといけない、大きな「罠」があります。
最大の罠:「窓の厚み」です
このクリーナーが使えるかどうかは、「ご自宅の窓ガラスの厚み」で全て決まります。
安価で売られている製品の多くは、昔ながらの「一枚板のガラス(単層ガラス)」にしか対応していません。磁力もそれに合わせて調整されています。
しかし、現在の日本の住宅の多くは、断熱性や防音性の高い「複層ガラス(ペアガラス)」が主流ですよね?
ペアガラスは、2枚のガラスの間に「空気層」があるため、非常に厚みがあります。
その厚いペアガラスに、単層ガラス用の磁石式クリーナーを使おうとしても…磁力が全く足りず、外側のパッドがすぐに「ポトッ」と落ちてしまいます。
「これ全然使えないじゃない!」ってなりますよね。
ペアガラスには「専用品」が必須!
もしご自宅がペアガラス(複層ガラス)なら、必ず「複層ガラス対応」「ペアガラス用」と明記された、強力な磁石を使っている専用品を選ぶ必要があります。
ただ、ペアガラス対応品は磁力が強力なぶん、お値段も高価になりがちです。また、強力すぎて操作が重かったり、万が一指を挟んだりすると危険な場合もあります。
安易に安価な製品に手を出すと「全く使えなかった」という失敗に陥りがちなので、購入前にはご自宅の窓の仕様を必ず確認してくださいね。
落下防止の紐は付いていますが、そもそも磁力が足りないと掃除になりませんし、ペアガラス対応品でも操作にはコツが必要です。これも「裏ワザ」としては、ちょっと注意が必要なアイテムですね。
届かない窓ガラス外側の掃除|裏ワザと家電

ここからは、私たち家電のプロが得意な分野、「家電」を使った解決策をご紹介しますね!
DIYの「拭き跡が残る」問題や危険な作業を、家電がどうスマートに解決してくれるのか、一緒に見ていきましょう!
窓用バキュームで拭き跡なし
先ほどのフローリングワイパーや伸縮ポールでは、「水ダレや拭き跡が残る」のが悩みでしたよね。この問題を一気に解決してくれるのが「窓用バキュームクリーナー」です。
これは、窓掃除の仕上げに使う「電動の水滴吸引機」だと思ってください。お店では、冬場の「結露取り」のアイテムとしてすごく人気があるんですよ。窓ガラスに付いた水滴を、ワイパーの先端で「キューッ」と吸い取ってくれるんです。
これが窓掃除の仕上げに大活躍します。
スクイージーで水切りした後の汚れた水分を、モーターの力で強力に吸引してくれるので、水ダレや拭き跡をほとんど残さず仕上げることができます。手動のスクイージーでスジが残ってイライラ…なんてこともありません。
「でも、それも手が届かないと意味ないんじゃ?」と思いますよね?
そこが家電メーカーの凄いところです。
ケルヒャーなどの主要メーカーは、この窓用バキュームクリーナーのために、「専用の延長ポール」を別売りで用意しているんです!
届かない場所の「拭き跡ゼロ」を実現
この「窓用バキューム + 専用延長ポール」の組み合わせこそ、安全なDIY掃除の「現実的なアップグレード案」だと私は思います。
例えば、ケルヒャーの「窓用延長ポール(型番: 2.633-144.0 など)」は、約1.5mまで伸ばすことができます。これに窓用バキュームクリーナー(「WV 1 プラス」や「WV 2 Plus」など)をカチッと装着できるんです。
先に(落下防止措置をした)フローリングワイパーや伸縮ポールで窓を洗い、その仕上げの「吸い取り作業」を、この延長ポール付きバキュームクリーナーで行うんです。これで、DIYでは不可能に近かった「拭き跡ゼロ」の仕上がりが、安全に実現可能になりますよ。
結露取りだけでなく、お風呂上がりの壁や鏡の水滴取りにも使えるので、一台あると年間通して活躍してくれる、とても便利な家電だと思います。
高圧洗浄機は危険?熱割れのリスク
「届かない2階の窓に水をかけるなら、高圧洗浄機で一気にやればいいじゃない!」
そう思いますよね?
確かに、ベランダや外壁、車の掃除には絶大な威力を発揮する高圧洗浄機。お店でも大人気です。
ケルヒャーやアイリスオーヤマなど、各社から色々なモデルが出ています。
ですが…。
こと「届かない窓の掃除」において、高圧洗浄機は「最悪の選択肢」になる可能性が非常に高いんです。これは「裏ワザ」ではなく、極めてリスクの高い「アンチ・裏ワザ」として認識してほしいです。
お店で高圧洗浄機をお求めのお客様にも、窓掃除(特に網入りガラス)に使うのは原則おすすめしていません。なぜなら、重大な危険があるからです。
高圧洗浄機が窓掃除にNGな理由
- ガラス破損(熱割れ)のリスク
特に注意が必要なのが「網入りガラス」です。太陽光でガラスが熱くなっているところに、高圧洗浄機の冷たい水を勢いよく噴射すると、ガラスが急激に温度変化します。ガラスは膨張し、内部に入っている金属ワイヤーとの歪みで「ピシッ!」と割れてしまう…これが「熱割れ」です。これは本当に起こり得る現象で、非常に危険です。 - 室内への浸水リスク
水の勢いが強すぎるため、窓のサッシやゴムパッキン(シール)のわずかな隙間から水が逆流し、室内側へ水が入る(浸水する)場合があります。壁紙や床が水浸しになったら大変ですよね。 - 反動(キックバック)による転落リスク
高圧洗浄機は、噴射時に「ガッ」という強い反動(キックバック)があります。もし足場が不安定な場所や、後述する脚立の上などで使おうものなら、反動でバランスを崩し、転落する重大な危険があります。清掃作業中の転落事故は後を絶たず、命に関わる問題です。 - 近所迷惑
汚れた水が広範囲に霧状になって飛散します。お隣の壁や、干している洗濯物を汚してしまう可能性があり、ご近所トラブルの原因にもなりかねません。
ケルヒャーなどには「延長ランス」というノズルを長くするアクセサリもありますが、それを連結して2階に届かせようとすると、先端が非常に重くなり、操作は困難を極めます。反動も制御できなくなり、危険が増すだけです。
窓ガラス、特に高所や網入りガラスに高圧洗浄機を使用することは、絶対に避けてくださいね。
脚立作業の危険性と安全な対策
「伸縮ポールでも届かない、あともうちょっと…」そんな時、脚立を使おうと考える方も多いと思います。ですが、この脚立作業こそ、家庭内の事故で非常に多いものの一つなんです。
「低い脚立だから大丈夫」と油断しがちですが、たとえ1mの高さでも、バランスを崩して転落すれば、打ち所によっては重大な怪我につながります。
特に窓掃除のように、片手に道具を持ち、もう片方の手で窓を拭くために「身を乗り出す」ような体勢は、最も危険な使い方の一つです。プロの清掃業者さんでさえ、身を乗り出すような安全確保ができない作業は断ることがあるほどなんですよ。
脚立作業の安全ルール
もし、どうしても脚立を使用する必要がある場合は、以下の点を絶対に守ってください。
- 平らで、滑りにくく、安定した固い地面(土の上などはNG)に設置すること。
- 脚立の「天板(一番上の板)」には絶対に乗らないこと。作業は天板から2段下まで。
- 窓に近づきすぎて、体が「くの字」にならないよう、適度な距離を保つこと。
- 絶対に「身を乗り出さない」こと。おへそが脚立の支柱の内側にある状態をキープしてください。
- 一番望ましいのは、必ず二人一組で作業し、一人が下で脚立をしっかりと支えることです。
家電店員としても、掃除道具をおすすめする立場としても、一番お伝えしたいのは「安全第一」だということです。
少しでも「怖いな」「危ないかも」と感じたら、絶対に無理をしないでください。脚立に登らなくて済む方法を考えることが、一番の「安全対策」だと思います。
最終手段は窓掃除ロボットの活用
「DIYは危険だし、道具を揃えるのも大変」
「磁石式はペアガラスで使えないし、落ちるのが怖い」
そんな、今までの問題をすべて解決してくれるのが、現代の『究極の裏ワザ』、窓掃除ロボットです!
これこそ、私たち家電量販店が自信を持っておすすめできる、最も安全で確実な解決策かもしれません。窓掃除ロボットは、強力なファン(掃除機のようなもの)で窓ガラスに「ブォー」っと吸着し、あとはスイッチを押すだけで自動で窓全体を拭き掃除してくれる家電です。
磁石式クリーナーが苦手だった、あの「複層ガラス(ペアガラス)」でも全く問題ありません。
磁力ではなく「吸引力」で張り付くからです。これは大きなメリットですよね。
最大の特長は「二重の安全機能」
お店でお客様に一番聞かれるのが、「掃除中に落ちたりしないの?」という点です。もちろん、高所で使う家電なので、安全機能は徹底されています。
① UPS (無停電電源装置)
掃除中に万が一、コンセントが抜けたり、停電したりしても、内蔵バッテリーが作動して、即座に落下するのを防ぎます。その場で窓に張り付き続けたまま、「ピーピー!」と警告音を鳴らして知らせてくれるんです。(例:約20分間保持など、機種によります)
② 落下防止ロープ
そして、そのバッテリーすら切れてしまったら…という「万が一の万が一」に備えて、必ず「落下防止ロープ」が付属しています。このロープを、室内のカーテンレールや柱など、頑丈な場所に結び付けておくことで、物理的な落下を防ぎます。
この二重の安全機能があるからこそ、私たちは安心しておすすめできるんです。
例えば、HOBOT(ホボット)や、ECOVACS(エコバックス)などが人気のモデルですね。最近の機種は、自動で洗剤をスプレーしてくれる機能が付いていたり、AIが効率的なルートを判断してジグザグ走行したりと、本当に賢くなっています。
もちろん、注意点もあります。クリーニングクロスが濡れすぎていると滑ってしまったり、逆に乾きすぎていると動きが遅くなったり。
また、すりガラスや凹凸のあるガラス、フィルムが貼られた窓には使用できない場合があるので、ご自宅の窓が対応しているかの確認は必要です。
ですが、危険な高所作業を全て「家電」に任せられるというのは、何物にも代えがたい安心感があると思います。
業者に頼む場合の料金相場

「窓掃除ロボットも届かないような高い場所(吹き抜けなど)がある」「掃除は数年に一度でいいから、ロボットを買うほどでもない」…そういう場合は、無理をせず「専門のハウスクリーニング業者」に依頼するのが、最も賢明な選択です。
安全をお金で買う、という考え方ですね。プロは専用の機材と技術、そして何より安全確保のノウハウを持っています。
気になる料金ですが、これは窓のサイズや枚数、汚れ具合、そして「足場」が必要かどうかで大きく変動します。
料金目安(あくまで一例)
例えば、ダスキンの標準料金(2025年時点の参考情報)では、掃き出し窓(床まである大きな窓、1~2平方メートル未満)で1枚あたり約3,000円~となっています。
ただし、これはあくまで標準的な窓の場合です。吹き抜けの高所窓などで、特別な足場やロープ作業が必要になると、料金は数万円単位になることもあります。
正確な料金は、必ず複数の業者に現地調査してもらい、「見積もり」を取って比較検討してくださいね。
ここで、窓掃除ロボットとコストを比較してみましょう。先ほどの窓掃除ロボットが1台約44,000円から(HOBOT-2Sの参考価格)、業者が1回3,000円から(標準的な窓の場合)と仮定します。
単純計算ですが、業者に約14~15回依頼する費用で、窓掃除ロボットが1台購入できる計算になりますね。もし年に2回掃除を依頼する場合、7年程度で元が取れる、とも考えられます。
「安全」と「いつでも好きな時に掃除できる手間からの解放」を初期投資で購入するか、「完璧なプロの仕上がり」を都度依頼するか。これは、ご家庭の窓の状況やライフスタイルに合わせて選ぶのが一番だと思います。
私のおすすめとしては、やはりお値打ち価格のくらしのマーケットですかね。
まとめ: 届かない窓ガラス外側の掃除裏ワザ
届かない窓ガラスの外側を掃除する「裏ワザ」、いかがでしたか?
家にあるもので手軽にできる方法から、専用の道具、そして最新の家電を使った方法まで、色々ありましたね。最後にポイントを整理してみましょう。
- レベル1:DIY(新聞紙・フローリングワイパー)
手軽ですが効果は限定的。水ダレや拭き跡が残りやすく、ワイパーは落下防止の安全対策が必須です。 - レベル2:手動ツール(伸縮ポール・磁石式)
2階にも届きますが、ポールは「重くて技術が必要」。磁石式は「ペアガラス非対応」の罠があり、失敗しやすい道具です。 - レベル3:家電(窓用バキューム+ポール)
DIYの「拭き跡」問題を解決する、現実的で安全なアップグレード案。結露取りにも使えて便利です。 - レベル4:家電(窓掃除ロボット)
最も安全で確実な「現代の裏ワザ」です。UPSと安全ロープで落下を防ぎ、自動で掃除を完了させます。初期費用はかかりますが、危険な作業から解放されます。 - 非推奨:高圧洗浄機
「熱割れ」「浸水」「転落」のリスクが非常に高い、危険な手段です。窓掃除には絶対に使わないでくださいね。
私たちがお店でお客様とお話ししていても、一番大切にしているのは、やはり「安全」であることです。
「裏ワザ」と聞くと、何か特別なテクニックを想像しがちですが、届かない窓の掃除に関しては、危険な身乗り作業や不安定な脚立作業は、もはや「裏ワザ」ではありません。
窓用バキュームクリーナーや窓掃除ロボットといった、現代の「家電の力」を上手に借りること。それこそが、ご家族の安全を守りつつ、家をキレイに保つための、最も賢い「裏ワザ」なんだと私は思います。
ご自宅の窓に合った、安全でキレイになる方法を見つけて、スッキリと晴れやかな景色を楽しんでくださいね!




