窓掃除をしたのに拭きスジが残ってしまったり、せっかくキレイにしたはずなのに曇って見えたり、そんな経験はありませんか?
実は窓の掃除には、ちょっとしたコツと正しい手順があるんです。晴れた日に水拭きするのが良いと思っていた方、それ実は逆効果かもしれません。
この記事では、家電量販店で日々お客様からいただく窓掃除に関する質問や悩みをもとに、プロも実践している効果的な掃除方法をご紹介します。
網戸やサッシの正しい掃除順序から、拭きスジを残さないガラスの拭き方、さらには時短を叶える便利な家電まで、明日からすぐに実践できる情報が満載です。
窓がピカピカになると、お部屋全体がワントーン明るくなって気持ちまでスッキリします。ぜひこの記事を参考に、効率的で失敗しない窓掃除のやり方をマスターしてくださいね!
基本的な窓掃除の仕方と準備

「窓掃除の仕方」と一口に言っても、ちょっとしたコツを知っているだけで、仕上がりが全然違ってくるんです。
この最初のセクションでは、窓掃除を始める前の「基本のキ」と、キレイに仕上げるための準備について、一緒に見ていきましょう!
窓掃除の正しい順番とは?
窓掃除を始めるとき、いきなり窓ガラスから拭き始めていませんか?
実はそれ、かえって汚れを広げてしまうかもしれないんです。
お掃除を効率よく進めるには、「順番」がとっても大事なんですよ。
おすすめの順番は、ズバリこれです!
- 網戸
- サッシ(窓枠・レール)
- 窓ガラス(外側 → 内側)
なぜこの順番かというと、先に網戸やサッシに溜まった「乾いたホコリ」や「砂ボコリ」を取り除いておきたいからなんです。もし先にガラスを水拭きしてしまうと、網戸やサッシのホコリが水に濡れて「泥」のようになってしまって…。
せっかく拭いたガラスに、その泥汚れがついてしまうこともあります。
それって、二度手間で悲しいですよね。
まずは乾いた汚れをしっかり外に出してから、最後にガラスを仕上げる。これが効率的な窓掃除の仕方の鉄則ですね。
ガラスを拭く順番も、「外側から先に」がおすすめです。
外側をキレイにしてから内側を拭くと、内側を拭いているときに「あれ?この汚れ、外側だっけ?」というのがすぐ分かります。拭き残しを見つけやすくなるので、結果的に両面ともピカピカに仕上がるんですよ。
窓掃除の順番まとめ
- まずはホコリっぽい「網戸」から。
- 次に砂ボコリが溜まる「サッシ」をキレイに。
- 最後に「窓ガラス」を拭き上げる(外側→内側の順で)。
この順番を守るだけで、泥汚れの広がりを防いで、お掃除がぐっと楽になりますよ!
窓掃除に適した天気と頻度
「さあ、窓掃除するぞ!」って、どんな日にやっていますか?
つい、カラッと晴れたお天気の良い日にやりたくなっちゃいますけど、実は窓掃除に「晴れすぎ」はNGなんです!びっくりですよね。
どうしてかというと、直射日光が当たってガラスが熱くなっていると、水拭きした水分がすぐに乾いてしまうから。水分が乾くときに、汚れや洗剤の成分が一緒に残って、あのイヤ~な「拭き跡」や「拭きスジ」になってしまうんです。
なので、窓掃除は「曇りの日」や「朝夕の涼しい時間帯」が一番適しているんですよ。湿度が少しあるくらいのほうが、ガラス面の汚れも浮きやすいですしね。
「雨の日」は、外側の汚れが流れやすいっていうメリットもありますけど、やっぱり拭き上げができないですし、せっかく拭いてもまた濡れちゃうので、基本的には避けたほうがいいかなと思います。
お掃除の頻度は?
お店でも「窓掃除って、みんなどのくらいやってるの?」なんて聞かれることがありますが、一般的には「半年に1回」、つまり年に2回くらいが目安と言われていますね。
例えば、花粉や黄砂のシーズンが終わった春と、台風シーズンが終わって年末の大掃除にかかる秋とか。季節の変わり目にやるのが、汚れもリセットできて気持ちいいんじゃないでしょうか。
ただし、これはあくまで目安です。
キッチンの近くにある窓は油煙でベタつきやすいですし、道路沿いの窓は排気ガスで汚れやすいですよね。手垢がつきやすいリビングの掃き出し窓なんかも、汚れが気になったらその都度サッと拭くのが一番です。
汚れをずーっと放置してしまうと、頑固にこびりついて落とすのが本当に大変になっちゃいますから。汚れを溜め込まないことが、結果的にお掃除を楽にする一番のコツだと思いますよ。
窓掃除に必要な道具一覧
さて、やる気が出たところで、まずはお掃除道具を揃えちゃいましょう!専用のすごい道具じゃなくても、おうちにあるもので代用できるものも多いですよ。
| 道具 | どんなもの? どこで使う? |
|---|---|
| ブラシ・ハケ | サッシの溝のホコリをかき出す用です。100円ショップの専用ブラシも便利ですし、古い歯ブラシでもOKです。 |
| 掃除機 | ブラシでかき出したホコリを吸い取ります。コードレスのハンディクリーナーに細口ノズルをつけるのが最強に便利です! |
| 雑巾・クロス | 水拭き用と乾拭き用に最低2枚は用意しましょう。繊維が残りにくいマイクロファイバークロスがおすすめです。 |
| バケツ | 水拭き用の水を汲んでおきます。 |
| スクイージー(ワイパー) | T字型の水切りワイパーですね。これがあると仕上がりのレベルが格段に上がります! |
| 洗剤(必要なら) | 基本は水でOKですが、手垢や油膜がひどい時に。台所用中性洗剤や窓用クリーナー(マジックリンなど)ですね。 |
家電店員のおすすめはコレ!
この中で、私が家電店員として「これはぜひ!」とおすすめしたいのは、やっぱり「コードレスのハンディクリーナー」ですね。
サッシのレール掃除って、ブラシでホコリをかき出すだけだと、結局そのホコリが舞っちゃったり、うまく取りきれなかったりしませんか?
そこでハンディクリーナーの出番です。ブラシで浮かせたホコリを、すかさず吸い取ってしまうんです。これが本当に効率的!
最近のハンディクリーナーは軽くて吸引力も強いですし、付属の「すき間ノズル」を使えば、あの細いレールの隅っこまでしっかり届きます。
お店でも、マキタやアイリスオーヤマ、シャークの小型クリーナーは、「ちょっと使い」用としてすごく人気がありますよ。窓掃除以外にも、車の中とか、パンくずとか、気づいた時にサッと使えるのが良いんですよね。
マイクロファイバークロスも、水拭き用と乾拭き用で色を変えておくと、「あれ、どっちだっけ?」ってならなくて便利ですよ。
基本の洗剤と便利な洗剤
窓ガラスの汚れって、実は2種類あるってご存知でしたか?
外側は、砂ボコリや排気ガス、花粉などの「外的な汚れ」。
内側は、手垢(皮脂)、タバコのヤニ、キッチンの油煙などの「内側からの汚れ」です。
外側の砂ボコリなんかは、基本的には水拭きだけで十分落ちるんです。でも、内側の皮脂や油膜は、水だけだとちょっと手強いんですよね。
基本は「中性洗剤」
もし水拭きだけで汚れが落ちないな、と思ったら、まずは「台所用の中性洗剤」を試してみてください。バケツ1杯の水(約1L)に対して、2~3滴たらすだけでOKです。
この薄めた洗剤液でクロスを絞って拭けば、軽い油膜や手垢はスッキリ落ちますよ。とっても経済的なのも嬉しいポイントですね。
洗剤を使ったあとは「二度拭き」を忘れずに!
中性洗剤を使った場合は、洗剤の成分がガラスに残らないように、必ずキレイな水で絞ったクロスで「水拭き」し、最後に「乾拭き」してくださいね。洗剤残りは、あとで白くムラになる原因になっちゃいます。
あると便利!専用クリーナー
「二度拭きって、正直ちょっと面倒…」って思いますよね(笑)
そういう時には、やっぱり「窓用スプレー洗剤(ガラスクリーナー)」が便利です。花王の「ガラスマジックリン」とか、アズマ工業の「アズマジック」とか、いろいろありますね。
これらの専用クリーナーは、泡切れが良くて拭き跡が残りにくいように作られているのが特徴です。シュッと吹きかけてサッと拭くだけで、二度拭きなしでもスッキリ透明になるものが多いので、時短にもなります。
他にも、「アルカリ電解水」のスプレーなんかも、皮脂汚れに強くて二度拭き不要なので手軽ですね。ただし、セスキ炭酸ソーダ水やアルカリ電解水は、アルミサッシに直接かかると変色させてしまう恐れがあるので、そこだけは注意して使ってください!
拭き跡を残さないガラスの拭き方
さあ、いよいよガラス拭きです!
ここが窓掃除のメインイベントであり、一番の難関ですよね。
「拭き跡を残さない」ための仕方を、しっかりお伝えしますね。
ステップ1:まずは「ホコリ落とし」
いきなり濡れた雑巾で拭くのはNGですよ!
ガラス表面についている乾いたホコリを、まずはサッと払ってあげましょう。これをやらないと、ホコリが泥になって拭きムラの原因になります。
ステップ2:基本は「水拭き」+「乾拭き」
私が一番おすすめしたいのは、このシンプルな方法です。
- 固く絞った濡れ雑巾(水拭き用)で拭く
- すぐに乾いたクロス(乾拭き用)で拭き上げる
「水拭き」と「乾拭き」はワンセット!と覚えてください。濡れたまま放置するのが水滴の跡(ウロコ)が残る一番の原因です。
一面ずつ、水拭きしたらすかさず乾拭き!このスピード感が大事なんです。
ステップ3:拭き方は「一方向」に
拭き跡を残さないための最大のコツは、「拭く方向」です。
よくやりがちなのが、円を描くように「ぐるぐる」磨く拭き方。
これ、実は一番拭きムラが残りやすい拭き方なんです…。
おすすめは、上から下へ、「コの字」を描くように拭く方法です。まず上端を横に拭いたら、そのまま縦に下ろし、下端を横に…という感じです。
または、S字を描くように拭くのもOK。
要は、一定の方向に、拭き幅を少し重ねながら拭き進めることで、汚れや水分を効率よく端に追いやって、ムラなく仕上げることができるんですね。
「ぬるま湯」も効果的です
内側の手垢や皮脂汚れは、水よりも40℃くらいの「ぬるま湯」を使うと落ちやすくなりますよ。油分が緩むんですね。キッチンの近くの窓には特に有効なので、試してみてください。(もちろん、熱湯はガラスが割れる危険があるので絶対ダメですよ!)
スクイージーの上手な使い方

「水拭きと乾拭き、2回も拭くの面倒…」という方には、ぜひ「スクイージー(窓用ワイパー)」を使ってみてほしいです!
プロのお掃除屋さんが使っている、あのT字型の道具ですね。
これがあると、水拭きのあとの「水切り」が一瞬で終わるので、作業時間が本当に短縮されます。乾拭きの手間がほぼなくなるので、仕上がりも断然キレイなんですよ。
家庭用なら、OXO(オクソー)が出しているような、持ち手がしっかりしたハンドワイパーが使いやすいと思います。
使い方のコツ
使い方はシンプルですが、ちょっとしたコツがあります。
- スクイージーのゴム刃を、窓ガラスの上端にぴったり当てます。
- そのまま一気に、まっすぐ下まで引き下ろします。
- 1回ごとに、ゴム刃についた水分を雑巾でしっかり拭き取ります。←コレ大事!
- 隣に少し(数センチ)重ねるようにずらして、また上から下へ。
- これを繰り返して、全面の水滴を切ります。
一番のポイントは、途中でスクイージーをガラスから離さないこと。離すと、そこにスジ(線)が残ってしまうんです。1ストロークごとに刃を拭くのも、水ダレを防ぐために重要ですよ。
最後に窓のフチに残った水分を乾いたクロスで拭き取れば完璧です!
もっと楽したい方には…
「スクイージーも、まっすぐ下ろすのが難しい…」というお声、実はお店でもよく聞くんです。
そんな方には、ドイツのケルヒャーが出している「窓用バキュームクリーナー」が本当におすすめです!
これは、水滴を電動で吸い取ってくれるハンディ掃除機みたいなもの。
洗剤液で窓を拭いたあと(専用のスプレーボトルもセットになってます)、このバキュームで吸い取るだけ。力もコツもいらず、誰でも拭きスジゼロの仕上がりになるんです。
私も家で使ってますが、窓掃除が「楽しい!」って思えるようになりました(笑)
お風呂上がりの浴室の水滴取りや、冬場の結露取りにも使えるので、一台あるとすっごく重宝しますよ。
窓まわりの掃除の仕方と便利家電

さて、基本的な窓ガラスの掃除の仕方がわかったところで、次は「窓まわり」です。
せっかくガラスがピカピカになっても、網戸やサッシがホコリだらけだと残念ですよね。
ここでは、網戸やサッシのお掃除方法と、お掃除をもっと楽にしてくれる「便利家電」について、家電店員目線もたっぷり入れながらご紹介していきますね!
網戸掃除の簡単な方法
窓掃除の順番、覚えていますか?
そう、一番最初は「網戸」からでしたね!
網戸って、外側の汚れ(砂ボコリ、排気ガス)と、内側の汚れ(部屋のホコリ、キッチンの油煙)で、実は両面ともすごく汚れてるんです…。
外せるなら「丸洗い」がベスト
もし網戸が取り外せるおうちなら、お風呂場やベランダで丸洗いしちゃうのが一番スッキリします。
バケツに中性洗剤を薄めて、柔らかいスポンジやブラシで優しく両面を洗います。
このとき、ゴシゴシ強くこすると網が傷んだり伸びたりしちゃうので、優しくなでるように洗うのがコツですね。
あとはシャワーでしっかり洗剤を流して、乾かせばOKです。
外せない時は「拭き掃除」
「網戸を外すなんて、重たいし大変!」
…ですよね。私もそう思います(笑)
そんな時は、「フロアワイパー」に「ウェットシート」を装着して拭く方法が、本当に簡単でおすすめです!
市販の網戸掃除用シートもありますが、普段使っている床掃除用のウェットシートで十分。ワイパーにつけて、まずは網戸の内側を縦・横に拭きます。それだけでシートが真っ黒になって、ちょっと感動しますよ(笑)
可能なら外側も同じように拭くと完璧です。
もう一つの裏ワザは、「メラミンスポンジ」です。
水で濡らして固く絞ったメラミンスポンジで網戸を軽くこするだけで、網目の細かい汚れをかき出してくれます。これも洗剤いらずで手軽ですね。
サッシのホコリと黒カビ掃除
窓まわりで一番の強敵、それは「サッシのレール」じゃないでしょうか。
見て見ぬフリをしてきた砂ボコリが、隅っこでカチカチになってたり…(笑)
ここも、「乾いた状態」でホコリを取るのが鉄則です!
先に水を流すと、ホントに悲惨な「泥」になりますからね。
サッシ掃除の手順
- かき出す:まずはサッシブラシや古い歯ブラシで、レールの隅に溜まった砂ボコリをかき出します。
- 吸い取る:ここで、あの家電の出番です!そう、「コードレスハンディクリーナー」。細口ノズルで、かき出したホコリを片っ端から吸い取っていきます。ブラシでかき出しながら同時に吸うと、ホコリが舞い上がらなくて最高です。
- 拭き上げる:乾いたゴミがなくなったら、ようやく水拭きです。固く絞った雑巾で、レールをなぞるように拭き上げます。指に巻き付けて拭くとやりやすいですよ。
レールの「黒カビ」を見つけたら…
サッシは結露で湿気やすいので、ゴムパッキンや隅っこに黒カビが発生しやすい場所でもあります。
もし黒カビを見つけたら、お掃除の仕上げに「アルコールスプレー」を吹きかけて拭き取っておきましょう。除菌・カビ予防になります。
カビ取り剤を使う時の注意点
もし頑固な黒カビに塩素系のカビ取り剤(カビキラーなど)を使う場合は、換気をしっかり行ってくださいね。また、薬剤がアルミサッシや木枠に長時間ついたままだと素材を傷めてしまう可能性があります。
綿棒などでカビの部分にだけ塗布して、時間を置いたら必ずしっかり水拭きと乾拭きをして、薬剤を残さないように注意しましょう!安全が第一ですからね。
新聞紙でピカピカにする裏ワザ
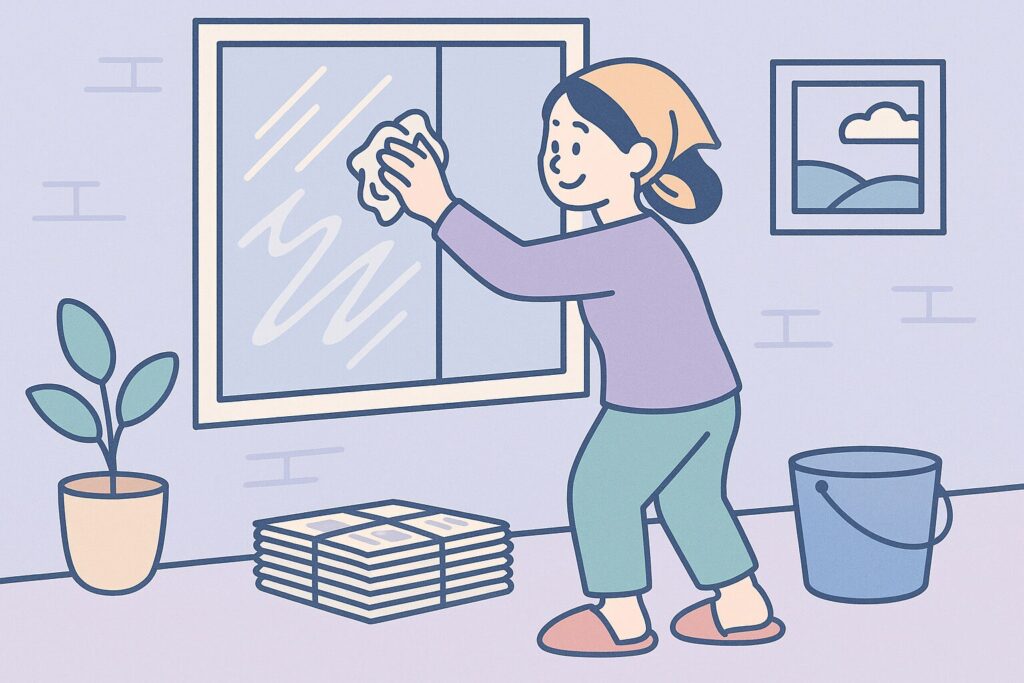
洗剤もクロスもない!という時に使える、昔ながらの裏ワザをご紹介しますね。
それは「新聞紙」です。
新聞紙を数枚、くしゃくしゃに丸めます。それを水で少し湿らせて、ガラスを拭いてみてください。新聞紙の繊維が、ガラス面の汚れをうまく絡め取ってくれるんです。
さらに嬉しいのが、新聞紙のインクに含まれる油分。これが、ガラスに自然なツヤを与えてくれて、拭きスジが残りにくくなるんです。軽いコーティング効果で、汚れがつきにくくなるとも言われていますね。
仕上げに、乾いた新聞紙でもう一度拭き上げれば完了です。
手がインクで黒くなってしまうのがちょっと難点ですけど、その効果は本物です。エコですし、道具がない時にはぜひ思い出してみてください。
ただし、最近はカラー印刷のページも多いですよね。インクがベッタリ手につきやすいので、できれば文字ばかりのモノクロのページを使うのがおすすめですよ。
窓用ロボットで掃除を自動化
さて、ここまでいろいろな窓掃除の仕方をご紹介してきましたが、「理屈はわかったけど、やっぱり面倒…」「高いところの窓は、そもそも届かない!」…。
そんなお悩みも、すごくよくわかります。
家電店員として働いていると、そんなお客様のお悩みを解決してくれる「救世主」のような家電に、毎日ワクワクさせられています。
窓掃除の最終兵器、それは「窓拭きロボット(自動窓掃除ロボット)」です!
ここ数年で、お店でもお問い合わせが本当に増えました。ボタンひとつで、窓ガラスにピタッと吸着して、AIが窓のサイズを検知しながら隅々まで自動で拭き掃除をしてくれるんです。
どんな製品があるの?
有名どころだと、ロボット掃除機で有名なエコバックスの「WINBOT(ウィンボット)」シリーズや、HOBOT(ホボット)のシリーズですね。
例えば「WINBOT」は、強力なファンでガラスに吸着しながら、クリーニング液を自動で噴霧して、マイクロファイバーパッドで拭き上げてくれます。
最新モデルだと、お掃除が終わったら自分でステーションに戻って、使ったパッドまで洗浄・乾燥してくれる…なんていう、夢のような全自動モデルも出てきているんですよ。
HOBOTの製品もすごく人気があって、四角いボディで隅っこまでしっかり拭けるタイプや、丸いパッドが回転しながら汚れを磨き取るタイプなど、いろいろな種類があります。
(ご興味のある方は、LIXILさんの公式サイトなどで機能比較も見てみてくださいね。
窓拭きロボットのメリット・デメリット
【メリット】
- とにかく楽!:ボタンを押すだけ。その間、他の家事ができます。
- 安全!:脚立やイスに乗る必要がなくなります。これが最大のメリットだと私は思います!吹き抜けや2階の高窓も、安全にお任せできます。
【デメリット】
- 隅(数センチ)は残る:機械なので、窓枠ギリギリの隅っこは少し拭き残しが出ることがあります。
- サッシは掃除しない:あくまで「ガラス面」専用です。
- お値段:初期費用はやっぱりかかりますね…(性能によりますが、大体3万円~)
お店でお客様とお話ししていても、「脚立に上るのが怖くなってきたから」というご年配の方や、「吹き抜けの窓を業者さんに頼むと毎回数万円かかるから」という方が、購入を決めていかれます。
「自分では絶対に無理」と思っていた場所がキレイになるって、本当に気持ちがいいですよね。窓掃除が「面倒な家事」から「家電に任せるもの」に変わる、すごいアイテムだと思います。
窓掃除の仕方の総まとめ
基本的な窓掃除の仕方から、網戸・サッシ、そして最新の便利家電まで、たくさんご紹介してきましたが、いかがでしたか?
窓掃除って、つい後回しにしがちな家事No.1かもしれません(笑)
でも窓がピカピカになると、お部屋がワントーン明るくなって、入ってくる光も空気もなんだか新しくなったみたいで、すっごく気持ちがいいんですよね。
今回のポイントをもう一度おさらいしますね。
- 順番が大事!:「網戸→サッシ→ガラス」で、乾いたホコリから先に。
- 天気が大事!:「曇りの日」がベストタイミング。晴れた日の水拭きはNG。
- 拭き方が大事!:「コの字」か「S字」で一方向に。水拭きと乾拭きはワンセットで。
- 家電も大事!:サッシの「ハンディクリーナー」や、水切り「バキューム」、全自動の「窓拭きロボット」など、便利な家電を上手に使って、お掃除をもっと楽に!
全部を一気に完璧にやろう!と思うと、疲れちゃいますよね。
「今週末はサッシのホコリを吸うだけ」とか、「来週はリビングの窓ガラスだけ」みたいに、小さく分けて「ついで掃除」するのも、キレイを保つコツだと思います。
ご自身のライフスタイルに合った窓掃除の仕方を見つけて、ピカピカの窓で快適な毎日を過ごしてくださいね!



