東芝掃除機をお使いの方で、壊れやすいと感じている人がいるのではないでしょうか。
電源が入らない状況に直面したり、本体のオーバーヒートに悩まされたりした経験をお持ちの方もいるかもしれません。
実際に、東芝掃除機をお使いの方から、お手入れサインが頻繁に点滅する、ブラシが回転しない、ヘッドの修理が必要になったといったお悩みを耳にすることがあります。これらの症状は確かに起こりやすいものですが、多くの場合で適切な対処により解決できることが分かっています。
大切なのは、症状の原因を正しく理解し、適切なメンテナンスや対処法を知ることです。
この記事では、東芝掃除機でよく発生するトラブルの原因から具体的な解決方法、さらには長く使い続けるためのコツまで、幅広い情報をお伝えしていきます。
東芝掃除機が壊れやすいと言われる理由と対処法

東芝掃除機で起こりやすいトラブルには、実は共通した原因があります。
電源系統の問題から本体の熱暴走、お手入れ不足による機能低下まで、それぞれの症状に応じた適切な診断方法と対処手順を詳しく見ていきましょう。
電源が入らない時の確認ポイント
| 確認順序 | チェック項目 | 対処方法 |
|---|---|---|
|
1
電源プラグ
|
コンセントに奥までしっかり差し込まれているか | プラグを一度抜いて再度確実に差し込む |
|
2
バッテリー
|
コードレス機種のバッテリー残量 | 充電器にセットして充電状態を確認 |
|
3
チャイルドロック
|
安全機能がオンになっていないか | 取扱説明書でロック解除方法を確認 |
|
4
パーツ接続
|
ヘッド・延長管・ホースの接続状態 | 「カチッ」と音がするまで確実に差し込む |
|
5
保護装置
|
本体保護装置の作動状態 | 電源を切り約10分待ってから再試行 |
対処:プラグを一度抜いて再度確実に差し込む
対処:充電器にセットして充電状態を確認
対処:取扱説明書でロック解除方法を確認
対処:「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
対処:電源を切り約10分待ってから再試行
東芝掃除機の電源が入らない症状は、実は多くの場合で簡単な確認作業によって解決できることが分かっています。まず最初に確認していただきたいのは、電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているかという点です。
意外かもしれませんが、プラグが奥まで差し込まれていないケースは珍しくありません。また、コードレスタイプの掃除機をお使いの場合は、バッテリーの残量を確認してください。バッテリーが完全に放電している状態では、当然ながら電源は入りませんね。
次に確認したいのは、チャイルドロック機能の状態です。小さなお子さんがいるご家庭では、何かの拍子にチャイルドロック機能がオンになってしまっている可能性があります。この機能が作動していると、安全のために電源が入らない仕組みになっているんです。
さらに重要なポイントとして、各パーツの接続状況をチェックしましょう。ヘッド、延長管、ホースなどが正しく差し込まれていないと、安全装置が働いて電源が入らないことがあります。「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込み直してみてください。
もしこれらの確認作業を行っても電源が入らない場合は、本体保護装置が作動している可能性が考えられます。この装置は、モーターの過熱を防ぐために自動的に作動するもので、約10分程度待つことで解除されることが多いです。
ただし、電源コードに損傷がある場合や、内部の電気系統に問題がある場合は、安全のため使用を中止し、メーカーサポートに相談することをおすすめします。
本体が熱くなるオーバーヒートの原因

東芝掃除機の本体が異常に熱くなる現象は、主にモーターへの過度な負荷が原因で発生します。最も一般的な原因として、ダストカップやフィルターにゴミが蓄積しすぎている状態が挙げられるでしょう。
ダストカップがゴミでいっぱいになると、空気の流れが悪くなり、モーターが通常よりも多くの力を使って吸引しようとします。この状態が続くと、モーター部分に熱がこもってしまうんです。特にサイクロン式の掃除機では、フィルターの目詰まりが深刻な影響を与えることが知られています。
また、床ブラシやヘッド部分にゴミが詰まっている場合も、同様の現象が起こります。髪の毛や糸くずが回転ブラシに巻き付いていると、ブラシが正常に回転できず、モーターに負担がかかってしまいます。
吸込口やホース内に大きなゴミが詰まっている状況も、オーバーヒートの原因となります。この場合、空気の通り道が塞がれることで、モーターが過剰に働こうとして熱を持ってしまうのです。
東芝掃除機には、このようなオーバーヒートを防ぐための保護装置が搭載されています。本体温度が一定以上に上がると、自動的に運転を停止する仕組みになっているんですね。この保護装置が作動した場合は、電源を切って約10分間待つことで、再び使用できるようになります。
ただし、焦げ臭いにおいがする場合や、触れられないほど本体が熱くなっている場合は、すぐに使用を中止してください。このような症状は、モーターの故障や電気系統の異常を示している可能性があり、火災の危険性もあるからです。
お手入れサインが点滅する時の対応
| 点滅の原因 | 対処方法 |
|---|---|
|
ダストカップが満杯
|
ゴミが8割溜まった段階で空にする 定期的な確認でオーバーヒート予防 |
|
フィルターの汚れ
|
フィルターを取り外して清掃 サイクロン式は複数フィルターを確認 |
|
ブラシにゴミが絡まり
|
髪の毛や糸くずをハサミで除去 回転部分の動作を確認 |
|
サインが消えない
|
取扱説明書でリセット操作を確認 手動リセットが必要な機種もあり |
定期的な確認でオーバーヒート予防
サイクロン式は複数フィルターを確認
回転部分の動作を確認
手動リセットが必要な機種もあり
東芝の最新モデルには、適切なメンテナンス時期を知らせるお手入れサインが搭載されています。このサインが点滅した時は、掃除機が「お手入れが必要ですよ」と教えてくれているサインなんです。
まず最初に確認していただきたいのは、ダストカップの状態です。ゴミが8割程度溜まっている場合、多くの機種でお手入れサインが点滅し始めます。この段階で放置してしまうと、先ほどお伝えしたオーバーヒートの原因にもなりかねません。
フィルターの汚れも、お手入れサインが点滅する主要な原因の一つです。特にサイクロン式の掃除機では、複数のフィルターが使用されており、それぞれが適切に機能していないと、本体が異常を検知してサインを表示します。
床ブラシの回転部分にゴミが絡んでいる場合も、センサーが反応してお手入れサインが点滅することがあります。髪の毛や糸くずが巻き付いていると、ブラシの回転が正常に行われず、掃除機本体がメンテナンスが必要だと判断するのです。
お手入れサインが点滅している状態で使用を続けると、掃除機の性能が大幅に低下するだけでなく、モーターや他の部品に負担をかけることになります。また、吸引力の低下により、掃除時間が長くなってしまい、結果的に電気代も余計にかかってしまうでしょう。
サインが点滅した際の対応としては、まずダストカップを空にし、フィルターを清掃または交換することから始めてください。その後、床ブラシやヘッド部分の点検も行い、必要に応じて清掃を実施しましょう。
これらの作業を行った後も、お手入れサインが消えない場合は、取扱説明書を確認してリセット操作を行ってください。機種によっては、手動でサインをリセットする必要があるものもあります。
ブラシが回転しない・自走しない原因

東芝掃除機の回転ブラシが動かない症状は、実は多くのユーザーが経験する代表的なトラブルの一つです。この問題の原因を理解することで、適切な対処ができるようになります。
最も頻繁に見られる原因は、回転ブラシに髪の毛や糸くずが巻き付いている状態です。これらの異物がブラシの軸に絡みつくと、モーターの回転力が伝わらなくなり、ブラシが止まってしまいます。特に長い髪の毛は、ブラシの端から端まで巻き付いてしまうことが多いんです。
また、回転ブラシを支えるベルトが外れている場合も、同様の症状が現れます。ベルトは小さな部品ですが、ブラシの回転には欠かせない重要な役割を果たしています。取り外し清掃の際に、うっかりベルトを正しく取り付けていないケースもよく見受けられます。
自走機能付きのヘッドをお使いの場合、自動停止装置にゴミが詰まっていることも考えられます。この装置は床面から浮いた時に安全のためブラシを停止させる機能ですが、ゴミが詰まっていると、床に置いていても「浮いている」と誤認識してしまうのです。
さらに深刻な原因として、ヘッド内部のマイクロスイッチの故障があります。このスイッチは床面への接地を感知してブラシの回転をコントロールしているのですが、長期間の使用により劣化することがあります。実際に、多くのユーザーがこのマイクロスイッチの交換によって問題を解決しているんです。
電気系統の問題も考慮する必要があります。ヘッド内部の配線が断線していたり、基板に異常がある場合は、専門的な修理が必要になることもあります。
大きなゴミや薄い敷物を巻き込んでしまった場合も、安全装置が作動してブラシが停止します。この場合は、電源を切って異物を取り除いた後、約10分待つことで保護装置が解除され、再び使用できるようになります。
自動停止装置が作動する理由
| 作動原因 | 状況・詳細 | 対処方法 |
|---|---|---|
|
モーター過熱防止
|
ダストカップ満杯・フィルター目詰まりによる空気流れ悪化 | ゴミ除去・フィルター清掃後10分待機 |
|
床ブラシ異物詰まり
|
大きなゴミ・薄い敷物・カーテンの裾の巻き込み | 電源オフして異物を手動で取り出す |
|
ヘッド浮上検知
|
自走式ヘッドが床面から浮いた状態での安全停止 | ヘッドを床面にしっかり接地させる |
|
吸込口ゴミ詰まり
|
ホースや吸込口の大きなゴミによる吸引不良 | 詰まったゴミを除去して通気確保 |
|
長時間連続使用
|
30分超の連続使用による本体温度上昇 | 使用を中断し本体冷却を待つ |
東芝掃除機に搭載されている自動停止装置は、安全性を確保するための重要な機能です。この装置が作動する背景には、いくつかの明確な理由があります。
まず、最も一般的な作動理由として、モーターの過熱防止が挙げられます。ダストカップがゴミで満杯になったり、フィルターが目詰まりを起こしたりすると、空気の流れが悪くなり、モーターに過度な負荷がかかります。このような状況を検知すると、装置が自動的に運転を停止して、モーターを保護するのです。
床ブラシに異物が詰まった場合も、自動停止装置が作動します。特に大きなゴミや薄い敷物、カーテンの裾などを巻き込んでしまった時は、ブラシの回転が阻害され、モーターに異常な負荷がかかることを防ぐために停止します。
自走式ヘッドの場合、床面から浮いた状態になると自動停止装置が働きます。これは安全機能の一環で、ブラシが空回りすることによる事故を防ぐためです。掃除機を持ち上げたり、階段などでヘッドが浮いた状態になると、すぐに停止するようになっているんですね。
ホースや吸込口に大きなゴミが詰まっている場合も、装置が作動することがあります。この状況では、正常な吸引ができなくなり、モーターが過剰に働こうとするため、保護機能が働くのです。
長時間の連続使用による本体の温度上昇も、自動停止の原因となります。家庭用の掃除機は、一般的に30分程度の連続使用を想定して設計されています。それを超えて使用すると、安全のために停止することがあります。
自動停止装置が作動した場合の対処法は、まず電源を切って原因を取り除くことです。ゴミの除去、フィルターの清掃、異物の取り出しなどを行った後、約10分程度待ってから再度使用してください。この待機時間は、モーターの冷却や内部温度の正常化に必要な時間なんです。
ただし、頻繁に自動停止装置が作動する場合は、掃除機本体に何らかの異常がある可能性があります。このような状況では、メーカーサポートに相談することをおすすめします。
東芝掃除機が壊れやすい症状別の修理方法
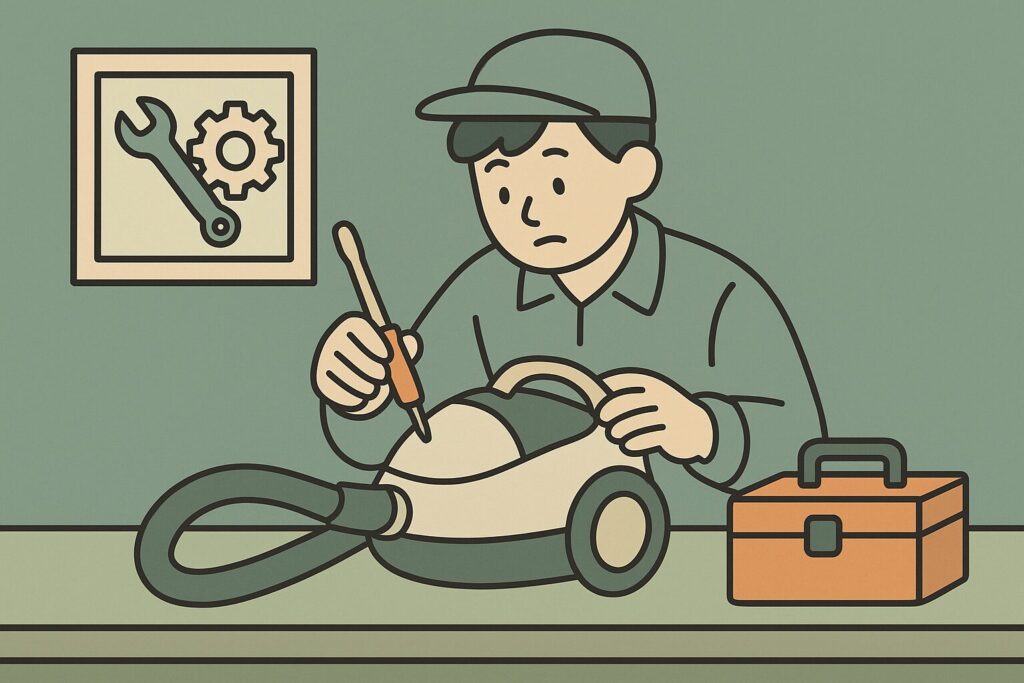
症状が特定できたら、次は具体的な修理作業です。
基本的なお手入れから部品交換まで、安全に作業を進めるための手順とポイントをご紹介します。また、修理か買い替えかの判断基準についても詳しく解説していきますね。
回転ブラシの手入れ方法と交換時期
回転ブラシの適切な手入れは、東芝掃除機を長く使用するために欠かせない作業です。まず、手入れの頻度についてですが、週に1〜2回の点検を心がけていただきたいと思います。
回転ブラシに髪の毛や糸くずが巻き付いている場合は、はさみを使って丁寧に切り取ってください。この作業を行う際は、必ず電源を切り、プラグをコンセントから抜いた状態で行うことが大切です。髪の毛は特にブラシの両端に巻き付きやすいので、端の部分を重点的にチェックしましょう。
ブラシに付着したほこりや細かいゴミは、お手入れ用のブラシや古い歯ブラシを使って取り除きます。この時、ブラシの毛を傷めないよう、やさしくこするようにしてください。
水洗いが可能な機種の場合、回転ブラシを取り外して水で洗浄することができます。ただし、洗浄後は完全に乾燥させることが重要です。濡れたままの状態で取り付けると、カビの発生や電気系統の故障の原因となってしまいます。陰干しで十分に乾かしてから、元の位置に戻してください。
ギア部分にゴミが付着している場合は、綿棒や小さなブラシを使って清掃します。この部分にゴミが蓄積すると、ブラシの回転がスムーズに行われなくなるため、定期的な清掃が必要なんです。
回転ブラシの交換時期については、ブラシの毛が著しく摩耗している場合や、毛が抜けて本数が減っている場合が目安となります。一般的には、1〜2年程度で交換を検討することが多いでしょう。使用頻度や掃除する環境によって、交換時期は前後することがあります。
また、ブラシの毛が変形して元に戻らない場合や、回転軸に歪みが生じている場合も、交換のタイミングです。このような状態で使用を続けると、床面を傷つけてしまう可能性があります。
交換用の回転ブラシは、東芝の正規部品を使用することをおすすめします。互換品を使用した場合、サイズが合わなかったり、性能が劣る場合があるからです。購入前には、必ずお使いの掃除機の型番を確認してください。
ヘッド修理と床ブラシ交換の手順

| 作業手順 | 詳細内容 | 注意点・ポイント |
|---|---|---|
|
1
電源OFF・分解準備
|
電源を切りプラグを抜く お手入れカバーをツマミ・レバーで取り外し |
安全のため必ず電源を完全に切断 |
|
2
回転ブラシ取り外し
|
軸受けホルダーを外す ブラシ本体を持ち上げて取り出し |
ベルトの位置と状態を確認 |
|
3
内部清掃作業
|
ほこり・髪の毛の除去 車輪部分をピンセットで清掃 |
自動停止装置周辺も丁寧に清掃 |
|
4
部品交換・組み立て
|
新しい床ブラシを正しい位置に設置 ベルトをギアに確実に装着 |
部品番号を事前に確認 |
|
5
最終確認・完了
|
各部品の位置確認 お手入れカバーをしっかり装着 |
配線挟み込みがないかチェック |
ヘッド部分の修理は、多くの場合でユーザー自身が行える作業です。ただし、安全性を最優先に考えて、慎重に作業を進めていただきたいと思います。
まず、ヘッドの分解作業から始めます。電源を切り、プラグをコンセントから抜いた状態で、お手入れカバーを取り外してください。多くの機種では、カバーの両側にあるツマミやレバーを操作することで、簡単に外すことができます。
次に、回転ブラシを取り外します。ブラシの両端にある軸受けホルダーを外し、ブラシ本体を持ち上げるようにして取り出してください。この時、ベルトの位置も確認しておきましょう。ベルトが外れている場合は、これが回転しない原因の可能性があります。
ヘッド内部の清掃では、蓄積されたほこりや髪の毛を取り除きます。実際に分解してみると、想像以上にゴミが溜まっていることが多いんです。この汚れが原因で、ブラシの回転不良や異音が発生することがあります。
車輪部分にゴミが絡んでいる場合は、ピンセットを使って慎重に取り除いてください。車輪が正常に回転しないと、掃除機の操作性が悪くなってしまいます。
自動停止装置の周辺も、重要な清掃ポイントです。この装置にゴミが詰まっていると、床に置いていてもブラシが回転しないことがあります。小さなブラシや綿棒を使って、丁寧に清掃しましょう。
床ブラシの交換が必要な場合は、まず正しい部品番号を確認してください。東芝の公式サイトや取扱説明書で、お使いの機種に対応する部品番号を調べることができます。
交換作業は、分解の逆の手順で行います。まず新しい床ブラシを正しい位置に設置し、ベルトをギアに確実に掛けてください。ベルトが正しく装着されていないと、ブラシが回転しません。
組み立て時の注意点として、各部品が正しい位置に収まっているかを必ず確認してください。特に配線が挟まれていないか、無理な力がかかっていないかをチェックしましょう。
最後に、お手入れカバーを取り付けて作業完了です。カバーが浮いていたり、隙間があったりしないよう、しっかりと装着してください。
臭いが発生した場合の対処方法
東芝掃除機から不快な臭いが発生する場合、その原因を特定して適切な対処を行うことが重要です。臭いの種類によって、対処法も異なってきます。
最も一般的な臭いの原因は、ダストカップやフィルターに蓄積された古いゴミです。特に、食べ物のカスやペットの毛などが長期間放置されると、嫌な臭いの原因となります。この場合は、ダストカップを空にして、水洗い可能な部品は中性洗剤を使って清掃してください。
カビの臭いがする場合は、湿った状態で掃除機を保管していた可能性があります。フィルターやダストカップを水洗いした後、完全に乾燥させずに取り付けてしまうと、カビが発生することがあるんです。このような場合は、該当部品を再度洗浄し、十分に乾燥させてから使用しましょう。
焦げ臭い臭いがする場合は、非常に注意が必要です。これはモーターの過熱や電気系統の異常を示している可能性があり、火災の危険性もあります。このような臭いを感じた場合は、すぐに使用を中止し、メーカーサポートに相談してください。
ペット特有の臭いが気になる場合は、専用の消臭剤を使用することも効果的です。ただし、掃除機内部に直接スプレーするのではなく、清掃後の部品に使用するようにしてください。
フィルターの交換も、臭い対策として有効な方法です。特に紙パック式の場合、紙パック自体が臭いの発生源となることがあります。定期的な交換により、臭いの問題を根本的に解決できることが多いでしょう。
HEPAフィルターを搭載している機種では、フィルターの寿命にも注意が必要です。フィルターが劣化すると、本来の性能を発揮できなくなり、臭いの原因となることがあります。
掃除機の保管方法も、臭い予防には大切な要素です。使用後は、ダストカップを空にし、各部品を清掃してから保管するようにしてください。また、湿度の高い場所での保管は避け、風通しの良い場所に置くことをおすすめします。
定期的なメンテナンスを行うことで、臭いの発生を予防することができます。週に一度はダストカップとフィルターの状態をチェックし、必要に応じて清掃を行いましょう。
モーターが動かない時の診断方法

掃除機のモーターが動かない症状は、様々な原因によって引き起こされます。正確な診断を行うために、段階的にチェックしていきましょう。
まず最初に確認すべきは、電源供給の状況です。コンセントに電気が来ているか、他の電気製品を使って確認してください。また、掃除機のプラグがしっかりと差し込まれているかも重要なポイントです。
コードレスタイプの場合は、バッテリーの状態を詳しく調べる必要があります。充電器にセットして、正常に充電が開始されるかを確認してください。バッテリーが完全に放電している場合、少し時間をおいてから再度電源を入れてみましょう。
電源スイッチの状態も確認ポイントの一つです。スイッチが正常に作動しているか、押し込み具合に異常がないかをチェックしてください。長期間使用していると、スイッチ内部の接点が劣化することがあります。
本体保護装置の作動も考慮する必要があります。過熱やゴミの詰まりによって保護装置が働いている場合、モーターは動作しません。この場合は、電源を切って約10分待ち、保護装置の解除を待ってから再度試してみてください。
モーターに異音がする場合や、回転音が普段と異なる場合は、モーター自体の故障が疑われます。この状況では、専門的な修理が必要となることが多いでしょう。無理に使用を続けると、他の部品にも影響を与える可能性があります。
電源コードの断線も、モーターが動かない原因として考えられます。コードを軽く動かしながら電源を入れてみて、反応があるかどうかを確認してください。ただし、この作業は感電の危険があるため、十分注意して行ってください。
内部の配線に問題がある場合、外見上は正常に見えてもモーターが動作しないことがあります。このような電気系統の故障は、専門知識がないと診断が困難です。
モーターの寿命も考慮する必要があります。一般的に、掃除機のモーターは5〜10年程度の寿命とされています。長期間使用している掃除機で、これまでに挙げた確認事項に問題がない場合は、モーターの寿命が考えられるでしょう。
診断の結果、モーター交換が必要と判断された場合は、修理費用と新品購入費用を比較検討することをおすすめします。修理費用が高額になる場合は、新しい掃除機への買い替えを検討した方が経済的かもしれません。
掃除機の寿命と買い替えタイミング

掃除機の寿命を正しく把握することは、計画的な買い替えのために非常に大切です。内閣府の消費動向調査によると、掃除機の平均使用年数は約7年となっています。
掃除機のタイプによって、寿命にも違いがあることを知っておきましょう。紙パック式の掃除機は約10年、サイクロン式は約7年程度が目安とされています。紙パック式の方が長寿命なのは、紙パック自体がフィルターの役割を果たし、モーターへの負担を軽減しているからです。
コードレス掃除機の場合、バッテリーの寿命が重要な要素となります。リチウムイオンバッテリーの寿命は一般的に3〜5年程度で、本体よりも先にバッテリーの限界が来ることが多いんです。バッテリー交換には数万円の費用がかかるため、この時期が買い替えのタイミングとなることも珍しくありません。
買い替えを検討すべき症状として、まず吸引力の著しい低下が挙げられます。フィルター清掃やダストカップの手入れを行っても改善されない場合は、モーターの劣化が考えられるでしょう。
電源の不安定さも重要なサインです。電源が入りにくくなったり、使用中に突然停止したりする症状が頻繁に起こる場合は、電気系統の劣化が進んでいる可能性があります。
異音や振動の発生も、寿命が近づいているサインの一つです。モーターやファンの軸受けが摩耗すると、今までになかった音や振動が発生するようになります。
本体の発熱や焦げ臭いにおいは、特に注意が必要な症状です。これらの症状が現れた場合は、安全のため即座に使用を中止し、買い替えを検討してください。
修理部品の入手可能性も、買い替えタイミングの判断材料となります。東芝では、補修用性能部品の保有期間を6年と定めています。製造終了から6年を超えた掃除機は、故障しても修理できない可能性が高くなるのです。
経済的な観点から考えると、修理費用が新品価格の半分を超える場合は、買い替えを検討した方が良いでしょう。また、最新機種は省エネ性能が向上しているため、古い掃除機を使い続けるよりも、電気代の節約効果が期待できることもあります。
買い替え時期としては、新製品の発売時期を狙うとお得になることが多いです。東芝では通常、春から夏にかけて新モデルが発表されるため、この時期には旧モデルが安くなる傾向があります。
私も家電量販店で働いていて感じるのですが、掃除機の調子が悪くなってから慌てて買い替えを検討する方が多いんです。しかし、事前に買い替え時期を想定しておくことで、より良い条件で新しい掃除機を購入できるようになります。
総括:東芝掃除機が壊れやすいと感じたら
それでは最後に、この記事の内容をまとめます。



