スーパーに行くとたくさんの種類のお米が並んでいて、毎日食べるお米だからこそ、精米にこだわってみたいと思ったことはありませんか?
でも、分づき米のメリットやデメリット、それに無洗米と普通米の違いなど、どれを選べばいいのか迷ってしまいますよね。
また、精米のやり方にも、コイン精米機や家庭用精米機といった選択肢があります。特に家庭用精米機はどれがいいのか、気になっている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、そんなお米の精米に関するさまざまな疑問をスッキリ解決していきます。
お米の精米はどれがいい?種類と特徴
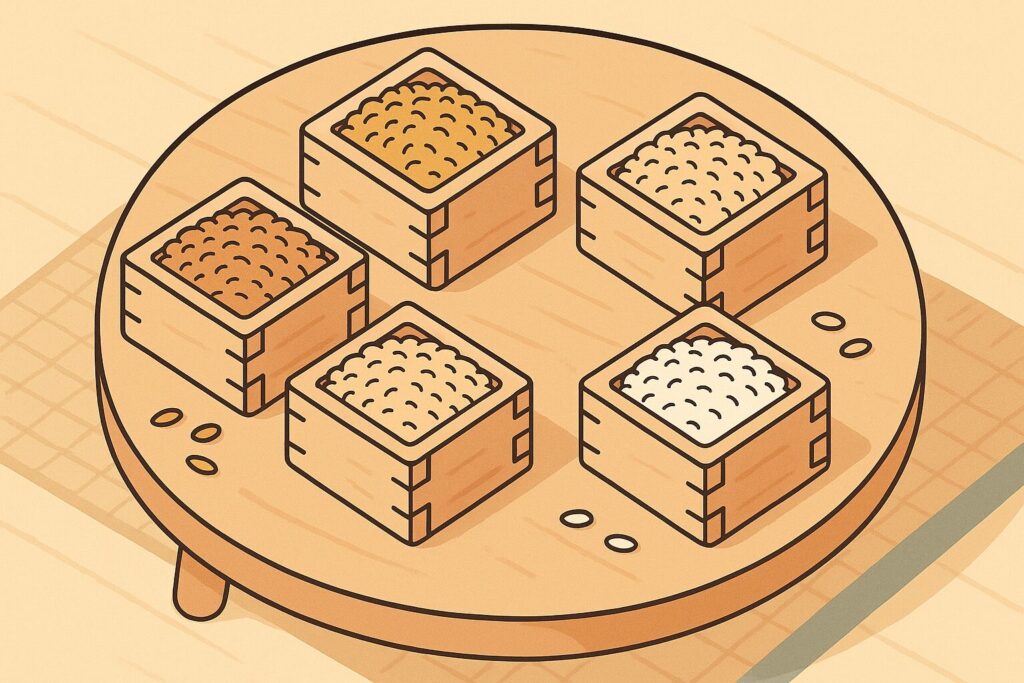
- まずは知っておきたい精米の種類
- 分づき米のメリット
- 分づき米のデメリット
- 無洗米と普通米の違い
まずはじめに、お米の精米にはどんな種類があって、それぞれにどんな特徴があるのかを見ていきましょう。
お米は精米の度合いによって、味も栄養価も大きく変わってくるんですよ。ご自身の好みや食生活に合ったお米を見つけるための第一歩ですね。
まずは知っておきたい精米の種類
「精米」とは、収穫したお米の籾殻(もみがら)を取り除いた状態の玄米から、ぬか層や胚芽(はいが)を取り除いて白米にする作業のことです。
このぬか層をどれくらい取り除くかによって、お米の呼び方や特徴が変わってきます。
一般的に、数字が小さいほど玄米に近く、大きいほど白米に近くなります。それぞれの特徴を下の表にまとめてみました。
| 種類 | 精米度合い | 見た目 | 食感・風味 | 栄養価 |
|---|---|---|---|---|
| 玄米 | 0分づき | 茶色い | 少しボソボソ。独特の風味がある | 非常に高い |
| 3分づき米 | 3割除去 | 玄米に近い茶色 | 玄米に近いが、少し食べやすい | 高い |
| 5分づき米 | 5割除去 | 少し白っぽくなる | 白米の食感に近づき、風味も残る | 比較的高い |
| 7分づき米 | 7割除去 | 白米に近い | 白米とほぼ同じで食べやすい | 白米よりは高い |
| 白米 | 10割除去 | 白い | ふっくらもちもち。甘みが強い | 低い |
上白米や無洗米とは?
上白米(じょうはくまい)は、通常の白米よりもさらに磨きをかけて、残っている「肌ぬか」をきれいに取り除いたお米です。より白く、ツヤがあり、雑味のないクリアな味わいが特徴ですね。
一方、無洗米(むせんまい)は、特殊な技術で肌ぬかを取り除いてあるので、お米を研がずに炊けるのが最大の特徴です。これについては後ほど詳しく解説しますね。
このように、精米度合いを選ぶことで、栄養価と食べやすさのバランスを自分好みに調整できるのが、お米の面白いところなんです。
分づき米のメリット
最近、健康を意識されるお客様からよくご質問いただくのが「分づき米」です。分づき米を選ぶ一番のメリットは、やはり栄養価の高さと食べやすさのバランスが良い点だと思います。
玄米が健康に良いとは分かっていても、独特の食感や風味が苦手で続かなかった…という方も少なくないのではないでしょうか。
分づき米なら、玄米の栄養を残しつつ、白米に近い感覚で美味しく食べられるのが嬉しいポイントですね。
分づき米の主なメリット
ビタミン・ミネラルが豊富
ぬか層や胚芽には、エネルギー代謝を助けるビタミンB群や、骨の健康に欠かせないマグネシウムなどのミネラルがたくさん含まれています。これらは白米にするとほとんど失われてしまう栄養素なんです。
食物繊維がたっぷり
玄米ほどではありませんが、白米に比べて食物繊維が豊富です。腸内環境を整える手助けをしてくれるので、お通じが気になる方にもおすすめですよ。
豊かな風味と食感
お米本来の風味や甘みが感じられ、「噛めば噛むほど味が出る」というお客様も多いです。プチプチとした食感も楽しめますね。
特に、初めて分づき米に挑戦するなら、白米に一番近い7分づきから試してみるのがおすすめです。慣れてきたら5分づき、3分づきと、少しずつ玄米に近づけていくのが良いと思います。
分づき米のデメリット
良いことずくめに見える分づき米ですが、いくつか知っておきたいデメリットや注意点もあります。購入してから「こんなはずじゃなかった!」とならないように、しっかり確認しておきましょう。
一番の注意点は、白米に比べて酸化しやすく、劣化が早いことです。ぬか層には脂質が含まれているため、空気に触れると酸化が進み、風味が落ちたり、ぬか臭さの原因になったりします。
分づき米の注意点
保存方法に注意が必要
酸化を防ぐため、購入後は密閉容器に入れて冷蔵庫で保存するのが基本です。できれば1〜2週間で食べきれる量を購入するのが理想ですね。
炊き方に少しコツがいる
ぬか層が残っている分、白米より水を吸いにくい性質があります。そのため、浸水時間を白米より長め(最低でも1〜2時間)にとるのが美味しく炊くポイントです。水の量も少し多めに調整すると、ふっくらと炊き上がりますよ。
消化に負担がかかることも
食物繊維が豊富ということは、裏を返せば消化に少し時間がかかるということです。胃腸が弱い方や小さなお子さん、ご年配の方が食べる場合は、少し柔らかめに炊いたり、少量から試したりすると安心です。
こうした点を理解しておけば、分づき米をより美味しく、安心して楽しむことができると思います。手間をかける価値のある美味しさと栄養が、分づき米にはありますね。
無洗米と普通米の違い
次に、最近すっかり定着した「無洗米」についてです。時短になって便利そうだけど、普通のお米と何が違うの?味は美味しいの?と疑問に思っている方も多いですよね。
無洗米とは、その名の通りお米を研がずに炊けるように加工されたお米のことです。
通常、精米した白米の表面には「肌ぬか」という粘着性の高いうまみ層が残っています。普通のお米を研ぐのは、この肌ぬかを取り除くためなんです。無洗米は、工場でこの肌ぬかをあらかじめ取り除いてあるんですね。
それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
| 無洗米 | 普通米 | |
|---|---|---|
| メリット | ・研ぐ手間が省け、時短になる ・節水、環境にやさしい ・栄養の流出が少ない | ・銘柄の種類が豊富 ・価格が比較的安い傾向 |
| デメリット | ・価格が少し高め ・炊くときの水加減にコツがいる | ・研ぐ手間がかかる ・とぎ汁が出る |
「無洗米は美味しくない」というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、それは少し前の話かもしれません。今の無洗米は加工技術がすごく進歩していて、味も普通のお米とほとんど変わらないんですよ。
むしろ、研ぎすぎによるお米の割れや、うまみ層の流出がない分、美味しく炊けるという声も聞きます。
炊くときのポイントは、お水を少し多めに入れることです。
肌ぬかが無い分、お米の正味量が多くなるので、計量カップで計ったお米1合に対して、大さじ1〜2杯ほどお水を足してあげると、ふっくら美味しく炊き上がりますよ。
炊飯器に無洗米用の目盛りがあれば、それに合わせればOKです。
自宅での精米はどれがいい?方法と選び方

- 自宅でできる精米のやり方
- コイン精米機と家庭用精米機の比較
- 家庭用精米機はどれがいい?
さて、ここまではお米の種類について見てきました。
ここからは、どうやって好みの精米度合いのお米を手に入れるか、その方法について解説していきます。
「精米」と聞くと少し難しそうに感じるかもしれませんが、実は意外と手軽にできるんですよ。
自宅でできる精米のやり方
精米したてのお米を食べる方法は、大きく分けて3つあります。
1. 精米されたお米を買う
一番手軽な方法ですね。スーパーなどで「7分づき米」のように、すでに精米された状態で売られているものを購入します。ただし、分づき米は先ほどもお伝えしたように酸化しやすいので、精米年月日が新しく、少量パックのものを選ぶのがおすすめです。
2. コイン精米機を利用する
玄米を購入してきて、お米屋さんやJA、スーパーの駐車場などにあるコイン精米機で自分で精米する方法です。一度にまとまった量を精米できるのが特徴です。
3. 家庭用精米機を使う
自宅に精米機を置いて、炊く直前に食べる分だけ精米する方法です。いつでも精米したての一番美味しい状態のお米が食べられる、とても贅沢な方法ですね。
どの方法にも良い点がありますので、ご自身のライフスタイルに合わせて選ぶのが一番です。
次の項目では、「コイン精米機」と「家庭用精米機」をさらに詳しく比較してみましょう。
コイン精米機と家庭用精米機の比較
「自分で精米してみたい」と思ったとき、多くの人が迷うのがコイン精米機と家庭用精米機のどちらを選ぶか、という点ではないでしょうか。
私もお客様からよく相談を受けますが、それぞれにメリット・デメリットがあるので下の表で比較してみましょう。
| コイン精米機 | 家庭用精米機 | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 不要 | 本体代(1万円~)が必要 |
| 1回あたりの料金 | 10kgで100円程度 | 電気代のみ |
| 手軽さ | 重いお米を運ぶ手間がかかる | 自宅でいつでも手軽にできる |
| 精米できる量 | 10kg~と大容量 | 1合~5合程度と少量 |
| お米の鮮度 | 一度に精米するため、後半は鮮度が落ちる | いつでも精米したてが食べられる |
| メンテナンス | 不要 | 使用後の掃除が必要 |
- 一度にたくさんの量(10kg以上)を精米したい
- 精米機を置くスペースがない、初期費用をかけたくない
- お米を運ぶのが苦にならない
- いつでも精米したての最高の味を楽しみたい
- 少量ずつ、色々な分づき米を試してみたい
- 新鮮な米ぬかを料理やお掃除、ぬか漬けなどに活用したい
コイン精米機は手軽に始められますが、やはり一番の魅力は、毎日精米したてのご飯が食べられる家庭用精米機にあると私は思います。お米の味が本当に変わるので、一度体験すると戻れなくなるかもしれませんよ。
家庭用精米機はどれがいい?
「よし、家庭用精米機を買ってみよう!」と思っても、いざ選ぶとなると、いろいろな種類があって迷ってしまいますよね。
ここでは、家電量販店で働いている経験から選ぶときのポイントをいくつかご紹介したいと思います。
まず、家庭用精米機には主に3つの精米方式があります。それぞれ特徴が違うので、ご自身の使い方に合ったものを選びましょう。
精米方式で選ぶ
| 方式 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| かくはん式 | カゴの中で羽根が回転し、お米同士をこすり合わせて精米する。 | ・価格が手頃なモデルが多い ・お手入れが比較的簡単 | ・運転音が大きめ ・お米が割れやすいことがある |
| 圧力式 | 圧力をかけながらお米を循環させて、優しくぬか層を剥がしていく。 | ・お米が割れにくく、味が良い ・運転音が静かめ | ・価格が高め ・構造が複雑でお手入れが少し大変 |
| 対流式 | かくはん式に似ているが、お米の対流を利用してムラなく精米する。 | かくはん式と圧力式の中間的な特徴を持つ。 | – |
最近の主流はかくはん式ですが、静音性やお米の仕上がりにこだわるなら圧力式もおすすめです。
チェックしたい4つのポイント
1. 容量
一度に精米できる量です。一人暮らしなら1〜2合、ご家族なら4〜5合炊けるモデルが一般的です。大家族やまとめて精米したい場合は、1升(10合)タイプもありますよ。
2. 精米モードの豊富さ
白米だけでなく、「3分・5分・7分づき」などの分づき米モードや、胚芽を残す「胚芽米」モード、古くなった白米の表面を磨く「リフレッシュ」機能など、多彩なモードがあると楽しさが広がります。
3. お手入れのしやすさ
精米すると必ず米ぬかが出ます。ぬかボックスやカゴ、羽根などが簡単に取り外せて、丸洗いできるモデルを選ぶと、清潔に保ててとても楽ですよ。
4. 静音性
特に集合住宅にお住まいの方や、早朝・夜間に使う可能性がある方は、運転音の大きさも重要なポイントになります。静音設計のモデルを選ぶと安心ですね。
これらのポイントを参考に、ご自身のライフスタイルにぴったりの一台を見つけてみてください。毎日のごはんが、もっと美味しく、もっと楽しくなるはずです。
具体的なおすすめモデル2選
「ポイントは分かったけど、具体的にはどれがいいの?」という方のために、お店でも人気があって、自信を持っておすすめできるモデルを2つご紹介しますね。
【家族みんなで楽しむなら】アイリスオーヤマ 精米機 RCI-B5-W
まずおすすめしたいのが、アイリスオーヤマのこちらのモデルです。一番の特徴は、お米の銘柄に合わせて精米具合を調整してくれる「銘柄純白づき」機能ですね。
「こしひかり」や「ゆめぴりか」など、40銘柄のお米の美味しさを最大限に引き出してくれます。お米好きにはたまらない機能じゃないでしょうか。
操作もシンプルで分かりやすく、ぬかボックスや精米かごも簡単に取り外して水洗いできるので、お手入れが簡単なのも嬉しいポイント。5合まで対応しているので、ご家族で使うのにぴったりの一台だと思います。
【コンパクトさと静かさで選ぶなら】ツインバード コンパクト精米器 MR-E751W
「キッチンに置くスペースがあまりない」「運転音が気になる」という方には、ツインバードのこちらがおすすめです。とてもコンパクトなので収納場所に困りませんし、静音性にもこだわって設計されているので、集合住宅でも気兼ねなく使えると評判ですよ。
白米の表面を少しだけ削って鮮度をよみがえらせる「白米みがきモード」や、栄養価の高い胚芽を残して精米する「胚芽モード」など、便利な機能もしっかり搭載されています。
シンプルで使いやすく、初めて家庭用精米機を使う方にもぴったりのモデルですね。
総括:お米の精米はどれがいいか
それでは最後に、この記事の内容をまとめます。



