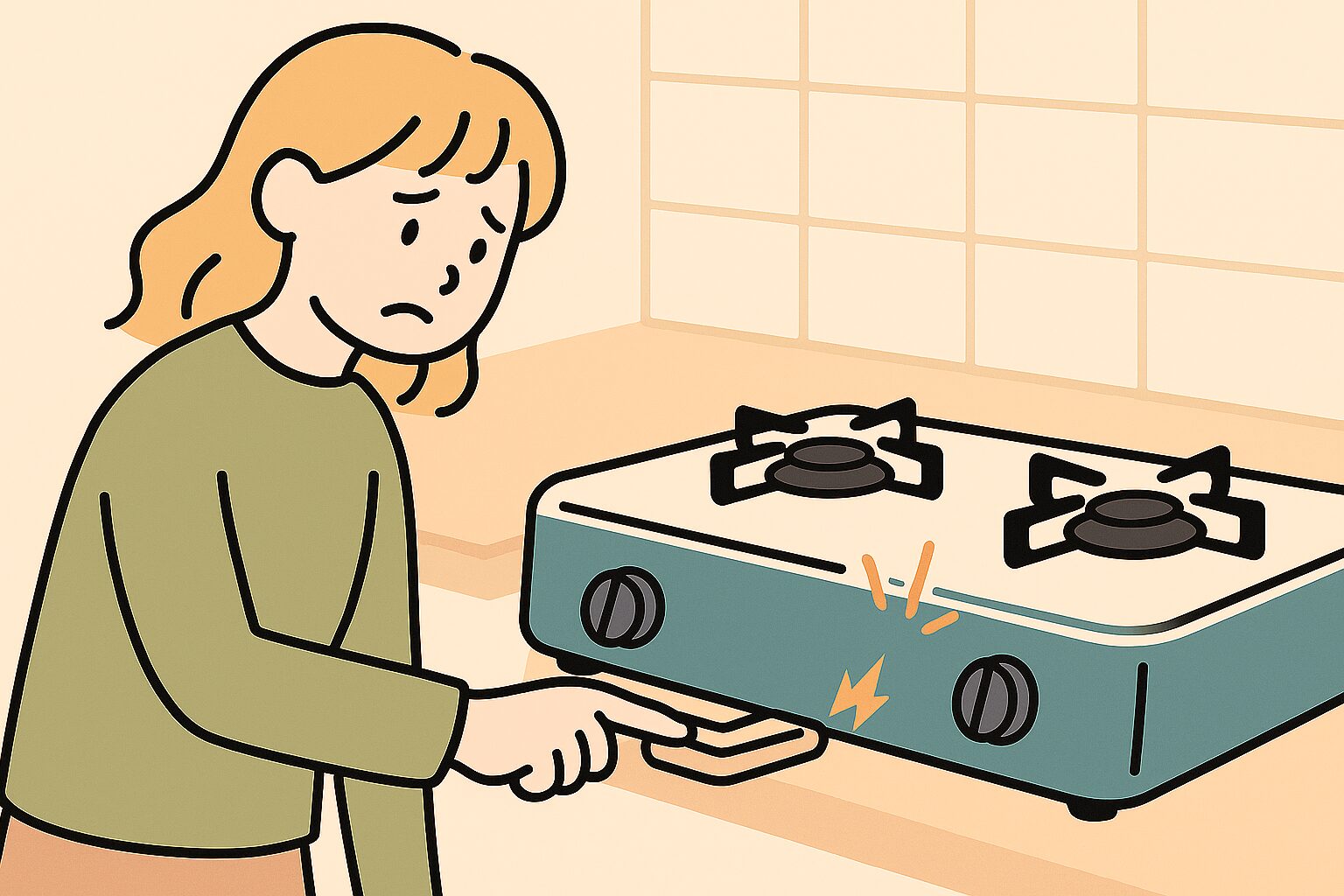ガスコンロがチチチとなるだけで、火がつかない症状に悩んでいませんか?
朝の忙しい時間、コンロのつまみをひねると火花を飛ばす音だけが響き、肝心の炎が上がらない。
そんな経験、誰しも一度はあるはずです。
実はこの症状、多くの場合は故障ではなく、適切な掃除やちょっとした見直しで改善できることをご存じでしょうか。
家電量販店で働いていると、コンロが点火しないというご相談を本当によく受けます。
お客様の多くが修理や買い替えを検討されていますが、実際には電池交換やバーナー周りの簡単なメンテナンスで解決するケースがほとんどなんです。
チチチという音の強弱によって原因が異なることや、バーナーキャップの目詰まり、点火プラグの汚れ、立ち消え安全装置のトラブルなど、自分で対処できるポイントは意外と多くあります。
また、一瞬火がついてもすぐ消えてしまう場合や、水濡れが原因で点火不良を起こしているケースも少なくありません。
この記事では、ガスコンロが点火しない原因を音の状態から診断する方法、各部品の正しい掃除手順、電池交換のタイミング、バーナーキャップの適切な設置方法まで、家庭ですぐに実践できる対処法を詳しく解説していきます。
修理業者を呼ぶ前に、まずはご自分でできることから試してみませんか?
ガスコンロがチチチとなるだけでつかない原因と掃除方法

ガスコンロの「チチチ」という音はするのに火がつかない時、まず疑うべきは「汚れ」や「水濡れ」といった物理的な原因なんです。
ここでは、火がつかない主な原因の見分け方と、ご自身でできる基本のお掃除方法について、詳しく見ていきましょう!
チチチ音の強弱でわかる原因
まず最初にチェックしてほしいのが、その「チチチ」っていう音の「強さ」と「速さ」なんです。実はこの音の状態で原因がどこにあるのか、だいたい見当がつくことが多いんですよ。
力強く、速い「チチチ」音の場合
「チチチチッ!」と元気よく、速い間隔で音が鳴っている場合、これは点火装置に電気を送る「電池」のパワーは十分にある証拠です。これは点火システムの基盤などが機能しているサインなんですね。
じゃあ、なぜ火がつかないのか?
それは、元気な火花は飛んでいるのに「火花」と「ガス」が出会うのを邪魔する「何か」があるからです。
主な原因は…
- バーナーキャップ(炎の出口)の汚れや目詰まり
- 点火プラグ(火花が飛ぶピン)の汚れや水濡れ
- バーナーキャップの設置ズレ
といった、物理的な問題がほとんどだと思います。
この場合は、後で詳しくお話しする「お掃除」や「部品の再設置」で解決する可能性がとっても高いですね。
弱々しく、遅い「チチチ」音の場合
「チ……チ……チ……」という感じで、音が弱かったり、間隔がゆっくりだったりする場合。
これはもう、十中八九「電池切れ」のサインです。
お店でも、「音は鳴ってたから、電池じゃないと思った」っておっしゃるお客様、すごく多いんです。でも、火花を飛ばすのと、ガスに着火させるのは別物なんですね。
火花が飛ぶギリギリの電力は残っていても、ガスに火をつけるほどの熱量(エネルギー)がない「弱いスパーク」しか起きていないんです。この場合は、お掃除よりも先に、まずは電池交換を試してみてください。
「チチチ」音 診断マトリクス
音の状態をチェックして、最初に何をすべきか確認しましょう。
| 音の状態 | 推定される原因 | 最初にやるべき対処法 |
|---|---|---|
| 強く、速い「チチチ」音 | 部品の汚れ、水濡れ、設置ズレ | 各部品の掃除・点検(この後の章へ) |
| 弱く、遅い「チチチ」音 | 点火用乾電池の消耗 | 電池交換(この後の章へ) |
| 音が全くしない | 電池の完全消耗、内部の故障 | 電池交換 → ダメなら要点検 |
音が全くしない場合は、電池が完全に切れているか、内部の電気系統の故障も考えられます。
まずは電池交換から試してみるのが良いと思います。
すぐ消える?センサーの汚れかも
「チチチ…ボッ!(点火)…スッ…(消火)」
こんな風に、一瞬は火がつくのに、すぐに消えてしまう…という症状に悩まされている方も多いんじゃないでしょうか?
これは、火がつかないのとは、また別の原因が考えられます。
この症状の犯人は、ほぼ間違いなく「立ち消え安全装置(安全センサー)」の汚れです。
立ち消え安全装置って?
点火プラグ(火花が飛ぶ白いピン)の隣にもう一つ、金属製の突起(ピン)がありますよね。これが「立ち消え安全装置」(熱電対とも言います)です。
このセンサーは「炎の熱」を感知して、「あ、今、火がちゃんとついてるな」と判断したらガスを流し続ける、という大事な役割を持っています。
汚れるとどうなる?
このセンサーの先端が、料理中の吹きこぼれや油ハネ、焦げ付きなどで汚れてしまうと、どうなるでしょう?
センサーが汚れで覆われて、せっかく点火した炎の熱を感じ取れなくなってしまうんです。
すると、コンロは「あれ?火がついてないぞ!危ない!」と勘違いして、安全のためにガスの供給をピタッと止めてしまいます。これが「一瞬つくけどすぐ消える」の正体なんですね。
センサーのお掃除方法
お掃除方法は、点火プラグと同じでとってもデリケートなんです。
まずは「やわらかい布」で先端の金属部分を優しく拭いてみてください。こびりついた汚れがある場合は、「毛がやわらかい歯ブラシ」で軽くこすってみましょう。
センサー掃除の注意点
このセンサーはコンロの安全を守る心臓部です。金属たわしやクレンザーでゴシゴシこすると、センサーが傷ついて感度が鈍ったり、故障したりする原因になります。
必ず、やわらかい布や歯ブラシで「優しく」拭き掃除してくださいね。
家電業界に勤めるものとしては、そもそも「吹きこぼれさせない」工夫も大事だなって思います。
最近は、パナソニックの「IHクッキングヒーター」や、シャープの「ヘルシオ ホットクック」みたいな自動調理鍋も、吹きこぼれ防止機能がすごく進化しています。コンロ掃除の手間を減らしたいってお客様にも人気ですよ。
ガスコンロでも、リンナイの「デリシア」やノーリツの「プログレ」など、上位モデルには温度を自動でキープしてくれる機能がついていて、吹きこぼれリスクを減らせるようになっています。
お掃除の手間を考えると、こういう機能も嬉しいポイントですよね。
バーナーキャップの目詰まり掃除
さて、チチチ音が強いのに火がつかない原因のNo.1、「バーナーキャップ」のお掃除に移りましょう!
バーナーキャップは、ガスと空気を混ぜて、炎を均一に出すための「炎の出口」です。ここが汚れていると、ガスの通り道がふさがれてしまいます。
目詰まりの原因は?
やっぱり多いのは、お味噌汁や煮物の「吹きこぼれ」ですね。あとは、炒め物の「油ハネ」や、それが焦げ付いたものです。
炎が出る小さな穴(溝)が詰まってしまうと(これを「目詰まり」と言います)、ガスが正常に出てこられません。いくら火花が飛んでも肝心のガスが来なければ火はつきませんよね。
バーナーキャップの掃除手順
安全にお掃除するために、まずは準備をしっかりしましょう。
- 安全の確保
まず、コンロのガス栓を閉めます。換気扇を回すか、窓を開けて換気も忘れずに。 - 完全に冷ます
調理直後は熱いので絶対に触らないでください!火傷しますよ。最低でも30分は置いて、五徳(ゴトク)やバーナーキャップが完全に冷めたのを確認します。 - 取り外して洗う
五徳とバーナーキャップを取り外します。やわらかいスポンジに台所用中性洗剤をつけて、全体の汚れを優しく洗いましょう。 - 【最重要】目詰まりを取る
小さな穴や溝に詰まった焦げ付きは、「竹串」や「爪楊枝」など、金属ではない細いもので、一つずつ丁寧に汚れをかき出します。地道な作業ですが、ここが一番大事です! - 完全に乾かす
洗浄後は、水気をキレイに拭き取り、風通しの良い場所で完全に乾燥させます。(水濡れも点火不良の原因になるので、しっかり乾かしてくださいね)
金属ブラシや針金は絶対NG!
「早く汚れを取りたい」と思って、金属ブラシや針金でガシガシこすりたくなる気持ち、わかります。でもそれは絶対にダメ!
部品を傷つけたり、ガスの出る穴を変形させてしまったりして、かえって正常な炎が出なくなる原因になります。必ず竹串や爪楊枝を使ってくださいね。
最近のガスコンロ、例えばリンナイやパロマの上位モデルは、このバーナーキャップや五徳が食洗機対応になっているものも増えました。
お店でも「コンロの掃除が面倒で…」というお客様には、こういう「洗いやすい」モデルをおすすめすることが多いですね。
パナソニックの「ラクシーナ」みたいなシステムキッチンと合わせると、食洗機でまとめて洗えて本当に便利だと思います。お手入れが楽だとキレイを保ちやすいですからね。
点火プラグの正しい掃除方法

次は、火花(スパーク)を飛ばす「点火プラグ」のお掃除です。
これは、バーナーの根元にある白いセラミック製の突起(ピン)のこと。ここが汚れていると、火花が飛ばなくなったり、飛んでもすごく弱くなったりします。
汚れの原因は?
バーナーキャップと同じく、吹きこぼれや油ハネ、焦げ付きです。
この白い部分が茶色く焦げて汚れていませんか?
そこが汚れていると、電気がうまく流れず、正常な火花が出せないんです。
点火プラグの掃除手順
この部品、実はものすごくデリケートです。お掃除には細心の注意が必要ですよ!
- 基本は「乾いた布」
まずは、乾いた「やわらかい布」で、白いセラミック部分を優しく拭いてみてください。軽い汚れならこれで十分落ちます。 - ガンコな汚れは「歯ブラシ」
布で拭いても取れない焦げ付きは、「毛がやわらかい歯ブラシ」(使い古しでOK)で、絶対に力を入れずに優しくこすってみてください。
点火プラグは「割れ物」です!
点火プラグはセラミック(陶器)でできています。つまり、衝撃にすごく弱いんです。
- クレンザー(磨き粉)
- 金属たわし、硬いブラシ
- 強い力でゴシゴシこする
これらは絶対にNGです!
プラグが割れたり、欠けたりしたら、もう部品交換しかありません。修理になると数千円~1万円以上かかることも…。本当に優しく扱ってくださいね。
お掃除のついでに、点火プラグの周り(バーナー本体の溝)に溜まったホコリや食材カスも気になりますよね。そういう時は、掃除機の「隙間ノズル」を使って吸い取るのが便利です。
ただし!その時も、掃除機のノズルを点火プラグ本体にガツンと当てないように、細心の注意を払ってくださいね。あくまで周りのゴミを吸い取るイメージでお願いします。
ダイソンのコードレスクリーナーみたいに、先端がブラシになっているノズルだと、吸い取りながら軽くゴミをかき出せるので便利かもしれませんね。
でも、くれぐれも優しくお願いします!
水濡れや湿気は点火不良のもと
「チチチ音はするけど、火花が飛んでるように見えない…」
そんな時は、部品の「水濡れ」を疑ってみてください。
点火プラグは、高電圧で火花を飛ばす仕組みです。でも、プラグの先端や周りに水分(水気)が付着していると、水が電気の逃げ道になってしまって、正常に火花が飛ばなくなるんです。
電気を通しやすいイメージがある水ですが、この場合は絶縁体のように働いてしまうんですね。
水濡れの原因
- お鍋の吹きこぼれ(お湯、お味噌汁、煮汁など)
- お掃除(水洗い)の直後
特に、お掃除した直後に「あれ?さっきまでと違って火がつかない!」となったら、ほぼ100%これが原因です。バーナーキャップや五徳を洗った水が、バーナー本体の溝に残っていることが多いんです。
対処法は「徹底的な乾燥」
対処法はシンプルです。
「乾いた布で、水分を徹底的に拭き取る」こと。
以下の場所を重点的に拭いてください。
- 点火プラグ(白いピン)
- 立ち消え安全装置(金属のピン)
- バーナーキャップ(特に裏側)
- バーナー本体(部品を外した土台部分、特に溝)
拭いただけでは不安な時や、吹きこぼれが溝の奥まで入ってしまった時は、ドライヤーの「冷風」を当てて、しっかり乾燥させるのもとても有効な方法ですよ。温風だと部品が高温になったり、変形したりする可能性があるので、必ず冷風にしてくださいね。
掃除してもガスコンロがチチチとなるのにつかない対処法

頑張ってお掃除したのに、まだ火がつかない…。
そんな時は、もう一度「チチチ」の音に耳を澄ましてみてください。もしかして音が弱々しくなっていませんか?
お掃除をしても改善しない場合、汚れ以外の「うっかりミス」や「電池」、「ガス供給」といった別の原因を探ってみましょう。ここもお客様からのご相談がすごく多いポイントなんですよ。
見落としがちな電池交換のサイン
店頭での「コンロの調子が悪い」というご相談で、実は一番多い原因がこれ、「電池の消耗」なんです。
先ほども少し触れましたが、「チチチ音は鳴るから、電池はあるはず」という思い込みが、点火不良を見落とす最大の原因なんですね。
音が鳴ってもパワー不足
ガスコンロの点火には、私たちが思っている以上に強い火花のエネルギーが必要です。
電池が消耗して電圧が下がってくると、「チチチ」と音を鳴らして火花を飛ばすことはできても、ガスと空気の混合気に着火させるほどの「熱量」が出せないんです。
特に、コンロを使い始めて1年以上経過しているなら、まず電池交換を強くおすすめします。
電池交換の正しいやり方
- 必ず「新品」の「アルカリ乾電池」に交換する
パワーが必要なので、マンガン乾電池はNGです。また、古い電池や種類の違う電池を混ぜて使うのもダメですよ。 - 「全部」まとめて交換する
2本使うタイプなら、2本とも新品に交換してください。 - 「+(プラス)」と「-(マイナス)」の向きを再確認!
これ、意外と間違えやすいんです。電池ケースの表示をよーく見て、正しくセットしてくださいね。
電池交換ランプがついている機種も多いですが、ランプがなくても、「1年に1回」を目安に定期交換するのが、点火不良を防ぐ一番のコツだと思います。
電池は消耗品なので、予備をストックしておくと安心ですよね。
うちのお店では、長期保存に優れたアルカリ乾電池(パナソニックの「エボルタNEO」など)も人気です。いざという時のために、買い置きしておくことをおすすめします。
掃除に使う道具(爪楊枝はOK?)
お掃除のところでも触れましたが、どんな道具を使うかは、コンロを長持ちさせる上でとっても大事です。特にバーナーキャップの目詰まり掃除ですね。
結論から言うと、「爪楊枝」や「竹串」はOKです!
これらは木製なので、バーナーキャップの金属よりも柔らかく、部品を傷つける心配がほとんどありません。目詰まりを取るのに最適な道具だと思います。
逆に、絶対に使ってはいけない道具もあります。
コンロ掃除 NG道具リスト
これらを使うと、部品の破損やコーティング剥がれ、故障の原因になります!
| NG道具 | ダメな理由 | 対象部品 |
|---|---|---|
| 金属たわし、硬いブラシ | 部品に傷がつく、コーティングが剥がれる | 全般(特に点火プラグ、安全装置) |
| クレンザー(磨き粉) | 研磨剤で傷がつく、センサー感度が鈍る | 全般(特にガラストップ、点火プラグ) |
| 針金、金属製の串、ピン | バーナーの穴を変形させる、破損させる | バーナーキャップ、点火プラグ |
しつこい焦げ付きには?
五徳やバーナーキャップの焦げ付きがひどい時は、ゴシゴシこする前に「つけ置き」が基本です。
ただ、重曹やセスキ炭酸ソーダ(アルカリ性洗剤)は、アルミ製の部品(白っぽく変色しやすい)には使えないことがあります。天板の素材(ホーロー、ガラストップなど)によっても相性がありますね。
まずは「台所用中性洗剤」を溶かしたぬるま湯につけ置くのが一番安全で確実です。
家電量販店では、ガラストップ専用のクリーナーや、焦げ付きを落とす専用の洗剤も扱っています。素材を傷めずキレイにできるので、お掃除に悩んだら、こういう専用品を使ってみるのも良いと思いますよ。
コンロ周りのお掃除には、油汚れに強いスチームクリーナー(ケルヒャーなど)を使いたいというご相談もありますが、点火プラグ周辺の電気部品には水気が大敵なので、直接噴射するのは避けた方が無難ですね。
バーナーキャップのずれをチェック
お掃除、お疲れ様でした!さあ、部品を元に戻して…点火!
「あれ!?まだつかない…というか、前よりひどくなった!?」
もしこうなったら、まず間違いなくコレです。
「バーナーキャップの設置不良(ずれ)」
お掃除のあと、バーナーキャップを元に戻す時、傾いていたり、正しい位置に「カチッ」とはまっていなかったりすると、点火不良の原因になります。
なぜ「ずれ」で火がつかない?
バーナーキャップがずれていると、その下から出てくるガスと空気の混ざり具合が不適切になります。また、点火プラグとの位置関係もずれてしまうため、火花が飛んでもうまくガスに引火しなくなるんです。
対処法は「置き直し」
対処は簡単です。
- もう一度、五徳とバーナーキャップを取り外します。
- バーナーキャップがハマる土台の溝などを確認します。
- ゆっくりとバーナーキャップを置き直し、水平にしっかりとはまる位置を探します。
- 軽く上下左右に揺さぶってみて、ガタガタしないことを確認してください。
裏表や向きが逆なことも…
お客様のお話を聞いていると、まれにバーナーキャップの「裏表」や「向き」を間違えて設置しようとしているケースもあります。
バーナーキャップは、ちゃんとはまる向きが一つだけ決まっています。無理やり置かずに、クルクル回しながら、ストンと落ちる場所を探してみてくださいね。
全部つかない時はガスメーターを確認

「ひとつのバーナーだけじゃなくて、コンロ全部がチチチって言うだけでつかない!」
「あれ?そういえば、お湯も出ないかも…」
もし、コンロだけでなく、給湯器など家中のガス機器が全部使えなくなっているとしたら、それはコンロの故障ではありません。
家の外にある「ガスメーター(マイコンメーター)」が、安全のためにガスを遮断している可能性が非常に高いです。
なぜガスが止まるの?
ガスメーターは、以下のような異常を感知すると、ガス漏れなどの事故を防ぐために自動でガスをストップします。
- 震度5程度以上の地震を感知した時
- ガスの長時間使用(煮込み料理などで、コンロの火を異常に長くつけっぱなしにした時など)
- ガス漏れの疑いがある時
確認と復帰の方法
まずは玄関の脇やマンションの共用廊下などにある、ガスメーターのボックスを確認してください。
メーターについている「ランプが赤く点滅」していませんか?
点滅していたら、ガスは遮断されています。
ガスメーターの復帰操作手順
ガス漏れなどの異常がなく、ガス臭くないことを確認したら、以下の手順で復帰できます。
- 家中のガス機器を全て止めます。(コンロ、給湯器、ファンヒーターなど全部です!)
- メーターの左側にある「復帰ボタン」のキャップを外し、ボタンを奥までしっかり押して、ゆっくり手を離します。(※この時、絶対にガス臭くないか確認してください!)
- ボタンを離すと、赤いランプが点灯し、その後ふたたび点滅が始まります。
- 【最重要】このまま約3分間、ガスを一切使わずに待ちます。
この3分間は、メーターが「家の中にガス漏れがないか」をチェックしている安全確認の時間です。ここでガスを使うと異常と判断され、復帰が失敗します。 - 約3分後、メーターの赤いランプの点滅が消えていれば、安全確認が完了!ガスが使えるようになります。
(参考:東京ガス:ガスメーターの復帰方法)
安全に関する重要なお願い
ガスメーターの復帰操作は、必ず「ガスの臭いがしないこと」を確認してから行ってください。
もし少しでもガス臭いと感じたら、ボタンは絶対に押さず、窓を開けて換気し、すぐに契約しているガス会社へ連絡してください。これは命に関わる重要なお願いです。
掃除してもダメなら寿命かも?
ここまで、お掃除、電池交換、部品の設置確認、ガスメーターの確認…と、ご自身でできる対処法を全部試してみたとします。
「それでも、やっぱり火がつかない…」
その場合は、残念ながら部品の劣化や、内部の電気系統の故障など、コンロ本体の「寿命」が来ている可能性が高いです。
判断の目安は「使用年数10年」
家電量販店でお客様のコンロ交換のご相談を受けていると、だいたい設置から8年~15年くらいでの交換が一番多くなります。メーカーさんが修理用の部品を持っている期間(部品保有期間)が、その製品の生産終了から約5年~7年程度であることが一般的なんです。
つまり、10年以上使っているコンロだと、故障箇所がわかっても、交換する部品がもう手に入らない…というケースがすごく増えてきます。
また修理できたとしても、次から次へと別の場所が壊れる「もぐら叩き状態」になって、かえって修理代が高くついてしまうことも…。
内部の故障は絶対に触らないで!
新品の電池に交換しても「チチチ」音すら鳴らない場合や、安全装置が掃除しても誤作動するような場合は、内部の電子基盤や配線の故障が疑われます。
このような内部の故障は、専門的な知識がないと修理できません。
ご自身でコンロを分解するようなことは、火災やガス漏れ、感電の危険があり、本当に危ないので絶対にやめてください。
10年近く使っていて、今回ご紹介したセルフチェックでも不具合が直らない場合は、修理を試みるよりも、安全で高機能な新しいコンロへの交換を検討するタイミングなのかもしれませんね。
最近のコンロは安全性も格段に上がっていますし、お掃除もすごく楽になっているので、新しいものを検討するのもおすすめですよ。
ガスコンロがチチチと鳴りつかない時の掃除まとめ
今回は、ガスコンロが「チチチ」と音はするのにつかない原因と、お掃除を中心とした対処法についてお話ししてきました。
「チチチ」という音は、「壊れた!」というサインではなく、「どこか調子が悪いよ」というコンロからのメッセージなんですね。
まずは慌てず、音の強弱をチェックしましょう。
- 音が「弱く、遅い」なら、まず「電池交換」。
- 音が「強く、速い」なら、「3大コンポーネント(バーナーキャップ、点火プラグ、安全装置)」のお掃除。
これだけで、かなりの確率で復活するはずです。
それでもダメな時は、「バーナーキャップのずれ」や「ガスメーターの遮断」といった、掃除以外の原因を一つずつ確認してみてください。
そして、セルフチェックを全部試しても改善しない場合や、使用年数が10年を超えている場合は、無理は禁物です。
火を扱う大切な家電ですから、少しでも不安を感じたら、ご自身で判断せず、必ず契約しているガス会社や、専門の修理業者さんに点検を依頼してくださいね。安全が第一ですから!
この記事が、皆さんのコンロの不具合解決に少しでもお役に立てたら嬉しいです!