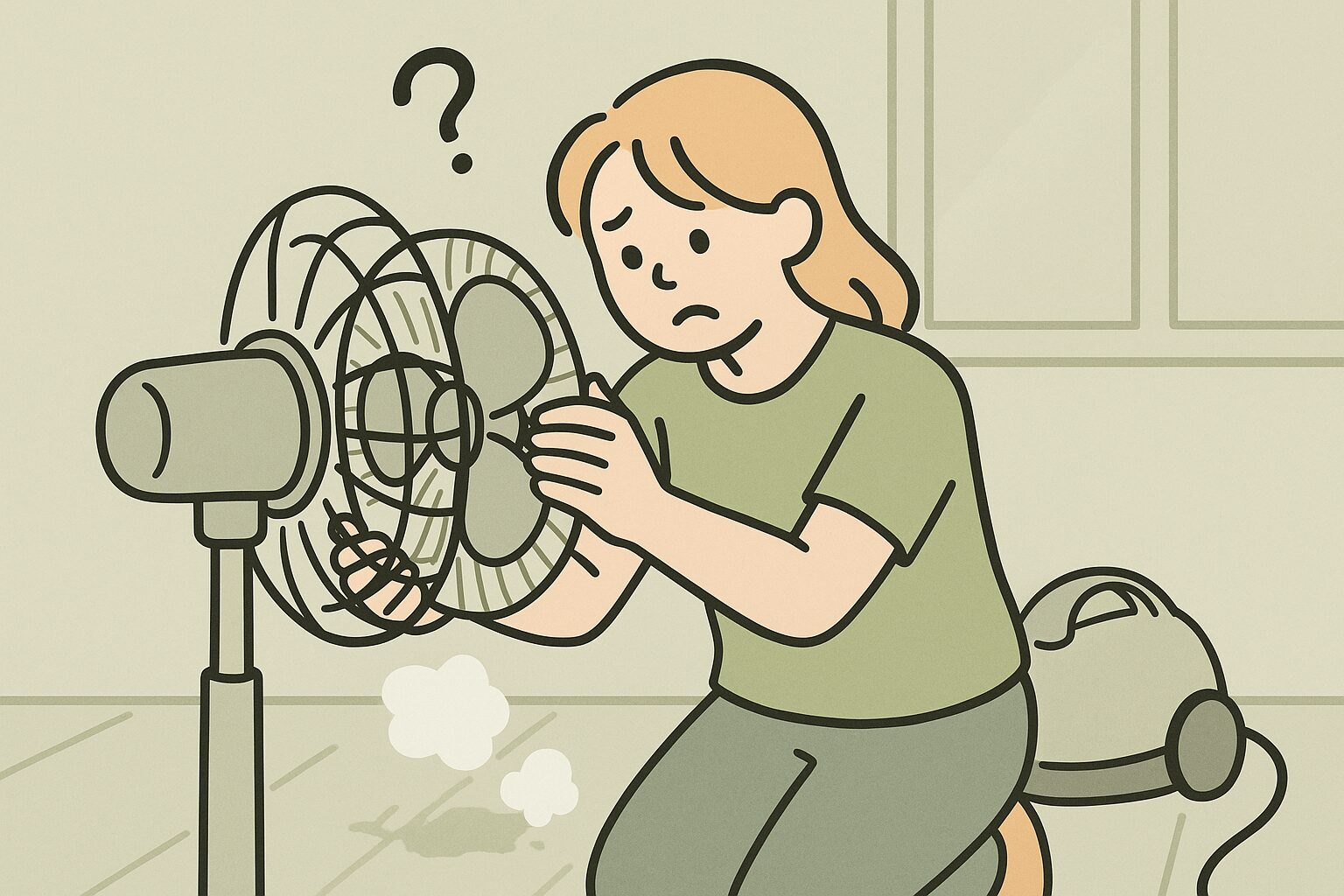扇風機を片付けようと思ったら、ガードが外れなくて困ってしまったことはありませんか?
昔の扇風機なら簡単に分解して丸洗いできたのに、最近の製品はどうしてこんなに頑丈なの?
と疑問に思う方も多いはずです。
実はこれ、安全基準が厳しくなったことが大きく関係しているんです。
でも安心してください。
分解できなくても、扇風機をしっかりキレイにする方法はちゃんとあります。
私も店頭でお客様から「ガードが外れないんだけど、どうやって掃除すればいいの?」という質問をよく受けるんですが、正しい手順を知っていれば分解しなくても十分にホコリや汚れを取り除くことができるんですよ。
この記事では、扇風機が分解できない理由から、安全で効果的な掃除方法、便利な掃除道具、さらには掃除しやすい扇風機の選び方まで詳しく解説していきます。
タワーファンや羽なし扇風機のお手入れ方法もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みくださいね!
分解できない扇風機の掃除方法と注意点

ここでは、なぜ扇風機が分解しにくくなっているのか、そして「分解できない扇風機」をどうやって安全に掃除すればいいのか、その方法と注意点を詳しく解説していきますね。
扇風機のカバーが外れない理由
「ホコリが見えてるのに取れない!」って、すごくストレスですよね。
でも、扇風機のカバーが外れないのは、不良品だからじゃない場合がほとんどなんです。
実は、意図的に「分解しにくい」または「分解できない」仕様になっていることが多いんですね。
主な理由は、大きく分けて3つあります。
安全基準(JIS規格)が厳しくなったから
これが一番大きな理由かもしれません。最近のリビングファンは、JIS(日本産業規格)という国の安全基準に合わせて作られています。
特に小さなお子さんがガードの隙間から指を入れて、中の羽根で怪我をしないように、ガードの隙間が狭くなったり、そもそも簡単に取り外せないように頑丈なツメや特殊なネジで固定されていることが増えました。
安全第一、ということなんですね。
2. 製品のタイプによる構造的な特性
すべての扇風機が「羽根を外して洗う」前提で作られているわけではないんです。
- タワーファン(スリムファン): 中にはエアコンの室内機と似た「シロッコファン」という筒状のファンが入っています。この構造は、もともと分解掃除を想定していません。
- 羽なし扇風機 (ダイソンなど): フィルターを通した空気をループ状の部分から出す複雑な仕組みです。お手入れは基本的に拭き掃除が中心ですね。
- サーキュレーターの一部: 空気をかき混ぜるのが目的なので、頑丈さを重視してガードと本体が一体化しているモデルもあります。
3. メーカーが分解を推奨していないから
お手元の取扱説明書に「分解不可」や「お手入れは拭き掃除のみ」と書かれていませんか?
例えば、テクノスの一部のモデルでは「羽根は外せない仕様です」と明記されていて、布で拭くよう指示されています。
まずはお掃除を始める前に、必ず「取扱説明書」のお手入れページを確認してみてください。そこにガードの外し方が書いていなければ、その扇風機は「分解非推奨」ということになります。
無理な分解は絶対にNGです!
説明書にない方法で、工具を使って無理やりこじ開けようとするのは絶対にやめてください!
- 破損のキケン: ツメが折れたり、プラスチックが割れたりして、元に戻せなくなる可能性があります。
- 火災・感電のキケン: 内部のモーターや配線を傷つけてしまうと、そこからショートして故障するだけでなく、最悪の場合、火災につながる危険性があります。
分解できないのは安全のため。無理せず、次のステップで紹介する「分解しない掃除方法」を試してみましょう。
分解しない安全な掃除ステップ
「分解できないなら、どうやって掃除するの?」と思いますよね。
大丈夫です!
分解できなくても、外側からアプローチするだけで十分キレイにできるんですよ。
次に、安全に作業するための4つのステップをご紹介しますね。
ステップ0:安全確保と準備
これが一番重要です!
お掃除を始める前に、必ず扇風機の電源プラグをコンセントから抜いてください。
万が一、掃除中に動いたら大変危険です。また、運転直後はモーターが熱いこともあるので、少し時間をおいてから作業しましょう。
床には新聞紙やシートを敷いておくと、落ちたホコリの片付けが楽ですよ。
ステップ1:【乾】掃除機で「吸う」
まずは、ホコリが舞い散らないように、表面の大まかなホコリを掃除機で一気に吸い取ります。ガードの外側、背面の吸気口、モーター部分など、全体的に吸いましょう。
この時、おすすめなのが「ブラシノズル」のアタッチメントです。ブラシでガードに詰まったホコリをかき出しながら吸えるので、とっても効率的なんです。
ステップ2:【乾】ブラシ・モップで「かき出す」
掃除機だけでは取りきれない、ガードの内側や羽根に付着したホコリを物理的にかき出します。
- ハンディモップ: ガードの隙間から差し込んで、内部のホコリを絡め取ります。モップを入れたまま、羽根をゆっくり手で回すと、羽根の表面全体をキャッチできますよ。
- 隙間ブラシ: モップが届かない細かい隙間や、羽根のフチに固まったホコリは、扇風機専用ブラシや使い古しの歯ブラシなどでこすり落とします。
ステップ3:【湿】洗剤を染み込ませた布で「拭く」
乾いたホコリが取れたら、油汚れや湿気でベタベタになった頑固な汚れを拭き上げます。
ここで絶対にやってはいけないのが、扇風機本体に洗剤を直接スプレーすることです!
注意!モーターや基板は絶対に濡らさないで!
扇風機の心臓部であるモーターや電子基板は、水分にとても弱いです。水がかかるとショートして故障したり、火災の原因になったりします。
安全な手順
- アルカリ電解水や薄めた中性洗剤などを、「布側」にスプレーします。
- 水分が滴らないよう、その布を固く、固く絞ります。
- 固く絞った布をガードの隙間から差し込み、羽根やガード内部を丁寧に拭きます。
- 洗剤を使った場合は、きれいな水で濡らして固く絞った布で、再度水拭きをします。
- 最後に乾拭きで仕上げます。
ステップ4:【予防】ホコリの付着を防ぐ
せっかくキレイにしたなら、長持ちさせたいですよね。
仕上げの乾拭きの際、乾いた布にごく少量の「柔軟剤」を染み込ませて拭き上げると、柔軟剤の静電気防止効果でホコリが付きにくくなるんです。これは裏ワザとしておすすめですよ。
ガードの隙間のほこりを取る道具
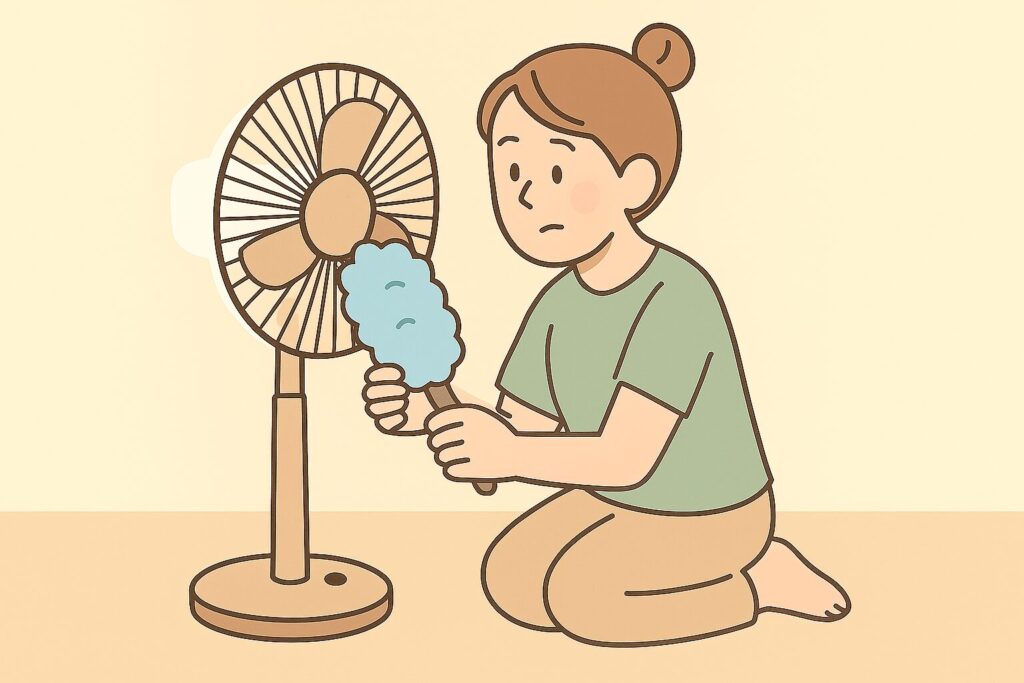
分解できない扇風機の掃除は、「いかに隙間にアプローチするか」が勝負です。
お店でも「こういうのない?」と聞かれることが多い、便利な掃除グッズを紹介しますね。これらを使うと、作業効率が格段にアップすると思います。
掃除機アタッチメント(専用ノズル)
まずは掃除機パワーを活用しましょう。標準で付いている「すき間ノズル」や「ブラシノズル」は基本ですね。特にブラシノズルは、ガード表面のホコリをかき出しながら吸えるので便利です。
ただ、扇風機のガードの細い隙間(数ミリ)に、掃除機のノズルを差し込むのはなかなか難しいかもしれませんね。
ガードの隙間を狙うなら、まずは標準の「すき間ノズル」で試してみて、それでも入らない場合は無理をせず、次の「専用ブラシ」などを使うのがおすすめです。
専用掃除ブラシ・モップ
やっぱり専用品は使いやすいです。「まめいた」や「アズマ工業」などから、扇風機のガードの隙間に特化した薄型ブラシや、サーキュレーター用ブラシが出ています。
山善からも「扇風機お掃除ブラシ」というマイクロファイバー製のものが販売されていて、ホコリをしっかりキャッチしてくれます。こういった専用ブラシは、100円ショップで見つかることもありますよ。
電動エアダスター(ブロワー)
これは「関連家電」になりますが、物理的に手が届かない場所のホコリを吹き飛ばす最終兵器ですね。スプレー缶タイプと違って、充電式で強力な風を連続噴射できます。
サンワサプライから出ているLEDライト付きのモデル(CD-ADE1BKなど)は、暗い隙間を照らしながら作業できて便利です。タワーファンの内部清掃にも活躍しますよ。
掃除に使える洗剤と注意点
扇風機のベタベタ汚れは、キッチンの油煙(油の煙)やタバコのヤニ、湿気を含んだホコリが原因のことが多いです。水拭きだけでは落ちにくい場合、洗剤の力を借りたいですよね。
ただ、先ほどもお伝えした通り、「使い方」が何よりも重要です。
安全に使える洗剤の例
基本的には、プラスチックを傷めにくい、マイルドなものがおすすめです。
- アルカリ電解水スプレー: 界面活性剤が入っていないので、二度拭きが不要なのが嬉しいポイント。手垢や軽い油汚れに強いです。
- 重曹スプレー (重曹水): 水100mlに重曹小さじ1程度を溶かしたもの。油汚れを分解する力があります。
- 薄めたキッチン用中性洗剤: しつこい油汚れには、やはり中性洗剤が効果的です。水で薄めて使い、使った後は必ず水拭きで洗剤成分をしっかり拭き取ってください。
【最重要】洗剤の使い方の再確認
繰り返しになりますが、扇風機本体やガードに直接洗剤をスプレーする行為は絶対にダメです!
モーターや配線部分、スイッチの隙間から洗剤(水分)が内部に入り込むと、
- 故障: 回路がショートして動かなくなる。
- 火災: トラッキング現象などを引き起こし、発火する。
といった、取り返しのつかない事故につながる可能性があります。
必ず、乾いた布や雑巾の「布側」に洗剤をスプレーし、それを固く絞ってから拭き掃除に使ってください。安全第一でお手入れしましょうね。
エアコンスプレーは絶対NG!
分解できないファンのお掃除方法として、「エアコン洗浄スプレーを流用すればいいのでは?」と考える方がいらっしゃるかもしれません。実際に、お店でも「あれって扇風機には使えないの?」と聞かれたことがあります。
結論から言います。エアコン洗浄スプレーの扇風機への流用は、非常に危険なため絶対にやめてください!
なぜ危険なのか、その理由を説明しますね。
エアコンと扇風機は「構造」が根本的に違います
エアコンの室内機(フィン部分)は、洗浄スプレーを使うと、発生した汚水が「ドレンホース」という専用の排水管を通って、自動的に室外に排出されるように設計されています。
一方、扇風機には当然ながら、そんな排水構造はありません。
もしエアコン洗浄スプレーを扇風機に噴射したら…想像してみてください。大量の洗浄液(水分と洗剤)が、ガードや羽根を伝って、どこへ行くでしょうか?
そうです。モーター部分や電子基板、スイッチ類にそのまま垂れ流しになってしまいます。
ショート・腐食・火災の直撃コースです!
アース製薬の「らくハピ」やショーワの「くうきれい」といった商品は、あくまでエアコン専用品です。扇風機に流用すると、内部の金属部品が腐食したり、回路がショートしたりする可能性が極めて高いです。
最悪の場合、故障するだけでなく、コンセントを差した際に発火・火災の原因となります。NITE(製品評価技術基盤機構)も、扇風機やエアコンの経年劣化や誤った取り扱いによる火災事故について、毎年注意喚起を行っています。
(出典:NITE 扇風機やエアコンの思わぬ火災を防ぐには)
「スプレーで一発洗浄」は絶対にやめて、地道ですが安全な拭き掃除をお願いします。
扇風機の掃除で分解できない時の最終手段
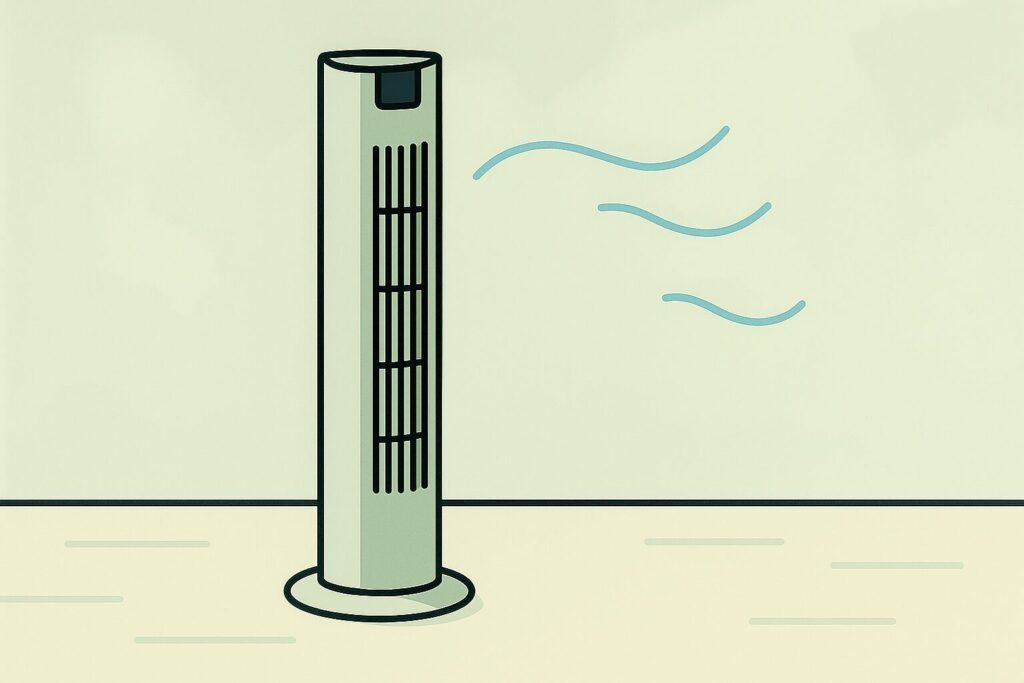
リビングファンが分解できない時の掃除方法は分かったけれど、うちにはタワーファンや羽なし扇風機もある…という方もいらっしゃるかもしれませんね。
これらのタイプは、リビングファン以上に分解が想定されていません。
ここからは、タイプ別のお手入れ方法と、もう「分解できない!」と悩まないための、根本的な解決策についてもお話ししたいと思います。
タワーファンの掃除方法
タワーファン(スリムファン)は、見た目がスタイリッシュで場所を取らないのが人気ですよね。
でも、内部の「シロッコファン」という筒型ファンは、残念ながら家庭では分解できません。
お手入れは、主に3つのポイントに絞られます。
吸気口(背面・フィルター)
タワーファンは、室内の空気を背面の吸気口から取り込みます。
ここが一番ホコリが溜まる場所です!
多くのモデルで、この吸気口部分にフィルターが装着されています。まずは掃除機のブラシノズルで、フィルターやグリルのホコリを徹底的に吸い取りましょう。
送風口(前面)
風が出てくる前面の細いスリット部分ですね。ここは、掃除機の「すき間ノズル」で表面のホコリを吸い取ります。
内部のシロッコファンに付着したホコリは、手の届く範囲で隙間ブラシを使ってかき出すか、「電動エアダスター」を使って、内部のホコリを送風口から一気に吹き飛ばすのが効果的です。
ただし、ホコリが室内にブワッと飛散するので、作業はベランダなど屋外で行うか、換気を十分に行い、マスクも忘れずに!
本体・操作パネル
本体の外装や、直接手で触れる操作パネルは、手垢で汚れやすい場所です。
アルコール除菌スプレーやアルカリ電解水を乾いた布に吹き付けてから、本体全体を拭き上げるとスッキリしますよ。
羽なし扇風機のお手入れ方法

ダイソンに代表される「羽なし扇風機」
これももちろん分解はできません。お手入れは「拭き掃除」が基本です。
送風口(ループ部)
風が出てくるリング状の部分です。
ここは、乾いた布か、水に濡らして固く絞った柔らかい布で、ループの内側と外側を優しく拭き上げます。
本体(下部・吸気口)
空気を取り込む本体下部(円筒形のフィルター部分)は、掃除機のブラシノズルで表面のホコリを吸い取ります。
ダイソンのお手入れで注意すべきこと
ダイソンのサポート情報では、洗剤やツヤ出し材の使用を明確に禁止しています。これらを使うと、本体のプラスチック素材を傷めてしまう可能性があるからだそうです。
お手入れは、必ず「乾拭き」または「水拭き」のみで行ってください。どうしても内部の汚れが気になる場合は、無理に分解しようとせず、メーカーのメンテナンスサービスに相談することをおすすめします。
掃除が簡単な扇風機の特徴
「もう、分解できない扇風機の掃除はこりごり!」
「次買うときは、絶対に掃除が簡単なものがいい!」
…私もそう思います(笑)
実は、お店で働いていても、「お手入れのしやすさ」を重視して扇風機やサーキュレーターを選ばれるお客様が、ここ数年で本当に増えたと感じています。
家電メーカー各社も、そのニーズに応えて「掃除のしやすさ」を最大のセールスポイントにした製品を次々と開発しているんですよ。
買い替えでチェックしたいキーワード
次に買い替える際は、こんなキーワードに注目してみてください。
- 「工具不要」
- 「全分解」
- 「丸洗い可能」
- 「お手入れ簡単」
これらのキーワードが書かれている製品は、ガードや羽根が簡単に取り外せて、水洗いできる(もちろんモーター部はダメですよ!)ものがほとんどです。
特に最近は、サーキュレーターの分野でこの「お手入れ革命」が進んでいるんです。
アイリスオーヤマのおすすめ機種
「掃除しやすいサーキュレーター」と聞いて、真っ先に思い浮かぶメーカーの一つが、アイリスオーヤマですね。店頭での人気もすごいです。
「WOOZOO (ウズ)」というブランドのサーキュレーターで、「丸洗い」や「全分解」を強く打ち出しています。
WOOZOO 360barrel (PCF-CD15TECA)
これは本当によく考えられているなと思います。
工具不要で、前面ガード、羽根、背面ガードまで「全分解」できるんです。
外したパーツは丸洗いOK。これならシーズンオフの片付けもストレスフリーですよね。360度の首振り機能も搭載していて、サーキュレーターとしての性能もバッチリです。
サーキュレーター扇風機 DC (STF-SDC15TEC-W)
こちらは背の高い扇風機タイプですが、サーキュレーターの技術が活かされています。
ヘッド部分(羽根やガード)が同じく工具不要で分解でき、水洗いも可能です。DCモーター搭載で静音性が高いのも嬉しいポイントですね。
お店でお客様からも、「本当にパチパチと外せて感動した」「これなら毎年キレイに使える」と、とても評判が良いモデルです。
| 商品名・シリーズ名 | 型番 | 清掃機能(特徴) | 適用畳数(目安) |
|---|---|---|---|
| WOOZOO 360barrel | PCF-CD15TECA | ◎ 全分解・丸洗い可・工具不要 | ~20畳 |
| サーキュレーター扇風機 DC | STF-SDC15TEC-W | ◎ ヘッド部分解・水洗い可・工具不要 | ~28畳 |
山善のおすすめ機種
アイリスオーヤマとよく比較されるのが山善ですね。
山善も「洗えるサーキュレーター」シリーズとして、清掃性を前面に出したラインナップを展開しています。
洗えるサーキュレーター 360度 DC (YAR-CD20ES)
こちらも「全分解」して水洗い可能なDCモーターサーキュレーターです。アイリスオーヤマのモデルと同じく、360度首振りに対応しています。
「デザインがシンプルで、部屋のインテリアに馴染む」という理由で選ばれるお客様も多いですね。
洗えるサーキュレーター DC (YAR-PDW182(W))
よりパワフルな風が欲しい方には、こちらの28畳モデルもおすすめです。もちろん、こちらも全分解に対応しています。
お客様の声としても、「去年買った扇風機が掃除できなくて買い替えたけど、これは本当に洗いやすくて最高」「分解も組み立ても簡単だった」といった満足度の高い声をよく聞きますよ。
| 商品名・シリーズ名 | 型番 | 清掃機能(特徴) | 適用畳数(目安) |
|---|---|---|---|
| 洗えるサーキュレーター 360度 DC | YAR-CD20ES | ◎ 全分解・丸洗い可・工具不要 | ~20畳 |
| 洗えるサーキュレーター DC | YAR-PDW182(W) | ◎ 全分解・丸洗い可・工具不要 | ~28畳 |
扇風機が分解できない掃除の総括
ここまで、分解できない扇風機の掃除方法について色々とお話ししてきました。
最後に、大切なポイントをまとめておさらいしましょう。
分解できない扇風機お掃除の総括
- 扇風機が分解できないのは、「安全基準(JIS規格)」で、子供の指が入らないよう頑丈に作られているのが主な理由です。
- 無理な分解は破損や火災のもと。取扱説明書に記載がなければ、絶対にやめましょう。
- 分解しなくても、「掃除機(ブラシノズル)」「ブラシ・モップ」「固く絞った布(洗剤使用可)」の3ステップで十分キレイになります。
- エアコン洗浄スプレーの流用は火災の危険があるため絶対NG!
- タワーファンや羽なし扇風機は、それぞれの構造に合った正しいお手入れ(拭き掃除、エアダスターなど)が必要です。
- どうしても掃除のストレスから解放されたい場合は、「工具不要」「全分解」「丸洗い」を謳った、アイリスオーヤマや山善のサーキュレーターへの買い替えが根本的な解決策になります。
ホコリが溜まった扇風機をそのまま使い続けると、アレルギーの原因になるだけでなく、モーターに負荷がかかって効率が落ち、無駄な電気代がかかってしまうことも…。
さらに、古い扇風機の場合はホコリが原因で火災につながる危険性もゼロではありません。
分解できなくても、できる範囲で安全にお手入れして、来シーズンも快適に扇風機を使ってくださいね!