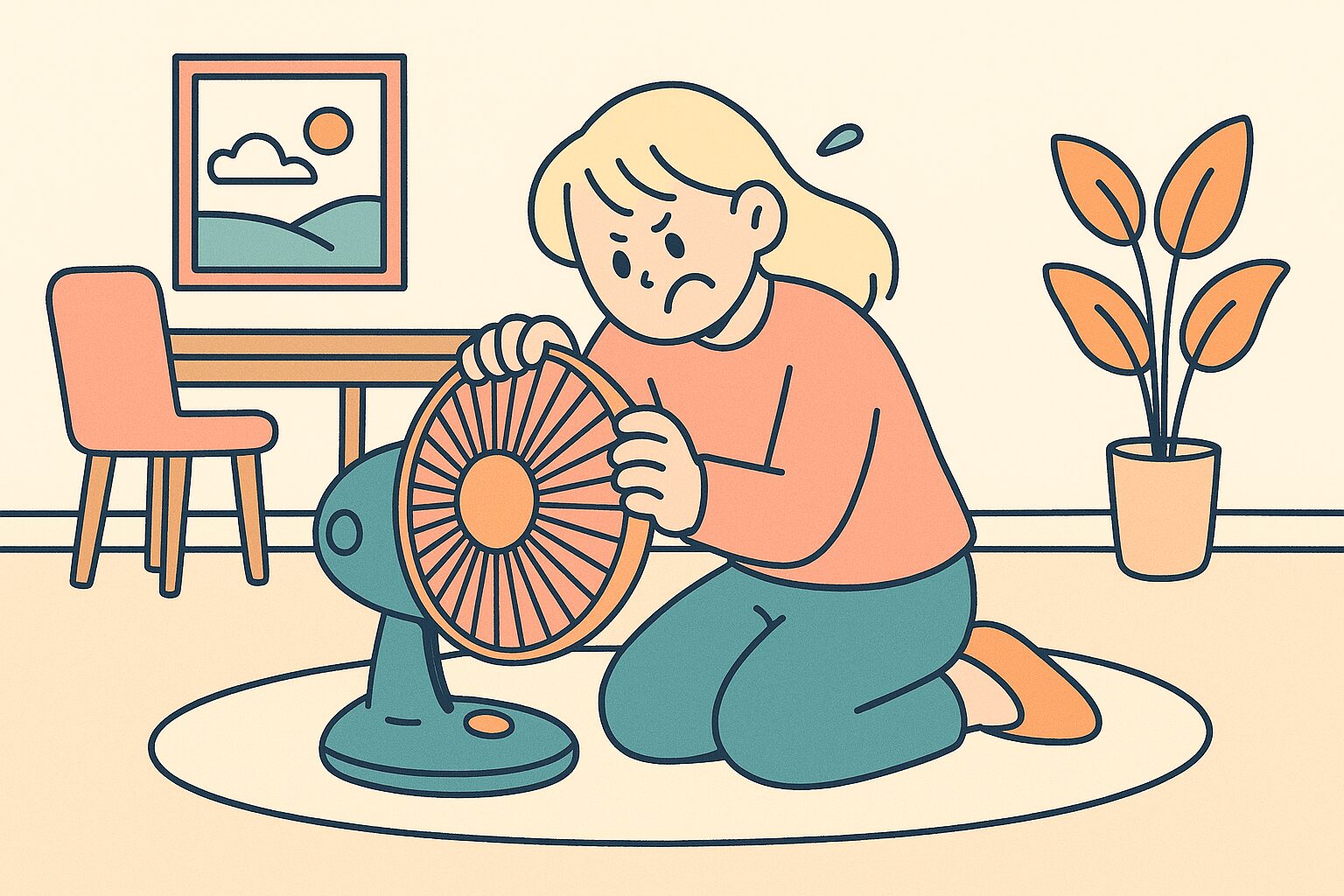サーキュレーターの掃除をしようと思ったのに、カバーが外れなくて困ったことはありませんか?
いざお手入れしようとしたら、ホコリだらけの羽根を前に途方に暮れてしまう。
実は、サーキュレーターが外れない原因は大きく分けて3つあります。
一体型の構造で分解を想定していないモデルかもしれませんし、ネジや留め具が固着してしまっているのかもしれません。また、アイリスオーヤマなど人気メーカーの特定モデルでは、前面は外せても背面ガードが外せない仕様になっていることも。
この記事では、サーキュレーターが外れない具体的な原因と対処法、分解できない場合の応急処置、そして掃除が簡単なおすすめモデルまで、家電店員の視点から詳しく解説していきます。
サーキュレーターの掃除で外れない時の原因
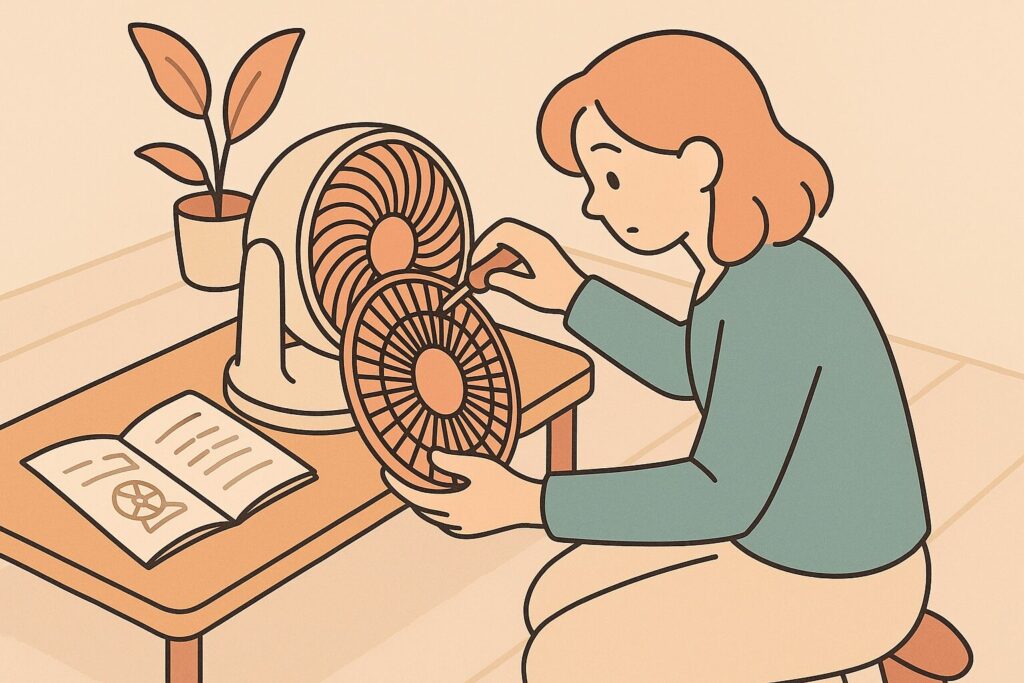
冒頭でお話しした、サーキュレーターが外れない3つの原因。ご自宅のモデルがどれに当てはまるのか、ここで一緒に詳しくチェックしていきましょう。
原因がわかれば、正しい対処法も見えてきますよ!
一体型かも?説明書で分解方法をチェック
まず最初に疑ってほしいのが、「そもそも構造的に分解を想定していない」一体型モデルである可能性です。
「え、そんなことあるの?」と思われるかもしれませんが、特に低価格帯のモデルやデザイン重視の小型モデルには、意外と多いタイプなんです。製造段階で完全に固定されていて、消費者が安全に分解することを前提に作られていないんですね。
見分け方は比較的簡単です。
前面ガード(カバー)のフチをぐるっと見てみてください。そこにネジや、カチッと留めるためのフック、ラッチ(留め具)のようなものが一切見当たらない場合、それは一体型である可能性が非常に高いです。
デザインがスッキリしている反面、お手入れのことはあまり考えられていない構造とも言えます。
一番確実なのは、やはり製品の取扱説明書(説明書)を確認することです。
「お手入れ」や「メンテナンス」のページを見て、カバーの取り外し方が記載されているかチェックしてみてください。もし分解方法が書かれていなければ、それは「分解不可」モデルということになります。
説明書をなくしてしまった場合は、メーカーの公式ウェブサイトで型番(本体の底面や背面にシールで貼ってあります)を検索すれば、PDFで見られることがほとんどですよ。
【最重要】一体型は絶対にこじ開けないで!
一体型モデルをドライバーなどで無理やりこじ開けようとすると、プラスチック製のガードが割れたり、本体が破損したりする原因に直結します。これは保証の対象外になってしまいますし、最悪の場合、内部の配線を傷つけて火災などの安全上のリスクを引き起こす可能性も…。お客様からも「ちょっと力を入れたらバキッといっちゃって…」という悲しいご報告を聞くこともあります。絶対にやめてくださいね。
このタイプだった場合は、残念ながら分解掃除は諦めるしかありません。
この後のセクションでご紹介する「分解できない場合の応急処置」で、できる範囲のホコリ取りをしていきましょう。
ネジやツメが固い時の外し方
「説明書には『外せる』って書いてあるのに、固くてどうにもならない!」というケースもあります。これは「分解可能」なモデルが、何らかの理由で固着してしまっている状態ですね。
主な原因は2つ考えられます。
ネジの固着
ガードを固定しているネジが回らないパターンです。
特に梅雨時の部屋干しや、お風呂上がりの脱衣所でサーキュレーターを使っていると、湿気でネジがサビて固着してしまうことがあるんです。
また、製造時にもともと強く締め付けられすぎているケースもありますね。
ご家庭の普通のドライバーでは歯が立たないことも多く、無理に回そうとするとネジ山(ネジの頭の溝)が潰れてしまって、余計に外せなくなる「詰み」の状態になりがちです…。
プラスチック製ツメの固着
ネジではなく、プラスチック製のツメ(ラッチ)で固定されているタイプも多いですが、これもまた固着しやすいんです。長期間の運転で、ツメの隙間にホコリや、キッチン近くなら油汚れが蓄積して固まってしまうんですね。
また、プラスチック自体が経年劣化や熱で硬化して、ラッチを押しても動かなくなっていることもあります。
「指が痛くなるほど押してるのに、ビクともしない!」というお悩み、本当によくわかります。
【上級者向け】固着の外し方とリスク
ここから先は、製品の破損やケガのリスクを伴う「最終手段」になります。もし試される場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、完全に自己責任でお願いします。少しでも「無理かも」と思ったら、すぐに中止してくださいね。
ネジが固い場合:
「ショックドライバー(貫通ドライバー)」という、グリップエンドをハンマーで叩けるタイプのドライバーを使う方法があります。ネジ溝にドライバーを当ててハンマーで軽く叩き、その衝撃で固着を緩めるんです。ただ、サーキュレーターのような家電製品に衝撃を与えると、内部のモーターや基盤が壊れる可能性もゼロではありません。あまりおすすめはできないですね…。
ツメが固い場合:
ツメの構造をよく見て、「押す部分」と「引っかかっているフック部分」を特定します。マイナスドライバーのような細いもので「押す部分」を押し込みつつ、別の薄いヘラ(プラスチック製が望ましいです)をガードと本体の隙間に差し込み、フック部分を押し出すようにして外します。力任せにやるとツメが簡単に折れますので、本当に慎重な作業が必要です。
正直なところ、ここまで固着してしまった場合、安全に外すのはかなり難しいと思います。
ケガや破損のリスクを考えると、無理せず「分解できない場合の応急処置」に切り替えるのが賢明かもしれませんね。
背面が外れないアイリスオーヤマの型番
サーキュレーターが「外れない」というお悩みで、実は一番多いかもしれないのが、この「ユーザーの認識と製品仕様のズレ」パターンです。
特に、アイリスオーヤマのベストセラーモデル「PCF-SC15T」などが、この代表格なんです。
店頭でも「お手入れ簡単って書いてあったのに、全然簡単じゃない!」とか「前面は外れたけど、一番汚れてる後ろ側が外れない!」とおっしゃるお客様が本当に多いモデルでして…。
私も「あ、そのモデルですね…」となってしまうことがよくあります。
皆さんがたどるプロセスは、大体こんな感じじゃないでしょうか。
- 「お手入れ簡単」という言葉を信じて購入する。
- 説明書通り、前面ガードはツメを内側に押しながら簡単に外せる。
- でも、本当に掃除したい羽根の裏側やモーター周りの「背面ガード」が外れない!
- 「話が違う!」と不満を感じて検索する。
これが「トラップ」の正体なんです。
同モデル「PCF-SC15Tの取扱説明書」には、「前面ガードの外し方」しか記載されていません。
つまり、メーカーとしては「背面ガードや羽根の分解は想定していない」モデルなんですね。
もしお手持ちのサーキュレーターがこの「PCF-SC15T」や、同様に「前面しか外せない」タイプだった場合、やはりこの後の「分解できない場合の応急処置」で対応することになりますね。
「お手入れ簡単」の定義に注意!
市場にあふれる「お手入れ簡単」や「分解可能」という言葉は、実は定義がとても曖昧なんです。多くの場合、それは「前面ガードだけなら工具不要で外せますよ」という意味合いで使われています。
私たちが期待する「モーター部も含めた全分解」を意味しないケースがほとんどなんですね。このマーケティング上の曖昧さが、購入後の「期待外れ」を生んでしまい、「外れない!」という検索行動につながっているんだと思います。
アイリスオーヤマの製品が悪いわけではなく、すべてのモデルが全分解できるわけではない、ということを知っておくのが大切ですね。もちろん、アイリスオーヤマ製品の中にも、ちゃんと「背面まで工具不要」の素晴らしいモデルもありますよ(これは後ほどご紹介しますね!)。
掃除しないと危険!火災やカビのリスク
「外れないし、面倒だからいいや…」と、ホコリまみれのままサーキュレーターを使い続ける。
その気持ちわかります。
でもそれ、本当に危険なんです。
単に不衛生だというだけでなく、重大な事故や健康被害につながる可能性が潜んでいます。これは家電販売に従事する者として、一番お伝えしたいことかもしれません。
危険性1:火災・発火のリスク
最も怖いのが火災です。
ホコリがモーター部分に蓄積すると、モーターが過熱して発火の原因になる…というのは、よく知られていますよね。
でも、危険はそれだけじゃないんです。
特に「首振り機能」があるモデルで注意が必要なのが、「配線コードの断線によるショート」です。
首を振るたびに、内部の配線コードは何度も何度も折り曲げられます。掃除を怠ってホコリやゴミが首振り機構に溜まると、動きがスムーズでなくなり、配線コードに余計な負荷がかかり続けます。
その結果、配線が断線してショートし、発火に至る…。
というケースが報告されているんです。
掃除は単にキレイにするだけでなく、こうした機械的な安全性を維持するためにも必須の作業なんですね。
危険性2:健康被害
サーキュレーターは、室内の空気を強力に循環させる家電です。
もし内部が汚れていたら…想像したくないですが、それは「汚染物質の拡散装置」になってしまいます。
拡散されるのは、ホコリやダニの死骸、そして最も厄介なのが「カビの胞子」です。
特に梅雨時や加湿器と併用する冬場は、サーキュレーター内部もカビが繁殖しやすい環境になります。カビの胞子を部屋中に撒き散らすことで、アレルギー反応や、ひどい場合には夏型過敏性肺炎などを引き起こすトリガーにもなりかねません。
お部屋の家電と連携しましょう!
サーキュレーター内部のカビを防ぐには、お部屋の湿度管理が不可欠です。ぜひ「除湿機」やエアコンの除湿機能と併用してください。また、すでに飛散してしまったホコリやカビの胞子をキャッチするために、「空気清浄機」と一緒に使うのも、とても効果的ですよ。家電同士、上手に連携させてクリーンな環境を保ちたいですね。
危険性3:電気代の増加
掃除をサボると、お財布にも優しくないんです。羽根にホコリが層のようにこびりつくと、空気抵抗が大きくなって、設計通りの風を送れなくなります。
「なんだか風が弱いなぁ」と感じて、つい設定を「強」にしてしまいがち…これ、消費電力が増加する原因です。
また、モーターの軸部分にホコリが侵入すると摩擦が大きくなり、同じ回転数を維持するためにより多くの電力が必要になります。
エアコンのフィルター掃除をしないと電気代がすごく上がる、という話は有名ですよね。
(ダイキン工業の実験では、なんと消費電力が約49%も悪化したとか… )
サーキュレーターも原理は全く同じなんです。
「外れない!」と格闘する面倒な掃除も、月々の電気代の節約につながると思えば、少しはやる気が出るかもしれませんね。
分解できない場合のホコリ取り応急処置

さて、お手持ちのサーキュレーターが「一体型」だったり、「固着して外せない」あるいは「背面だけ外れない」タイプだった場合。
分解を諦めて、安全な「応急処置」で掃除していきましょう。
目標は、「無理に分解せず、手の届く範囲の汚れとホコリを安全に除去する」ことです。
ちょっと手間はかかりますが、火災や健康被害のリスクを考えれば、やらないわけにはいきませんよね。
おすすめのステップをご紹介しますね。
ステップ1:安全確保(最重要!)
なにはともあれ、まずは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。清掃中に万が一動いてしまったら大変危険です。これは絶対に守ってくださいね。
ステップ2:表面のホコリ除去(ドライ)
ハンディワイパーや化学ぞうきんで、まずは本体とガード(カバー)表面の大きなホコリをサッと拭き取ります。
ステップ3:隙間と内部のホコリ除去(吸引・撹拌)
ここがメインです。掃除機(スティッククリーナーやキャニスター掃除機)の出番ですよ!
- まず、掃除機の「隙間ノズル」を使って、ガードの隙間(メッシュ部分)に詰まったホコリをできるだけ吸い出します。
- 吸い出しにくい固着したホコリは、「歯ブラシ」のような小さなブラシを隙間から差し込み、軽くこすってホコリをかき出します。掃除機の付属ノズルに「ブラシノズル」があれば、それが最強のツールになります。ブラシでかき出しながら同時に吸い取れるので、ホコリも舞い散りにくいんです。ダイソン(Dyson)のクリーナーに付属しているコンビネーションノズルなんかは、この作業にピッタリですね。
- かき出したホコリを、再度「隙間ノズル」で丁寧に吸い取ります。
ステップ4:羽根と内部の拭き掃除
ガードの隙間から、水や中性洗剤を薄めた液で濡らして固く絞った「綿棒」を差し込みます。これで、羽根(ファン)の表面や、ホコリが固着しやすい隅の部分を地道に拭き取っていきます。ウェットシートを割り箸に巻き付けて使っても便利ですよ。
ステップ5:仕上げ(ブロー)
最後に、内部のモーター付近や、どうしても手の届かない部分に残った微細なホコリを「エアダスター」で吹き飛ばします。
エアダスター使用時の重要注意点
エアダスターは便利ですが、最大の問題点は「室内にホコリが盛大に舞い散る」ことです。お部屋でやると、掃除したはずなのに余計に汚れてしまう…なんてことに。
- 実施場所:必ず、ベランダや玄関、または換気扇を最大にした浴室(お風呂)で行うことを強くおすすめします。
- 準備:床に新聞紙などを敷いておくと、後片付けがラクになりますよ。
ホコリ飛散を最小限にする「プロ推奨」プロセス
よく「まずエアダスターで吹く」というガイドを見かけますが、それだと表面のホコリを内部に押し込んでしまうリスクがあるんです。専門的な観点からは、
「1. 拭き取り(表面) → 2. 撹拌(ブラシ) → 3. 吸引(掃除機) → 4. ブロー(エアダスター)」
この順序が、ホコリの飛散と内部への侵入を最小限に抑えるための最適なプロセスだと私は思います!
…と、ここまで読んで「正直、めちゃくちゃ面倒…」と思いませんでしたか?
そうなんです、この応急処置は本当に手間がかかるんです。
だからこそ、この「面倒」を解決するアイテムや、根本的な解決策が重要になってくるんですね。
外れないサーキュレーター|掃除の最終手段
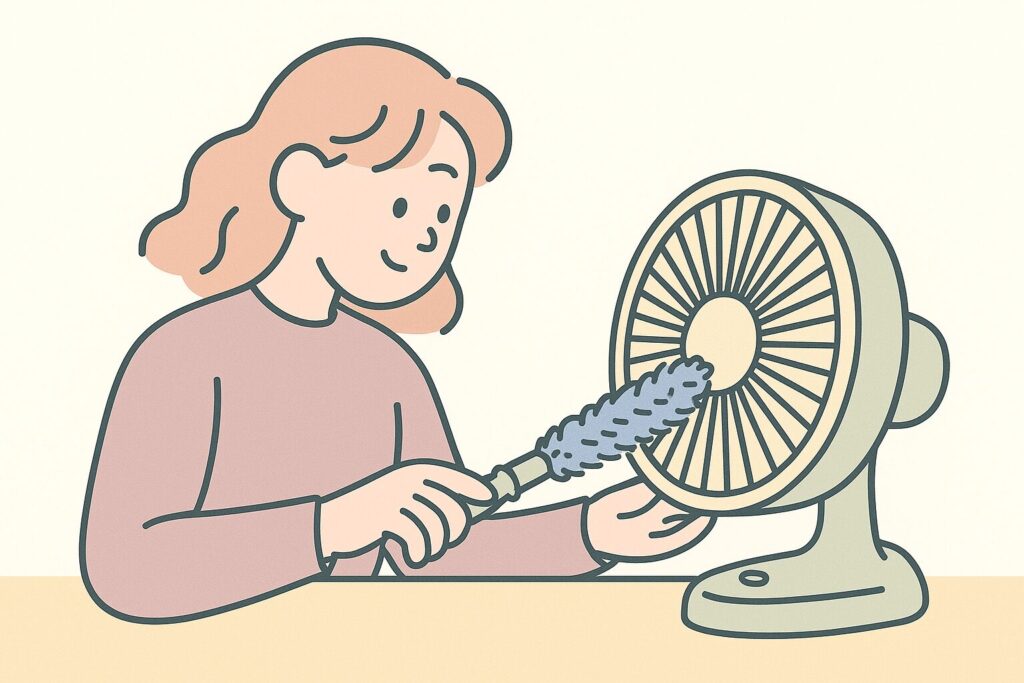
分解できないサーキュレーターの掃除がいかに大変か、お分かりいただけたかと思います。「もうこんな面倒な思いはしたくない!」というのが本音ですよね。
ここからは、その「外れない」ストレスから解放されるための、より積極的な対策や最終手段についてご紹介していきます。便利なガジェットから、根本的な解決策である「買い替え」のおすすめモデルまで、しっかり解説しますね!
隙間掃除にニトリの専用ブラシ
まずは、先ほどの応急処置(ステップ3と4)を、もっとラクにしてくれる「専用ガジェット」のご紹介です。これがあるだけで、あの地道な作業の効率が格段にアップしますよ。
お客様からも「あれ、すごく良かったよ!」と教えていただくことが多いのが、専用のクリーニングブラシです。特に人気なのがこの2つですね。
これはもう定番中の定番かもしれません。
以前は「しなるブラシ」という名前で知られていた製品です。
- 特徴:硬いブラシではなく、「もふもふ」とした超極細繊維がホコリをしっかり吸着してくれます。
- 嬉しいポイント:中心が柔らかいワイヤーでできていて、自由に「しなって曲がる」んです。これが本当に便利で、サーキュレーターの丸い形状や、ガードの隙間から入れた先の「羽根のカーブ」にもぴったりフィットしてくれます。
- 衛生的:本体は水洗いOKなので、汚れたら洗って清潔に保てるのもいいですよね。
100円ショップのダイソーも負けていません。
この製品、110円(税込)とは思えない多機能ぶりがすごいんです。
- 特徴:1本で「ブラシ(埃を掃う)」「クリーナー(汚れを拭う)」「ヘラ」の3役をこなします。
- 注目ポイント:私が特に「これは!」と思ったのが、先端の「ヘラ」機能です。
「ヘラ」が固着したツメにも使える!?
先ほど、「固着したプラスチックのツメの外し方」で「薄いヘラが有効」というお話をしましたよね。あの作業に、まさにこのダイソーの製品に付いているプラスチック製の「ヘラ」が使えるんです。
金属製のマイナスドライバーだと本体を傷つけてしまうリスクが高いですが、これならプラスチック製なので、本体を傷つけにくい「内張り剥がし」として活躍してくれる可能性があります。(もちろん、破損のリスクがゼロになるわけではないので、作業は慎重に!)
隙間掃除だけでなく、そんな裏ワザ的な使い方も期待できる、侮れないアイテムだと思います。
こうした専用ブラシを使えば、綿棒や割り箸でチマチマやるよりも、ずっと早く・キレイに掃除が終わると思いますよ。
応急処置派の方は、ぜひ試してみてください!
おすすめは山善の工具不要モデル
「専用ブラシでマメに掃除…もいいけど、やっぱり根本的にラクしたい!」…ですよね。
わかります。
私もズボラな方なので(笑)
結局は「お手入れが簡単なモノを選ぶ」のが一番だと思っています。
「外れない!」という不満を二度と抱かないための根本的な解決策は、「最初から掃除が簡単に設計されている製品に買い替える」こと。これに尽きます。
では、どのメーカーを選べばいいのか。家電量販店で様々なモデルを比較している私のイチオシは、ずばり「山善(YAMAZEN)」です。
山善は、サーキュレーター市場において「お手入れのしやすさ」を最大の強みとして打ち出しているメーカーさんで、製品ラインナップが本当に充実しているんです。
店頭で「とにかく分解して丸洗いできるサーキュレーターが欲しい」というお客様には、まず山善のコーナーにご案内することが多いくらいですよ。
山善の「簡単お手入れ」モデル例
- YAS-CH181:
「工具不要で全分解可能」をうたったモデルです。実際に触ってみると、本当に軽い力でパーツが外せて、羽根も前後ガードもぜんぶ水洗いOK。お客様からの評判も「本当に簡単だった」とすごく良いですね。 - RCRP-W015:
こちらも「全分解可能で簡単お手入れ、水洗いOK」。DCモーター搭載で静音性が高いモデルなので、寝室で使いたい方にもおすすめです。 - YAR-BH151:
「工具不要で全分解可能、羽根と前後ガードの水洗いが簡単」。デザインもシンプルで人気があります。
(※型番は時期によって変わることがありますので、店頭や公式サイトで「工具不要」「全分解」の記載をぜひチェックしてみてくださいね)
「サーキュレーター=掃除が面倒」という常識を覆してくれたのが山善だと思っています。
あの「外れない!」ストレスから解放されたい方には、本当におすすめのメーカーさんです。
洗い方も簡単な全分解タイプとは
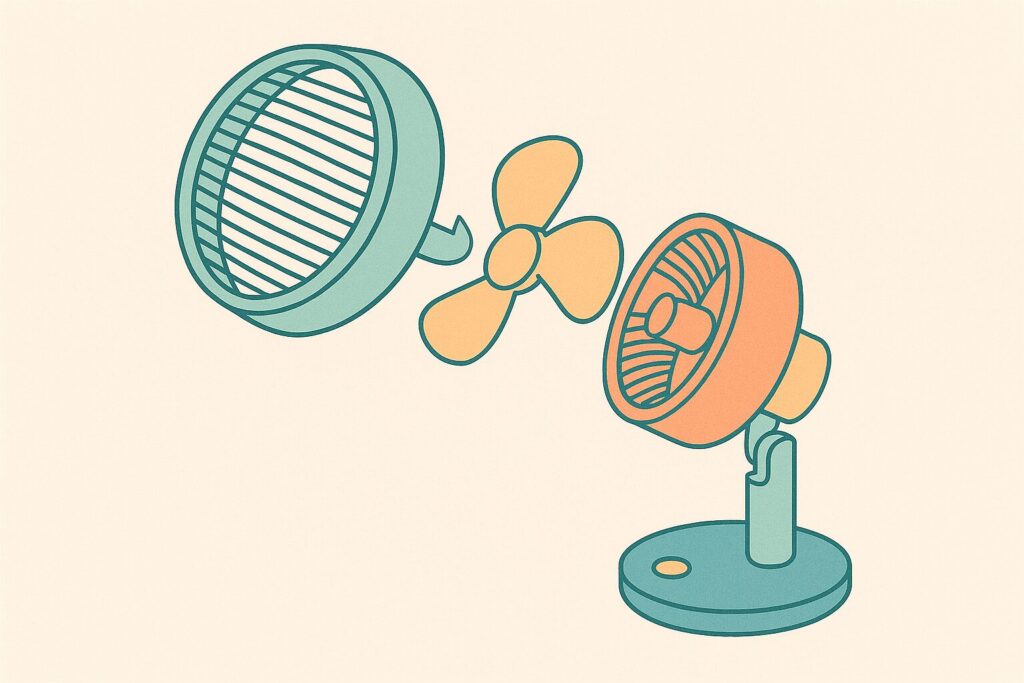
「全分解」と言っても、実はメーカーやモデルによって「どこまで」分解できるかが微妙に違うので注意が必要なんです。ここでは後悔しないモデル選びのために、「全分解」のレベルについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
先ほどご紹介した山善以外にも、「お手入れ簡単」をうたうメーカーさんはもちろんあります。例えば、大人気のアイリスオーヤマや、デザイン性の高いドウシシャなどですね。
ただ、ここで思い出してほしいのが、アイリスオーヤマの「PCF-SC15T」の例です。あのモデルのように「前面は工具不要、でも背面はネジ必須」というタイプも「お手入れ簡単」として売られていることがあるので、「工具不要で、どこまで外せるのか?」をしっかり見極めるのが最大のポイントです。
私が考える「本当に掃除が簡単なモデル」の定義は、「前面ガード・羽根・背面ガードのすべてが、工具不要で外せる」ことです。これなら、ホコリが溜まりやすい全てのパーツを、文字通りシンクで丸洗いできますからね。
下記に、おすすめの「本当に掃除が簡単な」モデルを比較表にまとめてみました。
(※あくまで一例です。型番や仕様は変更される場合がありますので、購入前に必ず最新情報をご確認くださいね)
| メーカー | 型番(例) | 分解レベル | 工具不要? | DCモーター |
|---|---|---|---|---|
| 山善 | YAS-CH181 | A:全分解 | ○ 完全 | × (AC) |
| 山善 | RCRP-W015 | A:全分解 | ○ 完全 | ○ (DC) |
| ドウシシャ | FCZ-181WH | A:全分解 | ○ 完全 | × (AC) |
| アイリスオーヤマ | KCF-BD151TEC-W | B:背面まで | ○ 完全 | ○ (DC) |
| バルミューダ | A02A-WK | C:前面+羽 | ○ 完全 | ○ (DC) |
| ※要注意 アイリスオーヤマ |
PCF-SC15T | D:要注意 | △ (前面のみ) | × (AC) |
※分解レベル定義(独自):A:前後G, 羽すべて工具不要 / B:背面まで工具不要 / C:前G, 羽が工具不要 / D:前面のみ工具不要、または要注意
アイリスオーヤマでも、「KCF-BD151TEC-W」のようなWOOZOO(ウーズー)シリーズの上位モデルは、ちゃんと「背面まで分解して部品の丸洗いが可能」と明記されていて素晴らしいですね。
このように、「全分解」という言葉だけを鵜呑みにせず、「工具不要で、どこまで洗えるのか」をしっかり確認して選ぶことが、未来の「外れない!」ストレスをなくす一番の近道ですよ。
無印良品のリコール情報
「掃除を怠るリスク」のセクションで、火災のリスクについて触れましたが、ここで、実際に起きた重大な事故とリコール(製品回収)について、具体的にお伝えしておかなければなりません。
これは私たち家電を扱う者にとっても、非常に衝撃的なニュースでした。
対象製品:株式会社良品計画(無印良品)
「お手入れがしやすい 首振りサーキュレーター 6畳」
型番:MJ-CIS06
この製品が、2023年8月に使用中に発煙・発火するという火災事故が発生しました。これを受けて、2023年9月8日よりリコール(回収・返金)が実施されています。
原因は、先ほどご説明した「首振りによる配線コードの断線ショート」の可能性が高いと報告されています。
お手元の製品をご確認ください!
もし、ご自宅で無印良品のサーキュレーター(特に「MJ-CIS06」)をお使いの方がいらっしゃいましたら、今すぐ使用を中止し、型番をご確認ください。
対象製品だった場合は、火災事故に至る危険性がありますので、絶対に使い続けないでください。詳しい情報や手続きについては、必ず下記の公式サイトで確認をお願いします。
(出典: 無印良品「「お手入れがしやすい首振りサーキュレーター6畳」 商品回収のお知らせ」)
※この記事で紹介しているリンクは一例です。最新の情報は必ずご自身でメーカー公式サイト等をご確認ください。
この製品、名前が「お手入れがしやすい」となっているのが、なんとも皮肉ですよね…。お手入れのしやすさだけでなく、「安全に使い続けられる設計か」というのも、家電選びの重要な視点だと改めて痛感させられる事例でした。
「外れない」という不満だけでなく、お使いの製品が「安全か」どうか、定期的にこうしたリコール情報にも目を向けていただくことを強くおすすめします。
外れないサーキュレーター掃除は買い替えで解決
ここまで、「外れない」サーキュレーターの原因から、危険性、そして面倒な応急処置まで、詳しく見てきました。
一体型モデルや固着してしまったモデルを、専用ブラシや掃除機を駆使して、ホコリが舞う中で地道に掃除し続ける…。それは、火災や健康被害を防ぐために「やらなければいけない」作業です。でも、正直なところ、その作業、ものすごくストレスじゃないでしょうか?
「またあの面倒な掃除か…」と憂鬱になったり、忙しくてつい後回しにしてしまい、ホコリまみれのサーキュレーターを見て見ぬふりしたり…。そんな状態は、精神衛生上もあまり良くないですよね。
だからこそ、私は最終的な解決策として、「お手入れが本当に簡単なモデルへ買い替える」ことを強くおすすめしたいんです。
買い替えがもたらす「本当の価値」
山善や、アイリスオーヤマ・ドウシシャの「工具不要・全分解モデル」に買い替えたお客様からは、本当に「もっと早く買い替えればよかった!」というお声をたくさんいただきます。
- ストレスからの解放:
「外れない!」と格闘するイライラがゼロになります。 - 圧倒的な時短:
応急処置にかかっていた時間(30分?1時間?)が、分解して丸洗い(5分~10分)で終わります。 - 完璧な清潔さ:
手の届かなかった羽根の裏側やモーター周りまで、スッキリ丸洗い。カビやニオイの心配もありません。 - 精神的な余裕:
「掃除がラク」というだけで、サーキュレーターを使うこと自体が楽しくなりますし、お部屋の空気もキレイになって、生活の質(QOL)がグッと上がると思いますよ。
もちろん、まだ使えるものを買い替えるのは「もったいない」と感じるかもしれません。でも、掃除にかかる「時間」と「労力」、そして「ストレス」は、目に見えないコストです。そして何より、掃除を怠った場合の「火災」や「健康被害」という取り返しのつかないリスク…。
それらを天秤にかけた時、数千円~1万円程度の投資で「安全」と「快適なお手入れ時間」が手に入るなら、私はそれが一番賢い選択じゃないかな、と思います。
もし今、目の前の「外れないサーキュレーター」を前にうんざりしているなら、ぜひ一度、家電量販店で「全分解モデル」を実際に触ってみてください。その驚くほどの簡単さに、きっと感動すると思いますよ!