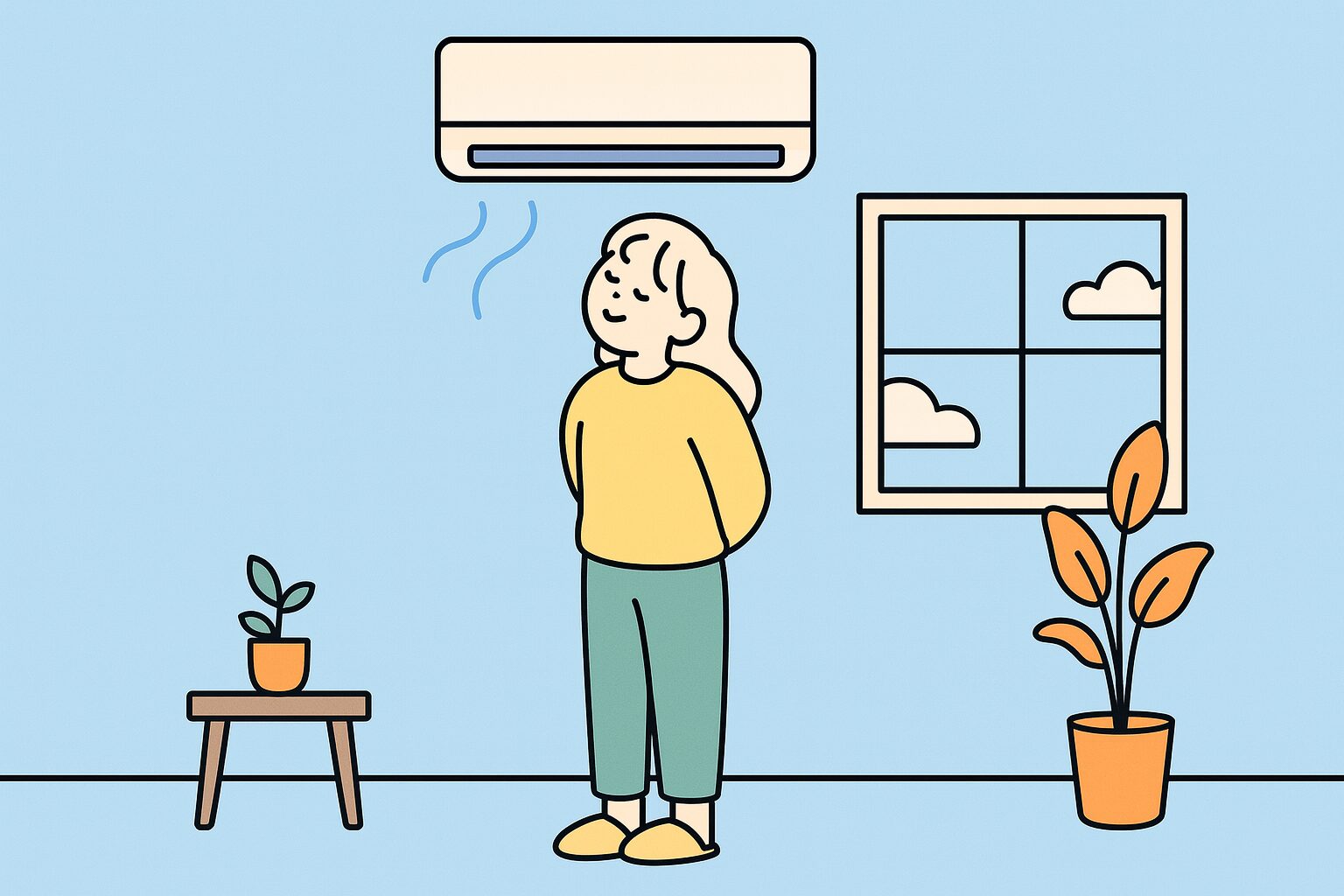夏の暑い日や冬の寒い日にエアコンを使っていると、電気代がどんどん上がっていくのが気になりますよね。特に風量の設定について、強くすると電気代が高くなりそうだから弱に設定している方も多いのではないでしょうか。
実は私も家電量販店で働いていると、エアコンの風量では電気代は変わらないという話をよく耳にします。
でも本当にそうなのでしょうか?
風量を変えても電気代に影響しないなら、強風にしたりしてもっと快適に使えるのにと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
最近では省エネ技術が進歩して、各メーカーから様々な機能を搭載したエアコンが発売されています。しずかモードや送風機能、AI制御など、これらの機能が実際にどれくらい電気代に影響するのかも気になるところです。
また、10年前や20年前のエアコンをまだ使っている方は、最新モデルに買い替えるとどれくらい電気代が変わるのかも知りたいですよね。設定温度を変えるのと風量を調整するのでは、どちらが節電効果が高いのかという疑問もあります。
この記事では、エアコンの風量と電気代の関係について最新情報をもとに詳しく解説します。各メーカーの省エネモデルの比較や、扇風機との電気代の違いまで幅広くご紹介しますので、エアコンの電気代を賢く節約したい方はぜひ参考にしてください。
エアコンの風量では電気代は変わらないのかを解説
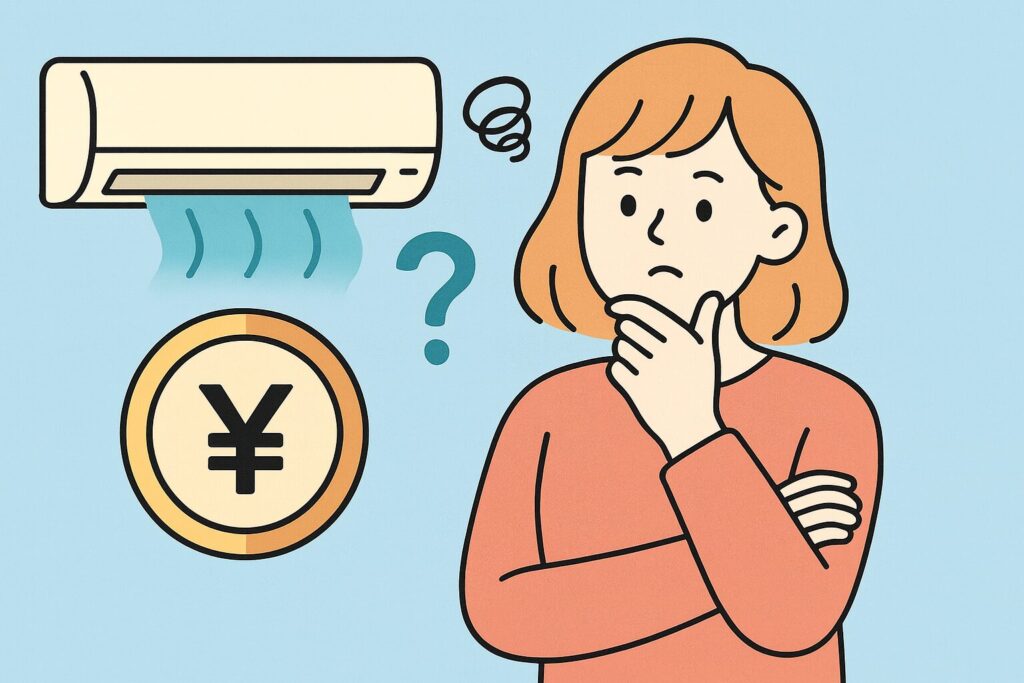
まずは、エアコンの風量と電気代の関係について多くの方が抱いている疑問にお答えします。
風量設定が実際に電気代にどのような影響を与えるのか、そして最も効率的な使い方について詳しく見ていきましょう。
風量で電気代は変わる?
エアコンの風量設定は電気代に大きく影響します。風量を「弱」にすると節電になると思われがちですが、実際には設定温度に到達するまでに時間がかかり、かえって多くの電力を消費してしまいます。最も効率的なのは「自動」設定で、エアコンが最適な風量を自動調整することで電気代を抑えることができます。
多くの方が気になるエアコンの風量と電気代の関係ですが、実は密接な関わりがあるんです。
エアコンの電気代は風量設定によって変動します。ただし、風量を「弱」にすれば節電になるという単純な話ではありません。むしろ逆の結果になることも多いんですね。
風量を「弱」に設定すると運転音が静かになるため、節電効果があるように感じられます。しかし実際には、室内を設定温度まで調整するのに時間がかかってしまい、かえって多くの電力を消費してしまうことがあります。
パナソニックの調査によると、「微風」設定は「自動」と比べて設定温度に到達するまでの消費電力が20%も高くなることが報告されています。また、設定温度に達するまでの時間も「自動」より6.4分長くかかるという結果も出ているんです。
一方で、風量を「強」に設定した場合はどうでしょうか。風量を強くすることで、エアコン本体にある熱交換器を経由する空気の量が増え、熱交換率が上昇します。結果として、短時間で室内を設定温度に調整できるため、総合的な電力消費量は少なくなる傾向があります。
これは冷房と暖房の両方に当てはまる現象です。エアコンが最も電力を消費するのは、室温を設定温度まで調整する際なので、効率的に温度変化を実現できる風量設定が節電につながります。
電気代を節約できる風量は?
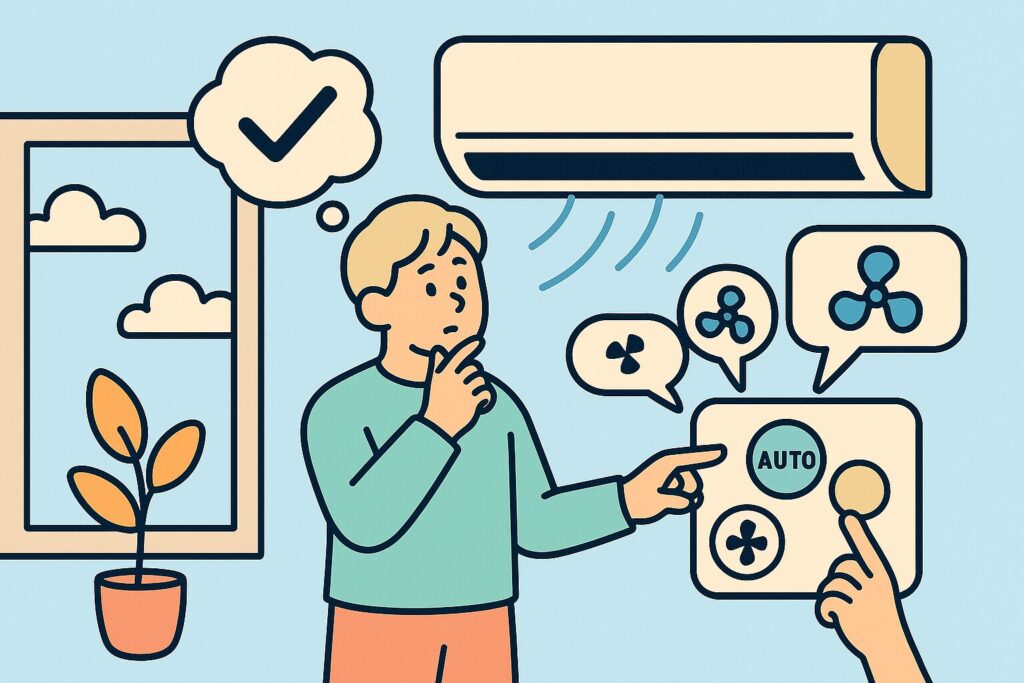
エアコンの電気代を最も効果的に節約できる風量設定は「自動運転」です。
自動運転モードでは、エアコンが室温と設定温度の差を感知し、最適な風量を自動的に調整してくれます。設定温度に到達するまでは「強風」で運転し、設定温度に達した後は「微風」に切り替えるという効率的な制御を行います。
ダイキンの実験データでは、設定温度を26℃から25℃に1℃下げた場合の消費電力が1.13kWhだったのに対し、28℃設定で風量を「強」にした場合の消費電力は0.52kWhという結果が出ています。電気代に換算すると、温度を下げた場合が約35円、風量を強にした場合が約16円となり、風量調整の方が約半分の電気代で済むことがわかります。
ただし、単純に風量を「強」に固定するのではなく、状況に応じて調整することが大切です。設定温度に達した後も風量を「強」のままにしておくと、今度は無駄な電力消費につながってしまいます。
そのため、エアコンに搭載されている自動運転機能を活用することで、最も効率的な風量制御が実現できます。自動運転なら、室温や湿度などの環境条件に応じて風量を自動的に調整してくれるため、必要以上に風量を上げすぎることなく、快適な室内環境を保ちながら節電効果も期待できます。
しずかモードの電気代
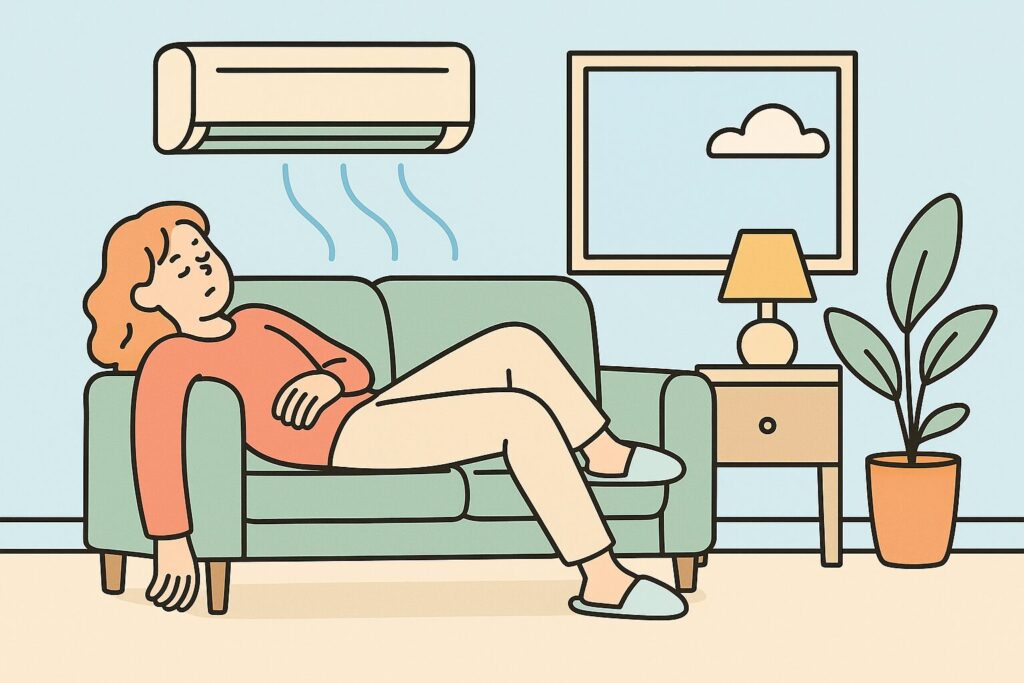
エアコンの「しずかモード」は、その名前の通り運転音を静かにすることを一番の目的とした機能です。
しずかモードの電気代について正直にお話しすると、節電効果はあまり期待できません。電気代の節約のためというよりは、快適な環境作りのための選択肢と考える方が適切でしょう。
しずかモードでは常に弱い風で運転し続けるため、特に暑い日や広い部屋では、いつまで経っても快適な温度にならず、エアコンがずっとフル稼働で頑張り続けてしまうことになります。結果として、電気代が高くなる可能性があるんです。
パナソニック製のエアコンにおいても、「しずかモード」はあくまで静かに過ごしたいシーンのための特別な機能として位置づけられています。電気代を意識するなら、先ほどもお伝えしたように「自動運転」を基本にするのが賢明です。
しずかモードの最大のメリットは運転音が圧倒的に静かになることです。風量を極端に弱めることで、ファンが回る音や風切り音を最小限に抑え、静かで快適な空間を作り出してくれます。風が直接体に強く当たる不快感も少ないため、やさしい空調を好む方にはぴったりです。
ただし、静かさは大きな魅力ですが、電気代や効きの面も考えて、上手に使い分けることが大切です。普段は「自動運転」を基本とし、「しずかモード」はどうしても音を静かにしたい特別なシーンでのみ使う「切り札」として活用するのが最も賢い使い方だと思います。
送風をつけっぱなしにした電気代
エアコンの送風機能は、温度を変えずに風を送る機能で、電気代が非常に安いのが特徴です。
送風機能の電気代は、1時間あたり約0.5円程度しかかかりません。これは扇風機とほぼ同じレベルの電気代です。1日24時間つけっぱなしにしても約12円、1ヶ月間つけっぱなしでも約377円という驚くほど安い電気代で済みます。
シャープの20畳用エアコン「AY-T63V2」を例にとると、送風運転時の消費電力は16.5Whとなっており、冷房運転時の消費電力と比べると30分の1以下という圧倒的な差があります。
送風機能がこれほど安い理由は、室内の空気を吸い込んでそのまま送り出すだけで、空気を冷やしたり温めたりする機能が働かないためです。サーキュレーターや扇風機と同様の原理で運転しているため、熱交換器や室外機を作動させる必要がありません。
送風機能は単独で使うだけでなく、冷暖房の効率を高める補助的な役割としても活用できます。冷房を使う前に窓を開けて送風機能で換気を行うことで、効率的に部屋を涼しくすることができるんです。
また、冷房を使った後のエアコン内部は湿度が高くなってカビが発生しやすい状態になるため、冷房の後に送風で運転すると、エアコン内部を乾燥させることができてカビ対策にも有効です。梅雨や雨の日などでジメジメした日は、エアコンの送風と換気扇を組み合わせて、電気代をカットしながら快適な環境を作ることもできます。
暖房の場合は?

暖房時の風量と電気代の関係についても、基本的な考え方は冷房と同じです。
暖房においても、風量を「弱」に設定するよりも「自動」に設定する方が電気代の節約につながります。エアコンが室温に合わせて自動的に風量を調整してくれるので、暖房を効率良く活用できるからです。
風量を「弱」に固定して使用すると、室温が設定温度に達するまでに時間がかかり、かえって消費電力量が多くなる原因となるため注意が必要です。暖房時の設定温度は20℃がおすすめで、これは環境省が推奨している設定温度でもあります。
パナソニックの調査によると、暖房利用者の平均設定温度は22℃から25℃がボリュームゾーンとなっており、環境省が推奨する20℃よりも高めの設定になっています。冬の暖房時は、設定温度を1℃下げるだけで消費電力を約10%も削減できると言われているため、多くの人が設定温度を下げる余地があると考えられます。
暖房時の風向きも電気代に影響します。暖かい空気は上に移動する性質があるため、サーキュレーターで室内の空気を循環させることが必要です。冬の場合はエアコンの対角線上に設置し、上向きに風を送ると天井付近にたまった暖気が室内に循環しやすくなります。
また、外気温が3℃より低い厳しい寒さの場合は、エアコンを停止後、室温が短時間でも大きく下がりやすく、帰宅後に設定温度に戻すために多くのパワーが必要になります。その分電気代も多くかかってしまうため、「つけっぱなし」運転の方がお得になることもあります。
エアコンの風量では電気代は変わらないのかを比較
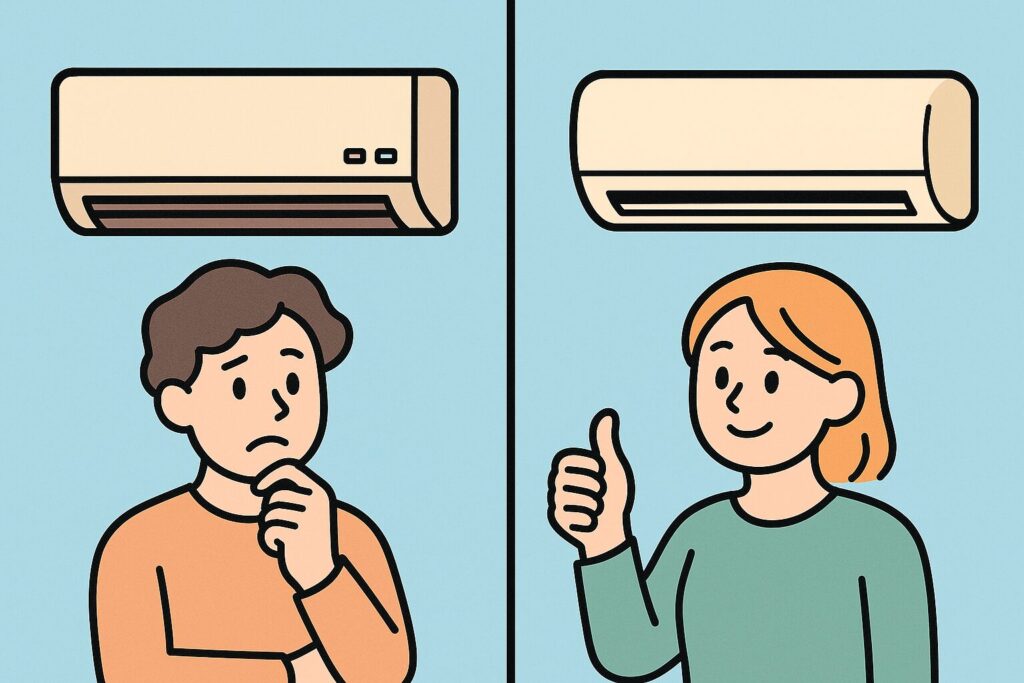
ここからは具体的なデータを使って、様々な角度からエアコンの風量と電気代を比較検証します。
10年前のモデルとの差額や、他の家電との比較など、気になる情報をまとめてご紹介します。
10年前のエアコンとの電気代の比較
年間電気代
年間電気代
年間電気代
年間電気代
最新のエアコンは省エネ技術が大幅に進歩しており、10年前のモデルと比べて年間13,000円以上、20年前のモデルと比べて年間64,000円以上の電気代削減が可能です。また、エアコンの標準使用期間は10年とされており、性能低下や故障リスクを考慮すると、適切なタイミングでの買い替えが経済的にもメリットがあります。
最新のエアコンと10年前のエアコンでは、電気代に大きな差が生まれています。
10年以上前のエアコンと最新のエアコンを比較すると、最新のエアコンは年間13,000円以上も電気代が安くなることがわかっています。これは省エネ技術の大幅な進歩によるものです。
具体的な比較例として、6畳用エアコンの場合、20年前のモデルでは年間電気代が約91,000円だったのに対し、2011年製では約34,000円、最新モデルでは約27,000円程度となっています。20年前と最新モデルを比較すると、年間で約64,000円もの差が生まれることになります。
ただし、これらの数値は使用頻度や設定温度、住宅の断熱性能などによって変動するため、あくまで目安として考えてください。
エアコンの買い替えには本体価格と設置費用がかかりますが、電気代の節約分を考慮すると、長期的にはお得になるケースが多いです。20年前のエアコンを最新モデルに買い替えると、約6年から7年で元が取れる計算になります。
また、エアコンは10年を超えて使用すると性能が低下し、故障のリスクが高まります。補修部品の保有期間が終了すると修理が困難になる場合もあるため、エアコンは10年を目安に買い替えを検討するのが良いでしょう。
設定温度を下げるのと風量を強にするのはどっちが節電?
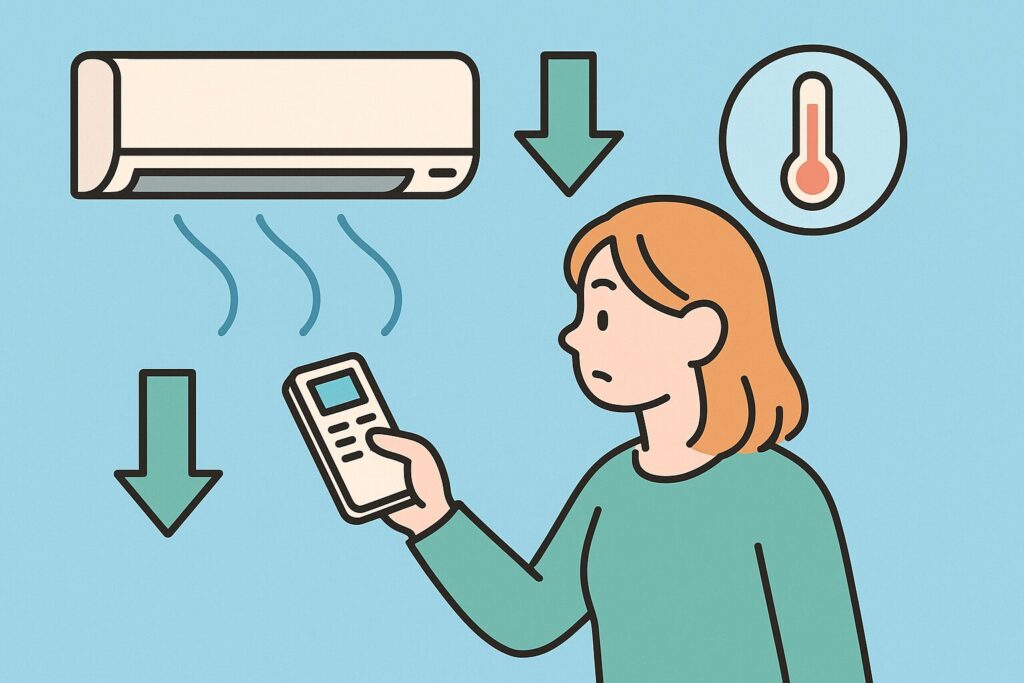
設定温度を下げることと風量を強にすることを比較すると、風量を強にする方が節電効果が高いことがわかっています。
ダイキンの実験では、真夏の日中(13時から15時)に設定温度を26℃から25℃に1℃下げた場合と、28℃設定で風量を「強」にした場合を比較しました。結果として、設定温度を1℃下げた時の消費電力量は1.13kWh(電気代約35円)だったのに対し、風量を強に設定した場合は0.52kWh(電気代約16円)という結果が出ています。
つまり、風量を「強」に設定した方が消費電力が少なく、電気代も約半分で済むということです。
この理由は、設定温度を下げた時にエアコンが室内の空気中からより多くの熱を集めるため、圧縮機の運転を強めなければならないからです。一方で、風量を「強」にすると室内機のファンの音が大きくなり、電気をたくさん使っているように感じますが、ファンが使う電力は圧縮機が消費する電力と比べるとわずかなんです。
人の体感温度は室温だけでなく、湿度や気流によっても変化します。室温を下げる代わりに風量を強くすることで体感温度が下がり、涼しく感じられるため、実際の室温はそれほど下げなくても快適に過ごせます。
パナソニックの調査でも、冷房の温度を1度上げるだけで約10%の節電になることが報告されており、冷やすために使う電力よりも風量を上げる方が使用量は少なくて済むことがわかっています。冷房を1度上げて風量を上げることで、年間約1,200円以上節約することができるという結果も出ています。
エアコンと扇風機の電気代を比較
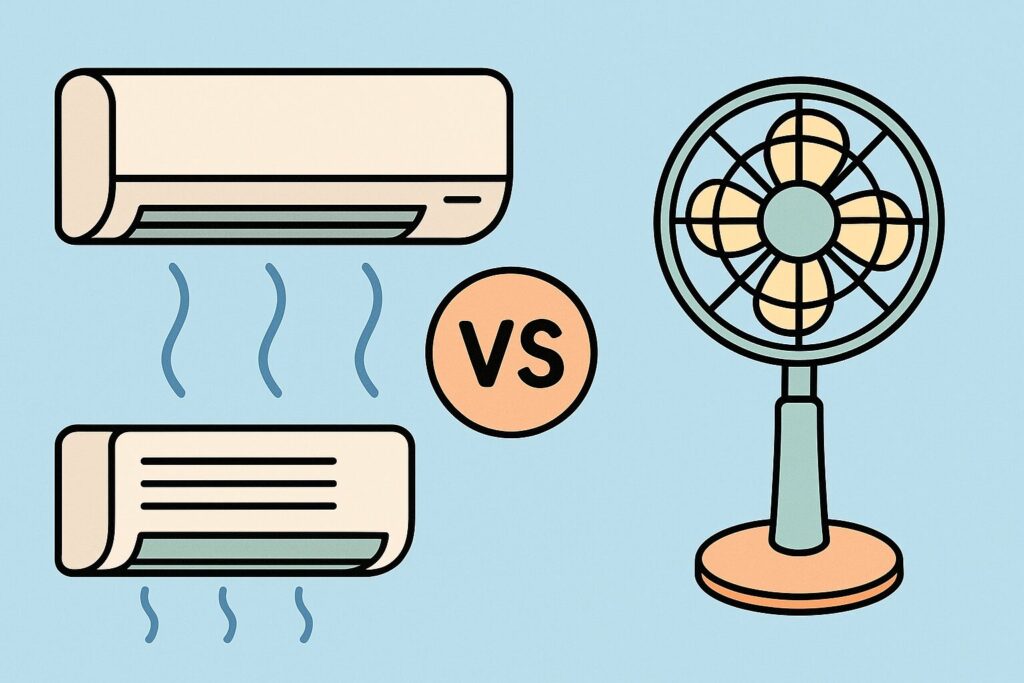
エアコンの送風機能と扇風機の電気代は、実はほとんど同じレベルです。
エアコンの送風機能の1時間あたりの電気代は約0.5円で、扇風機を最大風量で使用した場合の1時間あたりの電気代も約1.1円程度となっています。扇風機と比較した場合、エアコンの送風にかかる電気代は約42%程度と、むしろエアコンの送風の方が安いという結果になります。
サーキュレーターとの比較では、サーキュレーターの消費電力は約20から30Wとなっており、エアコンの送風機能と扇風機に比べて1時間あたり約1円程度高くなっています。
| 機器 | 1時間あたりの電気代 | 1日あたりの電気代 |
|---|---|---|
| エアコン送風 | 約0.5円 | 約12円 |
| 扇風機 | 約1.1円 | 約26円 |
| サーキュレーター | 約1.5円 | 約36円 |
一方で、冷房機能を使った場合のエアコンの電気代は大幅に高くなります。シャープの20畳用エアコンを例にとると、冷房運転時の1時間あたりの電気代は約90円となり、送風運転時よりも約89.5円も高くなります。
1ヶ月間つけっぱなしにした場合を比較すると、エアコンの送風運転時の電気代は冷房運転時よりも約66,570円も安くなる計算です。
このことから、室内の空気を循環させるだけなら、エアコンの送風機能や扇風機、サーキュレーターのどれを選んでも電気代にそれほど大きな差はないことがわかります。ただし、冷暖房機能を求める場合は、エアコンの消費電力が大幅に増加することを理解しておく必要があります。
各社の省エネエアコンの電気代を比較
| メーカー・機種名 | 冷房消費電力 | 暖房消費電力 | 特徴的な機能 |
|---|---|---|---|
| ダイキン S225ATES-W(6畳用) |
580W | 470W | ストリーマ技術 |
| 三菱電機 MSZ-GE2225-W(6畳用) |
425W | 465W | 高温みまもり機能 |
| パナソニック CS-EX225D-W(6畳用) |
520W | 450W | ナノイーX技術 |
2025年最新の省エネエアコンは、各メーカーが独自の技術を駆使して電気代の削減に取り組んでいます。
ダイキンのスタンダードモデル「S225ATES-W」(6畳用)は、冷房消費電力580W、暖房消費電力470Wとなっています。同社独自の放電技術「ストリーマ」を使った「水内部クリーン」機能を搭載しており、同クラスの製品の中でも機能性が優れています。
三菱電機の「霧ヶ峰 MSZ-GE2225-W」(6畳用)は、冷房消費電力425W、暖房消費電力465Wです。ベーシックモデルながら基本機能と品質にこだわりがあり、室内が28度以上の高温状態になると自動で冷房運転を開始する「高温みまもり」機能を搭載しています。
パナソニックの「エオリア CS-EX225D-W」は、清潔さと快適さにこだわったベーシックモデルで、冷房や除湿で発生した水でエアコン内部の汚れを洗い流す内部クリーン機能を搭載しています。外気温が55度でも冷房のパワーを持続する「快速」制御も採用されています。
上位モデルになると、各社ともAI機能を搭載した製品を展開しています。ダイキンの「AI快適自動運転」、パナソニックの「エオリアAI」、三菱電機の「ムーブアイmirA.I.+」など、それぞれ独自のセンサー技術とAI制御による省エネ運転を実現しています。
三菱電機の最新「霧ヶ峰FZシリーズ」では、世界初の「エモコテック」技術を搭載し、人の脈を非接触で計測して感情を推定する「エモコアイ」機能により、これまでにない快適性と省エネ性を両立させています。
総括:エアコンの風量では電気代は変わらないのかについて
それでは最後に、この記事の内容をまとめます。