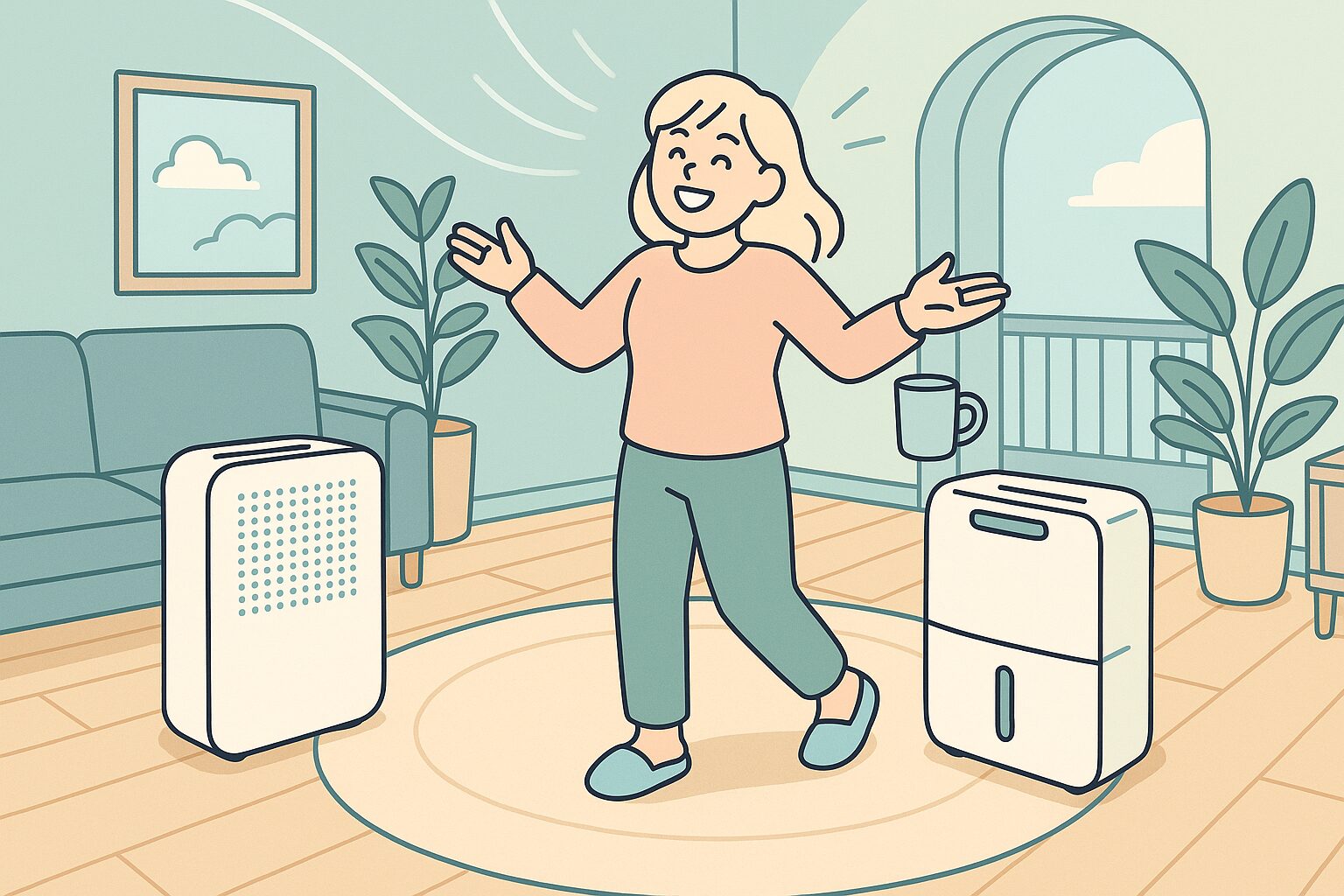「空気清浄機と除湿機って、一体何が違うの?」
「部屋干しの嫌なニオイを何とかしたいけど、どっちを選べばいいんだろう…」
そんな風に悩んでいませんか?
私も家電量販店で働いていると、この二つの違いについてお客様から質問されることが本当に多いんです。見た目が似ているモデルもありますし、最近では除湿機能付きの空気清浄機なんていう一体型もあって、ますます迷ってしまいますよね。
特に梅雨の時期や花粉の季節になると、どちらの機能も魅力的に見えて、一台で済ませたいという気持ちもよく分かります。
でも、それぞれの得意なことや、一体型ならではのデメリットをしっかり理解しないまま選んでしまうと、「思ったような効果が得られなかった…」なんてことにもなりかねません。
この記事では、空気清浄機と除湿機の基本的な役割の違いから、それぞれのメリット・デメリット、そして気になる一体型モデルについて、少し専門的な視点も交えながら、できるだけ分かりやすく解説していきます。
あなたのライフスタイルに本当に合う一台を見つけるお手伝いができれば嬉しいです!
空気清浄機と除湿機の根本的な違いを解説

まずは、そもそも空気清浄機と除湿機がそれぞれどんな役割を持っているのか、基本的な違いから見ていきましょう。
この二つは目的が全く違う家電なので、ここを理解するだけで、製品選びがぐっと楽になりますよ。
空気清浄機の主な役割と機能
空気清浄機の主な役割は、その名の通り「お部屋の空気をきれいにすること」です。
室内に浮遊している目に見えない小さなハウスダストや花粉、PM2.5、ウイルス、ペットの毛などを本体に吸い込み、内蔵されたフィルターでろ過して、きれいな空気を排出する仕組みになっています。
多くの空気清浄機には、役割の違う複数のフィルターが搭載されています。
中心となるのが「HEPAフィルター」と呼ばれる高性能なフィルターです。
このフィルターは、0.3μm(マイクロメートル)という非常に小さな粒子を99.97%以上キャッチできる性能を持っていて、花粉やハウスダストなどを逃しません。
もう一つ重要なのが「脱臭フィルター」です。
こちらは主に活性炭で作られていて、料理のニオイやタバコ臭、ペットのニオイといった生活臭を吸着して取り除いてくれます。
このように、空気清浄機はフィルターを使って空気中の汚れやニオイを除去することに特化した家電なんです。
そのため室内の湿度を下げる機能は基本的に持っていません。あくまで空気をきれいにすることが一番の目的なんですね。
除湿機が得意とする機能とは
一方、除湿機が得意なのは「お部屋の湿度を下げること」です。
ジメジメとした湿気を取り除き、室内をカラッと快適な状態に保つことを目的としています。特に梅雨の時期や、結露が発生しやすい冬場に大活躍しますね。
除湿機が湿気を取り除く方法には、大きく分けて2つのタイプがあります。
このように、除湿機は室内の空気から水分を取り除くことに特化した家電です。空気清浄機のように、空気中のホコリや花粉を取り除くフィルターは基本的に搭載されていません。
あくまでも「湿度コントロール」の専門家というわけですね。この違いをしっかり覚えておきましょう。
除湿機能付き空気清浄機という選択肢
「でも、空気もきれいにしたいし、除湿もしたい…」
「2台も置くスペースがない!」
そんな方のために登場したのが「除湿機能付き空気清浄機」です。
その名の通り、一台で空気清浄と除湿の両方の機能を持ったハイブリッドな家電ですね。
これは空気清浄機の本体に、除湿機の機能(主にコンプレッサー式やデシカント式)をそのまま搭載したモデルです。
空気清浄機としてお部屋の空気をきれいにしながら、同時に除湿もできるのでとても便利に感じられます。
特に、梅雨の時期には湿気とカビ対策、春や秋には花粉対策、と一年を通して活躍の場があります。
また、除湿機能を使って部屋干しの洗濯物を乾かしながら、空気清浄機能で生乾きの嫌なニオイの原因菌を抑制する、といった使い方ができるのも大きな魅力です。
一台で二役をこなしてくれるので、コンセントも一つで済みますし、置き場所に悩んでいる方にとっては非常に心強い選択肢になると思います。
一体型モデルの便利な点
除湿機能付き空気清浄機、いわゆる一体型モデルの便利な点は、何と言ってもその省スペース性です。
本来であれば空気清浄機と除湿機の2台を置かなければならないところを、一台分のスペースで済ませることができます。ワンルームにお住まいの方や、あまりお部屋に家電を増やしたくない方にとっては、これは最大のメリットじゃないでしょうか。
また、操作が一台で完結するのも嬉しいポイントです。
空気清浄と除湿のモード切替や風量調整などを一つの操作パネルで行えますし、コンセントも一つしか使いません。それぞれ別の機器を管理する手間が省けるのは、意外と日々の生活で快適に感じられる部分だと思います。
さらに、季節ごとに家電を入れ替える必要がないのも便利ですね。
春は花粉対策に空気清浄モード、梅雨は部屋干しに除湿モード、というように、一年中出しっぱなしにしておけるので、面倒な収納の手間がかかりません。季節家電の収納場所に困っている方にも、一体型モデルはおすすめできると言えます。
一体型のデメリット
便利な点が多い一体型モデルですが、もちろんデメリットというか、購入前に知っておいてほしい注意点もいくつかあります。お店でもこの点はよくご説明するんです。
まず、本体サイズが大きく、重くなりがちという点です。
空気清浄機能と除湿機能、両方の部品を内蔵しているため、どうしても構造が複雑になり、空気清浄機能のみのモデルと比べると、サイズが大きく、重量もかなりあります。キャスターが付いているモデルが多いですが、お部屋間の移動は少し大変かもしれません。
次に、価格が高くなる傾向があることです。
2つの機能を搭載している分、シンプルな機能の製品よりも価格は上がります。それぞれの単機能のモデルを2台買うのと同じくらいか、それ以上になることもあります。
そして、意外と見落としがちなのが運転音です。
除湿機能、特にコンプレッサー式を搭載しているモデルは、運転音が大きめになることがあります。寝室での使用を考えている場合は、静音モードの有無や、運転音のデシベル(dB)値を確認しておくと安心です。
最後に、どちらかの機能が故障した場合、丸ごと修理に出す必要があるという点も覚えておきたいですね。一体型ならではの注意点と言えるでしょう。
違いを理解!空気清浄機と除湿機の選び方
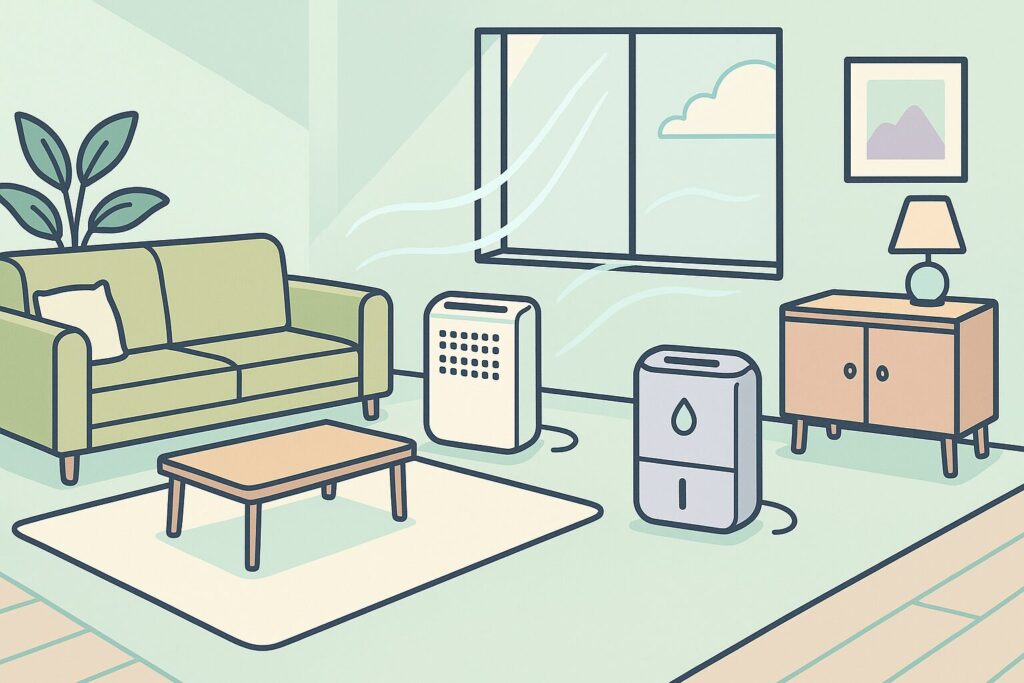
さて、ここまでで基本的な違いや一体型のメリット・デメリットが見えてきたと思います。
ここからは、それらを踏まえて、実際にどちらの製品が自分の生活に合っているのか、選び方のポイントを一緒に見ていきましょう。
除湿機と空気清浄機の併用はあり?
「一体型もいいけど、それぞれの性能を最大限に活かしたい!」という方には、空気清浄機と除湿機をそれぞれ単体で購入して「併用する」という使い方も、もちろんおすすめです。
併用する最大のメリットは、それぞれの専門分野で高いパフォーマンスが期待できることです。
除湿機は除湿能力の高いモデルを、空気清浄機は集じん性能や脱臭能力に優れたモデルを、といったように、自分のこだわりたいポイントに合わせて最強の組み合わせを選ぶことができます。
また、設置場所を分けられるのも利点です。
例えば、湿気がこもりやすい洗面所やクローゼットの近くに除湿機を置き、家族が集まるリビングには高性能な空気清浄機を置く、というように、お家の環境に合わせて最適な配置ができます。
一体型モデルだと本体が大きいので移動が大変ですが、単機能のモデルなら比較的コンパクトなものも多いので、使いたい場所に手軽に持っていけるのも便利ですね。
デメリットとしては、やはり2台分の設置スペースとコンセントが必要になること、そして購入費用が一体型よりも高くなる可能性があることでしょうか。
加湿機能もついた一体型モデルとは
最近では、空気清浄、除湿に加えて「加湿」機能まで搭載した、1台3役のモデルも登場しています。シャープの「プラズマクラスター除加湿空気清浄機」や、ダイキンの「うるるとさらら除加湿空気清浄機」などが代表的ですね。
これらのモデルは、春は花粉、梅雨は除湿、夏は空気清浄、そして冬は加湿と、日本の四季に合わせて一年中、お部屋の空気を快適にコントロールしてくれます。
まさに究極のオールインワンモデルと言えるかもしれません。
季節ごとに家電を入れ替える手間が一切なく、一年中最適な空気環境を一台で維持できるのは、最大の魅力です。
ただし、やはり多機能な分、本体サイズはさらに大きく、価格も高価になります。
また、給水タンク(加湿用)と排水タンク(除湿用)の2種類を管理する必要があり、お手入れの手間も増える点は理解しておく必要があります。
例えば、最新モデルであるダイキンの「うるるとさらら除加湿空気清浄機 MCZ704A-T」は、高い除湿・加湿・集じん・脱臭性能を誇りますが、その分お手入れの箇所も多くなります。
ズボラさんには少し大変かもしれませんね。
部屋干しでの空気清浄機の効果
雨の日が続くと、洗濯物の部屋干しをする機会が増えますよね。あの独特の生乾き臭、気になりませんか?
「部屋干し対策なら、どっちがいいの?」というのも、よく聞かれる質問です。
まず、通常の空気清浄機ですが、これは洗濯物を早く乾かす直接的な効果はありません。
ただし、生乾き臭の原因となる「モラクセラ菌」などの雑菌は、空気中を漂っています。空気清浄機はこれらの菌や、湿気によって発生しやすくなるカビの胞子をフィルターでキャッチしてくれるので、ニオイの発生を「抑制する」効果は期待できます。
サーキュレーターのように風を送る機能があれば、少しは乾燥の手助けにもなりますね。
一方、部屋干しに絶大な効果を発揮するのが「除湿機」または「除湿機能付き空気清浄機」です。
除湿機能は、洗濯物から出る水分をパワフルに吸収し、乾燥時間を大幅に短縮してくれます。これにより、雑菌が繁殖する前に乾かすことができるので、生乾き臭を元から防ぐことができるんです。
衣類乾燥モードが搭載されているモデルなら、洗濯物に直接風を当てて、さらに効率的に乾かせます。
したがって、部屋干しの時短とニオイ対策を本格的に行いたいのであれば、除湿機能は必須と言えるでしょう。
ライフスタイルに合わせた選び方のコツ
結局のところ、どのタイプが一番良いかは、あなたのライフスタイルやお部屋の環境によって変わってきます。
ここで、どんな方にどのタイプがおすすめか、簡単な選び方のコツをまとめてみました。
おすすめの除湿空気清浄機のポイント
もし一体型モデルを選ぼうと決めたなら、チェックしておきたいポイントがいくつかあります。
これを押さえておけば、きっと満足のいく一台が見つかるはずです。
まず一番に確認したいのは「除湿能力」です。
これは「一日にどれくらいの水分を取り除けるか」を示す数値で、「L/日」という単位で表されます。この数値が大きいほど、パワフルに除湿できます。部屋干しをメインで使いたいなら、この数値は特に重要視したいですね。
次に「適用床面積」です。
空気清浄と除湿、それぞれで目安となるお部屋の広さが示されているので、使いたいお部屋のサイズに合っているかを確認しましょう。少し余裕のあるモデルを選ぶのがおすすめです。
フィルターの種類と寿命も大切です。
HEPAフィルターが搭載されているか、脱臭フィルターの性能はどうか、そしてフィルターの交換目安がどれくらいかもチェックしておくと、ランニングコストの計算ができます。
シャープの「プラズマクラスター」やパナソニックの「ナノイーX」のように、メーカー独自のイオン技術が搭載されているモデルも多いです。
これらはフィルターでキャッチするだけでなく、空気中にイオンを放出することで、付着した菌やニオイにも効果があるとされています。こうした付加機能も選ぶ際のポイントになりますね。
例えば、シャープの衣類乾燥除湿機「CV-R120」は、部屋干しを重視する方にぴったりのモデルですね。
プラズマクラスター7000が搭載されているので、生乾きの嫌なニオイを抑えながら、洗濯物をカラッと乾かしてくれます。
1日あたり最大12L(60Hzの場合)というパワフルな除湿能力も頼もしいポイントです。
本格的な空気清浄機のように微粒子を捕集するフィルターはありませんが、プラズマクラスターイオンによるカビ菌抑制などの効果は期待できます。
4輪キャスター付きで移動も楽なので、リビングから洗面所へと、その日の使いたい場所で活躍してくれますよ。
総括:空気清浄機と除湿機の違いを理解する
それでは最後に、この記事の内容をまとめます。