毎日使っている炊飯器、あなたは何年使い続けていますか?
「まだ動くから大丈夫」と思っていても、実は寿命のサインが出ているかもしれません。炊飯器の寿命は一般的に何年くらいなのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
私も家電量販店で働いていると、お客様から「うちの炊飯器、もう10年以上使ってるんだけど、まだ大丈夫かしら」という相談を本当によく受けるんです。
中には20年も使い続けているという強者もいらっしゃいますが、正直なところ安全面やご飯の味を考えると、少し心配になってしまいます。炊飯器は高温の水を扱う家電だからこそ、内釜のコーティング剥がれやパッキンの劣化、電子部品の寿命など、様々な部分で経年劣化が進んでいくんですよね。
特に気になるのが、何年くらいで買い替えを検討すべきなのか、そして20年使うことは本当に可能なのかという点です。実は炊飯器の平均寿命は思っているよりも短く、メーカーの部品保有期間とも深い関係があるんです。
この記事では、炊飯器の平均的な寿命から具体的な買い替えサイン、長持ちさせるお手入れのコツ、そして10年や20年使い続けた場合のリスクまで、家電のプロ目線で詳しく解説していきます。
今お使いの炊飯器が安全かどうかチェックしながら、ぜひ読み進めてみてくださいね!
炊飯器の寿命は何年?買い替え時を解説

- 炊飯器は平均で何年くらい持つ?
- 5つの買い替えサイン
- 内釜の寿命について
- パッキンの劣化と交換目安
- リチウム電池の寿命
- ガス炊飯器の寿命は電気式と違う?
- 10年以上使って起こること
- 20年使うことは可能?
まずは、炊飯器の寿命や「そろそろ買い替えかも?」というサインについて、詳しく見ていきましょう。
ご自宅の炊飯器と見比べながらチェックしてみてくださいね。
炊飯器は平均で何年くらい持つ?
店頭でお客様とお話ししていても、「炊飯器って意外と長く使えちゃう」というお声を聞くんですが、実際のところ、炊飯器の平均寿命は一般的に3年~6年ほどと言われています。
「え、そんなに短いの?」と驚かれるかもしれませんね。
もちろん、これはあくまで平均なんです。
使い方やお手入れの頻度、炊飯する回数によって、寿命は大きく変わってきます。中には10年近く問題なく使えているという方もいらっしゃいますよ。
ただ、一つ知っておいていただきたい大切なポイントがあります。それはメーカーが修理用の部品を持っている期間(補修用性能部品の保有期間)です。
多くの家電製品にはこの期間が定められていて、炊飯器の場合は「製造終了後6年間」というのが一般的です。つまり、製造が終わってから6年以上経った炊飯器が故障してしまうと、「部品がなくて修理できません」となってしまう可能性が非常に高くなるんですね。
この「6年」という数字が、一つの買い替え目安と言われる理由でもあります。
豆知識:寿命の「3年~6年」って何の数字?
この3年~6年という期間は、特に「内釜」のフッ素コーティングの耐久性や、ヒーター部分、電子部品などの寿命が関係していることが多いんです。毎日高熱で炊飯し、保温もするわけですから、炊飯器は私たちが思う以上に頑張ってくれているんですね。
ですから、もし今お使いの炊飯器が6年を超えている場合は、「まだ使えるから」と思っていても、万が一の故障時には修理が難しいかもしれない、ということは少し頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。
最近の炊飯器は省エネ性能も上がっていますし、何よりご飯の味が格段に進化していますから、6年あたりを目安に新しいモデルをチェックしてみるのも、おいしいご飯に出会う良いきっかけになると思いますよ。
5つの買い替えサイン
「まだ使える」と思っていても、炊飯器がSOSサインを出していることがあります。毎日使うものだからこそ、ちょっとした変化に気づいてあげたいですよね。
ここでは、「これは買い替えかも?」という代表的な5つのサインをご紹介します。
サイン1:電源が入らない・液晶表示がおかしい
これは一番分かりやすいサインですね。
コンセントを抜き差ししても電源が入らない、または入っても液晶の表示が欠けたり、チカチカしたりする場合は、内部の電子部品や基板が寿命を迎えている可能性が高いです。
コードの根元が熱くなっていたり、焦げたニオイがしたりする場合は、漏電やショートの危険もあります。すぐに使用を中止して、コンセントを抜いてください。
サイン2:ご飯がうまく炊けない
「最近、ご飯に芯が残る」
「炊きムラがあってベチャッとした部分がある」
「おこげがやたらと増えた」
こんな風に、お米や水の量、設定を変えていないのに炊きあがりに変化が出てきたら要注意です。
これは、炊飯器の心臓部であるヒーターの火力が弱まっていたり、温度を感知するセンサーがうまく働いていなかったりするサインかもしれません。
ご飯の味は本当に正直ですよね。
私も経験があるんですが、同じお米なのに「あれ?」っと思ったら、炊飯器が原因だった…ということ、結構あるあるなんです。
サイン3:炊飯器やご飯から異臭がする
炊飯中や保温中に、プラスチックが焦げるようなニオイや、いつもと違う変なニオイがする場合も危険なサインです。内部の部品が劣化・発熱している可能性があります。
ただし、お手入れ不足で内ぶたやパッキンに汚れが溜まってニオイが出ている場合もあります。まずはしっかりお掃除してみて、それでも異臭が消えない場合は、寿命を疑った方が良いでしょう。
サイン4:炊飯器から異常な音がする
炊飯中の「ジー」「カチッ」といった音は正常な動作音の場合が多いですが、「いつもよりモーター音が大きい」「ブーンという音が鳴りやまない」「ガリガリ、キーキー」といった普段聞き慣れない音がする場合は注意が必要です。
内部のファンやモーターが故障しかけているかもしれません。
サイン5:内釜のコーティングが剥がれている
これは後ほど詳しく解説しますが、内釜のコーティングが広範囲にわたって剥がれてきたら、買い替えの大きなサインです。おいしく炊けない原因になるだけでなく、衛生的にもあまり良くありません。
これらのサインが一つでも見られたら、安全のためにも、一度メーカーに点検を相談するか、新しい炊飯器への買い替えを検討することをおすすめします。
内釜の寿命について
炊飯器の寿命を考える上で、絶対に外せないのが「内釜(うちがま)」の寿命です。
「炊飯器本体はまだ動くけど、内釜だけボロボロで…」というお悩み、本当によく聞きます。実は、炊飯器の寿命=内釜の寿命と言ってもいいくらい、大切なパーツなんですね。
内釜の寿命で一番問題になるのが、フッ素コーティング(テフロン加工など)の剥がれです。
このコーティングがあるおかげで、ご飯がこびりつかず、熱が均一に伝わってお米一粒一粒がふっくら炊きあがります。でも、毎日の洗米や、しゃもじでご飯をよそう時の摩擦、長時間の保温などで、コーティングは少しずつ傷つき、剥がれていってしまうんです。
コーティングが剥がれると、どうなるの?
まず、ご飯がこびりつきやすくなって、洗うのがとても大変になります。無理に剥がそうとすると、さらに傷が広がってしまいますよね。
そして、もっと大きな問題は、炊きムラの原因になることです。コーティングが剥がれた部分は熱の伝わり方が変わってしまい、そこだけ焦げ付いたり、逆に火が通りにくくなったりします。これがおいしさを損ねる大きな原因になるんです。
「剥がれたコーティングを食べても大丈夫?」と心配される方もいらっしゃいますが、主要メーカーの公式サイトなどを見ると、フッ素樹脂は体内に入っても吸収されず排出されるため、人体への影響はないとされています。
とはいえ、ご飯と一緒に剥がれた黒いかけらが入っているのは、あまり気分の良いものではないですよね。
内釜だけを買い替えることも可能ですが、これが意外と高価なんです…。
機種にもよりますが、数千円から、高級モデルだと1万円~2万円以上することも珍しくありません。「内釜を買い替える値段で、新しい炊飯器が買えちゃう…」なんてこともよくあります。
ですから、内釜のコーティングが目立って剥がれてきたり、ご飯がこびりついて取れなくなってきたリしたら、それは炊飯器全体の買い替えを検討する大きなサインだと考えて良いと思いますよ。
パッキンの劣化と交換目安
炊飯器のパーツで、内釜と同じくらい寿命に影響するのが「パッキン」です。
内ぶたについているゴム製の部品のことですね。このパッキン、実はとっても重要な役割を担っているんです。
パッキンは、炊飯器内部の密閉性を高めるためにあります。
圧力IH炊飯器はもちろん、マイコン式やIH式でも、内部の蒸気や圧力をしっかり閉じ込めることで、お米に高温でムラなく火を通すことができるんですね。
また、保温中も内部の湿度を保ち、ご飯が乾燥するのを防いでくれる役割も持っています。
このパッキン、ゴムでできているため、毎日の高温と圧力にさらされることで、どうしても劣化していきます。硬くなったり、ひび割れたり、変色したりしてくるんです。
- 炊飯中に、いつもより多く蒸気が漏れている気がする
- 内ぶたのフチや炊飯器本体との隙間に、水滴やご飯つぶが溜まりやすい
- 保温したご飯がすぐにカピカピに乾燥したり、黄ばんだりする
- パッキン自体が黄色っぽく変色したり、触ると硬くなっている
パッキンが劣化して密閉性が落ちると、うまく圧力がかからず、ご飯がベチャッとしたり、逆にパサついたり…と、炊きあがりに大きく影響してしまいます。
交換の目安としては、だいたい1年~3年ごとと言われていますが、毎日炊飯・保温するご家庭だともっと早い場合もあります。
パッキンは部品として取り寄せ可能な場合が多いですが、交換作業が自分でできるモデルと、メーカー修理(預かり)が必要なモデルがあります。まずはご使用の炊飯器の取扱説明書を確認してみるのが一番ですね。
「最近、保温ご飯がおいしくないな」と感じたら、内釜だけでなく、このパッキンの状態もぜひチェックしてみてください。
リチウム電池の寿命
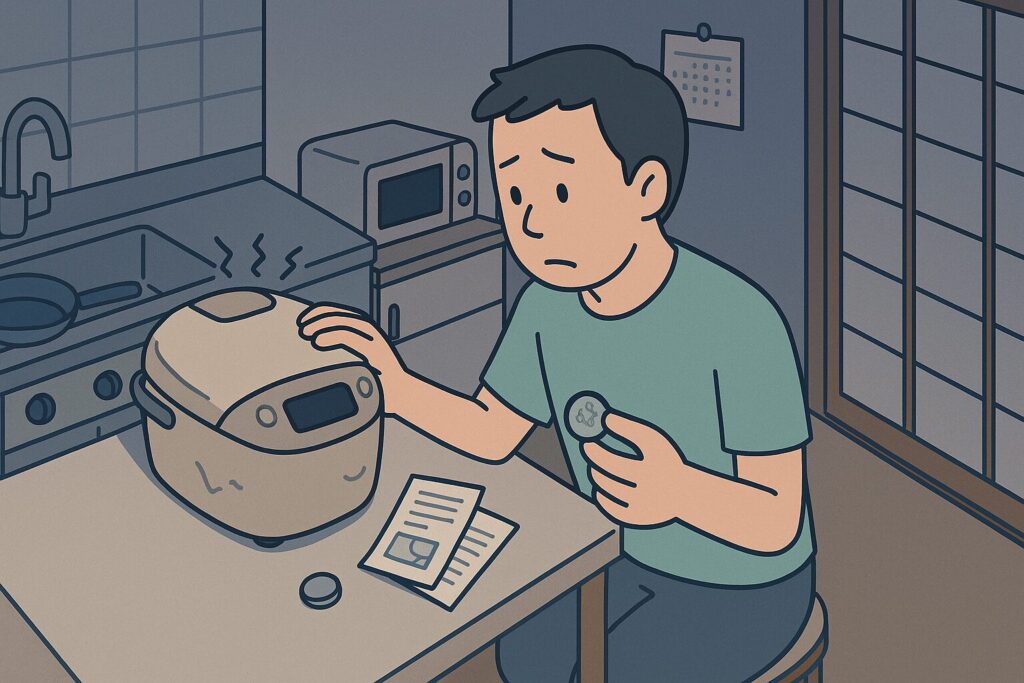
炊飯器に「電池」が入っていると聞くと、ちょっと意外に感じませんか?
実は、多くの炊飯器には、時計の表示や炊飯予約のメモリー機能を記憶させておくために、リチウム電池が内蔵されているんです。
コンセントを抜いても、次に差したときに時計が合っていたり、前回の炊飯設定を覚えていたりするのは、この内蔵電池のおかげなんですね。
このリチウム電池にも当然寿命があります。一般的には約4年~6年程度と言われていますが、これも使用状況によって前後します。
電池が切れるとどうなる?
一番分かりやすい症状は、「コンセントを抜くと、液晶の時計表示が消えたり、リセットされたりする」ことです。「0:00」という表示で点滅になったり、予約設定が消えてしまったりします。
「炊飯」機能そのものには影響がない場合がほとんどです。「コンセントを差している間は時計も見えるし、予約もできる」という状態ですね。
ただ、毎回コンセントを抜くたびに時計を合わせ直したり、予約を再設定したりするのは、結構なストレスじゃないでしょうか?
「じゃあ、電池交換すればいいんだ!」と思いますよね。でも、残念ながら、このリチウム電池はユーザー自身で簡単に交換できる場所にはないんです。
炊飯器の内部基板に直接取り付けられていることがほとんどで、交換するにはメーカーに修理を依頼する必要があります。
修理費用は数千円から1万円以上かかる場合もあり、「電池の寿命が来る=炊飯器本体の他の部分も劣化してきている時期」と考えると、悩ましいところです。
もしコンセントを抜くたびに時計がリセットされるようになって、「不便だな」と感じたら、それは修理に出すか、あるいは新しい炊飯器に買い替えるか、一つの検討タイミングが来たと考えても良いかもしれませんね。
ガス炊飯器の寿命は電気式と違う?
最近は電気炊飯器が主流ですが、根強いファンが多いのが「ガス炊飯器」です。
お店でも「やっぱりガスじゃないと!」とこだわって探されるお客様もいらっしゃいますよ。
ガスの強い火力で一気に炊き上げるので、かまど炊きのようなおこげと、お米の立ったおいしいご飯が楽しめるのが魅力ですよね。
さて、このガス炊飯器の寿命ですが、電気炊飯器とは少し異なります。
一般的に、ガス炊飯器の寿命の目安は約7年~10年程度と、電気式(3~6年)に比べて長く設定されていることが多いんです。
理由としては、構造の違いが挙げられます。
ガス炊飯器が長持ちしやすい理由
電気炊飯器は、IHコイルやマイコン基板、温度センサー、内蔵電池など、多くの電子部品で構成されています。これら電子部品のどれか一つが寿命を迎えると、故障につながりやすいんですね。
一方、ガス炊飯器は、ガスバーナーと点火装置、火力調整の仕組みがメインで、電気式に比べると構造が比較的シンプルです。もちろん電子制御の部分もありますが、主要な炊飯機能がガス(火)であるため、電子部品の劣化による影響が電気式よりは少ない傾向にあります。
ただし、ガス炊飯器ももちろん万能ではありません。
- 火がつきにくい、または途中で消えてしまう
- 炎の色がいつもと違う(赤い炎が出るなど)
- ガスのニオイがする(※これは非常に危険です!すぐに使用を中止し、ガス会社に連絡してください)
- お米がうまく炊けない(生煮え、焦げすぎなど)
電気炊飯器と同じように、内釜のコーティング(フッ素加工など)は消耗品ですし、パッキンも劣化します。
また、ガス機器も部品の保有期間(製造終了後6年が目安)がありますので、10年近く使っていて調子が悪いなと感じたら、点検や買い替えを検討するのがおすすめです。
「うちはガスだから丈夫!」と安心しすぎず、日々のチェックは大切にしてくださいね。
10年以上使って起こること
「うちは炊飯器、10年以上使ってるけど、まだ現役だよ!」という方もいらっしゃると思います。家電量販店にいても、本当に物持ちの良いお客様には頭が下がる思いです。
では、10年以上使い続けると、具体的にどのようなことが起こりやすくなるのでしょうか?
大きく分けて、「性能の低下」と「安全性のリスク」の2つが考えられます。
1. ご飯の味が落ちる(性能の低下)
これが一番実感しやすい変化かもしれません。先ほどもお伝えしたように、長年使うと様々な部品が劣化していきます。
- 内釜の劣化:コーティングが剥がれ、熱伝導にムラができて炊きムラの原因に。
- パッキンの劣化:密閉性が落ち、うまく蒸らせずパサついたご飯に。
- ヒーターの劣化:火力が弱まり、お米の芯まで熱が伝わりにくくなる。
- センサーの劣化:温度管理が甘くなり、ベチャッとしたり、焦げすぎたりする。
「同じお米なのに、昔の方がおいしかった気がする…」というのは、気のせいではなく、炊飯器の性能が落ちているサインかもしれないんです。
また、保温性能の低下も顕著になります。
「保温するとすぐ黄ばむ」「ニオイが気になる」というのも、パッキンの劣化や温度管理の不具合が原因の場合が多いですね。
2. 故障や事故のリスク(安全性の低下)
こちらの方がより深刻な問題です。家電製品は、時間が経てば経つほど部品が劣化し、漏電やショート、発火といった事故のリスクが高まります。
特に炊飯器は、水を使いながら高熱を出す家電です。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなっていないか?
- コードの根元がグラグラしたり、中の線が見えたりしていないか?
- プラスチックが焦げるような異臭はしないか?
- 本体(特に底の部分)から水が漏れた形跡はないか?
もし一つでも当てはまったら、それは非常に危険なサインです。すぐに使用を中止してください。
そして、10年以上経過した炊飯器が故障した場合、ほぼ修理は不可能だと考えた方が良いです。先述のとおり、メーカーの部品保有期間(6年)を大幅に過ぎているため、「部品がない」という理由で修理を断られてしまいます。
10年というのは、家電にとって一つの大きな節目なんですね。
安全においしいご飯を食べ続けるためにも、10年を超えた炊飯器は「よく頑張ってくれたね」と感謝しつつ、新しいモデルへの買い替えを具体的に検討する時期だと思いますよ。
20年使うことは可能?
「10年どころか、うちは20年使ってる!」…すごいことだと思います!
そこまで動いているのは、製品の当たりが良かったのか、お手入れが本当に素晴らしかったのか、もしくは両方かもしれませんね。
では、炊飯器を20年間使い続けることは、現実的に「可能か?」と聞かれれば、「動いているなら可能」としか言えません。
ですが、家電のプロの視点から「おすすめしますか?」と聞かれれば、「安全のために、ぜひ買い替えをおすすめします」とお答えします。
20年使用の大きなリスク
先ほど「10年以上使って起こること」でお話しした内容が、さらに高いレベルで当てはまります。
1. 火災・事故のリスク
経年劣化による危険性が極めて高い状態です。電源コードの劣化、内部基板のホコリや結露によるトラッキング現象、部品の絶縁不良など、いつ発煙・発火してもおかしくないと言っても過言ではありません。20年前の製品は、現在の安全基準を満たしていない可能性もあります。
2. 性能の著しい低下
内釜やパッキン、ヒーターなど、ほぼすべての部品が本来の性能を発揮できていないはずです。「炊ければいい」というレベルであっても、お米本来のおいしさを全く引き出せていない可能性が高いですね。
3. 電気代の問題
家電の省エネ技術は、この20年で劇的に進歩しました。特に炊飯器や冷蔵庫は、毎日使うものなので差が出やすいんです。20年前の炊飯器を使い続けることは、おいしくないご飯を炊くために、余計な電気代を払い続けていることにもなりかねません。
20年間の技術の進歩って、本当にすごいんですよ!
最近の炊飯器(特に圧力IH)で炊いたご飯を初めて食べたお客様が、「これが同じお米!?甘みが全然違う!」と驚かれる姿を私は何度も見てきました。それくらい炊飯技術は進化しているんです。
もちろん、一つのものを大切に長く使う心はとても素晴らしいと思います。
ですが家電製品、特に熱と水を扱う炊飯器に関しては、「安全」と「おいしさ」、そして「省エネ」という観点から、10年、遅くとも15年を一つの区切りとして、新しい製品への買い替えを強くご検討いただきたいな、というのが私の本音です。
20年頑張ってくれた炊飯器には「お疲れ様」と伝えて、新しい炊飯器で炊く「今のご飯」のおいしさを楽しんでみるのはいかがでしょうか?
炊飯器の寿命は何年も延びる?長持ちのコツ

- 内釜に入れてはいけないもの
- 内釜を傷つけない洗い方
- 内ぶたのお手入れ方法
- 吸気口と排気口の掃除
- 長持ちするメーカーはどこ?
- 耐久性が高い!おすすめ炊飯器3選
せっかく買った炊飯器、できるだけ長く、おいしく使いたいですよね。
ここでは、炊飯器の寿命を延ばすために、今日からできる「長持ちのコツ」をご紹介します。ちょっとした心がけで、数年後の状態が大きく変わってきますよ。
内釜に入れてはいけないもの
炊飯器の寿命を縮める一番の原因は、やはり「内釜の傷み」です。
「え、それダメだったの?」というNG行為がないか、チェックしてみてください。
内釜の寿命を縮めるNG行為3選
1. 内釜で酢飯(すし飯)を作る
これは意外とやっている方が多いかもしれません。ちらし寿司や手巻き寿司の時、炊きあがったご飯にそのまま寿司酢を混ぜていませんか?
お酢は酸性が強く、内釜のフッ素コーティングを劣化させてしまう大きな原因になります。すし飯を作るときは、必ず別のボウルや飯台(はんぎり)に移してから、お酢を混ぜるようにしてくださいね。
2. 金属製の調理器具を使う
ご飯をよそう時に、しゃもじの代わりに金属製のお玉やスプーンを使ったりしていませんか?
これもコーティングを傷つけるNG行為です。
また、内釜の中で「炊飯器レシピ」として、泡だて器で混ぜたり、フォークで何かを刺したりするのも絶対にやめましょう。必ず付属のしゃもじか、木製・シリコン製の柔らかいものを使ってください。
3. 炊飯以外の目的で使う(直火・IHにかける)
「内釜を鍋代わりにして、ガスコンロやIHクッキングヒーターで調理する」といった使い方は、非常に危険です。
内釜は炊飯器専用に作られているため、直火にかけると変形したり、コーティングが一気に剥がれたりするだけでなく火災の原因にもなります。絶対にやめてください。
他にも、豆類や麺類、重曹など、炊飯器の蒸気口をふさいでしまう可能性のある食材を使った「炊飯器レシピ」も注意が必要です。調理機能がついていない炊飯器で無理な調理をすると、吹きこぼれや故障の原因になります。
取扱説明書に記載されている用途以外での使用は、寿命を縮めるだけでなく、保証の対象外にもなってしまうので気をつけましょう。
内釜を傷つけない洗い方
内釜のNG行為がわかったところで、次は毎日の「洗い方」です。
ここにも長持ちさせるポイントがたくさんありますよ。
ポイント1:内釜で洗米しない(できれば)
「内釜で洗米OK」とうたっている炊飯器も多いですが、やはりお米と内釜が擦れることで、コーティングが傷つくリスクはゼロではありません。
もし手間じゃなければ、ボウルやザルで洗米するのが内釜を一番長持ちさせる方法です。ちょっとした手間ですが内釜の持ちが全然違ってくるんですよ。
ポイント2:柔らかいスポンジで優しく洗う
内釜を洗う時は、絶対に硬いタワシや研磨剤入りのクレンザーを使ってはいけません。一発でコーティングに傷がつきます。
食器用の柔らかいスポンジに中性洗剤をつけて優しく洗ってください。ご飯がこびりついて取れない時もゴシゴシ擦るのはNGです。お湯にしばらく浸けてふやかしてからスポンジでそっと洗いましょう。
もちろん、食器洗い乾燥機の使用も高温や水圧でコーティングを傷める原因になるので避けた方が無難です(※食洗機対応の内釜を除く)
ポイント3:熱いうちに水につけない
炊きあがったご飯をすぐにおひつなどに移して、熱々の内釜を「ジュッ」と水につけていませんか?
急激な温度変化(ヒートショック)は、コーティングが剥がれやすくなる原因の一つです。内釜が手で触れるくらいの温度に冷めてから、水につけたり、洗ったりするように心がけましょう。
この3つを気をつけるだけでも、内釜の寿命はかなり延びるはずです。
内ぶたのお手入れ方法
内釜の次に見落としがちなのが、「内ぶた」のお手入れです。
炊飯中、お米のでんぷんやうまみ成分を含んだ蒸気が一番当たる場所なので、実はすごく汚れているんです。
ここをキレイにしておかないと、ニオイの原因になったり、パッキンの劣化を早めたり、ひどい場合は蒸気口が詰まってうまく炊けなくなったりすることも…。
理想は、「使うたびに毎回洗う」ことです。
最近の炊飯器は、内ぶたがワンタッチで簡単に取り外せるモデルがほとんどですよね。取り外したら、内釜と同じように柔らかいスポンジと中性洗剤で洗い、しっかり乾かしてから元に戻します。
炊き込みご飯の後は、特に入念に!
調味料や油分を使った炊き込みご飯の後は、特に汚れやニオイが残りやすいです。パッキンの溝なども丁寧に洗ってください。
もしニオイが取れない場合は、炊飯器の「お手入れ(クリーニング)」モードを使ったり、クエン酸洗浄(※メーカー推奨の場合のみ)をしたりするのも効果的ですよ。
「毎回はちょっと大変…」という方も、最低でも2~3回に1度は洗うように心がけてみてください。ご飯の味やニオイが、きっと変わってくるはずです。
パッキン部分も優しく洗い、水分をしっかり拭き取ることが、パッキンを長持ちさせるコツにもつながります。
吸気口と排気口の掃除
炊飯器を長持ちさせるために、意外と知られていない「隠れ重要ポイント」があります。
それが、炊飯器の本体側面や底面にある「吸気口(きゅうきこう)」と「排気口(はいきこう)」のお掃除です。
「え、そんなところにあるの?」と思われるかもしれませんが、炊飯器は内部の電子部品を冷やすために、ここから空気を取り込んだり、熱を逃がしたりしているんです。
ちょうど、パソコンのファンのような役割ですね。
ホコリが詰まると、どうなる?
この吸気口や排気口にホコリがびっしり詰まってしまうと、うまく熱を逃がすことができなくなります。
そうなると、内部に熱がこもり、電子部品の劣化を早めたり、故障の原因になったりするんです。最悪の場合、ホコリが原因でショートし、火災につながる危険性もゼロではありません。
これは炊飯器に限らず、冷蔵庫やテレビ、エアコンなど、ファンがついている家電全部に言えることなんです。家電にとって「熱」と「ホコリ」は大敵なんですよ。
お掃除の方法はとっても簡単!
お掃除といっても難しくありません。月に1回程度、炊飯器の置き場所から動かして、側面や底面をチェックしてみてください。
ホコリが溜まっていたら、掃除機で吸い取るか、乾いた布で拭き取るだけでOKです。水拭きするとホコリが固まってしまうので、まずは乾いたもので取り除くのがポイントです。
また、炊飯器を壁にピッタリくっつけすぎず、空気の通り道を確保してあげることも大切ですよ。
このひと手間が、炊飯器の「隠れた寿命」を延ばすことにつながります。
長持ちするメーカーはどこ?

「どうせ買うなら、少しでも長く使えるメーカーがいい!」というのは、誰もが思うことですよね。私も店頭で「どこのメーカーが一番壊れにくいの?」と、こっそり聞かれることがよくあります(笑)
正直にお話しすると、「このメーカーだから絶対に長持ちする!」と断言するのは、とっても難しいんです…。
なぜなら、先ほどもお伝えしたように、炊飯器の寿命は使い方やお手入れの頻度に大きく左右されるからです。どんなに高級なモデルでも、お手入れを全くしなければ、すぐにダメになってしまうこともあります。
ただ、「長く使うこと」を想定したサービスや設計に力を入れているメーカーはあります。
選ぶ時のヒントとして、いくつかご紹介しますね。
ヒント1:内釜の「保証期間」が長いメーカー
寿命に直結する内釜のコーティング剥がれに対して、「3年保証」や「5年保証」といった長期保証をつけているメーカーがあります。
例えば、パナソニックや日立、東芝などの上位モデルには、内釜のフッ素加工剥がれに対する長期保証が設定されていることが多いですね。(※保証条件はモデルや年式によって異なります)
これは、「それだけ内釜の耐久性に自信がありますよ」というメーカーの意思表示でもあると思います。内釜の寿命が心配な方は、この「内釜保証」をチェックするのはおすすめです。
ヒント2:部品の「保有期間」が長いメーカー
平均的な部品保有期間は「製造終了後6年」だとお伝えしましたが、例えばタイガー魔法瓶は、「全商品の補修用性能部品を製造打ち切り後10年間保有する」ことを目指していると公表しています。(※一部例外あり)
これは、業界水準よりもかなり長いですよね。
「万が一、6年過ぎて故障しても、部品があれば修理できる可能性が残る」というのは、長く愛用したい方にとっては大きな安心材料になるんじゃないでしょうか。
このように、「壊れにくいメーカー」を探すよりも、「長く使うためのサポート(保証や部品供給)が手厚いメーカー」という視点で選んでみると、ご自身の使い方に合った炊飯器が見つかりやすいかもしれませんよ。
耐久性が高い!おすすめ炊飯器3選
「長持ち」をキーワードに炊飯器を選ぶとしたら、どんなモデルがあるでしょうか?
ここでは「内釜の耐久性」や「お手入れのしやすさ(=清潔に保ちやすい)」という観点から、私が個人的におすすめしたい炊飯器を3つ、具体的な商品名も交えてご紹介しますね。
1. アイリスオーヤマ:銘柄炊き ジャー炊飯器 5.5合 RC-ISA50
「高機能じゃなくていいから、コスパ良く使いたい」「消耗品と割り切って、数年で買い替えたい」という方には、アイリスオーヤマのシンプル機能モデルがおすすめです。
例えば「RC-ISA50」は、50銘柄炊き分け機能を搭載しつつ、価格が手頃なのが大きな魅力です。お手入れも内ぶたと内釜の2つを洗うだけとシンプルなので、毎日清潔に保ちやすいんですね。
高価な炊飯器をヒヤヒヤしながら長く使うのも一つですが、こうしたお手頃なモデルを、寿命やコーティングの剥がれを気にせず、3年~5年サイクルで気兼ねなく買い替えていくというのも、衛生的で、常においしいご飯を食べるための一つの賢い選択肢だと思いますよ。
2. タイガー魔法瓶:圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉JPA-Z100KM
「やっぱり、おいしさと耐久性の両方が欲しい!」という方には、タイガーの土鍋コーティングを採用したモデルがおすすめです。
「JPA-Z100KM」は、「遠赤5層土鍋蓄熱コート釜」を採用しており、土鍋に迫るおいしさを追求しています。高い蓄熱性と遠赤効果で、ふっくら甘みのあるご飯が炊きあがるのが特徴です。
そして先ほどもお伝えしたように、タイガーは部品の長期保有(10年目標)を掲げている点が、長く使いたい派の方にとって大きな魅力です。内釜自体の耐久性にもこだわって作られているモデルが多いので、安心して選びやすいメーカーさんだな、と店頭でも感じますね。
3. パナソニック:可変圧力IH炊飯器 おどり炊き SR-M10B-W
「内釜のコーティング剥がれが、とにかく一番心配!」という方には、パナソニックの「おどり炊き」シリーズがおすすめです。
「SR-M10B-W」などに採用されている「ダイヤモンド竈釜」は、丈夫さにも定評があり、機種によっては「内釜3年保証」や「5年保証」(※モデルや購入条件によります)がついている場合があります。
保証期間が長いというのは、メーカーの自信の表れですよね。毎日のお手入れも、内ぶたが凹凸の少ない「ワンタッチふた加熱板」だったりと、清潔さを保ちやすい工夫がされているのも嬉しいポイントです。
もちろん、ご飯の味は「おどり炊き」の名前の通り、一粒一粒がしっかりしていて甘みとハリがあると店頭でもとても人気がありますよ。
どの炊飯器がご自身のライフスタイルに合うか、ぜひ想像しながら選んでみてくださいね。
総括:炊飯器の寿命は何年か
それでは最後に、この記事の内容をまとめます。




