毎日の食卓に欠かせないお米選びで、玄米と白米の値段はどちらが安いのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
スーパーで買い物をしていると、玄米の方が高く見えることもあれば、時には白米の方が高い場合もあって、どちらを選べばお得なのか迷ってしまいますよね。
実は2025年現在、お米の相場は大きく変動しており、従来の常識とは異なる価格傾向が見られるようになっています。さらに、保冷庫での保存方法や日持ちの違い、玄米を安く購入できる場所についても知っておくと、より賢いお米選びができるでしょう。
また、自宅で精米するメリットを活用すれば、さらなる節約効果も期待できます。
この記事では、玄米と白米の価格比較から栄養価の違い、お得な購入方法、保存のコツまで、お米選びに役立つ情報を詳しくご紹介します。
玄米と白米の値段はどっちが安い?その違いについて
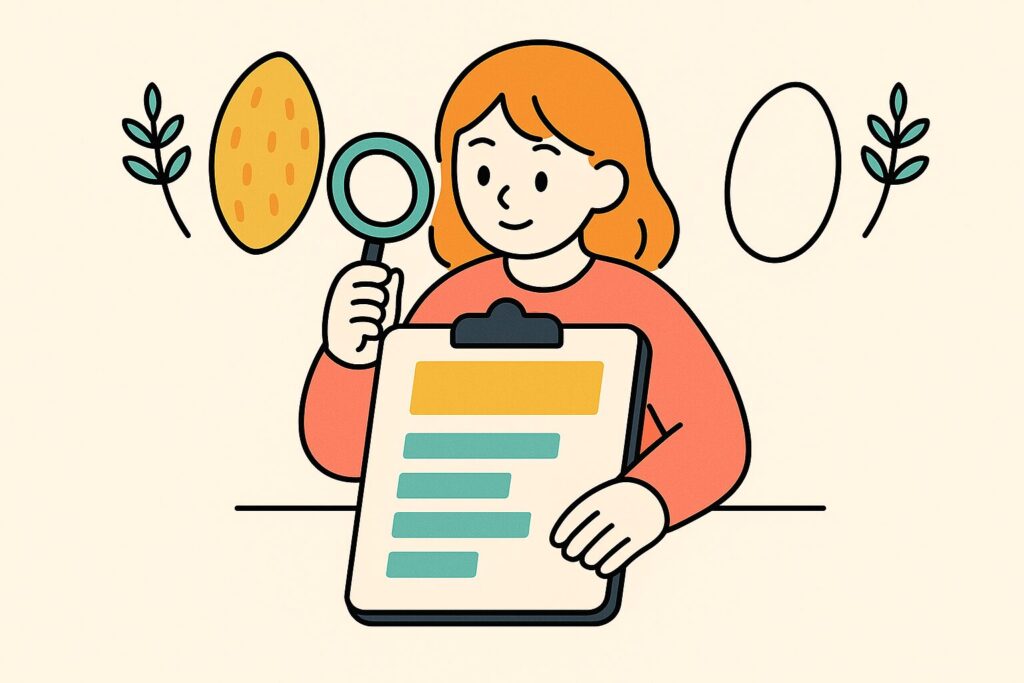
玄米と白米の価格について詳しく見ていく前に、まず基本的な相場感を把握しておくことが大切です。
2025年現在のお米市場は従来とは異なる動きを見せており、単純に「玄米の方が高い」とは言い切れない状況になっています。栄養価や保存期間の違いも含めて、総合的に判断していきましょう。
玄米の相場と高くなる原因
玄米の値段は1キロあたり400〜600円程度が相場となっています。白米と比較すると、一般的に100〜200円ほど高い価格設定になっているんです。
ただし、最近では市場の状況が変化してきており、2025年4月時点では玄米の方が安くなるケースも見られるようになりました。コシヒカリであれば、玄米と白米の価格差が100〜500円程度開く場合もあるのですが、玄米の方が安く購入できる傾向が強まっています。
玄米が高くなる主な原因として、まず手間の問題が挙げられます。
玄米を食べられる状態にするためには、不純物の選別作業が必要になるんですね。モミ殻や小石などを丁寧に取り除く工程が必要で、この手間が価格に反映されています。
また、需要と供給のバランスも価格に大きく影響しています。
玄米は白米に比べて需要が少ないため、生産量も限られており、採算を取るために価格を上げざるを得ない事情があります。
さらに、栽培方法によっても価格は大きく変わります。
有機栽培や無農薬栽培で育てられた玄米は、通常の栽培方法よりもはるかに高価になる傾向があるんです。
私も店頭で、炊飯器を選ぶお客様からよく「玄米の値段が気になる」という相談を受けますが、栽培方法の違いは本当に価格に大きく影響しますね。
品種による価格差も無視できません。
山形県産のつや姫のような人気品種は、豊かな風味と濃厚な甘みが特徴的である一方、知名度と人気の高さから値段はやや高価になっています。
白米の相場と高くなる原因
以前は、白米の値段は1キロあたり300〜500円程度が一般的な相場となっていました。
ただし、2025年現在は「令和の米騒動」とも呼ばれるほど価格が高騰している状況なんです。
コシヒカリの場合、5キロあたり4,000〜5,000円ほどが相場となっており、1キロあたりでは800〜1,000円という価格帯になります。
一方、ヒノヒカリは比較的お得な選択肢として注目されています。
30キロあたり15,000〜16,000円と、相場よりもやや安めの値段になっているんですね。安くて美味しいお米を探している方には特におすすめの銘柄だと思います。
白米が高くなる主な原因として、まず供給不足の問題があります。
農林水産省のデータによると、2024年度の主食用米の作付面積は前年比で約1万ヘクタール減少しており、その影響で店頭価格も上昇傾向にあります。
人気品種の価格上昇も顕著で、コシヒカリやつや姫では1キロあたりの価格が昨年比で約20円以上高騰した例も報告されているほどです。
ブランド力や品質の違いも価格に大きく影響します。
新米や特定の産地で作られたお米は、どうしても価格が高くなってしまいます。また、精米の度合いや品質管理の方法によっても、最終的な販売価格は変わってくるんです。
中間業者を通すことによるコスト増加も見逃せません。
農家から消費者の手に届くまでに、複数の業者を経由することで、それぞれの段階でマージンが上乗せされ、最終価格を押し上げる要因となっています。
栄養価で比較
玄米と白米の栄養価には圧倒的な差があります。
特に注目すべきは食物繊維の含有量で、玄米は白米の約6倍もの食物繊維を含んでいるんです。
ビタミン類についても、玄米の方が豊富に含まれています。ビタミンB1は白米の約5〜8倍、ビタミンB2も白米より多く摂取できます。
特に注目したいのは、白米には含まれていないビタミンEが玄米には豊富に含まれていることです。ビタミンEは約12倍もの差があり、活性酸素を抑える働きがあるため、細胞の酸化を防ぎ、肌の若々しさを保つ効果が期待できます。
ミネラル分でも玄米の優位性は明確です。
マグネシウムは玄米ごはん100gあたりに49mg含まれており、これは白米ごはんの約7倍に相当します。マグネシウムは骨や歯の形成に重要な役割を果たす栄養素なんですね。
カリウムとマンガンについても、玄米は白米の2倍以上の量が含まれています。
カリウムはナトリウムとバランスを取りながら細胞を保つ働きがあり、マンガンは酵素の活性化や骨の形成に関与しています。
しかし、玄米にも不足している栄養素があることは理解しておく必要があります。
ビタミンAやビタミンD、ビタミンK、ビタミンCなどは不足しているため、バランスの良い食事を心がけることが大切です。
カロリーについては、実は玄米と白米でそれほど大きな違いはありません。
食べ過ぎれば玄米でも肥満になる可能性があるため、成人男性は200g、成人女性は150gを目安として摂取することをおすすめします。
どちらが日持ちする?

保存期間の面では、玄米の方が白米よりも長持ちするという特徴があります。
この理由は、お米の構造にあります。
白米は精米によって中身の部分が直接空気に触れてしまうため、酸化が進みやすくなります。一方、玄米は糠(ぬか)層に守られているため、劣化の進行が緩やかなんですね。
具体的な保存期間の目安として、白米は精米後2週間から1ヶ月以内での消費が推奨されています。
季節によっても違いがあり、春夏は精米後2週間から1ヶ月、秋冬は1〜2ヶ月程度が美味しく食べられる期間とされています。
対して玄米は3ヶ月程度が基本的な保存期間の目安ですが、保存環境が良ければ半年程度は品質を保ちやすくなります。
ただし、玄米も決して劣化しないわけではありません。
糠に含まれる油分が酸化していくため、時間が経てば確実に劣化は進行します。特に温度が高くなると劣化が急速に早まるため、保存環境には注意が必要です。
お米には賞味期限の表示義務がないため、基本的には賞味期限は記載されていません。
これは野菜や果物と同様に農産物として扱われているためですが、保存方法によって賞味期限が著しく変わってしまうことも理由の一つです。
保存の際に最も気をつけたいのは、高温多湿によるカビや虫の発生です。特に玄米は白米よりも油分が多く含まれているため、適切な保存が必要になります。
保冷庫による保存

玄米と白米の保存において、冷蔵庫での保存は非常に効果的な方法です。特に玄米の場合、冷蔵保存が強く推奨されているんです。
玄米は白米よりも油分が多く含まれており、高温多湿で酸化しやすく、カビや虫が発生しやすいという特徴があります。そのため、気温が20℃以上になる季節は冷蔵庫の野菜室での保存が理想的とされています。
保存容器についても重要なポイントがあります。
米袋のまま放置すると、袋の表面に開いた小さな穴から湿気が入ってしまい、カビや虫の発生リスクが高まります。密閉性の高いプラスチック容器やガラス瓶、チャック付きの厚手保存袋に入れ替えることが大切です。
私も店頭でお客様に炊飯器をご案内する際、保存方法についてよく質問を受けるのですが、ペットボトルなどの少量ずつ取り出せる容器がおすすめだとお伝えしています。
計量カップに出すのが簡単なだけでなく、冷蔵庫や野菜室の隙間でも収納しやすいからです。
冷蔵保存のメリットは温度と湿度の安定化にあります。
冷蔵庫内では湿度の心配はそれほどありませんが、乾燥しすぎてしまう可能性もあるため、密閉容器の使用は水分の蒸発を防ぐ役割も果たします。
白米の場合も、夏場などの高温期には冷蔵保存が選択肢に入ります。
精米後は劣化が進みやすいため、特に開封後は密閉容器に移し、冷蔵庫で保存することで品質を維持しやすくなります。
常温で保存する場合は、15℃以下の涼しい場所を選ぶことが重要です。直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。ただし、これでも冷蔵保存と比べると劣化は早くなってしまいます。
真空パックや密閉容器を使用した冷蔵保存では、1年以上鮮度を維持することも可能ですが、2ヶ月を超えるとお米内部の乾燥も進むため、美味しく食べたいなら2ヶ月以内の消費を心がけることをおすすめします。
玄米と白米の値段はどっちが安い?自宅で精米という選択

玄米を購入して自宅で精米するという選択肢は、コストパフォーマンスを考える上で非常に有効な方法です。
初期投資は必要になりますが、長期的に見ると大きな節約効果が期待できるだけでなく、いつでも新鮮なお米を味わえるというメリットもあります。
玄米を安く買えるのはどこ?
玄米を安く購入したいなら、まとめ買いが効果的な方法の一つです。
5kgより10kg、30kg、60kgと、多く買うほど1kgあたりの金額が安くなるという特徴があります。
実際の価格比較を見てみると、玄米の方が安く購入できる場合が多いんです。少量購入では玄米の方が高くなりがちですが、まとめ買いすることで価格のメリットを享受できるんですね。
ネット通販の活用も非常におすすめです。
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのサイト経由で購入すると、ポイント還元や送料込みの最安値を選択できるため、かなりお得感があります。特にセールに合わせて購入することで、安く購入できるだけでなくポイントも付与されます。
農家直送のルートも注目すべき選択肢です。中間業者を通さないことで、10〜30%ほど安く購入できるケースがあります。
農協の直販所や農家のSNS販売、業務用米問屋の個人向けルートなど、一般にはあまり知られていない穴場ルートも存在します。これらのルートでは、精米済みなのに玄米並みの価格で購入できる無名ブランド米や、JAS認証付き有機栽培米なども見つけることができます。
ふるさと納税を活用するのも賢い方法です。
実質負担2,000円で全国各地の名産品として玄米を受け取ることができ、還元率の高さと量の多さに加え、産地や品種を自由に選べるメリットがあります。
ただし、まとめ買いには注意点もあります。
理想は1ヶ月を目安に食べきれる量を購入することですが、大容量で安く購入できても食べきれなければ結果的に無駄になってしまいます。保存環境と消費計画をしっかり立ててから購入することが大切です。
玄米と白米を混ぜるのはアリ?

玄米と白米を混ぜて炊くことは、玄米初心者にとって非常に有効なアプローチです。玄米のしっかりとした食感が苦手という方には、特におすすめの方法だと思います。
混合比率については、最初は白米の割合を多めにして、徐々に玄米の比率を上げていくのが良いでしょう。例えば、白米7:玄米3から始めて、慣れてきたら白米5:玄米5、最終的には白米3:玄米7といったように段階的に調整していけます。
炊き方にはコツがあります。
玄米は白米よりも水を多く必要とし、浸水時間も長く取る必要があるため、混ぜて炊く場合は玄米に合わせた水加減と浸水時間を設定することが重要です。玄米の水加減は1.77倍、白米は1.42倍が基本ですが、混合する場合は玄米寄りの水加減にするのがポイントです。
また、玄米の硬さが気になる場合は、低アミロース米の玄米を選ぶという方法もあります。
低アミロース米はもちもちとした食感と強い甘みが特徴で、糠層に覆われていてもその特徴をしっかりと感じることができます。
分づき米という選択肢も考えてみてください。
3分づき米は玄米に近い状態ながら玄米よりは食べやすく、5分づき米は玄米と白米の中間で胚乳がほぼ残っています。7分づき米は少し硬めの白米といった印象で、ほぼ食味は白米と変わりません。
酵素玄米(寝かせ玄米)という方法もあります。
玄米を小豆と塩と一緒に炊き、3〜4日程度保温して熟成させることで、通常の玄米よりもギャバなどの栄養素がアップし、もちもちした食感で食べやすくなります。
混ぜて炊く際の注意点として、炊飯器によっては玄米専用の設定がない場合があります。その場合は玄米モードがある炊飯器の使用を検討するか、水加減と炊飯時間を手動で調整する必要があります。
玄米を精米する方法
- 初期費用がかからない
- 100〜200円で10kg精米可能
- 業務用レベルの高品質仕上がり
- 立地に制約があり移動が必要
- 重い玄米の持ち運びが大変
- 夜間利用は防犯面で不安
- 混雑時は待ち時間が発生
- 好きな時間に必要分だけ精米
- 精米度の細かな調整が可能
- 持ち運び不要で自宅で完結
- 毎日新鮮なお米が味わえる
- 1万円台の初期投資が必要
- 定期的な掃除とメンテナンス
- 動作音が気になる場合がある
- ぬかの処理が必要
玄米を精米する方法として、主にコイン精米機と家庭用精米機の2つの選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。
コイン精米機のメリットは、なんといっても初期費用がかからないことです。
100円から200円程度の料金で10キロ程度の玄米を精米できるため、たまにしか精米しない方にとっては経済的な選択肢と言えるでしょう。また、業務用レベルの高性能な機械を使用できるため、仕上がりの品質は非常に良好です。
一方、コイン精米機のデメリットとして、まず立地の問題があります。
近くにコイン精米機がない場合は、わざわざ遠くまで出向く必要があり、交通費や時間を考慮すると意外にコストがかかってしまいます。また、重い玄米を持参する必要があるため、特に女性や高齢者にとっては身体的負担が大きくなります。
さらに、営業時間の制約もあります。
多くのコイン精米機は24時間利用可能ですが、夜間の利用は防犯面で不安を感じる方も多いでしょう。混雑時には待ち時間が発生することもあり、思った時にすぐ精米できないケースもあります。
家庭用精米機のメリットは、何より利便性の高さです。
好きな時間に必要な分だけ精米できるため、毎日精米したばかりの新鮮な米でご飯を炊くことができます。重い玄米を持ち運ぶ必要もなく、自宅で手軽に作業が完了します。
また、精米度の細かな調整が可能な点も大きな魅力です。
白米、無洗米、7分づき、5分づき、3分づきなど、その日の気分や料理に合わせて自由に調整できます。米の種類や産地に応じて最適な精米を行う機能を搭載したモデルもあり、こだわりの味を追求できるんですね。
一方、家庭用精米機のデメリットとして初期投資が必要になります。
1万円台から購入可能とはいえ、コイン精米機と比較すると最初にまとまった費用がかかります。また、定期的なメンテナンスや掃除が必要で、使用後には削り取った「ぬか」が大量に出るため、これを放置しておくと虫がつく可能性があります。
動作音の問題も考慮する必要があります。
集合住宅や小さな子供がいる家庭では、精米機の動作音が気になる場合があります。圧力式は比較的静かですが、かくはん式は動作音が大きめになる傾向があるため、購入前に確認することをおすすめします。
私も家電量販店で精米機について相談を受けることがありますが、使用頻度が週に2回以上であれば家庭用精米機の方がお得になるケースが多いとお伝えしています。
毎日のように精米するなら、間違いなく家庭用精米機が便利だと思います。
自宅で精米するメリット

自宅で精米する最大のメリットは、毎日精米したばかりの新鮮な米でご飯を炊けることです。精米直後から米の酸化は進行するため、精米したてのお米の美味しさは格別なんですね。
経済的なメリットも見逃せません。
玄米で購入して自宅で精米することで、白米を購入するよりもコストを抑えることができる場合があります。特に大容量でまとめ買いした玄米を必要な分だけ精米すれば、食費の節約にもつながります。
保存期間の長さも大きな利点です。
先ほどもお伝えしたように、玄米は白米よりも長期保存が可能なため、まとめ買いしても安心です。必要な時に必要な分だけ精米すれば、いつでも新鮮な白米を味わうことができます。
精米度の自由な調整も魅力的です。
その日の気分や料理に合わせて、白米、7分づき、5分づき、3分づきなど、好みの精米度を選ぶことができます。栄養価と食べやすさのバランスを自分で調整できるのは、家庭用精米機ならではのメリットです。
また、表面が酸化してしまった白米を再精米する機能を持つ機種もあります。
古くなってしまった白米でも、表面を軽く削ることで味や香りを蘇らせることができるため、無駄を減らすことにもつながります。
家族構成や食べる頻度に合わせて、精米量を調整できることも便利です。
一人暮らしなら2合程度、家族なら5合以上と、必要な分だけ精米すれば食材の無駄を最小限に抑えることができます。
2025年現在の米不足や価格高騰の状況を考えると、自宅で精米できる環境を整えておくことは、食料安全保障の観点からも意味があると思います。市場の変動に左右されにくい食生活を維持できるのは心強いですね。
おすすめの家庭用精米機
家庭用精米機を選ぶ際は、まず精米容量を確認することが大切です。一人暮らしなら2合程度、家族なら5合以上の容量が適していますが、使用頻度も考慮して選びましょう。
タイガーの「RSF-A100」は、1〜5合用の無洗米機能付き精米器として人気があります。
DCモーターを採用することでお米への負荷を軽減しながら上質な精米ができ、変速かくはん式でお米が割れにくい設計になっています。やわらか玄米コースでは玄米の栄養価を残しつつ、食べやすいごはんが炊けるのが嬉しいポイントです。
アイリスオーヤマの精米機は、40種類の米の銘柄に対応している点が特徴的です。銘柄にこだわってお米を選んでいる方には特におすすめで、それぞれの銘柄に最適化された精米が可能になります。
ツインバードの製品は、静音性に配慮されたモデルが多く、集合住宅や小さな子供がいる家庭でも安心して使用できます。運転中の音や振動が気になる方には特に適していると思います。
精米方式による選び方も重要です。
圧力式や圧力循環式は比較的静かな傾向があり、早朝や夜間でも周囲に迷惑をかけにくいでしょう。一方、かくはん式は価格が手頃な反面、動作音が大きめになる傾向があります。
お手入れのしやすさも選択の重要な基準です。
一体型のぬかボックスを採用しているモデルなら、こぼれたぬかを掃除する手間も省けます。分解して洗えるモデルであれば、より細かくお手入れができて衛生的です。
私が店頭で相談を受ける際に、使用頻度と家族構成を最初に確認するようにしています。
毎日使用するなら耐久性の高いモデルを、週に1〜2回程度なら比較的安価なモデルでも十分対応できるからです。
価格帯は1万円台から購入可能で、機能や容量によって幅があります。
高機能モデルでは米の種類や産地に応じて最適な精米を行う機能を搭載したものもあり、こだわりの味を追求したい方にはこうした機種も検討する価値があるでしょう。
総括:玄米と白米の値段はどっちが安い?
それでは最後に、この記事の内容をまとめます。



