キッチンから出る生ゴミの処理に頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか?
特に夏場は臭いも気になりますし、コバエの発生も心配になります。
そんな悩みを解決してくれるのが生ゴミ処理機ですが、最近注目されているのがハイブリッド式というタイプです。
ハイブリッド式の生ゴミ処理機は、従来のバイオ式と乾燥式の良い部分を組み合わせた新しいタイプで、室内でも使えて臭いも抑えられると評判です。ただし、価格が高めというデメリットもあり、購入を迷っている方も多いかもしれません。
実は多くの自治体では生ゴミ処理機の購入に対して助成金制度を設けており、初期費用の負担を軽減できる可能性があります。また、電気を使わないコンポスト式と比較して、ハイブリッド式にはどのような特徴があるのか、気になる方も多いでしょう。
この記事では、ハイブリッド式生ゴミ処理機の仕組みから、実際の電気代、メリット・デメリット、人気メーカーまで詳しく解説していきます。
おすすめハイブリッド式生ゴミ処理機|基礎知識

ハイブリッド式は生ゴミ処理機の中でも比較的新しいタイプで、その名の通り複数の処理方式を組み合わせた製品です。
ここでは、ハイブリッド式の基本的な仕組みから、電気代、脱臭システム、静音性まで、購入前に知っておきたい基礎知識をご紹介します。
ハイブリッド式の生ゴミ処理機とは
ハイブリッド式の生ゴミ処理機は、乾燥式とバイオ式を掛け合わせた処理方式を採用しています。
処理機の内部には微生物が入っており、温風による乾燥と微生物による分解を同時に行うことで、効率的に生ゴミを処理します。熱を加えることで微生物の働きが活性化し、分解力が向上すると同時に、臭いの発生も抑えられる仕組みになっています。
生ゴミは水と二酸化炭素に分解されるため、乾燥式のように処理後すぐに中身を取り出す必要がありません。半年から1年に1度程度、中身が増えてきたタイミングで取り出せば、そのまま堆肥として利用できます。
使い方もシンプルで、蓋を開けて生ゴミを入れるだけです。微生物が24時間働いて分解してくれるので、生ゴミが出るたびに処理機に投入できます。
バイオ式と乾燥式の良いとこ取り
ハイブリッド式は、バイオ式と乾燥式それぞれのメリットを併せ持っています。
バイオ式の良い点である「堆肥として再利用できる」という特徴と、乾燥式の「室内で使える」「処理が早い」という利点を両立させているのが大きな特徴です。
従来のバイオ式は主に屋外設置が前提でしたが、ハイブリッド式は臭いを抑える技術により室内設置が可能になりました。また、乾燥式では処理後の生ゴミは燃えるゴミとして捨てる必要がありましたが、ハイブリッド式なら有機肥料として活用できます。
処理時間についても、純粋なバイオ式では堆肥化まで2週間から1ヶ月程度かかることもありますが、ハイブリッド式なら24時間後にはほとんどの生ゴミが分解されます。
電気代は本当に安いのか

ハイブリッド式の電気代は、1時間あたり約1.62円という試算があります。
24時間稼働させた場合でも1日あたり約38.88円となり、月額では1,200円程度の電気代がかかる計算です。これは乾燥式の1回あたり30〜37円と比較すると、使用頻度によってはハイブリッド式の方が電気代を抑えられる可能性があります。
消費電力は一般的に52W程度で、これは乾燥式の約3分の1、従来のバイオ式の約2分の1という省エネ設計になっています。熱を加えて乾燥処理を行う乾燥式と比べ、熱とバイオの力を組み合わせることで、効率的な処理を実現しています。
ただし、24時間稼働が基本となるため、使用頻度が少ない家庭では乾燥式の方が電気代を抑えられる場合もあります。家族の人数や生ゴミの量に応じて、どちらがお得かを検討することが大切です。
強力脱臭システムの仕組み
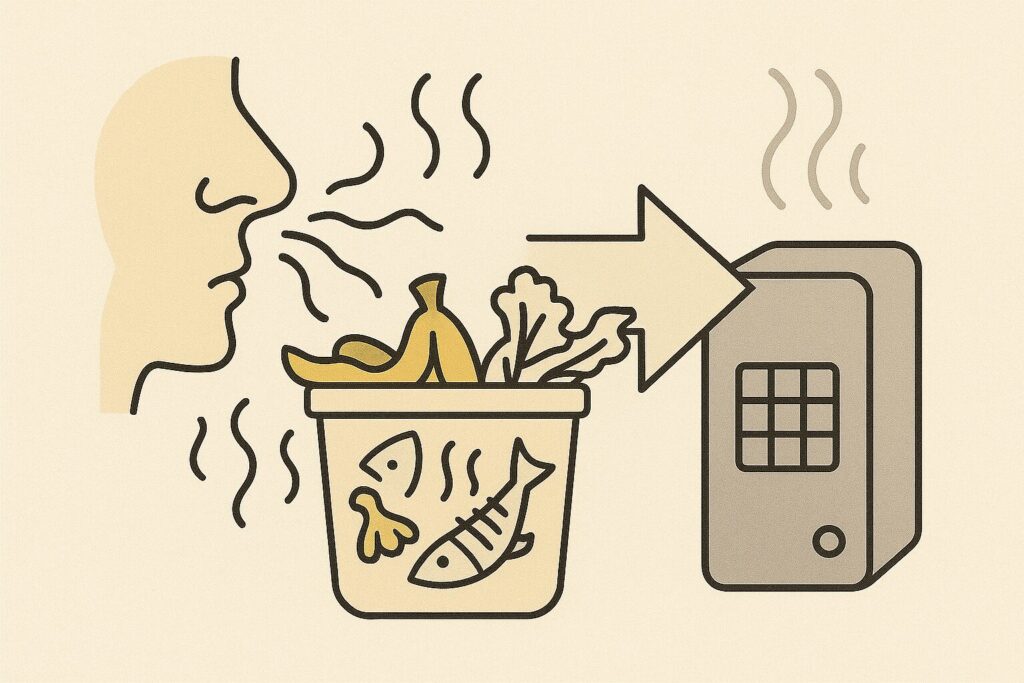
ハイブリッド式生ゴミ処理機の大きな特徴の一つが、強力な脱臭システムです。
多くの製品では3層から4層の脱臭システムを採用しており、段階的に臭いを除去していきます。例えば、脱臭効果のある専用バイオフレーク、高濃度イオン酸化触媒、活性炭フィルター、UV-C脱臭装置などを組み合わせることで、99.8%以上の悪臭成分を除去できるとされています。
具体的な脱臭プロセスは、まずUVランプの紫外線で殺菌とオゾンによる悪臭粒子の除去を行い、次にセラミックボールで臭いを吸着、最後にカートリッジの加熱で水分を気化させるという流れになっています。
これらの技術により、従来のバイオ式で問題となっていた発酵臭を大幅に軽減し、室内設置を可能にしています。自動消臭装置を内蔵しているため、排気管なども不要です。
室内でも置ける静音設計
ハイブリッド式の運転音は25db以下と、冷蔵庫よりも静かな設計になっています。
乾燥式の生ゴミ処理機は熱を加えて処理を行うため、処理中のモーター音が大きくなりがちですが、ハイブリッド式は内部の攪拌がゆっくりと回転し、バイオの力で処理を行うため、処理音を最小限に抑えることができます。
25dbという音量は、図書館内の環境音(約40db)よりも静かなレベルで、深夜でも気にならない程度の音です。マンションやアパートなどの集合住宅でも、隣室への影響を心配する必要がありません。
この静音性により、キッチンやリビングなど、生活空間に設置しても快適に使用できます。24時間稼働が基本となるハイブリッド式にとって、静音設計は重要な要素となっています。
おすすめハイブリッド式生ゴミ処理機|導入ガイド
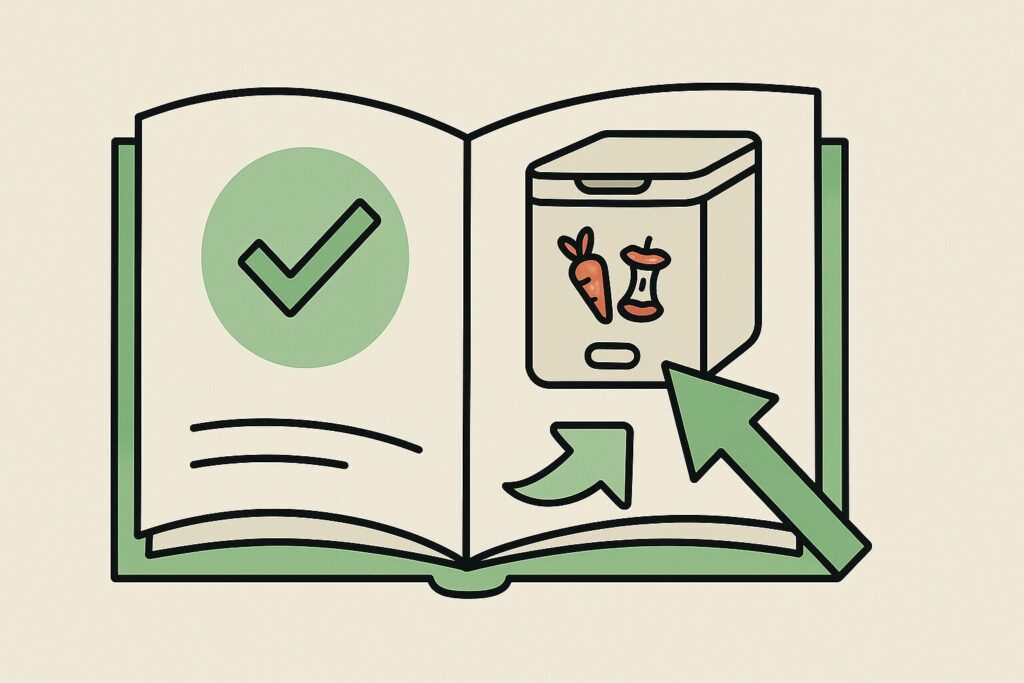
ハイブリッド式生ゴミ処理機の購入を検討する際は、価格や助成金制度、デメリットなど、さまざまな要素を考慮する必要があります。
ここでは、実際の導入に向けて知っておきたい情報を詳しく解説していきます。
価格相場と助成金について
ハイブリッド式生ゴミ処理機の価格相場は、おおよそ10万円を超える設定となっています。
これは乾燥式やバイオ式と比較して高価格帯に位置しますが、両方の技術を組み合わせた高機能製品であることを考えると、妥当な価格設定といえるでしょう。初期投資は高くなりますが、バイオチップの交換が不要なため、長期的なランニングコストは抑えられます。
多くの自治体では、生ゴミ処理機の購入に対して助成金制度を設けています。助成金額は自治体により異なりますが、購入費用の2分の1から3分の1程度、上限2万円から5万円程度が一般的です。
助成金の申請には、購入前の事前申請が必要な自治体と、購入後の申請でも可能な自治体があります。お住まいの地域の制度を確認し、条件に合わせて手続きを進めることで、初期費用の負担を大幅に軽減できます。
デメリットと注意点
ハイブリッド式生ゴミ処理機にもいくつかのデメリットがあります。
最大のデメリットは価格の高さです。10万円を超える初期投資は、多くの家庭にとって大きな負担となるでしょう。また、サイズも比較的大きめで、ワンルームマンションなど限られたスペースでは設置が難しい場合があります。
24時間稼働が基本となるため、月額1,200円程度の電気代が継続的にかかることも考慮する必要があります。使用頻度が少ない家庭では、かえってコストパフォーマンスが悪くなる可能性もあります。
処理できないものもあり、硬い骨や貝殻、割り箸などの木片、ビニールやプラスチックは投入できません。これらを誤って入れると故障の原因になるため、分別には注意が必要です。
電気を使わない処理機との比較
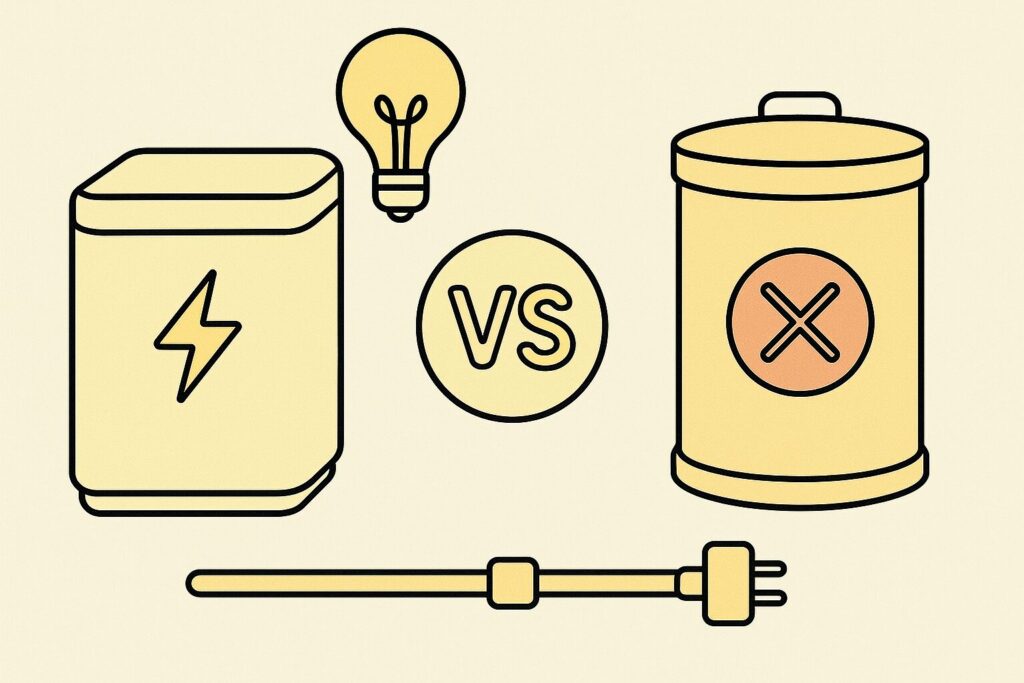
電気を使わないコンポスト式と比較すると、ハイブリッド式にはメリットとデメリットの両方があります。
コンポスト式は電気代が0円で環境に優しく、初期費用も数千円から数万円と安価です。しかし、手動でかき混ぜる必要があり、堆肥化まで時間がかかること、臭いの問題から主に屋外設置となることがデメリットです。
一方、ハイブリッド式は自動で処理してくれるため手間がかからず、臭いも抑えられるため室内設置が可能です。処理時間も早く、24時間後にはほとんどの生ゴミが分解されます。
家庭菜園を楽しんでいて、時間に余裕がある方にはコンポスト式が向いていますが、忙しい現代人や集合住宅にお住まいの方には、ハイブリッド式の方が使いやすいでしょう。
おすすめメーカーと人気商品
ハイブリッド式生ゴミ処理機の主要メーカーと、それぞれのおすすめ人気商品をご紹介します。
ナクスル(NAXLU)は、ハイブリッド式生ゴミ処理機の分野でよく知られるメーカーです。
独自の強力な脱臭技術により、気になる生ゴミの臭いを99.8%もカットすると評価されています。そのため、キッチンなど室内に置いても快適に使用できる点が魅力です。
リエンクル(Reencle)の「Reencle Prime」モデルは、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
この機種は、4層からなる高度な消臭システムに加え、運転音が25db以下という優れた静音設計が特徴です。消費電力も52Wと省エネに配慮されており、月々の電気代を抑えたい方には嬉しいポイントとなるでしょう。
取り出した肥料の活用方法

ハイブリッド式生ゴミ処理機で作られた堆肥は、優良な有機肥料として活用できます。
処理機から取り出した堆肥は、そのまま家庭菜園の土に混ぜ込むことができます。野菜や花の栽培に適しており、化学肥料と比べて土壌改良効果も期待できます。取り出す頻度は半年から1年に1度程度で、手間もかかりません。
堆肥として使用する際は、新鮮な状態よりも1〜2週間程度寝かせてから使用すると、より効果的です。プランターでの使用なら、土と1対3程度の割合で混ぜるのがおすすめです。
家庭菜園をしていない場合でも、観葉植物の肥料として使用したり、近所の菜園愛好家に分けてあげたりすることもできます。ゴミとして捨てていた生ゴミが資源として活用できるのは、環境にも優しい選択といえるでしょう。
総括:おすすめハイブリッド式生ゴミ処理機
それでは最後に、この記事の内容をまとめます。



