「床のベタベタが気になるけど、赤ちゃんやペットがいるから強い洗剤は使いたくないなぁ」なんて悩んでいませんか?
ナチュラルクリーニングの代表格である重曹とクエン酸ですが、いざ床掃除に使おうとすると「結局、床掃除は重曹とクエン酸どっちを使えばいいの?」と迷ってしまうこと、ありますよね。
私も店頭でお客様から「ネットで見たけど、どっちが正解か分からなくて」と相談されることが本当に多いんです。実はこれ、汚れの種類や床の材質によって正解が全く違うんですよ。
間違った使い方をすると、せっかくのフローリングが白く変色したり、ワックスが剥げてしまったりする大惨事になりかねません。逆に言えば、正しい使い分けさえマスターすれば、素足で歩いてもサラッサラの気持ちいい床が手に入ります。
この記事では、家電量販店で働く私の視点から、化学的な汚れ落ちの仕組みと、床材を傷めないための鉄則を分かりやすく解説します。さらに、毎日の拭き掃除が劇的に楽になる最新の清掃家電もこっそり教えちゃいますね。
「えっ、こんなに楽になるの?」と驚くような情報も満載ですので、ぜひ最後までお付き合いください。
- 皮脂汚れには重曹で水垢にはクエン酸
- 二つを混ぜると洗浄効果がなくなる
- 無垢材フローリングへの使用はNG
- 最新家電で拭き掃除の手間が激減
床掃除は重曹とクエン酸どっちを使うべきか解説
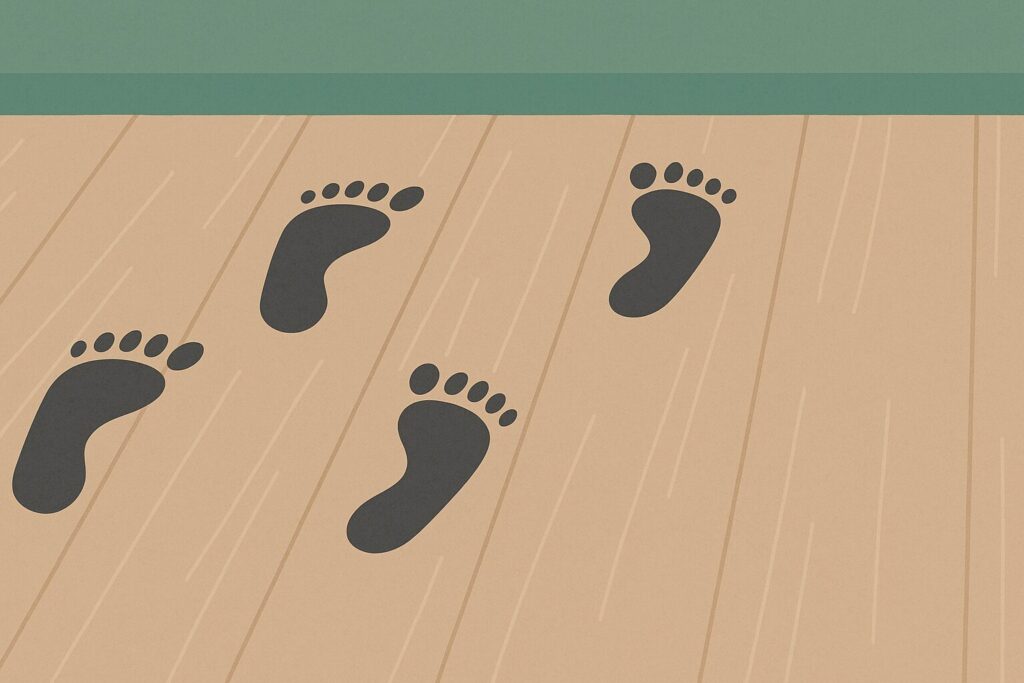
「結局のところ、うちの床にはどっちを使えばいいの?」という疑問、ここですっきり解決しちゃいましょう。
実はこれ、どっちが優れているかという話ではなく、敵(汚れ)の正体を知って武器(洗剤)を選ぶパズルみたいなものなんです。
ここでは、それぞれの得意分野と絶対にやってはいけない組み合わせについて、詳しくお話ししますね。
重曹とクエン酸とセスキの使い分け早見表
まず結論から言っちゃいますね。
床のベタベタ汚れの正体である「皮脂」や「油」には、弱アルカリ性の「重曹」や「セスキ炭酸ソーダ」が正解です。一方で、トイレ周りのアンモニア臭や、水回りの白っぽい水垢汚れには、酸性の「クエン酸」が効果を発揮します。
お店でお客様とお話ししていると、「重曹は万能だから何にでも使える」と思っている方が意外と多いんですが、実はこれ、半分正解で半分間違いなんです。
汚れの性質と逆の性質(pH)を持つ洗剤をぶつけることで中和・分解するのが掃除の基本ルール。だから、酸性の汚れ(皮脂)にはアルカリ性、アルカリ性の汚れ(水垢・アンモニア)には酸性が効くんですよ。
分かりやすく表にまとめてみたので、まずはこれを見てイメージを掴んでくださいね。
| 洗剤の種類 | 液性(pH) | 得意な汚れ | 床掃除での役割 |
|---|---|---|---|
| 重曹 | 弱アルカリ性(pH8.2) | 皮脂、油汚れ、手垢 | リビングのベタつき解消、研磨作用 |
| セスキ炭酸ソーダ | 弱アルカリ性(pH9.8) | 頑固な油汚れ、血液 | 重曹より強力な油汚れ分解、水に溶けやすい |
| クエン酸 | 酸性(pH2.0〜3.0) | 水垢、アンモニア臭、石鹸カス | トイレ床の消臭、重曹拭き後の仕上げ(中和) |
この表を見ると一目瞭然ですよね。
リビングの床掃除には基本的に「重曹」や「セスキ」を使い、クエン酸は「仕上げ」や「トイレ」で使うというのがセオリーなんです。
特にセスキは水に溶けやすくて使いやすいので、私も個人的には重曹よりセスキ推しかも(笑)
セスキとアルカリ電解水の違いって?
最近よく聞く「アルカリ電解水(激落ちくんなど)」は、セスキよりもさらにアルカリ度が強い(pH12〜13)強力な洗浄水です。汚れ落ちは抜群ですが、フローリングのワックスを溶かしてしまうリスクも高いので、使うときは要注意ですよ!
重曹とクエン酸を混ぜるのは効果がない理由
これ、本当によく聞かれるんです。
「重曹とクエン酸を混ぜるとシュワシュワして汚れがすごく落ちそう!」って。
確かにあの発泡を見ると、なんだか効きそうな気がしちゃいますよね。でも残念ながら床掃除においては「混ぜちゃダメ」というか「意味がない」のが真実なんです。
化学のお話になっちゃいますが、アルカリ性の重曹と酸性のクエン酸を混ぜると、「中和反応」が起きます。あのシュワシュワの正体は、ただの二酸化炭素(炭酸ガス)の泡。反応が終わった後に残るのは、中性の「クエン酸ナトリウム」と水だけなんです。
つまり、お互いの洗浄パワー(アルカリパワーと酸性パワー)を打ち消し合ってしまうんですね。
排水溝のぬめり取りなどでは、あの発泡の物理的な力で汚れを浮かすこともありますが、床の拭き掃除でそれをやっても、ただの「汚れ落ちの悪い水」で拭いているのと同じことになりかねません。
「混ぜるな危険」ではないですが、「混ぜたら無意味」と覚えておいてくださいね。
絶対にやってはいけない「混ぜる」
クエン酸などの酸性タイプと、カビキラーなどの「塩素系漂白剤」を混ぜるのは絶対にNGです!有毒な塩素ガスが発生して命に関わります。お風呂掃除のついでに脱衣所の床を掃除する時なんかは、うっかり併用しないように気をつけてくださいね。実際に、家庭内の清掃中に塩素系洗剤と酸性洗剤を一緒に使ってガスが発生した事例については、洗剤事故をまとめた自治体の資料でも「塩素系洗剤と酸性洗剤を一緒に使うと有毒なガスが発生する」とはっきり注意喚起されています。
(出典:東京消防庁「身近にある洗剤の事故に注意!」)
床掃除に効果的な重曹スプレーの作り方
さて、重曹が皮脂汚れに効くと分かったところで、実際に使うための「重曹スプレー」の作り方をご紹介します。
「粉のまま撒くの?」と聞かれることもありますが、床掃除では水に溶かしてスプレーにするのが基本です。粉のままだとザラザラして床を傷つける原因になりますからね。
作り方はとってもシンプルです。
- ぬるま湯(約40℃):100ml
- 重曹:小さじ1杯
- スプレーボトル
ポイントは「ぬるま湯」を使うこと!
水だと重曹は溶けにくくて、底に粉が溜まっちゃうんです。
これをお湯でしっかり溶かすことで、スプレーのノズルが詰まるのも防げますし、温かい方が皮脂汚れも緩んで落ちやすくなります。一石二鳥ですよね。
使い方は、汚れている箇所にシュッと吹きかけて、雑巾やフロアワイパーで拭き取るだけ。
でも、ここで一つ注意点があります。
重曹水は作り置きができません。時間が経つと効果が薄れたり、水が腐ったりするので、その日に使い切れる分だけ作るのがコツです。余ったら排水溝に流して、消臭効果を期待しちゃいましょう(笑)
私の裏技テクニック
スプレーを作るのが面倒な時は、「クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ストロング」のような、最初から洗浄成分が含まれているシートを使うのも賢い選択ですよ。忙しい平日はシート、週末は重曹水、と使い分けるのもおすすめです。
クエン酸や重曹の床掃除はベタベタする?

「重曹で拭いたら、なんだか床がザラザラする…」「白く跡が残っちゃった」という失敗談、実は結構多いんです。これ、原因は「重曹の濃度が濃すぎる」か「拭き取りが不十分」かのどちらかです。
重曹は乾くと白い結晶に戻る性質があります。これが「白残り」や「ザラザラ」の正体。
これを防ぐためには、先ほど紹介した濃度(水100mlに小さじ1)をしっかり守ることと、重曹水で拭いた後に必ず「水拭き(清め拭き)」をすることが大切です。
そして、ここで登場するのが「クエン酸」のリンス効果なんです!
シャンプーの後にリンスをするように、重曹(アルカリ性)で拭いた後に、薄いクエン酸水(水100mlに小さじ1/2程度)で仕上げ拭きをすると、残ったアルカリ成分が中和されます。
こうすると、成分が残らず、床が本当に「サラッ」とした感触に仕上がるんですよ。まるで素肌のような触り心地になるので、この「中和仕上げ」はぜひ試してほしいテクニックです。
中性洗剤を使った床掃除の手順やベタつきを防ぐコツをもっと詳しく知りたい方は、ベタベタを防ぐ中性洗剤での床掃除の詳しいやり方も参考にしてみてください。
ベタベタの原因はワックスかも?
もし掃除してもベタベタが直らない場合は、汚れではなく「ワックスの劣化」かもしれません。古いワックスが溶けてネチャついている場合は、掃除では解決しないので「ワックス剥離」という作業が必要になります。
重曹でフローリングの黒ずみを除去する方法
フローリングの黒ずみって、見た目も悪いし気になりますよね。
この黒ずみの正体、実は「皮脂汚れが積み重なって酸化したもの」か「カビ」、あるいは「ワックスに汚れが入り込んだもの」のどれかです。
足の裏の皮脂が原因の黒ずみなら、重曹の出番です!
まず、掃除機で表面のホコリをしっかり吸い取ります(これ重要!)。
次に、先ほどの重曹スプレーを黒ずみに吹きかけ、5分ほど放置して汚れを浮かせます。
その後、雑巾で少し力を入れて拭き取ってみてください。軽い黒ずみなら、これで驚くほどキレイになりますよ。
もし、重曹でも落ちない場合は、汚れがワックスの層に入り込んでしまっている可能性大です。
こうなると、上からいくら拭いても落ちません。むしろ、ゴシゴシ擦りすぎてワックスを剥がしてしまうことも…。
そんな頑固な黒ずみには、リンレイ「オール床クリーナー」のような専用の洗剤を使うのが一番の近道です。無理に家にあるものでなんとかしようとせず、専用品に頼るのもフローリングを長持ちさせる秘訣ですよ。
| 黒ずみのタイプ | 見分け方 | 対処法 |
|---|---|---|
| 皮脂汚れ | よく歩く場所にある | 重曹またはセスキで拭き取り |
| カビ | 観葉植物や窓際にある | 無水エタノールで拭く(塩素系はNG) |
| ワックス劣化 | 全体的に薄暗い、洗剤で落ちない | 専用剥離剤で古いワックスを除去 |
床掃除で重曹とクエン酸のどっちを使うか最終結論

ここまで読んでいただいて、汚れに合わせた使い分けについてはバッチリだと思います。でも、実は「洗剤選び」よりももっと大事なことがあるんです。
それは「床の材質」との相性。
ここを間違えると取り返しのつかないことになっちゃうかも…。
ここでは、絶対に知っておいてほしい注意点と、私が家電量販店で働いていて「これは革命だ!」と感じた最新のお掃除方法についてお話ししますね。
フローリングに使ってはいけない洗剤と注意点
一般的なフローリング(複合フローリング)は、表面が樹脂やワックスで保護されています。ここに相性の悪い洗剤を使うと、保護膜を溶かしてしまい、床の寿命を縮めてしまうんです。
特に注意が必要なのが、「アルカリ電解水」や「高濃度の重曹水」の放置です。
アルカリ性の成分には、ワックスの膜を分解する作用があります。スプレーしてすぐに拭き取れば問題ないことが多いですが、長時間放置したり、濃度が高すぎたりすると、ワックスが白く濁ったり(白化)、ボロボロと剥がれてきたりします。
私も昔、張り切って濃いめの重曹水をたっぷり撒いて放置したら、床がまだら模様になって泣きそうになった経験があります…(苦笑)
また、「塩素系漂白剤(ハイターなど)」もフローリングには絶対NG!
脱色作用があるので、木目が消えて真っ白になってしまいますよ。
床掃除には「中性洗剤(ウタマロクリーナーなど)」が一番リスクが低くて安全、というのは間違いありません。
水分は大敵!
フローリングの継ぎ目から水が入ると、中の木材が膨らんで表面が波打ったり剥がれたりします。重曹拭きでも水拭きでも、終わった後は必ず「乾拭き」をして、水分を完全に残さないことが鉄則ですよ!
無垢材の床掃除で注意すべきポイント
最近、おしゃれなお家で増えている「無垢材(むくざい)」のフローリング。木の温かみがあって素敵ですが、お手入れに関しては重曹もクエン酸も基本的にはNGだと思ってください!
無垢材、特にオイル仕上げや無塗装の床にアルカリ性の重曹を使うと、木に含まれるタンニンなどの成分と反応して、木が黒く変色(アルカリ焼け)してしまうことがあるんです。一度変色すると、削らない限り元には戻りません。想像するだけで怖いですよね…。
また、アルカリは油分を分解するので、木に必要な油分まで奪ってしまい、カサカサになったりささくれができたりする原因にもなります。
無垢材の場合は、基本は「乾拭き」のみ。もし汚れが気になるなら、「未晒し蜜ロウワックス」やメーカー指定の専用クリーナーを使うのが一番安心です。自然素材には自然素材のケアを、ということですね。
あわせて、無垢材の床でロボット掃除機や水拭き機能をどう使うべきか知りたい方は、無垢床でロボット掃除機を安全に使うための詳しいガイドもチェックしておくと安心です。
フローリングの床をピカピカにする最新家電
さて、ここまで「重曹水を作って、拭いて、水拭きして、乾拭きして…」という手順をお話ししてきましたが、正直なところ「面倒くさい!」って思いませんでしたか?(笑)
私も主婦なので、その気持ち痛いほど分かります。
膝をついて雑巾がけなんて、腰も痛くなるし毎日は無理ですよね。
そこで、家電量販店の店員として私が猛プッシュしたいのが、これらの工程を一気に解決してくれる最新家電たちです。
まずおすすめなのが、CCP「コードレス回転モップクリーナー Neo+」です。
これ、電動でモップパッドがくるくる回転して、床を勝手に磨いてくれるんです。
自分の手でゴシゴシする必要一切なし!
しかも、水だけで99.9%雑菌を除去できる特殊な繊維を使っているので、重曹水を作る手間すら不要になります。軽くて操作も楽なので、プレゼントに購入される方も多いんですよ。
そして、今一番ホットなのが「水拭き掃除機」というジャンル。
例えば、Tineco(ティネコ)「Floor One S5」なんかは凄いです。
掃除機のようにゴミを吸いながら、同時に水拭きをして、さらに汚れた水は別のタンクに回収してくれるんです。
「汚れた雑巾で汚れを塗り広げている」という水拭きの矛盾を完全に解決した革命児!
洗剤を使わなくても、常にキレイな水で洗うので床がピカピカになります。
さらに使用後はブラシを自動洗浄してくれる機能付き。
もう、バケツと雑巾には戻れません…。
こうした水拭き掃除機を選ぶときの比較ポイントや注意点については、水拭き同時型スティック掃除機の選び方完全ガイドで詳しく解説しています。
「熱」の力で汚れを落とすなら、ケルヒャー「SC2 EasyFix」などのスチームクリーナーも最強です。100℃近い高温スチームで油汚れを溶かすので、洗剤なしでベタベタ汚れが瞬殺です。
ただ、熱に弱い床材もあるので、そこだけは注意してくださいね。
私のイチオシ
お子様の食べこぼしが多いお家なら「Tineco」、とにかく楽に床をサラサラにしたいなら「CCPの回転モップ」がおすすめです。初期投資はかかりますが、毎日の「拭く・絞る・洗う」のストレスから解放されると思えば、安い買い物だと思いますよ!
床掃除は重曹とクエン酸どっちも使い分けが重要
長くなってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございます!
「床掃除 重曹 クエン酸 どっち」問題、答えは見つかりましたでしょうか?
最後に、今日の大事なポイントをまとめておきますね。これさえ覚えておけば、もう洗剤選びで迷うことはありません。
| 場面・悩み | 正解アイテム | ポイント |
|---|---|---|
| リビングのベタベタ(皮脂) | 重曹 or セスキ | 弱アルカリ性で中和!濃度に注意して白残りを防ぐ |
| トイレの臭い・水回りの水垢 | クエン酸 | 酸性で中和!重曹拭きの後の仕上げリンスとしても優秀 |
| 無垢材・デリケートな床 | 専用クリーナー or 乾拭き | 重曹・クエン酸は変色の元!絶対に使わない |
| とにかく楽をしたい時 | 電動モップ・水拭き掃除機 | 「CCP」や「Tineco」などの家電に頼るのが現代の賢い選択 |
結局のところ、「汚れの種類に合わせてどっちも使い分ける」のが正解であり、もしそれが面倒なら「中性洗剤(ウタマロなど)」や「優秀な家電」に頼るのが、ストレスフリーな生活への近道かなと思います。
無理なく続けられる方法を見つけて、ぜひ裸足で歩きたくなるような気持ちいいフローリングを手に入れてくださいね。
お店でも、いつでもご相談お待ちしています!(なんて、ブログですけど笑)



