お部屋の空気循環や部屋干しにサーキュレーターを活用していますか?
エアコンの効率を上げてくれるし、一年中出しっぱなしで大活躍というお家も多いですよね。
でも、ふと気づくと羽根やガードにホコリがびっしり…なんてことになっていませんか?
「見なかったことにしよう」とそっと視線を逸らしたくなる気持ち、痛いほどわかります。
扇風機と違ってサーキュレーターって、なんであんなにホコリを吸い寄せるんでしょうね?
しかも、「掃除しよう!」と意気込んでみたものの、ネジが見当たらなかったり、隙間が狭すぎて指が入らなかったりして、「これ、どうやって掃除するの?」と途方に暮れた経験がある方も多いはずです。
実は、お店でお客様とお話ししていても「サーキュレーターの掃除が面倒くさい」というお悩みは本当によく聞くんです。中には「汚れすぎて掃除する気が起きないから、新しいのを買いに来た」なんて強者もいらっしゃるくらい(笑)
でもちょっと待ってください!
そのサーキュレーター、まだ諦めるのは早いかも。
実は機種のタイプに合わせた正しいやり方と、ちょっとした便利な道具さえあれば、あの厄介なホコリ汚れもスッキリ落とせるんです。
この記事では、家電量販店員の私がプライベートで実践している、分解できるタイプからどうしても分解できないタイプまで、それぞれの構造に合わせた最適なメンテナンス方法を徹底的に解説します。
100均で買える神アイテムや、「次に買い替えるなら絶対これ!」という推し機種まで、出し惜しみなくお伝えしますね。これを読めば、もうホコリまみれの風を浴びる生活とはサヨナラできますよ!
- 分解できるかどうかの見極め方とタイプ別の掃除手順
- 分解できない機種でも諦めない隙間掃除の裏技テクニック
- 100均や身近な店で手に入る最強の掃除グッズと洗剤
- 掃除の手間を劇的に減らすメンテナンスフリーな機種の選び方
まず確認したいサーキュレーター掃除の仕方

「よし、掃除するぞ!」といきなりドライバーを握りしめたあなた、ちょっとストップです!
実はサーキュレーターの掃除において一番大事なのは、手を動かす前の「観察」なんです。
私がお店で扱っている商品を見ても、簡単にバラバラにできるものから、どうやっても開かない「鉄壁の要塞」のようなものまで千差万別なんですよね。
まずは、お手持ちの相棒がどのタイプなのかを見極めることから始めましょう。ここを間違えると、最悪の場合壊してしまうこともあるので、まずは深呼吸して構造チェックからスタートです。
分解できるモデルか構造を確認
まず最初にやるべきは、「どこまで外せるか」の確認です。これを把握していないと、無理にこじ開けてプラスチックの爪を折ってしまったり、戻せなくなってしまったりという悲劇が起きます。
実はサーキュレーターには、大きく分けて3つのレベルがあるんです。これを私は勝手に「掃除の難易度クラス」と呼んでいます(笑)
このクラス分けを知っているだけで、メンテナンスの計画が立てやすくなりますよ。
一つ目は「全分解クラス」。
これは前面のガード、中の羽根(ファン)、そして背面のガードまで、工具を使わずにパカパカ外せるタイプです。山善の「YAR-DDW151」や、アイリスオーヤマの「PCF-SDC15T」などがこれに当たりますね。
このタイプなら、後述する水洗いがガンガンできるので、掃除の難易度は一番低いです。「お手入れ」の項目を見て、ガードの外し方が図解されていれば、このタイプの可能性が高いですよ。
二つ目は「セミ分解クラス」。
前面のガードだけは外せるけれど、羽根はネジで固定されていたり、そもそも外せないようになっているタイプです。アイリスオーヤマのスタンダードなモデルや、無印良品の一部のモデルがここに含まれます。
このタイプの場合、前面ガードは水洗いできますが、羽根や内部は拭き掃除がメインになります。「外せるのは前だけ」と割り切って作業する必要がありますね。
そして三つ目が、一番厄介な「密閉・非分解クラス」。
安価なUSB扇風機や、少し古い小型のモデルによく見られます。ネジ穴が塞がれていたり、特殊なネジが使われていたりと、メーカーが「分解しないでね」という強い意志を感じる設計になっています。
これを無理に開けようとすると、保証対象外になるどころか、怪我をする恐れもあります。このタイプの場合は、外からのアプローチだけで戦うしかありません。
カバーがどうしても外れない場合の原因と対処法を詳しく知りたい方は、外れないサーキュレーターの掃除方法と対処ステップもチェックしてみてください。
お手持ちの機種の型番をスマホで検索して、取扱説明書(PDF)を確認するのが一番確実です。
「お手入れ」のページに「ガードの外し方」が載っていなければ、残念ながら非分解クラスの可能性大です。
でも安心してください。
分解できなくても綺麗にする方法はちゃんとありますから!
分解レベルの確認ポイント
- 前面ガードの縁に「爪」があるか?:あれば手動で外せる可能性大。
- 背面にネジがあるか?:プラスネジならドライバーで外せるかも。
- ファンの真ん中に留め具があるか?:スピンナーがあれば羽根も外せます。
分解できないタイプの対処法

「うわっ、うちのサーキュレーター、どこを見てもネジがない…絶望。」なんて落ち込まないでください。分解できないタイプこそ腕の見せ所です!
このタイプの掃除の基本戦略は、「風の力を利用する」こと。分解できないなら、風で汚れを吹き飛ばしてしまえばいいんです。
ここで絶対に用意してほしいのが「エアダスター」です。パソコンのキーボード掃除なんかで使う、シュッと空気が出るスプレーですね。
ただし、適当なものを選んではいけません。必ず「逆さ噴射OK」と書いてあるものを選んでください。サーキュレーターの内部を掃除するときって、どうしても缶を傾けたり逆さまにしたりする場面が出てきます。対応していないものを使うと、液化ガスが噴き出してプラスチックが割れたり、内部の基板がショートして故障の原因になったりするんです。
私はエレコムの「ダストブロワー ECO (AD-ECOM)」を愛用しています。これならどんな角度でも安心してシュッシュできますよ。
エアダスター全般の使い方やNG行為について深掘りしたい場合は、PC掃除の正しいやり方とエアダスターの注意点を解説した記事も役立つと思います。
掃除の手順ですが、まずは屋外かお風呂場へGO!
部屋の中でやると、溜まりに溜まったホコリ爆弾が炸裂して大惨事になります(笑)
どうしても室内でやるなら、大きなゴミ袋の中にサーキュレーターごと入れて、その中で作業する「簡易無菌室」方式がおすすめです。
ポイントは「逆流」させること。
普段サーキュレーターは後ろから空気を吸って前に出していますよね?
つまりホコリは後ろのガードやファンの裏側に張り付いています。
なので、まずは前面から背面に向かってエアダスターを思いっきり噴射!
逆方向から風を当てることで、フィルターのように詰まったホコリを剥がすんです。
次に、背面からモーターの軸やコイル部分に向けてピンポイント射撃。これで奥に潜んだホコリたちを追い出します。
エアダスターを使う際は、必ず換気の良い場所で行ってください。また、連続して噴射しすぎると缶が冷えて威力が落ちるので、休み休み使うのがコツですよ。
隙間のホコリはどうやって取るか
エアダスターでおおまかなホコリを吹き飛ばしても、長年蓄積した「こびりつきホコリ」や、油を含んだベタベタ汚れはしつこく残っていますよね。
特にガードの網目の交差部分!
あそこに絡みついた綿埃を見ると、なんだかムズムズしませんか?
ここからは物理攻撃、つまり「ブラシ」での掻き出し作業に入ります。
まず、手元にあると最強なのが「マツイ棒」的な自作ツール。割り箸にキッチンペーパーを巻き付けて輪ゴムで止めただけのあれです。これにお湯で薄めた中性洗剤を少し染み込ませて、ガードの隙間を一本一本拭いていきます。
地味な作業ですが、ペーパーが汚れたらすぐに捨てられるので衛生的ですし、何よりコストがかかりません。油汚れを含んだホコリは、乾いたブラシで擦っても伸びるだけなので、この「拭き取り」が意外と重要なんです。
そして、どうしても届かない奥のファンや、複雑な曲面の汚れには、市販の隙間ブラシを活用します。
ここで重要なのは、ブラシの「硬さ」です。柔らかすぎるブラシだと、ホコリを撫でるだけで取れませんし、硬すぎるとプラスチックに傷がつきます。
私が試行錯誤の末に行き着いたのは、無印良品の「隙間掃除シリーズ」のヘラとブラシです。特にヘラの方は、こびりついた頑固な汚れをこそぎ落とすのに絶妙な硬さなんです。100円以下で買えるので、見かけたら即ゲットしてください。
あと、意外と盲点なのが掃除機の活用。細いノズルをつけて、ブラシで掻き出したホコリをその場で吸い込みながら作業すると、ホコリが再付着しなくて効率的です。
ブラシで浮かせて、掃除機で吸う。このコンビネーション技で、分解できないイライラを解消しましょう!
便利な掃除グッズとブラシ選定
さて、先ほども少し触れましたが、サーキュレーター掃除は「道具選び」が勝敗の8割を決めると言っても過言ではありません。「弘法筆を選ばず」なんて言いますが、掃除に関しては「筆(道具)」を選ばないと日が暮れます(笑)
私が実際に使って感動した「神ツール」たちをご紹介しますね。
まず、全サーキュレーターユーザーに全力でおすすめしたいのが、ニトリの「サーキュレーター用お掃除ブラシ」です。
これ本当にすごいんです。中心にワイヤーが入っていて、好きな角度にグニャッと曲げられるんですよ。
アイリスオーヤマの「サーキュレーターアイ」シリーズのような、丸っこくて隙間から手が届きにくい機種にはまさに救世主。ファンの裏側のカーブに合わせてブラシを曲げれば、今まで諦めていた死角の汚れもゴッソリ掻き出せます。
見えないところからホコリの塊が出てきたときの「取れたー!」という快感、ぜひ味わってほしいです。
次に、100均グッズの優秀選手。ダイソーの「隙間の達人」シリーズや、セリアの「清掃用綿棒 ロング」も侮れません。
特に「スキマの汚れスッキリ棒」は、使い捨て前提の細いロッド形状で、分解不可能なメッシュガードの奥の奥まで侵入してくれます。汚れたらポイできるので、油汚れがひどいキッチン周りのサーキュレーター掃除には最適ですね。
そして、ケミカル(洗剤)部門での推しは、花王の「クイックル ホームリセット 泡クリーナー」。
これ一本で家中の掃除ができる万能選手ですが、サーキュレーター掃除にも相性抜群なんです。
泡立ちすぎないので拭き取りが楽ですし、二度拭きがいらないのが最高。界面活性剤が入っているので、油を含んだホコリもサッと落ちます。
分解できない本体部分を拭くときは、直接スプレーするのではなく、クロスに吹き付けてから拭くのが故障を防ぐポイントですよ。
| ツール名 | メーカー/購入先 | おすすめポイント |
|---|---|---|
| サーキュレーター用お掃除ブラシ | ニトリ | 自由自在に曲がるので、羽根の裏まで届く最強ツール |
| ダストブロワー ECO (AD-ECOM) | エレコム | 逆さ噴射OKで、内部の基板やモーター周りのホコリ飛ばしに必須 |
| ホームリセット | 花王 | 二度拭き不要で、プラスチックにも優しい中性クリーナー |
前面カバーの取り外し方のコツ
分解できるタイプをお持ちの方、おめでとうございます!
前面カバーさえ外せれば、掃除のクオリティは格段に上がります。
でも「爪が固くて外れない」「割れそうで怖い」という声もよく聞きます。ここでは安全にカバーを外すコツを伝授しますね。
まず「爪(ツメ)固定式」の場合。アイリスオーヤマの製品に多いタイプですね。
基本的にはガードの裏側に指をかけて、爪の部分を軽く押し込みながら手前に引くと外れます。…と言うのは簡単ですが、これが意外と硬い!
コツとしては、一箇所だけを無理に外そうとせず、対角線上の爪を順番に少しずつ浮かせていくイメージで作業すること。どうしても指の力だけでは無理な場合は、マイナスドライバーの先端に薄い布を巻いて(傷防止のため)、爪の隙間に差し込み、テコの原理で優しく持ち上げるとスムーズです。
ただし、冬場など部屋が寒いときはプラスチックが硬化して割れやすいので、少し暖房で部屋を暖めてから作業するのが裏技です。
次に「ネジ固定式」。背面の深い穴の中にネジがある場合が多いです。
ここで大事なのはドライバーのサイズ。
「プラスなら何でもいいでしょ」と思いがちですが、サイズが合っていないドライバーを使うと、ネジ山を舐めてしまって二度と開かなくなる悲劇が起きます(泣)
基本的には「No.2」というサイズのプラスドライバーがあれば対応できますが、小型モデルだと「No.1」の場合も。ネジ穴をライトで照らしてしっかり確認しましょう。
外したネジは米粒みたいに小さいので、100均で売っているマグネットトレーに入れておくか、養生テープに貼り付けておくと紛失を防げますよ。
カバーが外れた瞬間に、溜まっていたホコリが「バフッ」と舞うことがあるので、マスク着用は必須です!
外したカバーはお風呂場直行コースでOKです。
実践的なサーキュレーター掃除の仕方と手順
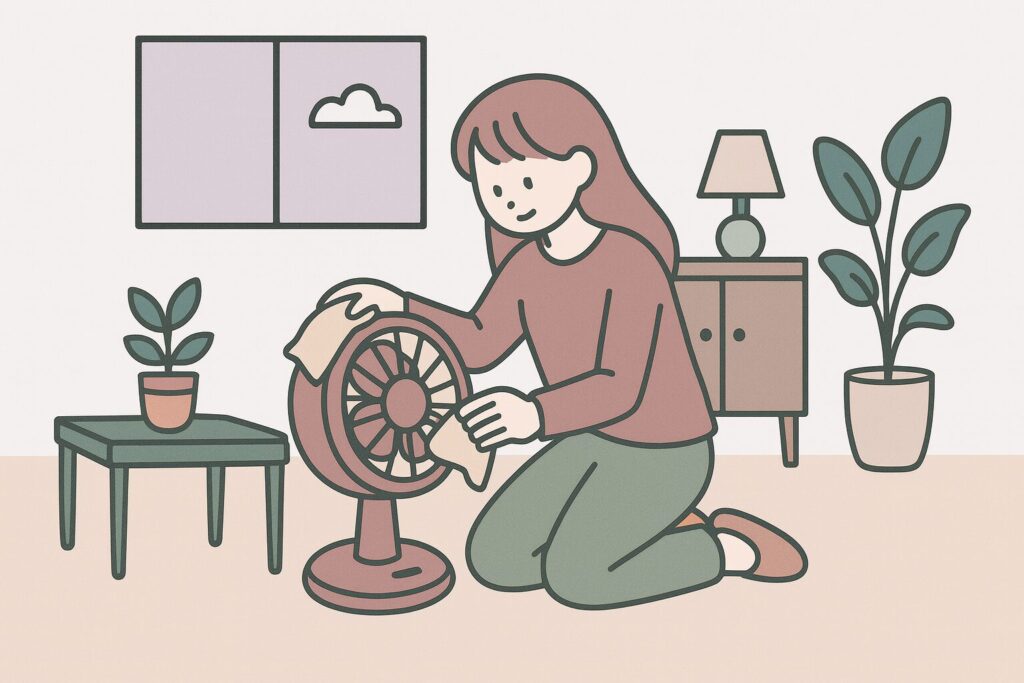
さあ、ここからはいよいよ実践編です。分解して丸裸になったパーツたちをピカピカに磨き上げ、新品同様の風を取り戻しましょう。
特にキッチンの近くで使っている方や、部屋干しメインで使っている方は、想像以上に「見えない汚れ」が付着しています。
ただの水洗いだけでは落ちない頑固な汚れへのアプローチや、組み立て時の重要な注意点など、家電のプロならではの視点でステップ・バイ・ステップ解説していきますね。
こびりついた羽根の汚れの落とし方
前面カバーを外して、羽根(ファン)とご対面。
よく見ると、羽根のフチに灰色のラインがこびりついていませんか?
これ、ただのホコリじゃありません。
空気中の水分や油分を含んで圧縮された、いわば「ホコリのミルフィーユ」なんです。これを雑巾でゴシゴシ擦っても、汚れを塗り広げるだけでなかなか綺麗になりません。
ここで登場するのが「つけ置き洗い(ハイドロ・クリーニング)」です!
バケツや洗面器にぬるま湯(40度くらい)を張り、台所用の中性洗剤を少し溶かします。そこに外した羽根やガードをドボンと漬け込んで、20分〜30分放置してください。これだけで界面活性剤が油膜を分解し、ホコリをふやかしてくれます。
あとは柔らかいスポンジで優しく撫でるだけで、嘘みたいにツルッと汚れが落ちますよ。文字の凹凸や細かいリブの裏側は、使い古した歯ブラシで軽く擦れば完璧です。
もし、キッチン周りで使っていて油汚れが酷い場合は、セスキ炭酸ソーダやアルカリ電解水を少し混ぜると最強です。
ただし、アルカリ性は強力すぎてプラスチックが白くなったり、アルミ部品を腐食させたりするリスクもあるので、使用後はこれでもかというくらいしっかり水ですすぐことを忘れないでくださいね。基本的には中性洗剤(チャーミーやキュキュットなど)で十分です。
「羽根が外れないタイプ」の場合は、洗剤を含ませたマイクロファイバークロスで包み込むように拭きます。
ポイントは「裏側」。
風を生み出すのは羽根の裏側のカーブなので、ここを念入りに拭くと風量復活の効果が絶大です。
豆知識:リンスで静電気防止
洗い終わった後、水に柔軟剤や衣類用リンスを数滴垂らし、その水を含ませた布で仕上げ拭きをすると、静電気防止効果でホコリが付きにくくなります。これ、結構長持ちするのでおすすめです!
アイリスオーヤマ製品の注意点
サーキュレーターといえば、やっぱりアイリスオーヤマですよね。私の働くお店でも一番売れています。
特に「サーキュレーターアイ (Woozoo)」シリーズは、あのコロンとした可愛いフォルムと大風量で大人気。でも、メンテナンスの観点から言うと、ちょっとした「クセ」があるのも事実なんです。
まず、Woozooシリーズの多くは、前面ガードは外せても、羽根の取り外しが公式には推奨されていない(または非常に難しい)モデルが多いんです。
「羽根の奥にネジが見えるのに、ドライバーが入らない!」と悩む方が多いのですが、これは無理に分解しようとしない方が無難です。隙間が狭い上に球体デザインなので、先ほど紹介したニトリの「サーキュレーター用お掃除ブラシ」のような、柔軟性のあるツールがないと奥まで掃除できません。
アイリスオーヤマ製品を使っている方は、セットでこのブラシを買っておくのが正解です。
あと、アイリスオーヤマの製品は、前面ガードを戻すときに「カチッ」と音がするまでしっかり爪を嵌めないと、稼働中にガードが外れて飛んでくる…なんてホラーな話も稀に聞きます(汗)
掃除の後は、全ての爪が浮いていないか、指で押して念入りにチェックしてくださいね。
山善など洗いやすい機種の活用
「掃除のしやすさ」という点において、個人的に猛プッシュしたいのが山善(YAMAZEN)のサーキュレーターです。山善は「洗えるサーキュレーター」シリーズを展開していて、これがもう、メンテナンスマニアの私の心を鷲掴みなんです。
例えば「YAR-DDW154」というモデル。これ、工具が一切いらないんですよ!前面ガードをクリップでパチンと外し、羽根も手で回して外し、さらに背面ガードまで大きなナットを回すだけで全部取れちゃいます。
所要時間わずか1分で丸裸。「掃除が面倒」という人類共通の悩みを、技術で解決してくれた名機だと思います。
ここまで簡単にバラせると、掃除が苦痛じゃなくなるどころか、綺麗にするのが楽しくなってくるから不思議です。
ドウシシャの「CoCochi-Na」シリーズも、分解清掃に力を入れていますね。
こういった「全分解モデル」を選ぶメリットは、単に掃除が楽なだけじゃありません。モーターの軸に絡まった髪の毛や糸くずを、直接目視して取り除けるのが最大の利点なんです。
実はサーキュレーターの故障原因の多くは、この軸へのゴミの巻き込みによる回転不良や発熱。ここを定期的にケアできる全分解モデルは、結果的に製品寿命も長持ちします。
これからサーキュレーターを買う方、あるいは買い増しを考えている方は、風量や静音性だけでなく、「背面ガードまで外せるか?」をスペック選びの最優先事項に入れてみてください。未来のあなたが絶対に感謝しますよ。
水洗い後の乾燥と組み立て手順

綺麗に洗ってスッキリ!
…でも、ここで油断すると大失敗します。
水洗い後の最重要工程、それは「完全乾燥」です。
プラスチックの表面が乾いていても、ネジ穴の奥や、ガードの重なり部分に水分が残っていると、そこからカビが生えたり、最悪の場合は内部でサビが発生して故障の原因になります。
浴室乾燥機があれば最高ですが、なければ風通しの良い日陰で、半日〜1日はしっかりと干してください。「早く使いたいから」といって生乾きのまま組み立てるのは絶対にNGです。
そして組み立て時の最大のトラップ、それが「羽根の固定」です。
ファンを軸に差し込み、スピンナー(留め具)で固定するわけですが、ここで多くの方が混乱します。「あれ?右に回しても閉まらない?」と。
実は扇風機やサーキュレーターの羽根を止めるネジは、物理学的な理由から「逆ネジ(左ネジ)」になっていることがほとんどなんです!
羽根は通常時計回りに回転しますよね。もし普通の右ネジだと、回転の反動でだんだん緩んで外れてしまうんです。だから、回転方向と逆に締まる「左回りで締める」構造になっています。スピンナーに「しまる」「ゆるむ」と矢印が書いてあるはずなので、よーく見てくださいね。
これを無理やり逆に回してネジ山を潰してしまうトラブル、本当にお店でもよく相談されます…。
最後に、羽根の裏にある「切り欠き(凹み)」と、モーター軸の「ピン(出っ張り)」をしっかり噛み合わせること。ここがズレたまま無理やり締め付けると、スイッチを入れた瞬間にガタガタガタ!と凄まじい振動と騒音が発生して壊れます。
慎重に、確実にセットしてくださいね。
掃除頻度とトラブル対処法
「じゃあ、この掃除をどれくらいの頻度でやればいいの?」という疑問にお答えします。
理想を言えば、簡易清掃(ハンディワイパーで表面のホコリを撫でる程度)は週に1回。そして本格的な分解清掃は、使用頻度にもよりますが、夏場や部屋干しで毎日使っているなら「1ヶ月に1回」が目安です。
特に重要なのが「シーズンの終わりと始まり」です。秋になって収納する前には、必ず分解掃除をしてホコリと油汚れを落とし切ってください。汚れたまま半年間押入れに入れておくと、カビの温床になります。
そして久しぶりに出してきた春先や梅雨時、スイッチを入れる前にもう一度中を確認しましょう。内部で増殖したカビの胞子を部屋中に撒き散らすことだけは避けたいですからね。
こんな症状が出たら要注意!
- 掃除しても異音が治らない:モーターの軸受(ベアリング)が寿命かも。5年以上使っているなら買い替え時です。
- 羽根の回転が遅い:軸に髪の毛が大量に絡まっている可能性があります。ピンセットで除去してください。
- 焦げ臭いにおいがする:危険!すぐにコンセントを抜いて、使用を中止してください。発火の恐れがあります。(出典:総務省消防庁「住宅における電気火災に係る防火安全対策のポイント」)
よく「異音がするから軸に油(KURE 5-56など)を差してもいい?」と聞かれますが、プラスチック対応のシリコンスプレー以外は絶対NGです!
プラスチックを溶かして割れる原因になりますし、逆にホコリを吸着して固めてしまうこともあります。素人判断での注油はリスクが高いので避けてくださいね。
快適なサーキュレーター掃除の仕方
ここまで、サーキュレーターの掃除について熱く語ってきましたが、いかがでしたでしょうか?
「意外とできそうかも?」と思っていただけたら嬉しいです。
サーキュレーターは単に風を送るだけでなく、私たちの健康や快適な空間を守ってくれる大切なパートナー。だからこそ、少しだけ手間をかけてケアしてあげてください。
最後に、今回の内容をざっくりまとめておきます。
次に掃除するときや、買い替えるときの参考にしてくださいね。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 分解可否の確認 | まずは爪とネジをチェック。「無理に開けない」が鉄則。 |
| 必須ツール | ニトリ「サーキュレーター用お掃除ブラシ」、エレコム「エアダスター(逆さOK)」、中性洗剤。 |
| 分解できない時 | 「エアダスター」で吹き飛ばし、「隙間ブラシ」で掻き出し、「掃除機」で吸うの3段構え。 |
| 分解できる時 | つけ置き洗いで時短。組み立て時の「逆ネジ」と「ピン合わせ」に注意。 |
| 買い替え推奨 | 山善「YAR-DDW154」など、背面まで外せる「全分解モデル」一択! |
綺麗なサーキュレーターから送られる風は、心なしか澄んでいて気持ちがいいものです。
今度の週末、お気に入りの音楽でもかけながら、サーキュレーターの大掃除にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
きっと、部屋の空気も気分もスッキリするはずですよ!



