和室のお掃除、いつもどうしていますか?
毎日掃除機を出すのは面倒だけど、ホコリや髪の毛は気になりますよね。クイックルワイパーなら手軽にサッとお掃除できるから、畳にも使えたらとても便利です。
でもちょっと待ってください。
フローリングと同じ感覚で使ってしまうと、大切な畳を傷めてしまうかもしれません。
畳は天然のい草でできているとてもデリケートな素材。特に湿気や水分が大の苦手なんです。
だからこそ、クイックルワイパーのドライシートとウェットシートでは使い方が全く違います。
さらに、良かれと思ってやっている掃除方法が、実は畳を劣化させる原因になっていることも少なくありません。
この記事では、クイックルワイパーを畳に正しく使う方法から、やってはいけないNG掃除、そして家電を活用した効果的な畳のお手入れ方法まで、家電のプロとしての知識を活かして詳しくご紹介していきます。
畳の掃除へのクイックルワイパーの使い方

このセクションでは、クイックルワイパーの「ドライシート」と「ウェットシート」、それぞれの正しい使い方と、畳を傷めないための注意点を詳しく見ていきましょう。
クイックルワイパーは畳に使っていい?
「畳にクイックルワイパー、使っていいですか?」というご質問、店頭でも本当によく耳にします。毎日掃除機をかけるのは大変だけど、ホコリや髪の毛は気になる…そんな時に、手軽なクイックルワイパーが使えたら嬉しいですよね。
答えは、「シートの種類を選べば、使ってもOK」です!
ただし、畳は「い草」という天然素材でできていることを忘れてはいけません。
い草は呼吸するように湿気を吸ったり吐いたりしていますが、水分には非常に弱いんです。水分が畳内部に残ると、そこからカビやダニが発生する原因になってしまいます。
ですから、クイックルワイパーを使う上で一番大切なのは「畳を湿らせすぎないこと」。
この一点に尽きます。
「じゃあ、どのシートなら大丈夫なの?」と思いますよね。
ポイントは、乾拭き用の「ドライシート」と、水拭き用の「ウェットシート」を明確に使い分けることなんです。次のセクションからそれぞれ詳しく解説していきますね。
畳掃除の基本原則
- 基本は「乾拭き」:畳のデリケートな表面を傷めず、ホコリや髪の毛を効率的に取り除きます。
- 湿気は厳禁:畳は水分を吸うとカビやダニの温床になりやすいです。
- 畳の目に沿って:掃除機でもワイパーでも、畳の目に沿って優しく拭くのが鉄則です。目に逆らうと、い草が毛羽立ったり、ささくれができたりする原因になります。
この3つの原則を頭に入れておくだけで、畳をずっとキレイに長持ちさせることができますよ。
ドライシートは毎日使ってもOK
畳のお掃除で、私が一番おすすめしたいのが「ドライシート」を使ったクイックルワイパーです。
これはもう、毎日使っても大丈夫です。
なぜドライシートがおすすめかというと、畳掃除の基本である「乾拭き」を、最も手軽に、かつ効率的にできるからなんです。
畳は湿気に弱いので水分は大敵。
でもホコリや髪の毛、ペットの毛は毎日溜まりますよね。
掃除機を出すほどではないけれど、ちょっと気になる…。
そんな時、ドライシートなら畳を一切湿らせることなく、表面のゴミをしっかりキャッチしてくれます。
例えば、花王の「クイックルワイパー 立体吸着ドライシート」なんかは、メーカーの公式な情報でも畳への使用が推奨されています。あのフワフワした立体構造が、畳の目の隙間に入り込んだ細かいホコリもしっかり絡め取ってくれる感じがします。
(参考:花王「Q&A 和室をきれいに保ちたいのですが、お手入れ方法は?」)
ドライシートの上手な使い方
使い方はとても簡単ですが、一つだけコツがあります。
それは、必ず「畳の目に沿って」優しく拭くこと。
ゴシゴシと力を入れたり、畳の目に逆らって拭いたりすると、畳の表面を傷つけて「ささくれ」の原因になってしまいます。
掃除機のように大きな音も出ませんし、排気も出ないので、早朝や夜間、小さなお子さんがお昼寝している時でも、気づいた時にサッとお掃除できるのが嬉しいポイントですよね。
掃除機をかけると、どうしても排気で細かいホコリが舞い上がりがちですが、ドライシートはホコリを吸着させて取るので、その点も安心です。
家電との使い分け
「掃除機があるのに、あえてドライシートを使う意味は?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
でも、ドライシートは掃除機とは役割が違うんです。掃除機は「吸引」、ドライシートは「吸着(乾拭き)」です。畳の表面をサラッと保つための日常的な「乾拭き」として、ドライシートは最適解だと思います。そして、週に1〜2回、畳の目の奥のゴミを吸い出すために、掃除機をかける。こんな風に使い分けるのがおすすめですね。
ウェットシートはカビの原因になる?
さて、問題は「ウェットシート」です。
「皮脂汚れでベタベタするから、ウェットシートでスッキリ拭きたい!」というお声も、店頭でよく伺います。
ですが、ここは声を大にしてお伝えしたいのですが、一般的なフローリング用のウェットシートを、畳にそのまま使うのは非常に危険です!
使い方を間違えると、カビやダニの大きな原因になりかねません。
なぜかというと、理由は大きく2つあります。
リスク1:水分が多すぎる
先ほどからお伝えしている通り、畳(い草)は湿気が大の苦手。一般的なウェットシートは、フローリングをピカピカにするために、たっぷりと水分を含んでいます。
これを畳に使うと、い草がその水分をぐんぐん吸い込んでしまい、畳の内部がジメジメした状態になってしまいます。これがカビやダニが最も好む環境なんです。
リスク2:シートに含まれる成分
もう一つの問題が「成分」です。
多くのウェットシートには、洗浄力を高めるために「アルコール」や「界面活性剤」が含まれています。
これらの化学成分が、い草の植物繊維と反応して、畳が変色したり、劣化してボロボロになったりする可能性があるんです。
ウェットシート使用の危険性
- カビ・ダニの発生:畳が吸い込んだ水分が抜けず、カビやダニの温床になります。
- 変色・劣化:アルコールや界面活性剤が、い草を黄ばませたり、傷めたりする原因になります。
- シミ:シートの水分が多すぎてムラになり、そのままシミとして残ってしまうこともあります。
もし、ウェットシートを使ってしまった場合は、その後の「強制乾燥」が必須です。
拭いた直後に必ず乾いた雑巾やタオルで乾拭きをして、さらに扇風機やサーキュレーターの風を当てて、畳の表面に残った湿気を完全に飛ばし切ってください。
梅雨時なら、エアコンの除湿運転や除湿機をフル稼働させる必要があります。
…これ、クイックルワイパーの「手軽さ」が、ほぼ無くなってしまいますよね(苦笑)。
だからこそ、日常的な使用はおすすめできないんです。
畳に使えるウェットシートの選び方
「それじゃあ、畳のベタつきはどうすればいいの?」と思いますよね。
基本はドライシートでの乾拭きや、固く絞った雑巾での水拭きが一番です。
でも、どうしてもウェットシートを使いたいという場合は、製品の「選び方」が重要になってきます。
もし選ぶのであれば、以下のポイントをチェックしてみてください。
成分をチェック(アルコール・界面活性剤フリー)
畳を変色させたり傷めたりする可能性がある、アルコールや界面活性剤が入っていない製品を選びましょう。最近は「水」を主成分にしたウェットシートも増えています。
例えば、レックの「Ba水の激落ちシート」などは、「アルカリ電解水」を使用しています。これは洗剤を使わずに皮脂汚れなどを浮かせて落とす力があるので、畳のベタつきにも効果が期待できます。
専用品のリスクも知っておく
中には、「畳用」や「ダニよけ」を謳った専用のウェットシートもあります。
例えば、レックの「激落ちくん シート 畳用 ダニよけプラス」などですね。
一見、専用品だから安心!と思いがちですが、ここにも注意点があります。
ダニよけ効果があるということは、何かしらの「薬剤」が使われているということです。実際に製品の注意書きを見ると、「畳の上に長時間放置しないでください。変色の原因となる場合があります」といった記載があったりします。
薬剤による化学反応のリスクを考えると、個人的にはあまり積極的におすすめしにくいところです。
家電店員としてのダニ対策アドバイス
もし畳のダニ対策を本気で考えるなら、薬剤を使ったシートよりも、家電を使った「熱」での対策が最も効果的で安全だと私は思います。
ダニは50℃以上の熱で死滅します。一番のおすすめは「布団乾燥機」ですね。畳の上に布団乾燥機を直置きして、その上から掛け布団をかぶせて「ダニ退治モード」で運転すれば、畳の温度をしっかり上げてダニを死滅させることができます。その後、死骸を掃除機で吸い取れば完璧です。薬剤による変色リスクを負うよりも、ずっと根本的な解決になりますよ。
結局のところ、ウェットシートは「皮脂汚れがひどい時だけ、成分を選んで、使った後の乾燥まで徹底して行う」という、特別なアイテムとして捉えるのが良さそうですね。
正しい水拭きのやり方と乾燥のコツ
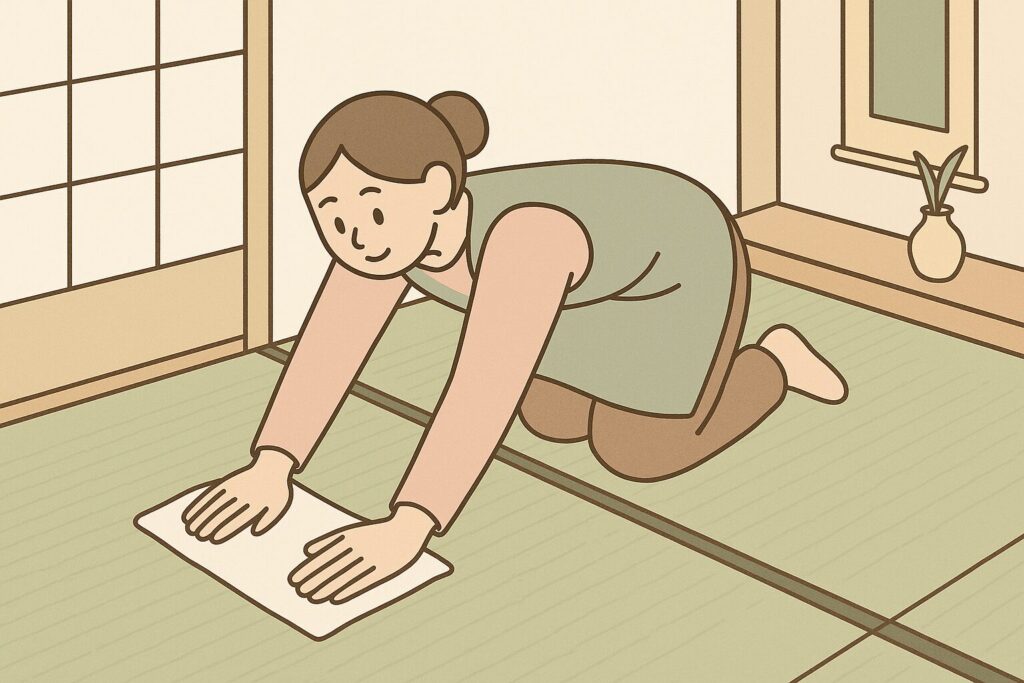
「ウェットシートがダメなら、雑巾で水拭きするのはどう?」という疑問も出てきますよね。
畳の皮脂汚れやベタつきが気になるとき、昔ながらの雑巾がけは有効です。ただしこれも「正しいやり方」を守ることが大前提です!
ウェットシートのリスクと同じで、最大の敵は「水分」。畳を水浸しにしないよう、細心の注意を払いましょう。
もし汚れがひどい場合は、水拭きの前にクエン酸水を使うのもおすすめです。バケツ半分のお湯にクエン酸小さじ1杯ほどを溶かしたもので雑巾を絞って拭くと、皮脂汚れや(い草の)匂いが気になる場合にもさっぱりしますよ。
クエン酸は電気ケトルや加湿器の内部洗浄にも使われる、家電とも親和性の高い安全な洗浄剤ですね。
畳の正しい水拭き・4ステップ
- 雑巾を「固く」絞る:これが一番重要です!雑巾から水が滴るなんてもってのほか。ねじ切れるくらい(笑)、固ーく絞ってください。
- 畳の目に沿って拭く:い草を傷つけないよう、畳の目に沿って優しく、一方通行で拭いていきます。ゴシゴシ往復するのはNGです。
- すぐに「乾拭き」する:水拭きした箇所が乾く前に、乾いたタオルや雑巾で、残った水分を完全に拭き取ります。水拭きと乾拭きは必ずセットで行ってください。
- 換気&強制乾燥:最後に、窓を開けて部屋の風通しを良くします。さらに、扇風機やサーキュレーターで風を当てたり、除湿機をかけたりして、畳に残ったわずかな湿気も強制的に乾燥させます。
…どうでしょうか。
この手順を見て、「結構、大変…」と思いませんでしたか?
そうなんです。クイックルワイパーの最大のメリットである「手軽さ」は、畳の水拭きにおいては実質なくなってしまうんです。
だからこそ、普段のお掃除はドライシートや掃除機(乾拭き)をメインにして、水拭きは「どうしてもベタつきが取れない時」の最終手段、と考えるのが良いと思いますよ。
クイックルワイパー以外の畳掃除とNG集

畳のお掃除、クイックルワイパーの手軽さは魅力ですが、畳を長持ちさせるには、掃除機や他の道具の使い方も大切になってきます。
特に、良かれと思ってやっていることが、実は畳をどんどん傷めてしまっている…なんていう「NG行為」も結構あるんです。
このセクションでは、畳掃除の「やってはいけないこと」と、ロボット掃除機やスティック掃除機など、「家電を使った正しいお掃除方法」について、家電店員ならではの視点で詳しく解説していきますね!
畳掃除にコロコロがだめな理由
これはもう、声を大にして言いたいのですが、畳のお掃除に粘着シートクリーナー(いわゆる「コロコロ」)は、使わないでください!
フローリングやカーペットのついでに、和室もコロコロ…とやってしまいがちなのですが、これは畳にとって最悪の行為の一つなんです。
なぜかというと、コロコロのあの強力な粘着力が、畳の表面(い草)の繊維を無理やり引っ張り、引きちぎってしまうからです。それを繰り返していると、畳はあっという間に毛羽立ち、ささくれだらけになってしまいます。
コロコロ(粘着シート)が畳を傷める仕組み
粘着シートを畳の上で転がす↓
粘着剤がい草の繊維に強力にくっつく
↓
シートを剥がす(転がす)力で、繊維が引っ張られる
↓
繊維が毛羽立つ・ささくれ(ほつれ)が発生する
↓
畳の寿命が縮み、見た目もボロボロになる
「お客様の中にも、「最近、畳のささくれがひどくて…」というご相談で、よくよくお話を聞いてみると、毎日コロコロをかけていた、というケースが本当に多いんです。
畳に落ちている髪の毛やホコリが気になる場合は、コロコロの代わりに、クイックルワイパーの「ドライシート」を使いましょう。これなら畳を傷めずに、優しくホコリを吸着できます。もしくは、昔ながらの「ほうき」も、畳にはとても優しい道具ですよ。
重曹で畳が黄ばむ?
はい、これもよくある「NG」の一つです。重曹で畳を拭くと、黄ばみます!
「ナチュラルクリーニング」として、重曹は油汚れや消臭に万能!というイメージが強いですよね。キッチン周りのお掃除などで大活躍するので、畳にも使えそう…と思ってしまうお気持ち、とてもよく分かります。
でも、重曹は「アルカリ性」です。一方、畳の「い草」は天然の植物繊維。このアルカリ性が、い草の組織と化学反応を起こして、畳を黄色く変色させてしまうんです。これは「黄ばみ」であり、元の日焼けしたきれいな色とは全く違う、不自然な変色です。
一度黄ばんでしまうと、元に戻すのは非常に困難です。絶対に重曹は使わないでください。
畳掃除の「酸性・アルカリ性」豆知識
- 重曹(アルカリ性) → NG
い草と化学反応し、黄ばみの原因になります。 - クエン酸(酸性) → OK
畳(い草)を傷めにくい特性があります。皮脂汚れやアンモニア臭(おしっこなど)が気になる場合は、水に溶かしたクエン酸水で固く絞った雑巾拭きが有効です。
ちなみに、この「クエン酸」は、電気ケトルや加湿器のカルキ汚れ(水アカ)を落とすのにも使われる、私たち家電店員にとってもおなじみの洗浄剤なんです。家電のお手入れにも、畳のお手入れにも使えるんですね。
万能に見える重曹も、素材によって向き不向きがある、という良い例だと思います。
ルンバなどロボット掃除機の注意点
「和室もロボット掃除機で自動でキレイにしたい!」というご要望、これも店頭で本当に多くいただきます。ルンバをはじめとするロボット掃除機、本当に便利ですもんね。
ですが…、これも残念ながら、「い草」の畳の部屋でロボット掃除機を使うことは、原則として推奨できません。
理由は、畳を傷めてしまう大きな要因が2つあるからです。
理由1:畳の目に沿って動けない
畳掃除の基本は「畳の目に沿って」ですが、ロボット掃除機は部屋をランダム、あるいはマッピングしながら効率的に動きます。畳の目を無視して縦横無尽に走行するため、い草の表面を傷つけ、ささくれを発生させてしまうんです。
理由2:硬い回転ブラシ
多くのロボット掃除機には、カーペットの奥のゴミを掻き出すために、硬い毛の「回転ブラシ」が搭載されています。このブラシが、畳にとっては大敵!コロコロと同じように、畳の表面を無理やり引っ掻いてしまい、毛羽立ちやほつれの原因になってしまいます。
ロボット掃除機が畳を傷める主な理由
- ランダムな動き:畳の目に逆らって走行し、い草を傷める。
- 硬い回転ブラシ:畳の表面をこすり、ささくれや毛羽立ちを引き起こす。
対策と例外
「じゃあ、絶対にダメなの?」というと、いくつか例外や対策はあります。
- ブラシの回転をオフにできるモデルを選ぶ:吸引だけでも、ある程度のホコリは取れます。
- 柔らかいブラシが搭載されているモデルを選ぶ:最近のモデルには、素材に配慮したものも出てきています。
- 畳の素材が「い草」ではない場合:最近は、耐久性の高い「樹脂製」や「和紙製」の畳もありますよね。これらはい草よりも傷つきにくいので、ロボット掃除機が使える場合もあります。(ただし、樹脂製なども目に沿った掃除が推奨されることが多いので、畳メーカーの情報を確認してくださいね)
とはいえ、ロボット掃除機の最大のメリットである「全自動の便利さ」は、畳の部屋では少し制限されてしまうのが実情です。い草の畳を長持ちさせたいなら、やはり手間はかかっても、後述する「軽量スティック掃除機」で、ご自身の目で確認しながら畳の目に沿って優しく掃除するのが一番のおすすめですね。
掃除機のかけ方とおすすめヘッド

畳掃除の主役は、やっぱり「掃除機」です。でも、掃除機もかけ方を間違えると、畳を傷める原因になってしまいます。
ここでは、畳をいたわりながらゴミをしっかり吸い取る「正しいかけ方」と「おすすめのヘッド」をご紹介しますね。
畳の「正しい」掃除機のかけ方
ポイントはたったの3つです。
- 必ず「畳の目に沿って」かける:これはもう、基本中の基本ですね。い草を傷つけず、畳の目の隙間に入ったゴミを効率よく吸い取るためです。
- 強く押し付けず、ソフトに扱う:ヘッドを畳に強く押し付けると、摩擦でい草が傷んでしまいます。
- ゆっくり、丁寧に吸引する:畳1畳あたり「1分程度」かけるのが理想と言われています。ササッと往復するだけでは、目の奥のゴミは取れません。ゆっくりと掃除機を動かすことで、奥に潜むダニの死骸やフン(アレルゲン)もしっかり吸引できます。
「1畳1分」って、実際にやってみると結構長いですよね…。だからこそ、掃除機は「軽量」であることが、畳掃除にとってはすごく重要なんです。
(出典:全日本畳事業協同組合『畳のお手入れ』)
畳と相性が良い「ヘッド」は?
掃除機選びで重要なのが「ヘッド(ブラシ)」です。畳を傷つけない「柔らかい」ブラシが絶対条件ですね。
家電店員おすすめのヘッド2選
1. ダイソン:「ソフトローラークリーナーヘッド」
これは本当におすすめです!ダイソンというと「吸引力が強すぎて畳が傷みそう」というイメージがあるかもしれませんが、このヘッドは別。硬いナイロンブラシ(ダイレクトドライブヘッド)とは全く違い、柔らかいフェルトのような素材で覆われています。ゴミを吸うと同時に、畳の表面を優しく「乾拭き」してくれるような効果もあって、畳掃除の基本(乾拭き)とも合致します。和室がメインのお家がダイソンを選ぶなら、「ソフトローラーヘッド」が同梱されているモデルを「指名買い」すべきですね。
2. パナソニック:「Y字毛ブラシ」(Jコンセプトなど)
日本の床(畳)に合わせて開発されたヘッドです。柔らかい「Y字毛」が、畳の目地までしっかり届き、ゴミを「拭きあげる」ように取ってくれるのが特徴です。ダイソンのソフトローラーと同じ発想ですよね。また、「親子ノズル」機能も隠れた名脇役!ヘッドのペダルを踏むだけで子ノズル(隙間用)に切り替わるので、畳の端や家具の隙間のゴミも、わざわざノズルを付け替えずにサッとお掃除できて、とても便利だと思います。
アイリスオーヤマの軽量スティックも人気ですね。
多くのモデルに「ほこり感知センサー」が搭載されていて、畳の目に沿ってゆっくり掃除する際に、ランプの色で「まだゴミがあるか」を教えてくれるのは、畳掃除においてユニークな利点だと思います。不要な往復(=畳へのダメージ)を減らせますからね。
ただし、モデルによってはブラシが硬めの場合もあるので、購入時はブラシの素材感や、回転をオフにできるかを確認すると安心ですね。
カビやダニの家電を使った対策
畳のお悩みで、クイックルワイパーの使い方と同じくらいご相談が多いのが、「カビ」と「ダニ」の問題です。特に梅雨時から夏にかけては、本当に深刻ですよね…。
でも安心してください。
カビもダニも、「なぜ発生するのか」を知って、適切な「家電」を使えば、しっかり対策できるんです!
【ダニ対策】「殺して、吸い取る」が鉄則!
ダニは熱に弱く、「50℃以上の温度で死滅する」という特性があります。
この特性を利用するのが一番効果的です。
メイン家電:布団乾燥機
「え?布団乾燥機って、布団に使うものでしょ?」と思いますよね。もちろん、布団のダニ対策が本業ですが、畳のダニにも絶大な効果を発揮するんです。
使い方(重要):布団乾燥機を畳に直置きし、その上から掛け布団をかぶせて、「ダニ退治モード」で運転します。こうすることで、布団と畳の間の空間がサウナのようになり、畳の温度がダニが死滅する50℃以上に上がります。
連携家電:掃除機(必須)
布団乾燥機でダニを「死滅」させても、それだけではダメなんです。ダニの「死骸」や「フン」は畳に残ったまま。そして、この死骸やフンこそが「アレルゲン」の正体なんです!
ダニ退治の後は、必ず掃除機(できれば前述したソフトローラーヘッドなど)で、畳の目からアレルゲンをしっかり吸引除去してください。「殺ダニ(布団乾燥機)」と「吸引(掃除機)」は、必ずワンセットで行いましょう。
(ちなみに、スチームクリーナーは、熱でダニを殺せますが、畳に大量の「湿気」を注入してしまうので、その後の強制乾燥が不十分だと、逆にカビや生き残ったダニの温床になり、状況を悪化させる可能性があるので注意が必要ですよ。)
【カビ対策】「予防」こそが最重要!
カビは「高い温度・湿度」と「ホコリや皮脂(栄養源)」が大好き。つまり、カビ対策は「発生してから除去する」のではなく、「発生させない環境を作ること(予防)」が最も重要です。
メイン家電(予防):除湿機
畳のカビ対策において、除湿機は「最重要の予防家電」だと私は思っています。特に梅雨時や湿気の多い日は、除湿機で部屋の湿度を常時コントロールし、カビの発生条件(高湿度)をなくすことが、畳を長持ちさせる一番の近道です。
連携家電(予防):空気清浄機
空気中に浮遊しているカビ菌やアレルゲンをキャッチするのも予防に繋がります。特に、シャープの「プラズマクラスター」搭載機などは、「浮遊カビ菌」だけでなく、「付着カビ菌の増殖を抑える」効果も謳っています。畳の表面にカビが根付くのを「予防」する効果が期待できますね。
もしカビが生えてしまったら…
予防していても、カビが生えてしまうこともあります…。その時は、慌てずに「消毒用エタノール(濃度70~80%)」を使いましょう。
- まず、畳の目に沿って掃除機でカビの胞子をそっと吸い取ります。
- エタノールをスプレーボトルで吹きかけ、歯ブラシなどで目に沿ってカビを掻き出し、乾いたタオルで拭き取ります。
- 【重要】最後に、必ず扇風機や除湿機で、エタノールの水分(湿気)を強制的に乾燥させます。これを怠ると、カビが再発します!
結局、カビ対策もダニ対策も、最後は「湿気を残さない」ことが一番大切なんですね。
畳掃除とクイックルワイパーの総まとめ
ここまで、畳掃除とクイックルワイパーの使い方、そして家電を使った対策まで、詳しく見てきました。最後に大切なポイントをまとめておきますね。
畳掃除で一番大切なのは、「畳はデリケートな植物(い草)である」と理解すること。そして、その大敵は「摩擦」と「湿気」である、ということです。
畳掃除の結論
- クイックルワイパー:
ドライシートは日常使いに最適。ホコリや髪の毛を優しく吸着できます。
ウェットシートは原則NG。もし使うなら、「成分(アルコール・界面活性剤フリー)」を選び、「強制乾燥(扇風機・除湿機)」とセットで行う覚悟が必要です。 - やってはいけないNG掃除:
コロコロ(粘着シート):畳がささくれます。絶対にダメ!
重曹:畳が黄ばみます。
ロボット掃除機(硬いブラシ):畳を傷つけます。 - 最強の畳ケア家電:
日常の掃除:軽量スティック掃除機(ソフトローラーヘッドなど)で優しく。
ダニ対策:布団乾燥機(熱で殺ダニ)+掃除機(死骸吸引)。
カビ予防:除湿機(湿度コントロール)+空気清浄機。
畳はデリケートで、少し手がかかる子のように思えるかもしれません。
でも正しい知識を持って、適切な道具(クイックルワイパーのドライシートなど)と、頼れる「家電」の力を上手に使えば、い草の香りが心地よい、快適な和室をずっと長持ちさせることができますよ。
皆さんの和室ライフが、もっと快適になるお手伝いができたら、私も家電店員としてとても嬉しいです!





